
 中国「武闘派女性記者」が英国保守党大会で大乱闘…の深層心理
中国「武闘派女性記者」が英国保守党大会で大乱闘…の深層心理10/17(水) 8:00配信 現代ビジネス
中国「武闘派女性記者」が英国保守党大会で大乱闘…の深層心理
写真:現代ビジネス
「背後には強大な祖国がある」
「日本のメディアは、どうして中国の現状についてもっと報道しないのでしょう?」
先日都内で開かれた中国関係者の食事会に参加した時、初対面の日本人が突然筆者に聞いてきた。
中国製品の物販サイトなどを手がけているというこの男性は、その一例として「例えば中国では昨年映画『ウルフ・オブ・ウォー』が大ヒットしましたが、日本のメディアではほとんど伝えていませんよね?」という。
彼の口から『ウルフ・オブ・ウォー』という言葉が出たのを聞いて、「確かにそうかもしれないけど」と言いながらも、思わず苦笑いしてしまった。最近この『ウルフ・オブ・ウォー』ばりの女傑が英国で大暴れしたのが、大きな話題になっていたからだ。
『ウルフ・オブ・ウォー』(原題は『戦狼』)は中国のアクション映画で、大ヒットした第2作は、アフリカの某国で中国人民解放軍の元特殊部隊員が、悪役の欧米人傭兵部隊から現地人や中国人を守る内容。
「犯我中華者、雖遠必誅」(我が中華を犯す者は、遠きにありても必ずや誅せん)という決め台詞が有名になり、世界の映画興行収入トップ100に入った初のアジア映画となった(2017年8月、中国紙『青年参考』より)。
ただ興行収入は中国国内では約56億8000万人民元(約920億円)の大ヒットだったが、米国では272万ドル(約3億円)と不人気だった。
だがこの映画は攻撃的な愛国主義を強く押し出したとして、ベトナムやアフガニスタンを舞台に強いアメリカを押し出した米国映画『グリーンベレー』や『ランボー』の中国版だとの指摘を受けた。
特にアフリカを舞台に中国の特殊部隊が活躍するという設定は、以前(3月7日)、このサイトでも取り上げた中国中央テレビ(CCTV)の春節特番で、アフリカを取り上げたコントが問題を呼んだように、中国がアフリカを自らのテリトリーと考えているとのメッセージを与えたことになった。
「我が中華を~」と並ぶこの映画の有名なセリフは、「あなたが海外で危険に遭遇した時、諦めてはいけない! あなたの背後には、強大な祖国があるということを忘れないでほしい!」というものだった。
ここから、海外でトラブルに巻き込まれた時、「中国(人)を侮辱した!」などとすぐに「中国」を持ち出し、国歌を歌うなど騒動を起こすことを、「戦狼式維権」(戦狼式の権利主張)と呼ぶようになった。例えば以前(2月6日)取り上げた成田空港での国歌合唱騒ぎもその一つで、こうした行動がますます「傲慢」だと海外で反感を呼ぶようになった。
そしてこの映画のヒットから、外国で攻撃的な態度を取る中国人を自虐的に「戦狼」と呼ぶようになっている。先に英国でこの「戦狼」がひと暴れしたと書いたが、今回戦狼を演じたのはCCTVの女性記者だった。
「戦狼記者」が英国で大暴れ
事件については、日本のメディアでも一部報じているが、9月30日、英保守党が中部バーミンガムで開いた大会で香港問題を取り上げた際、CCTVの女性記者、孔琳琳がスタッフの男性を殴打したとして、一時拘束されたというものだ。
保守党人権委員会のロジャース副主席が「私は親中であって反中ではない。中国の人民が成功することを望んでおり、(香港で)『一国両制度』を保障することは、英中両国にメリットがある」と発言すると、孔記者が突然立ち上がって「ペテン師!」「中国を分裂させようとしている!」と叫び、会場にいた香港民主派を「漢奸(売国奴)」「傀儡」「ニセ中国人」などと罵倒した。
さらにスタッフが孔記者に退場を求めたところ、もみ合いとなり、ボランティアスタッフを平手打ちするなどしたことから、警察に一時拘束されたという顛末だった。
事件後、CCTVと在英国中国大使館はただちに声明を発表し、孔記者を擁護した。CCTVは「正常な職務であり、会議の主催者の対応は不適切だ。英国側に記者の権益を守るよう求める」、大使館は人権委員会が「反中分裂勢力のために騒ぎ立て」孔記者は「自らの意見を表明したのに、妨害され人身に危害を加えられた」として、英国側に「中国への内政干渉をやめ、記者に謝罪するよう」求めた。
タカ派の環球時報編集長、胡錫進はツイッターで、「なぜ中国人の記者に質問する権利がなかったのか? なぜ中国本土の意見が排除されたのか? このような機会があれば、自分もきっと参加するだろう」と書き込んだ。
事件を受け中国国内の世論も「女豪傑」「中国の主権と尊厳を断固として守った」「香港独立派は殴られて当然だ」といった擁護の声が上がったという。
だがこうした対応は、前回取り上げた(9月26日)スウェーデンでの中国人観光客の態度、さらには彼らを擁護した中国外務省の対応と同様に、国際社会で強い違和感を生んだ。
フランス国際ラジオ(4日)は、彼らは少数の中国人にすぎないが、これは中国政府の愛国教育の結果であり、近年中国による「戦狼式」愛国行動が大いにまかり通ることになった。しかも中国政府は事の是非を問わず、急いで身内をかばおうとして、声高に「辱華」(中国を侮辱した)などと批判し、一部のネット市民からは(前回のコラムで取り上げた)「巨嬰」をかばう「巨嬰的行動」だと揶揄されていると指摘した。
そして、中国は近年国際的な場で同様の事件を次々と起こしており、彼らが対外的に与えるイメージは中国が公言する外交的立場とは相反するもので、「中国脅威論」を強化しているのではないか、と批判した。
中国はしばしば日本や欧米のメディアが偏向報道をしていると批判、自国に対するプラスイメージを伝えようと対外宣伝に力を入れている。先日行われたペンス米副大統領の中国に対する演説でも、対外宣伝に数十億ドルを費やしていると発言している。
CCTVの国際部門、中国国際テレビ(CTGN)も、欧米など主要各国にスタジオを構え、ふんだんな政府予算を使って全世界に「中国の声」を伝えようとしている。
中国の対外宣伝強化について、清華大学の研究者は朝日新聞(4日)の取材に「正しい中国の姿を知ってもらうため、公平なメディア秩序を作ることが中国の目標だ」と語っている。 その目的に異を唱えるつもりはないが、今回のような事件はせっかくの努力を無にしているのではないか。
誰を呼び、発言させるかは主催者の権利」
中国国内でも孔記者擁護論一辺倒ではなく、反省、批判する意見もある。「孔琳琳は何を間違えたのか 大使館は何を間違えたのか」という微信で公開された文章は、「保守党の会議は公的な空間ではなく、同党の私的空間だ。公的な場での言論の自由は私的な場には適用されない。私的な場ではルールはそのホストが決める権利があり、ゲストにはない。もしゲストがホストの規則を守らなければ、ホストは追い出す権利がある」として、次のように指摘した。
「ホストが誰をスピーカーに招くかは、ホストの権利であり、孔記者に演説させなかったのも、彼らに決める権利がある。」
「ホストは講演と質問に関するルールを決めており、講演が終わるまでは静粛にしなければならず、質問の中で人身攻撃をしてはならない。」
「孔はスピーカーを無理やり遮り、スピーカーを侮辱するなど、ホストのルールを破った。そして静かにしてほしいとの要請も断った、それゆえホストは彼女を会場から追い出した。」
「ホストが孔を追い出したのは、彼女の言論の自由を制限するためではない。私的な場の秩序を破壊したからで、ホストはこのようなゲストを歓迎しない。彼女の言論の自由は守られており、会場を出た後で、街頭で発言を続ければいいのだ。だが彼女がホストの命令に従わず、その場から立ち去らなかったら、それは違法である。さらにその相手に平手打ちをしたら、人身への侵害であり、さらに違法である。」
第3者の空間に勝手に入り込み、ありもしない権利を主張する、こうした状況は、まさに前回のスウェーデンの事件と全く図式だ。
中国人の公的な空間への認識が独特であるという指摘は、中国哲学の大家、故・溝口雄三氏(東京大学名誉教授)の著書『方法としての中国』(1989年)で読んだ記憶がある。つまり中国では公と私が明確に分かれておらず、公の中にも自分の私的な取り分を主張できるという考え方を、中国人は伝統的に持っているのだという。このあたりも彼らの一見身勝手な行動を理解するカギになるかもしれない。
さらにネットでは、孔記者の息子が英国の学校から退学処分になり、孔はこれを恨んでいたとの情報もあるが、これは確認ができていない。
孔記者が取った行動について、『環球時報』英文版で編集を担当した米『フォーリン・ポリシー』誌編集者は、もし外国人の記者が中国の記者会見であのように大騒ぎしたら、取材資格を取り消され、国外追放されてしまうだろうと述べた上で、孔の行為は愛国の熱情の爆発というものではなく、意図的に仕組んだパフォーマンスであり、自らの出世の道を開くものだったと述べた。そして中国の対外宣伝は実際には外国人に見せるのではなく、習近平ら自国の指導者に見せるのが真の目的だと論じている。
「国内の支持を狙ったパフォーマンス」
CCTVではかつて、韓国記者の質問タイムなのに「自分はアジアを代表する記者だ」とオバマ米大統領の前で豪語したり、スターバックスが北京の故宮の中に出店したことを「文化侵略」などと批判したりして名を挙げた芮成鋼(ぜい・せいごう)という「俺様記者」がいた。(彼はその後中国政界のスキャンダルに巻き込まれ、有罪判決を受けて現在は行方知らずとなった。)
孔記者の行動もこうした国内向けのパフォーマンスの側面があったのだろう。香港のネットメディア、「端伝媒」は孔記者の騒動を取り上げた長文の評論の中で、孔はスウェーデン事件の啓発を受けて、自分の行為が中国国内の世論や政府の支持を得るだろうと考え、たとえメディアの寵児になれなくても、自分の政治的な立場をはっきりとさせることで、昇進の機会を得られるだろうと考えた可能性があるとした。
だがこうした「戦狼」的なナショナリズム・パフォーマンスは、外国からは反感を生み、中国の国際的イメージを改善することに全く役に立たないだろうと述べているが、全く同感だ。
さらに、こうした記者の態度は中国外交のここ数年の変化を反映しているとして、次のように非常に的確な指摘をしている。
「改革開放後、中国当局はそれまでの強硬な外交が中国に与えた教訓を反省し、鄧小平は『韜光養晦』(目立たぬようにして力を蓄える)という外交方針を打ち出した。国際社会で威張り散らしたり目立とうとしたりせず、経済発展のための良好な国際環境を作るのが狙いだった。1980年代から90年代前半までは、中国は外交面で非常に控えめで、重大な問題で西側と衝突や摩擦が起きるのを避けていた。」
「ところがその後中国経済が飛躍的に発展し、多くの人が中国が強大になったと考えるようになり、『ノー』と言える資本を手に入れ、『韜光養晦』をやめて『有所作為』(やれることはやる)という強硬外交を追求するようになった。
共産党はますますナショナリズムを統治を合法化するよりどころとするようになったが、民族主義は諸刃の剣であり、多くの中国人が『百年の恥辱』の歴史から『強硬に戦うのが愛国であり、妥協や譲歩は売国だ』と安易に考えるようになり、政府が外交問題を処理するときの余地を狭めてしまった。」
こうしたタカ派外交に異を唱えてきたのがハト派であり、その代表的人物が呉建民元フランス大使(2016年死去)だった。
彼は「中国が猛々しい態度に出れば、(外国の)人々は次のように考えるだろう。つまり中国が平均所得3000ドルでこんなに凶暴だったら、将来2万ドルに達したら一体どうなるだろう、全く誰も眼中になくなる(傲慢になる)のではないか?」。
そして「外交とは厳しく相手を批判し威張り散らすことではない。外交とは平和的に、礼儀正しく国益を守ることであり、友を増やし敵を減らすことだ」と述べたという。
呉氏とは生前、東京で開かれた日中関係についてのシンポジウムでお会いしたことがあった。だが彼の不慮の死とともに習近平が進めるタカ派外交が主流となり、こうした指導者のお先棒を担ぎ、(習への)政治的忠誠を示すようになったとこの文章は指摘している。
そして一旦今回のような事件が起きれば、前述したように国内のナショナリズムに押され、外交当局もこれを追認するような対応しか取れなくなるのであり、「孔琳琳事件はこれが初めてでも、おそらく最後でもないだろう」としている。
「怒ってばかりでは友人は増えない」
「外国で中国人が中国を持ち出して騒ぎを起こす」→「環球時報などタカ派メディアがあおる」→「ナショナリズムに引火」→「外交当局も中国人が被害者だとして外国を批判」→「海外での中国のイメージ低下」、この図式は前回のスウェーデン事件とまさに同じ流れだ。
こうしたとげとげしい対応を続ければ、損をするのは自分たちの側だということを、そろそろ彼らも気付くべきだろう。
先述の「孔琳琳は何を間違えたのか~」でも、「一部の中国人が他人の私的な領域を尊重せず、好き勝手なことをやっているが、これは決してすべての中国人がそうだというわけではない」と断っているが、「大使館がスウェーデンや英国で騒ぎを起こした少数の無頼漢をかばい、外交ルートで高飛車に抗議した結果、彼ら無頼漢が頻繁に西側メディアに登場すればするほど、西側の人々はすべての中国人が同様(に傲慢なのだ)と錯覚するだろう」と警告している。
端伝媒の文章も、最近の米中摩擦などに触れ、「現在米国内部では全面的に中国を抑え込もうとする共通認識が形成され、国際情勢が空前の厳しさを迎えている。こうした中、中国にとって最良の策は、友人を増やし、支持を増やすことだというのは明らかであり、あちこちに敵を作り、友を敵にすることではない。この種の『剣を振りかざす』行為は中国のプラスで友好的な国際的イメージを樹立するのに役立つだろうか?」と指摘しているが、まさにその通りだ。
スウェーデンの旅行客といい、今回の記者といい、筋違いの権利を主張して大騒ぎを起こして顰蹙を買っている、そういう中国が外国からどのように見られているかということを、外交当局やメディアはまず考えるべきではないか。前述したような毎回お決まりの「悪循環」を繰り返す愚を、そろそろ自覚したほうがいい。
映画『戦狼』のようなナショナリズムを強く押し出した映画は、確かに中国ではヒットしたかもしれないが、海外では歓迎されるものではない。
では筆者がお勧めする中国映画はと聞かれれば、旧作ではあるが、迷わず『變臉 この櫂に手をそえて』(1996年)を挙げたい。約20年前に日本や海外でも上映され、多くの人々に感動を与えた。
先日なくなった名優、朱旭さんが演じる大道芸人と女の子との美しい愛情を描き、涙なしで見ることがいまだにできない。ネットでは中国語字幕版を見ることができるが、日本語字幕を付けたDVDの発売をぜひやってほしい。
自分は時に中国に批判的なことを書いても決して「反中」「嫌中」ではないのは、中国にはまさにこのような麗しい文化や伝統があると知っているからだ。『戦狼』で国民のナショナリズムを鼓舞するよりも、中国はもっとこうした文化や伝統を国際的に伝える努力をすれば、世界が見る目も変わってくるだろう。
(本稿は筆者個人の見解であり、所属組織を代表するものではない)
古畑 康雄


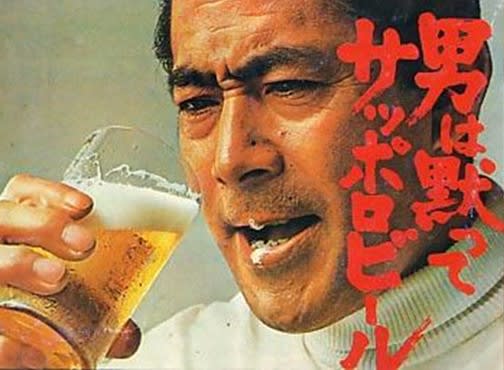


























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます