10月25日、衆議院で教育基本法改定案の審議が再開されました。
私はあらためて、この法案の問題点の一部をご紹介し、私たちの子どもたち・孫たち、そしてまだ生まれていない子どもたちに、今の政府・与党が一体何をさせようとしているのかを考えてみたいと思います。
■ 「伝統と文化を尊重し、・・・我が国と郷土を愛する」
国や郷土を愛するのは「当たり前」だという主張もあります。「当たり前」なのであれば、なおさら自由で自発的な意思に任せておけば良いのです。
これを敢えて条文化することには特別な意味があります。
学校で「国を愛する」ことが求められ、子どもたちの「心」に権力が踏み込もうというのです。
既に学習指導要領にはこれが盛り込まれ、一部の学校では既に「どの子が、どれだけ愛国的か」が評価・競争の対象となっています。今のところ政府・与党は評価まではしないとしていますが、かつて強制まではしないとした「日の丸」「君が代」が今どうなっているのかをみれば、画一的な「国への愛」つまり「忠誠」が、子どもたちの間で比べられます。しかも、子どもたちには、その「忠誠」を「態度」で示すことが求められます。
さらに法案には、子どもたちの「心」に踏み込もうとする部分が20箇所以上もあります。
それほど本腰を入れて子どもたちの「心」を支配しようとしているのです。
■ 「他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う」
一見、「愛国心」は排他的ではない、他国への尊重とバランスを取った、と誤解させるような一節です。
戦前も「修身」で「他の国家や民族を軽んずるやうなことをしてはならぬ。」と教えていましたが、実際には「他の国家や民族」に何をしていったか、ご存知の通りです。
ただし、この規定を盛り込むことについての、政府・与党、とりわけ自民党の思惑は、もっと別のところにあるように思います。
近年の外交政策はどのようなものだったか思い出して下さい。
小泉前首相は「日米関係がうまく行けば全ての国との関係がうまく行く」と小泉首相は言い続けました。確かに米国との関係は、イラク戦費などの負担、米軍司令部機能の受入れなど日本の犠牲によって、ある程度うまく行っているようですが、その他の国々とは溝を深めていきました。
政府は「国際貢献」だとして、自衛隊をインド洋やイラクに派遣しましたが、それは米軍のアフガン戦争の後方支援や、イラク占領政策のための派遣に過ぎませんでした。つまり、彼らが言う「他国」や「国際」とは、ほぼ米国に限定されたものと言って良いでしょう。
彼らが推し進めようとする新憲法草案は「集団的自衛権の行使」、つまり「他国(米国)との共同軍事行動に踏み込むこと」に主眼が置かれています。
彼らは「国家のため」「政府のため」だけでなく「米国のために寄与する態度」も、子どもたちに求めようとしているのではないでしょうか。
■ 現行「真理と平和を希求し」から「真理と正義を希求し」へ
一見「平和」を「正義」に置き換えただけに見えるかもしれません。
しかし、この違いはとても大きなものです。
以前、米国や英国、日本などでは、イラクを攻撃することを首脳が「テロとの戦い」と呼ぶと同時に「正義の戦い」と呼びました。日本でも多くの人々が、その「正義」にだまされましたが、真実が明らかになるにつれ、その「正義」を本気で信じる人々は、かなり減りました。「真理」は別のところにあったのです。
しかし、ブッシュ大統領やブレア首相、そして小泉首相らが唱えた「正義」によって、「平和」が壊され、計り知れない命が失われたのは、紛れもない事実です。
歴史上のあらゆる侵略戦争は、例外なく「正義」を唱え、国民を駆り立てていきました。
この法案を推進する人々は、「正義」とさえ言えば、進んで自他の「平和」を捨て、破壊することを求める子どもたちを作ろうとしているのではないでしょうか。
■ 「個人の価値をたつとび」から、「公共の精神を尊び」へ
「個人の価値」は、「子どもたち一人一人の価値」です。
子どもたちはもちろん国民には、憲法によって「生命権」をはじめ数十の権利・自由が一人一人に保障されています。
判例などで派生して認められている権利も含めれば、さらに多くの権利・自由が約束されています。
しかし政府・与党、とりわけ自民党は「新憲法草案」で、このような権利・自由の全てを「公益」「公共」の下に置いて、まとめて制限してしまおうとしています。
「公益」「公共」は誰が決めるのでしょうか。それは政府です。
彼らが教育現場に求めているのは「君たちの価値、命や権利・自由よりも、政府の利益のための精神を大切にしろ」という教えではないでしょうか。
■ 教育行政は「公正かつ適正に行われなければならない」
一見、問題がないような文言ですが、現行法では「教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立」との規定が、これに書き換えられようとしています。
「公正」「適正」という曖昧な基準は、誰が決めるのでしょうか。これも政府です。
これまで「子どもたちのための教育」の条件を整備するという義務が、国や自治体に課せられていたのが、「政府が決める基準の達成」の義務に変えられようとしています。
では、「政府が決める基準」とは何でしょう。
これまで書いてきた、「子どもたちが、国家・政府、そして米国を大切に思い、正義への寄与のために、自分の命や権利を進んで投げ出す教育」に他なりません。
このような教育を、都道府県・市区町村にまで「行われなければならない」と徹底して義務付けようとしているのではないでしょうか。
■ 「国は、…教育に関する施策を策定し、実施」
これまでの教育は、まがりなりにも「子どもたちのため」のものでした。そして現行の教育基本法が「国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである」と定めている通り、親も含めて「国民全体」のために行われてきました。
しかし、今回の改定案が通れば、これからは「国」が教育に関するすべての「施策」の策定、そして「実施」と介入してくることになるのです。
それがどういう教育か、それは言うまでもなく、これまで書いてきたような「国のため」の教育、つまり「国家主義教育」です。
しかも今度は、この法律(法案)の「お墨付き」を得て「国」が、教育姿勢や、その具体的な内容、教え方にまで公然と介入してくる危険性を秘めています。
条文に残されることになった「不当な支配に屈すること」がない、という規定は、そもそも教育内容を、国家や権力による「不当な支配」から守ることを意味していましたが、以後は国の「支配」に対して、国民が口を出すことを禁じる規定に変えられていこうとしているのです。
これは、国が自分の子どもたちに対して教えることに、たとえ親でも何も言えなくなってしまいかねません。
しかも、それは学校だけにとどまりません。
■ 「家庭教育」の新設
現行の教育基本法は、教育に関しての条件整備など、国がしなければならいことを定めたものです。これは、教育基本法が憲法から直接の負託を受け、子どもたちの「教育を受ける権利」を保障するために設けられた法律だからです。
しかし、今回の改定案は、国が、子・親を問わず国民の上に立って「こうしなさい」と命令するものです。
国が踏み込もうとする、その領域は「家庭教育」にまで及んでいくのです。
■ 国家主義教育への改悪は、「国家による虐待」
これまでご紹介してきたように、こうした政府案が与党に押し切られてしまえば、戦後になって子どもたちが初めて手に入れた「自分たちのための教育を受ける権利」が、再び奪われてしまいます。
学校は「子どもたちのための教育」の場から、「国家権力のための教育」「国家主義教育」の場へと変えられてしまうのです。しかも、そうした教育は家庭にまで公然と入り込んでくるのです。
これが改悪でなくて何でしょうか。
幼い子どもたちの心にの純真さに付け込んで、国家や権力者のための「死」を刷り込もうとするような教育は「国家による虐待」に他なりません。
私は国民として、また一人の親として、このような「改悪」「国家による虐待」を見過ごすことは出来ません。
■ 今後の審議の行方
しかし、与党はこれを一気に進めようとしています。
23日の特別委員会の理事懇談会で与党は、前回国会で49時間37分間の審議を済ませているとして、あと20時間程度の審議で採決に持ち込みたいという考えを示しています。問題点など中身よりも「審議時間という形式だけ」という非民主的な手法が、国会ではまかり通るのです。
その時間数を言うならば、昨年の郵政民営化法案における衆議院での審議は100時間以上でした。子どもたちの未来を大きく左右する教育と、前首相の「趣味」で行われた郵政民営化、どちらが慎重な審議を要するでしょうか。
また与党は、重要法案において欠かすことができない地方公聴会についても、前回国会でまだ十分に審議されていないとして野党側が開催に反対したことをあげつらい、今回も開催せず、これを「省略」すると言い出すなど極めて強硬な姿勢です。
もし与党の予定通りに進められてしまえば、最短で11月7日の委員会採決、同日の本会議採決・衆議院通過という強行もあり得ます。そうなれば参議院での審議時間は、衆議院の7~8割程度ですから、安倍首相が固執する「今国会での成立」は十分に可能になってきます。
これからのわずかな期間に、私たちの子や孫、そしてこれから生まれる子どもたちの将来と、その命がかかっているのです。
私はあらためて、この法案の問題点の一部をご紹介し、私たちの子どもたち・孫たち、そしてまだ生まれていない子どもたちに、今の政府・与党が一体何をさせようとしているのかを考えてみたいと思います。
■ 「伝統と文化を尊重し、・・・我が国と郷土を愛する」
国や郷土を愛するのは「当たり前」だという主張もあります。「当たり前」なのであれば、なおさら自由で自発的な意思に任せておけば良いのです。
これを敢えて条文化することには特別な意味があります。
学校で「国を愛する」ことが求められ、子どもたちの「心」に権力が踏み込もうというのです。
既に学習指導要領にはこれが盛り込まれ、一部の学校では既に「どの子が、どれだけ愛国的か」が評価・競争の対象となっています。今のところ政府・与党は評価まではしないとしていますが、かつて強制まではしないとした「日の丸」「君が代」が今どうなっているのかをみれば、画一的な「国への愛」つまり「忠誠」が、子どもたちの間で比べられます。しかも、子どもたちには、その「忠誠」を「態度」で示すことが求められます。
さらに法案には、子どもたちの「心」に踏み込もうとする部分が20箇所以上もあります。
それほど本腰を入れて子どもたちの「心」を支配しようとしているのです。
■ 「他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う」
一見、「愛国心」は排他的ではない、他国への尊重とバランスを取った、と誤解させるような一節です。
戦前も「修身」で「他の国家や民族を軽んずるやうなことをしてはならぬ。」と教えていましたが、実際には「他の国家や民族」に何をしていったか、ご存知の通りです。
ただし、この規定を盛り込むことについての、政府・与党、とりわけ自民党の思惑は、もっと別のところにあるように思います。
近年の外交政策はどのようなものだったか思い出して下さい。
小泉前首相は「日米関係がうまく行けば全ての国との関係がうまく行く」と小泉首相は言い続けました。確かに米国との関係は、イラク戦費などの負担、米軍司令部機能の受入れなど日本の犠牲によって、ある程度うまく行っているようですが、その他の国々とは溝を深めていきました。
政府は「国際貢献」だとして、自衛隊をインド洋やイラクに派遣しましたが、それは米軍のアフガン戦争の後方支援や、イラク占領政策のための派遣に過ぎませんでした。つまり、彼らが言う「他国」や「国際」とは、ほぼ米国に限定されたものと言って良いでしょう。
彼らが推し進めようとする新憲法草案は「集団的自衛権の行使」、つまり「他国(米国)との共同軍事行動に踏み込むこと」に主眼が置かれています。
彼らは「国家のため」「政府のため」だけでなく「米国のために寄与する態度」も、子どもたちに求めようとしているのではないでしょうか。
■ 現行「真理と平和を希求し」から「真理と正義を希求し」へ
一見「平和」を「正義」に置き換えただけに見えるかもしれません。
しかし、この違いはとても大きなものです。
以前、米国や英国、日本などでは、イラクを攻撃することを首脳が「テロとの戦い」と呼ぶと同時に「正義の戦い」と呼びました。日本でも多くの人々が、その「正義」にだまされましたが、真実が明らかになるにつれ、その「正義」を本気で信じる人々は、かなり減りました。「真理」は別のところにあったのです。
しかし、ブッシュ大統領やブレア首相、そして小泉首相らが唱えた「正義」によって、「平和」が壊され、計り知れない命が失われたのは、紛れもない事実です。
歴史上のあらゆる侵略戦争は、例外なく「正義」を唱え、国民を駆り立てていきました。
この法案を推進する人々は、「正義」とさえ言えば、進んで自他の「平和」を捨て、破壊することを求める子どもたちを作ろうとしているのではないでしょうか。
■ 「個人の価値をたつとび」から、「公共の精神を尊び」へ
「個人の価値」は、「子どもたち一人一人の価値」です。
子どもたちはもちろん国民には、憲法によって「生命権」をはじめ数十の権利・自由が一人一人に保障されています。
判例などで派生して認められている権利も含めれば、さらに多くの権利・自由が約束されています。
しかし政府・与党、とりわけ自民党は「新憲法草案」で、このような権利・自由の全てを「公益」「公共」の下に置いて、まとめて制限してしまおうとしています。
「公益」「公共」は誰が決めるのでしょうか。それは政府です。
彼らが教育現場に求めているのは「君たちの価値、命や権利・自由よりも、政府の利益のための精神を大切にしろ」という教えではないでしょうか。
■ 教育行政は「公正かつ適正に行われなければならない」
一見、問題がないような文言ですが、現行法では「教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立」との規定が、これに書き換えられようとしています。
「公正」「適正」という曖昧な基準は、誰が決めるのでしょうか。これも政府です。
これまで「子どもたちのための教育」の条件を整備するという義務が、国や自治体に課せられていたのが、「政府が決める基準の達成」の義務に変えられようとしています。
では、「政府が決める基準」とは何でしょう。
これまで書いてきた、「子どもたちが、国家・政府、そして米国を大切に思い、正義への寄与のために、自分の命や権利を進んで投げ出す教育」に他なりません。
このような教育を、都道府県・市区町村にまで「行われなければならない」と徹底して義務付けようとしているのではないでしょうか。
■ 「国は、…教育に関する施策を策定し、実施」
これまでの教育は、まがりなりにも「子どもたちのため」のものでした。そして現行の教育基本法が「国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである」と定めている通り、親も含めて「国民全体」のために行われてきました。
しかし、今回の改定案が通れば、これからは「国」が教育に関するすべての「施策」の策定、そして「実施」と介入してくることになるのです。
それがどういう教育か、それは言うまでもなく、これまで書いてきたような「国のため」の教育、つまり「国家主義教育」です。
しかも今度は、この法律(法案)の「お墨付き」を得て「国」が、教育姿勢や、その具体的な内容、教え方にまで公然と介入してくる危険性を秘めています。
条文に残されることになった「不当な支配に屈すること」がない、という規定は、そもそも教育内容を、国家や権力による「不当な支配」から守ることを意味していましたが、以後は国の「支配」に対して、国民が口を出すことを禁じる規定に変えられていこうとしているのです。
これは、国が自分の子どもたちに対して教えることに、たとえ親でも何も言えなくなってしまいかねません。
しかも、それは学校だけにとどまりません。
■ 「家庭教育」の新設
現行の教育基本法は、教育に関しての条件整備など、国がしなければならいことを定めたものです。これは、教育基本法が憲法から直接の負託を受け、子どもたちの「教育を受ける権利」を保障するために設けられた法律だからです。
しかし、今回の改定案は、国が、子・親を問わず国民の上に立って「こうしなさい」と命令するものです。
国が踏み込もうとする、その領域は「家庭教育」にまで及んでいくのです。
■ 国家主義教育への改悪は、「国家による虐待」
これまでご紹介してきたように、こうした政府案が与党に押し切られてしまえば、戦後になって子どもたちが初めて手に入れた「自分たちのための教育を受ける権利」が、再び奪われてしまいます。
学校は「子どもたちのための教育」の場から、「国家権力のための教育」「国家主義教育」の場へと変えられてしまうのです。しかも、そうした教育は家庭にまで公然と入り込んでくるのです。
これが改悪でなくて何でしょうか。
幼い子どもたちの心にの純真さに付け込んで、国家や権力者のための「死」を刷り込もうとするような教育は「国家による虐待」に他なりません。
私は国民として、また一人の親として、このような「改悪」「国家による虐待」を見過ごすことは出来ません。
■ 今後の審議の行方
しかし、与党はこれを一気に進めようとしています。
23日の特別委員会の理事懇談会で与党は、前回国会で49時間37分間の審議を済ませているとして、あと20時間程度の審議で採決に持ち込みたいという考えを示しています。問題点など中身よりも「審議時間という形式だけ」という非民主的な手法が、国会ではまかり通るのです。
その時間数を言うならば、昨年の郵政民営化法案における衆議院での審議は100時間以上でした。子どもたちの未来を大きく左右する教育と、前首相の「趣味」で行われた郵政民営化、どちらが慎重な審議を要するでしょうか。
また与党は、重要法案において欠かすことができない地方公聴会についても、前回国会でまだ十分に審議されていないとして野党側が開催に反対したことをあげつらい、今回も開催せず、これを「省略」すると言い出すなど極めて強硬な姿勢です。
もし与党の予定通りに進められてしまえば、最短で11月7日の委員会採決、同日の本会議採決・衆議院通過という強行もあり得ます。そうなれば参議院での審議時間は、衆議院の7~8割程度ですから、安倍首相が固執する「今国会での成立」は十分に可能になってきます。
これからのわずかな期間に、私たちの子や孫、そしてこれから生まれる子どもたちの将来と、その命がかかっているのです。










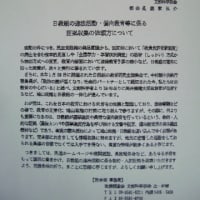
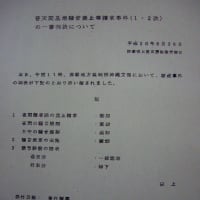
Janjanから飛んで来ました。
私が思うに、思想教育に関して、不適格な教師を解任するのは当然だと思います。
現場では多くの教師が一生懸命、生徒達の成長を考えて教鞭を取っているはずですが、中には、生きていく駄目だけに教師になったデモシカ教師や、組合活動や政治闘争に現を抜かして、教師としての本分をまっとうしようとしない方も少なからず居られるようです。
そういう意味で、思想の狂った教師を解雇するのは、教育にとって本来良い事だと思います。
ことの問題の本質は、安部内閣が教育に改めて思想を持ち込もうとしていて、今まで、散々問題にされてきた、左翼的な所謂新北朝鮮・新中国的で、買国的な行動を繰り返されてきた方々と正反対のことをしゆおとしているだけで、本質的にはその所謂“良識的知識人”とやらと何も変わらないところにあると思います。
教育に、下らない思想を持ち込んで欲しくないと思います。
なぜなら、民主主義とは、多様な価値観を認めることであって、そのなかで、議論し、問題のより良い解決策を見つけていく手法だからです。
なんだか、自民党も共産党と変わらなくなってきたので、非常に残念です。
そもそも、教育の目的は、平和国家に資する人間を育成するためでも、美しい国を作るためでもありません。
子供それぞれに、夢ややりたいこと、憧れなどがあるわけですから、それが実現できるように、少しでも、手助けするのが教師の役目だと考えています。
私から言わせると、「平和のため」と言いつつ、君が代は軍歌だから歌ってはいけないなどと主張する左翼や、日本の為、世界の為に日米同盟が必要だと、美しい国とやらを作るために教育をする等と言う、右翼は、好きではありません。
あくまで、何が素晴しいか?何が良いことなのか?これらの価値判断を下すのは、一個人ですので、教師自身の考え方を生徒に押し付けようとする教師は私は不適格だと思います。
ただ、人間の選別をするなかれ、という意見に関しては、同感です。失礼致しました。
確かに、言われるように、人の選別をすることは本来民主主義の原則に反しますし、何より、私自身が選別してしまったら、所謂、右翼や左翼と何も変わらなくなってしまいますからね。
しかしながら、一点ほど、教育の場に思想教育は持ち込んで欲しくないですし、教師がいくら嘘をついてまで、己の思想を生徒に押し付けようとしても、子ども達が大人になって、自分で勉強すれば、それが正しいか否かを理解できるようになります。
教育の場では、平和が云々、愛国心が云々などと言う高尚なこと(?)よりもまず、他人に感謝する心、困っている人が居たらおのずと助ける優しさ、色々な人から(先輩、同輩、後輩関係なく)謙虚に学ぶ姿勢など、人として生きていく上で大切なものを、学べるようにしていって欲しいと私は思っています。
以前運営しようとしましたが、面倒臭かったので、直ぐに辞めてしまいました。
ところで、私にBlogがあると何か見たいことでもあるのですか?
ただ、要は心を洗う事ですよ。理屈抜きで その一言に尽きます。心の汚れが色々な歪みを造りだす分けです。今の日本は、心の汚れが深刻な人が増えて、おかしくなっています。
私の話 理解できますか?
それに、imacocoさんのサイトも匿名で、ご自身をお隠ししているのと同じでは、と思います。
さて、あなたのお話を理解できますか?とのことですが、非常に良く理解できます。
こう書き込めば、こうなるだろうな、と思って書き込みしましたしね。
以前、goo-needsさんのサイトで、奥村さんという方に
「奥村サンの言うことは 根本的に間違っている。 強い正義が心の中に無いから。」
とあなたが仰っている時点で、あなたの話は良く理解出来ます。
そして、私は元々民○同盟に近い関係にある組織に属していたので、その関連の人々がどのような考え方をされるかは重々承知ですよ。
心の汚れについてですが、日本人の多くが、心の汚れが深刻であると、断罪するご意見には違和感を覚えます。
ようは、人によって、正義は異なると言うことです。
例えば、私自身、中川政調会長の核問題に対するご発言は、如何なものかと思いますが、彼の発言自体問題だと非難しては、それこそが民主主義の否定につながりますね。
「民主主義社会とは、何が正しいことで、何がより価値のあることで、それを議論し、より良い社会に向けて、皆が目指していく社会である」とimacocoさんは思っておられるように思います。
ご自身で、ご自分の中に正義を持たれるのはとても結構なことですが、ご自身と異なる考え方の人を、「間違っている」や「心が汚れている」と断罪されることに関しては、違和感を覚えます。
民主主義とは、問題解決の方法論を議論する手法です。
例として、北朝鮮の核実験問題を出しますが、差し迫った危機も無いのに、核兵器を持つべきだ、などと唱える政治家には違和感を覚えますが、その政治家を無節操に非難する人達にも違和感を覚えます。
まずは、如何にして、北朝鮮に核を打たせないか?を考える(北朝鮮のミサイル基地への攻撃能力の検討)。そして、次に北朝鮮をどうやって国際社会に復帰させるか?を考える(例えば、段階的民主化の導入や、人事交流などによる情報の公開、経済援助などによる支援)。こういうことを議論するのであれば非常に有益ですし、教育問題に関しても、現状の破綻している教育現場で生じている問題をどのように解決していくのかを話し合うのであれば、非常に有益です。
しかし、「どうあるべきだ」などという、個人個人で異なってくる正義に関することを議論していても、根本的な問題は解決しませんし、この議論をしていると、最終的には、お互いがお互いを「君は間違っている」と言い、非難し合って終ります。つまり極めて非生産的です。
ここまで、色々と書かせて頂きましたが、私の経験上、恐らく、私の発言の趣旨をimacocoさんは理解出来ないと思います。
強いて言うなら、「ご自分の正義が全て正しいと思うのは避けられたほうが良い」と言うところでしょうか。
goo-needs様。他人の土俵で、本題(安部首相の教育観)からズレたことでのレスになってしまって申し訳ありません。
私自身、「大学生にボランティアを強制する」、「教育の目的は美しい国を作るためである」などと平気で国会答弁する安部首相には、疑問を持っております。
私自身も、本来自然と養われるべき、愛国心・愛郷心や公共におけるマナーを国が教育で強制しようとする辺りには疑問を持っております。
論題がずれて申し訳ありません。
まさに これが本題なのです。
そのことに気がついてくださいね。
心の浄化、ですよ^^
お二人のご発言、興味深く読ませていただきました。
率直な感想を言わせていただければ、お二人のご主張、そして私の思いには、大きな違いがないように思います。
一点だけ異なる点は、思想教育という行為を排除するか、思想を持った人間を排除するかという点ではないかと思います。
私は、あらゆる思想は、子どもたちの自由で自発的なものでなければならないと思います。
ですから、様のおっしゃる思想教育が、もし現状あった場合、その「行為」を止めることには異論はありません。
しかし、それを「排除」あるいは「解雇」という手段で行うことは、適切ではないと思います。
まして、国家や権力者が一人一人の思想にまで踏み込み、監視し、恣意的な判断で排除するというやり方、そして教育を、子どもたちのためではなく、国家や権力者のために行おうとする今の教育基本法改悪の動きを、容認できないのです。
その点、一致できる可能性があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。