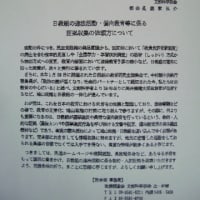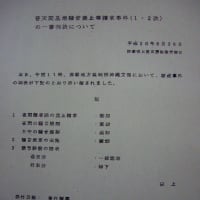■ 引用された「被仰出書」
「邑(むら)に不学の戸なく、家に不学の人なからしめん事を期す。」
麻生首相は、2月12日付けのメールマガジン「国づくりの基本は人づくり」で、「学制序文」すなわち「学事奨励に関する被仰出書(おおせいだされしょ)」(太政官布告第214号)の一節を引用し、施政方針演説にもあった「教育改革」への取り組みを訴えました。
この「被仰出書」については、私も以前、拙稿“「愛国」は伝統や文化ではない”において、取り上げたことがありますが、この「被仰出書」を読む上で最も重要なのは「教育は誰のためにあるのか」「学校は何のために必要なのか」という点です。
■ 「子どもたち」「国」、誰のための教育か
「被仰出書」の冒頭部分を現代語で読むならば、「人々が自立して財産を管理し、その仕事を成功させ、その人生を全うさせるのは、他でもなく自分を律して知識を開き、才能を伸ばすことによるものである。そのためには、学ぶということがなくてはならない。それが学校を設置する理由であり…」と述べています。
つまり、教えられる側の「人々」である子どもたちのためだったのです。そして、そのために「不学の人なからしめんこと」を目指すことが、日本の近代教育の原点だったのです。
ところが、麻生首相のメールマガジンでは「教育」を「人づくり」と呼び、「国づくりの基本」としています。さらにその中では「国力の向上」や「活力ある日本を取り戻し、世界に貢献する。これを支えるのは人です」など、教育や本来「権利主体」である子どもたちは、まるで「国のため」の「材料」か「部品」のような扱いです。
■ 情けない「尻すぼみ」
確かに、「被仰出書」も、冒頭では「人々」のため、という崇高な精神を掲げたものの、「国家」のため、というのも出てきます。
しかも、それが実に情けない「お金」の話として、末尾に登場するのです。
「これまで学問はサムライ以上のことで、『国家のため』と言っていたのを理由に、学費から衣食まで政府をあてにして、これを給付しなければ学ばないものと思い、一生を棒に振る者も少なくない。これからは皆そんな勘違いをせず、学問以外のことをなげうってでも、自ら奮って学ばせること」
分かりやすく言えば、「人々(子どもたち)のため」「国のため」と言ってきたけれども、政府はお金は出しませんよ、という「ケチ」な話で終わっていたのです。
このために当時の就学率の伸びは低調でした。
■ 「不断の改革」なのに削減された「教育予算」
その点で言うならば、麻生首相が、国会冒頭の施政方針演説で「経済状況の厳しい中でも不安なく教育を受けられるようにすること」を訴え、今回のメールマガジンでもそれを繰り返している点は立派だと思います。しかし、これも「被仰出書」同様、「尻すぼみ」に終わっているのです。
いま麻生首相や政府・与党が「早期成立を」と訴える来年度予算案を見てみると、「文教及び科学振興費」は、前年度に比べて15億円のマイナスです。さらに、そこから「科学技術振興費」を引いた本当の教育予算は、合わせて164億円の削減となっています。
もちろん、金をかければ良いというものではありませんが、今回の予算案で一般歳出が4兆4千億円以上の増額となる中での教育予算としては「不断の改革」が泣くというものです。
正に明治政府と同じく、言うことは「ご大層」ながら中身は「しみったれ」、というものです。
麻生首相ですが、「被仰出書」の精神や「漢字」は読めなくとも、せめて重大な職務の一つとして「予算案」くらいは読めるようになって頂きたいものです。
■ 「貧困」だからこそ必要な「教育」
明治初期における、それまでの飢饉による困窮という事情、そして現代における構造的に貧困を作り出すシステムに追い討ちをかけた世界同時不況という事情。
こうした中で、「不学の人なからしめん」教育は必要不可欠です。
それは「国づくり」などという支配者の論理ではなく、教育の権利主体である子どもたちの将来のためです。
親の経済状態によって、満足な教育を受けられず、それが理由で満足な職に就けず、明日をも知れぬ不安定かつ低賃金な非正規雇用に甘んじなければならない、という「貧困の固定化」は、現実に数百万という単位で存在しています。
いま本当に必要なのは、「被仰出書」を引用した麻生首相のメールマガジンにもある通り、「国民皆学」の精神です。そのためには施政方針演説で述べたように、親の経済状態に関わらず、しっかりと「子どもたちの権利」としての教育を支える予算措置が必要なのです。
■ 「金がなければ学校に行けない」という現実
これまで支持率低下に悩む首相ほど、子どもたちを「ダシ」にして「教育改革」を叫ぶという傾向があります。安倍元首相などはその最たるものと言えますが、いま本当に必要な「教育改革」とは、憲法26条に保障された、子どもたちの「その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利」を。国民全体で力の限り支援できる制度を作ることですし、そうした予算編成を行うべきです。
現実問題として、明治期と同様「金がなければ学校に行けない」という現実があるのですから。
「教育」を「人づくり」「国づくり」と呼ぶことの正当性はともかくとして、そこまで「ご大層」なことを言うならば、せめて、そのために必要な「教育予算を拡充させてから」にして頂きたい、少なくとも私はそう思います。
「邑(むら)に不学の戸なく、家に不学の人なからしめん事を期す。」
麻生首相は、2月12日付けのメールマガジン「国づくりの基本は人づくり」で、「学制序文」すなわち「学事奨励に関する被仰出書(おおせいだされしょ)」(太政官布告第214号)の一節を引用し、施政方針演説にもあった「教育改革」への取り組みを訴えました。
この「被仰出書」については、私も以前、拙稿“「愛国」は伝統や文化ではない”において、取り上げたことがありますが、この「被仰出書」を読む上で最も重要なのは「教育は誰のためにあるのか」「学校は何のために必要なのか」という点です。
■ 「子どもたち」「国」、誰のための教育か
「被仰出書」の冒頭部分を現代語で読むならば、「人々が自立して財産を管理し、その仕事を成功させ、その人生を全うさせるのは、他でもなく自分を律して知識を開き、才能を伸ばすことによるものである。そのためには、学ぶということがなくてはならない。それが学校を設置する理由であり…」と述べています。
つまり、教えられる側の「人々」である子どもたちのためだったのです。そして、そのために「不学の人なからしめんこと」を目指すことが、日本の近代教育の原点だったのです。
ところが、麻生首相のメールマガジンでは「教育」を「人づくり」と呼び、「国づくりの基本」としています。さらにその中では「国力の向上」や「活力ある日本を取り戻し、世界に貢献する。これを支えるのは人です」など、教育や本来「権利主体」である子どもたちは、まるで「国のため」の「材料」か「部品」のような扱いです。
■ 情けない「尻すぼみ」
確かに、「被仰出書」も、冒頭では「人々」のため、という崇高な精神を掲げたものの、「国家」のため、というのも出てきます。
しかも、それが実に情けない「お金」の話として、末尾に登場するのです。
「これまで学問はサムライ以上のことで、『国家のため』と言っていたのを理由に、学費から衣食まで政府をあてにして、これを給付しなければ学ばないものと思い、一生を棒に振る者も少なくない。これからは皆そんな勘違いをせず、学問以外のことをなげうってでも、自ら奮って学ばせること」
分かりやすく言えば、「人々(子どもたち)のため」「国のため」と言ってきたけれども、政府はお金は出しませんよ、という「ケチ」な話で終わっていたのです。
このために当時の就学率の伸びは低調でした。
■ 「不断の改革」なのに削減された「教育予算」
その点で言うならば、麻生首相が、国会冒頭の施政方針演説で「経済状況の厳しい中でも不安なく教育を受けられるようにすること」を訴え、今回のメールマガジンでもそれを繰り返している点は立派だと思います。しかし、これも「被仰出書」同様、「尻すぼみ」に終わっているのです。
いま麻生首相や政府・与党が「早期成立を」と訴える来年度予算案を見てみると、「文教及び科学振興費」は、前年度に比べて15億円のマイナスです。さらに、そこから「科学技術振興費」を引いた本当の教育予算は、合わせて164億円の削減となっています。
もちろん、金をかければ良いというものではありませんが、今回の予算案で一般歳出が4兆4千億円以上の増額となる中での教育予算としては「不断の改革」が泣くというものです。
正に明治政府と同じく、言うことは「ご大層」ながら中身は「しみったれ」、というものです。
麻生首相ですが、「被仰出書」の精神や「漢字」は読めなくとも、せめて重大な職務の一つとして「予算案」くらいは読めるようになって頂きたいものです。
■ 「貧困」だからこそ必要な「教育」
明治初期における、それまでの飢饉による困窮という事情、そして現代における構造的に貧困を作り出すシステムに追い討ちをかけた世界同時不況という事情。
こうした中で、「不学の人なからしめん」教育は必要不可欠です。
それは「国づくり」などという支配者の論理ではなく、教育の権利主体である子どもたちの将来のためです。
親の経済状態によって、満足な教育を受けられず、それが理由で満足な職に就けず、明日をも知れぬ不安定かつ低賃金な非正規雇用に甘んじなければならない、という「貧困の固定化」は、現実に数百万という単位で存在しています。
いま本当に必要なのは、「被仰出書」を引用した麻生首相のメールマガジンにもある通り、「国民皆学」の精神です。そのためには施政方針演説で述べたように、親の経済状態に関わらず、しっかりと「子どもたちの権利」としての教育を支える予算措置が必要なのです。
■ 「金がなければ学校に行けない」という現実
これまで支持率低下に悩む首相ほど、子どもたちを「ダシ」にして「教育改革」を叫ぶという傾向があります。安倍元首相などはその最たるものと言えますが、いま本当に必要な「教育改革」とは、憲法26条に保障された、子どもたちの「その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利」を。国民全体で力の限り支援できる制度を作ることですし、そうした予算編成を行うべきです。
現実問題として、明治期と同様「金がなければ学校に行けない」という現実があるのですから。
「教育」を「人づくり」「国づくり」と呼ぶことの正当性はともかくとして、そこまで「ご大層」なことを言うならば、せめて、そのために必要な「教育予算を拡充させてから」にして頂きたい、少なくとも私はそう思います。