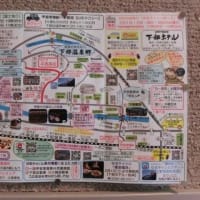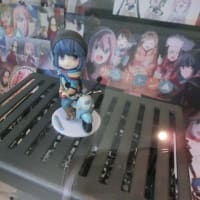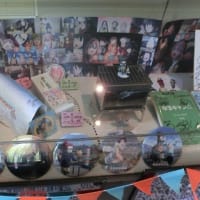本堂内陣を拝した後、境内地の奥まった場所にある細川頼之および碧潭周皎(へきたんしゅうこう)の墓所に行きました。墓所の案内木札には、碧潭周皎は宗鏡(そうきょう)禅師と記されます。夢窓国師の高弟にあたる碩学の禅僧でした。細川頼之が地蔵院の創建にあたって開山に招きましたが、禅師は恩師の夢窓国師を開山に仰いで自らは第二世となりました。

細川頼之の墓石です。老樹の根に寄りかかるように据えられた、苔むした自然石で「細川石」と呼ばれます。レイコさんが意外そうに驚いていて、「これが、あの室町幕府初代の管領の、足利分流の名門の細川京兆家の家祖の墓・・・。自然石を置いただけの質素なお墓なんですね・・・」と呟いていました。

隣にある碧潭周皎の墓も自然石を置いただけの質素な造りです。この碧潭周皎に深く帰依した細川頼之が、この師の墓に倣って自らの墓も自然石とするように遺言して亡くなったのです。葬儀は将軍足利義満が主催して相国寺で盛大に執り行いましたが、地蔵院への埋葬は足利義満および喪主の細川頼元ら近親者のみで密やかに行われたそうです。それが細川頼之の遺言であったそうです。
伝わるところによれば、細川頼之は管領と言う幕府ナンバー2の地位にありながらも質素な生活を好み、華美や贅沢をものすごく嫌ったとされます。和歌や詩文、連歌などもよくして、彼が詠んだ和歌が勅撰集に入撰しているほか、失脚時代に四国にて詠んだ漢詩「海南行」も知られます。
また、幼少時に夢窓疎石の影響を受けて若い頃から禅に傾倒し、山中で坐禅修行に打ち込む事を好んだといいます。管領在職時には主君足利義満との意見対立もしばしばでしたが、そうなると大抵の場合は管領辞任を言い出して出家を志し、本気で松尾山に入山して隠れてしまい、周囲を慌てさせたそうです。足利義満は彼の禅への傾倒ぶりをよく知っていましたから、自ら単騎で飛び出して慰留に努めた事もあったそうです。
とにかく、当時の武将、政治家には稀な、信仰心の篤い人物でした。京都の景徳寺・地蔵院、阿波の光勝寺などの建立にも関わるなど、宗教活動にも積極的でした。
以上の事を説明すると、レイコさんは「凄いじゃないですか、政治家としては一流だったんですね」と感心して小さく拍手していました。
一流というより、室町幕府の歴代管領の中でも傑出した超一流の政治家だったのです。そのことは後の織田信長や徳川家康などが細川頼之を高く評価してその偉業をたたえていることからも伺えますが、何よりも足利義満を補佐して南北朝合一を達成し、室町幕府の全盛期を築いた管領だったのですから、その器量、手腕は際立っていたに違いありません。

墓所の近くには上図の真新しい「一休禅師母子像」があります。アニメにもなった一休さんこと一休宗純は、六歳で出家するまで母と共にこの寺で過ごしたと伝えられています。
アニメでも、一休さんが母の草庵を訪ねる場面が何度かありましたが、その草庵がここ地蔵院境内にあったとされています。一休宗純の母親は、東坊城和長の日記「和長卿記」に「秘伝に云う」として後小松天皇の官女であったとされ、いわゆる一休皇胤説として知られています。
彼女は楠木氏の娘または藤原北家中御門流の持明院家の娘とも言われますが、地蔵院に母子で住んだのが史実とすれば、母は持明院家の娘であった可能性が高いかな、と思います。なぜならば、地蔵院は細川京兆家の菩提寺ですから、その縁者でなければ入れないであろうし、開祖細川頼之の正室が持明院保世の娘でありますから、持明院家の縁にて地蔵院に入ったのではないか、と思います。

地蔵院は応仁の乱で焼失して一時は壊滅したため、寺運も衰えて江戸期には境内に末寺を二つ残すのみであったといいます。広い境内地のあちこちに堂塔および塔頭の遺跡とみられる平坦地が多く見られますが、いずれも苔に覆われて寂漠の雰囲気を濃く漂わせて静まり返っています。

現在は、江戸期の貞享三年(1686年)に再興された方丈が寺の中心施設になっています。

その方丈の庭を見ました。中世期の寺院には一般的であった平庭式枯山水庭園の遺構のようですが、上図のように大部分が埋もれて景石の露出も疎らになっています。園池の汀線すら不明なので、作庭当時の規模すら分かりませんが、中島の痕跡とみられる盛り上がりが少なくとも三つ見えますので、園池だけでもかなりの面積を持っていたであろうと推定されます。発掘すれば、禅宗庭園の一典型の見事な姿が甦るでしょう。

方丈内の説明板には、十六羅漢の庭、とあります。レイコさんが「こういう名前って、庭が造られた当時からのものじゃなくって、後から付けられたケースが多いんですよね?」と聞いてきましたが、私もあまり詳しくはないので、「うーん、そうかもしれませんね・・・」と小声で返しておきました。

方丈内の一室のなにかよく分からない演出です。レイコさんも「何かの意味があるんですかね?」と首をかしげていました。

ともあれ、夕方に近くなってきたので退出することにして、方丈から山門への長い道を引き返しました。広い境内地の殆どが苔庭になっていますので、レイコさんは「苔寺(西芳寺)よりもこっちのほうが断然素敵ですよ、けっこう穴場のお寺かも」と、たいそう気に入った様子でした。
それで、帰りはわざとゆっくり進んで、レイコさんが楽しそうに境内地の色々な景色をスマホで撮影したり、立ち止まって苔庭を眺めたりしているのに合わせました。そうして、私自身は、「海南行」の漢詩を思い出して室町幕府の確立に奔走した質素無欲の武将の心に静かに想いを馳せたことでした。 (了)
「海南行」 康暦元年(1379) 従四位下細川武蔵守頼之
人生五十愧無功(じんせいごじゅう こうなきをはず)
花木春過夏己中(かぼくはるすぎて なつすでになかばなり)
満室蒼蠅掃難去(まんしつのそうよう はらえどもさりがたし)
起尋禅榻臥清風(たってぜんとうをたずね せいふうにがせん)
意訳
人生五十年、さしたる功績もなく恥ずかしい思いだ。
春が過ぎて夏も半ばになった今となっては、咲く花も無い。
部屋いっぱいの煩い青蝿は追い払ってもなかなか去らない。
ならば部屋を出て、座禅の床で清々しい風に吹かれて寝ころぶとするか。