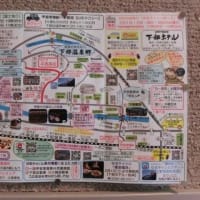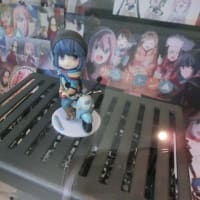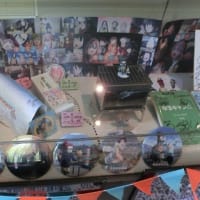境内散策路を順路表示にしたがって進むと、庭園の西にある向月台および銀沙灘の横を通ります。向月台も銀沙灘も宮城丹波守豊盛による江戸期の修築事業によって形成されたもので、おそらくは直前の安土桃山期に流行した作庭における人工的アートのブームの影響を受けていると思われます。
織田信長や豊臣秀吉の頃には色んな奇抜な造形やモニュメントが流行り、建物や庭園にそれを表現することが珍しくありませんでしたから、その直後の時期である慶長年間にもその流れが残っていたのかもしれません。
いずれにせよ、足利義政の頃には無かった代物であることは間違いありません。義政ほど自然の景観を愛した将軍は居ませんし、最も好んだ庭園が西芳寺庭園であったのですから、それを模倣して造営したここの庭園に向月台や銀沙灘のような表現物を加える筈がありません。

銀沙灘の北には方丈があります。寛永年間に宮城主膳正豊嗣が再建したもので、一説では向月台および銀沙灘も方丈の再建にあわせて追加構築されたのではないか、とされていますが確証はありません。

方丈の正面です。これを再建した宮城主膳正豊嗣は、慶長年間に慈照寺庭園の大修築を行なった宮城丹波守豊盛の孫にあたります。宮城氏は土木技術に長けた技術屋の家柄で、江戸幕府では代々が普請奉行を務めています。さらに宮城豊嗣は寛永十六年(1639)に父宮城頼久の三十三回忌にあわせて観音殿の修造も行なっています。慈照寺との縁も豊盛の時から深く、年忌は常に慈照寺で行なっています。
つまり、現在に至る慈照寺境内地の景観は、江戸期における宮城氏の尽力によって整えられたわけです。

方丈の東に建つ、文明十八年(1486)建立の東求堂です。足利義政の持仏堂であったもので、観音殿とともに東山山荘および室町期慈照寺以来の現存建築として知られ、かつ最古の書院建築遺構として国宝に指定されています。
いまは方丈と渡り廊下で結ばれていますが、元からここに在ったのではなく、室町期にはもう少し観音殿に近い位置、いまの向月台のあたりに建っていたようです。移築はおそらく江戸期の方丈の再建にともなって行われたのでしょう。

東求堂は、本尊を阿弥陀如来とする持仏堂ですので、本来は慈照寺における仏殿のひとつ、阿弥陀堂としての役割を担ったようです。ともに現存する観音殿が観音菩薩を安置して観音堂としての機能を持ちますから、足利義政のもともとの信仰観の基本軸は天台浄土教にあったことが伺えます。そのうえで禅にも傾倒して侘び寂びの境地を愛し、東山山荘への隠棲に行き着いたのでしょうが、現職の将軍がそのような現実逃避にはまりこんでいては、応仁の乱が起こらなくても世の中が乱れる成り行きには変わりがなかったことでしょう。

正面扉口の上に懸かる扁額「東求堂」は足利義政の筆になります。拝観は外から見るだけですので、建物の内部とかはあまり見えません。たまに特別拝観の時期があるようですので、その機会を狙いたいところですが、いまだにチャンスに恵まれていません。一度でもいいから、堂内東北の足利義政の茶室空間「同仁斎」の四畳半間に坐してみたいものです。

慈照寺は戦国期に戦火を被って大半の建物および庭園の殆どを失いました。その被害のはじめは天文十六年(1547)四月で、三好越後守政長率いる阿波衆が将軍足利義晴を「東山御城」に攻めた時です。「東山御城」は慈照寺の裏山に築かれていたとされ、現在の中尾城跡にあたるようですが、その攻防戦によって慈照寺も兵馬の蹂躙にあいました。足利義政時代以来の建物の多くがこのときに失われたらしく、庭園も荒廃してしまったようです。
それから22年後の永禄十二年(1569)、織田信長が将軍足利義昭の二条御所を新造する際、その庭園を築くにあたって京都の内外から多くの庭樹および庭石を集めましたが、慈照寺庭園からは「九山八海石」を移しています。「九山八海石」は当時は天下に聞こえた名石であったらしいのですが、庭園が荒廃してボロボロの状態では在っても意味が無い、といわんばかりに信長が二条へ運ばせてしまいました。
おそらく、織田信長の頃には慈照寺庭園はほとんど壊滅状態であったのでしょう。
ちなみに「九山八海石」は、足利義満の北山鹿苑寺の庭園にも有ります。そちらは義満が中国から運ばせた霊石であったとされていますが、おそらく足利義政も先祖に倣って東山山荘の庭園に同じような形姿の石を置いて愛でたのでしょう。

かくして戦国期に建物も庭園もほぼ壊滅状態になっていた慈照寺ですが、その様子を奈良興福寺の僧侶であった多聞院英俊が元亀元年(1570)三月の鞍馬寺参詣の途上にて東山付近を通過の際、日記に記しています。
「東山殿ノ御舊跡名ノミ、アハラヤノ民ノ家ニマシリテ一宇見へ了」
(東山殿(足利義政)ゆかりの旧跡も名ばかり、あばら家の民家に混じって(建物)が一宇見えるだけ)
この「一宇」はおそらく遠くからも見えたであろう観音殿だったと推測されますが、とにかく寺は「名ノミ」残る悲惨な状況であったわけです。
なので、東求堂や観音殿が残ったのは奇跡のようにも思えてしまいますが、実は天正十二年(1584)に慈照寺6世の陽山瑞暉の兄である前関白近衛前久が戦火を避けて慈照寺を本寺相国寺より借りて移り住み、以後亡くなるまでの28年間を過ごしました。その関係で慈照寺は実質的に近衛家の別荘扱いとなりました。
そのため、戦国末期のまだ戦乱続く中にあって、慈照寺にはそれ以上の戦火が及ぶことがなくなり、結果的に東求堂や観音殿が残ったのだと言えます。何がどうなるか分からないものです。

ですが、近衛前久も不遇な境涯に陥ってここに隠棲し、東求堂を仮の住居にして居たのですから、寺の保護管理などをする余裕は無かったようです。境内地が自然の荒廃に任されたままであったことは、慶長十七年(1612)に本寺の相国寺が慈照寺賃借の件に関して近衛家に返還を求める旨を徳川家康に訴えた際の覚書にも明らかです。
要約すれば、寺は大破し山林庭園は押妨(不当に他人の土地に侵入し乱暴を働く、不当な課税をしたりする)状態、庫裏は小屋掛(仮小屋みたいな状態)であるので、なんとかして古来著名なる慈照寺の姿、足利義政公の位牌所としての体裁に戻したい、という内容です。
これを受けて徳川家康はすぐに近衛家に還付の裁決を通達せしめ、慈照寺はようやく相国寺の末寺に復帰しました。宮城丹波守豊盛が慈照寺庭園の大修築にかかったのはその三年後でしたから、これは江戸幕府の保護下における復興支援事業の第一歩であったのでしょう。

当時、足利義政以来の庭園は壊滅し荒廃して原形をとどめていなかったのに相違ありません。庭園の主な石も織田信長が抜き取って二条へ運んでしまっており、近衛前久もここに28年も住んでいながら全く手を付けていなかったようですから、庭園自体が林間に埋もれて大方の痕跡すら見えなかったのでしょう。
江戸期には、いまのように古い遺跡を発掘し調査して復元し、原形に戻すという文化財保存の試みがまだありませんから、庭園の修理を行う場合は全て新造になります。庭石も無くなっている状態ですから、一から造り直しになるのは当然です。宮城丹波守豊盛による慈照寺庭園の大修築は、その意味では完全な新造です。
だから、現在の慈照寺庭園は、完全に江戸期の大名家の作庭事業による遺構と見なされます。足利義政時代の庭園の遺構は、戦後の発掘調査の繰り返しによって一部がやっと明らかになってきている程度です。 (続く)