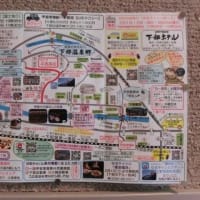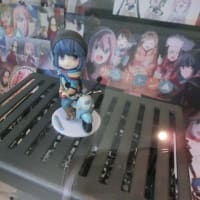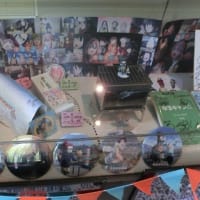市役所を出る際に北側の町並みの甍の波を見ました。各所に青く浮き出るブルーシートが地震被害の広がりを端的に示していました。大部分は屋根瓦にダメージがあったようですが、逆に言えば建物本体への被害は大きくはなく、全体的に行って倉吉の町並みが地震にも割合に耐えられるように造られてきた歴史がうかがえます。
倉吉は江戸期に二度の大火を経験しているので、耐火防火の意識も強めており、さらに鳥取藩は幾多の地震に直面してその都度対策を施してきた経緯があります。他地域の古い町並みに比べると街路の幅が広くとられ、クランクや屈曲のある道が減らされているのもその表れでしょう。倉吉を自分手政治にて任された国家老荒尾志摩家の施策が、いかに民政に重きを置いていたかが理解出来ます。

再び町並みエリアに入り、広がる青空の下での散策をOさんに楽しんでいただきました。大洗よりも広く深い町並みの風情に、色々と感慨を重ねていたようでした。

この日は、町並みエリアの各所の古民家の内部見学もやりました。最初に上図の「豊田家住宅」へ案内しました。

解説ボランティアの方の説明に導かれつつ、表向から中庭、奥座敷、その二階へと進みました。

奥座敷二階から見る土蔵の、二つの棟の段差辺りに地震被害の大きな亀裂が見られました。構造的に二つの建物を貼り合わせてある部分ですから、揺れると双方の小屋組みがそれぞれに振動します。外壁の漆喰がそれに耐えられずに剥がれたり破れたりして、亀裂が生じるわけです。
ですが、この程度で済んでいます。漆喰の補修で大体は済むところに、この地域の古建築の堅牢さがうかがえます。

土間に並ぶ福の神の像です。こういう福の神ってあちこちにありますね、とOさん。

続いて近くの駄菓子店に行きました。芽兎めうのパネルがありますが、あまり「ひなビタ」に入れ込まないOさんなので、店内の駄菓子類のほうに興味津々のようでした。

その後、店先にて店主の息子さんと色々話していましたが、元々ガルパンファンはこうした交流には慣れています。問題は、大洗の人々と違って倉吉の人々の社交性があまり無いことでありました。多くのお店では会話が挨拶程度に終わってしまうので、なにか物足りません。

次に、倉吉では最古の民家建築遺構として有名な淀屋へ行きました。

とりあえず、どういった古建築であるかを簡潔に説明するホシノ。(上画像はOさん提供)

和泉一舞のパネルも健在でした。と言うか、もうパネルが無いと淀屋の「風景」が成立しないまでに定着してきています。ガルパン大洗でも同様なので、パネル設置の常態化の視覚的効果というものが、思った以上に大きい事が分かります。

淀屋内部の構造や修理箇所を眺めるホシノ。何も考えて無さそうなボンヤリした頼りない外見ですが、その頭は猛烈に回転しさまざまな思索を重ねています。ただ、その大部分を次の瞬間に忘却してしまうという特技もあります。(上画像はOさん提供)

二階部分には、この建物の修理事業における修理箇所の具体的な解説展示が実際の木組みによってなされてありました。釘を使わずに木をどのように組み合わせるか、という大工の知恵の数々が示されて興味深いものがあります。
日本人は古代からずっと木造建築と向き合っており、神殿建築もその原始形態は丸太を組み合わせる形式であり、仏教と共に導入された伽藍建築も木組みによる接合で建物を構える形でした。釘を使ったとしても、基本的には木釘または竹釘であったところに、金属製品の耐久度の低さを理解していた歴史が垣間見えます。

現存最古の現役の銭湯である大社湯の建物を見ました。先日の地震で内装に相当の被害を受け、一時は廃業を考えたそうですが、最終的判断としては存続に落ち着いた、と聞いています。

色々な建物を見て、とにかく歩いているせいか、Oさんは「倉吉って広いですねー」と三回ぐらい言いました。ガルパン大洗は細長い商店街と散在する古民家の繋ぎ合わせにしか過ぎませんから、町並みの広さと奥行きにおいては倉吉の方がはるかに上です。面の広がりによって、重要伝統的建造物保存地区とその周辺景観保全地区とに指定されているわけですから、町並み散策の面白さの中身が格段に違います。 (続く)