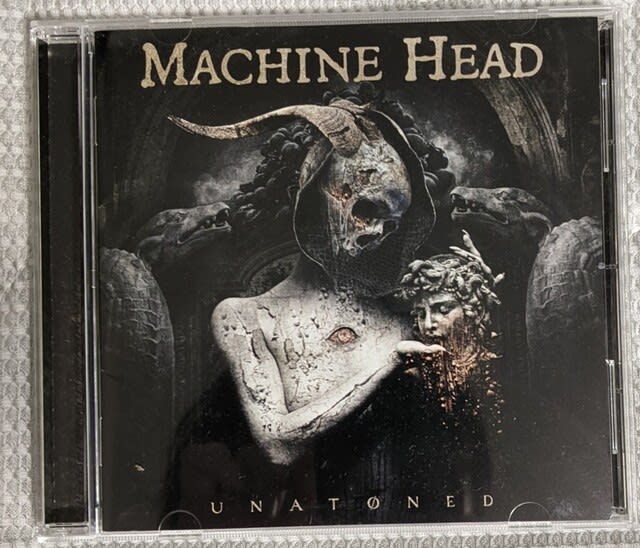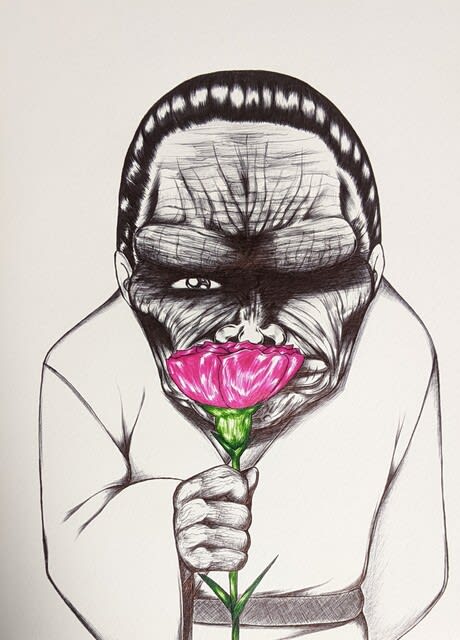この間、NEVERMOREの『THIS GODLESS ENDEAVOR』がリリースから20年を迎えたという投稿をしたが、オレにとってもう一つ大事なアルバムが、リリースから30年を迎えてるんだよね。

FEAR FACTORYの2ndアルバム『DEMANUFACTURE』は、このバンドにとっての記念碑的アルバムになったと同時に、所謂インダストリアル・ヘヴィミュージックに於ける究極形を体現して見せたアルバムだと言えるだろう。
オレがFEAR FACTORYを知った時点でバンドは3rd『OBSOLETE』をリリースしていた時だが、とてつもなくヘヴィであるというこのバンド中でも、強烈至極な名盤という触れ込みを見て最初に手にしたのがこの『DEMANUFACTURE』だった。
このアルバムで最初にこのバンドを体感したのは良かったと思う。
ホントに強烈だった。
表題曲である「DEMANUFACTURE」の機械音の不穏なSEから、いきなり無機質且つ正確無比な高速ツーバスが入り込んでくるイントロは、当時のオレからしたら衝撃だった。
勿論、超速ツーバスを放つドラマーはその前から様々なバンドを聴いて知っていたんだが、この時期に在籍していたレイモンド・ヘレーラのドラミングは、オレにとってのツーバスドラミングとしての在り方を決定づけた存在だった(断っておくが、今の時点でもオレのドラムはこのバンドの曲を演奏出来る程のレヴェルには到達していない)。
多分、最初に聴いたのが『OBSOLETE』であったらそんなでもなかっただろうし、1st『SOUL OF A NEW MACHINE』だったらバンドを追っていこうとも思わなかった可能性があった。
当時のFEAR FACTORYの何が凄かったかと言えば、全楽器のユニゾン度合い。
ギターのリフに合わせてベース、ドラムもシンクロしてその突進力を押し上げる方法は、遡ってみればMEGADETHがある意味では原点とも考えられ、その括りで言えばPANTERAも驚異的であったと思われたところに、FEAR FACTORYが件の2ndを投下してきた。
あの当時、どのバンドと比べてみてもユニゾン度合いはFEAR FACTORYは異常とも言える程にずば抜けていた。
あの時期で言えば、ツーバステクニックの極致を披露していたのがレイモンドであり、インダストリアルメタルを語る上で、手数足数はさておきとして、こういった無機質感のあるドラミングは必須である事を決定づけた様に思う。
そして、そんな強烈な音楽はドラムだけで語れるワケではなく、やはりディーノ・カザレスのこれまた倍音を殆ど感じさせない無機質感満載な7弦ギターによる高速ギターリフの妙技がこのバンドの無慈悲と言えるサウンドを生み出しており、FEAR FACTORYというバンドの世界観を決定づけているのが、バートン・C・ベルの歌唱だったのは間違いない。
もう一つ上げておくとすれば、正規メンバーとはなっていなかったが、当時5人目のメンバーとしてキーボード/プログラミングで協力していたリース・フルバーによる装飾音は、FEAR FACTORYがかつて近未来型メタルとも言われていた要素として外せないものであった点も、事実であろう。
1980年代でのメタルでは生み出す事のできなかったヘヴィネスが顕現された、1990年代であったという時代背景も大きかったと思う。
今の時代から見ても、やはりあの年代に現れたヘヴィロック系のバンドは何処かに狂暴性を孕んだサウンドをしており、ヘヴィ/ラウドという言葉がフィジカルと合致して放出されていたギリギリの年代であったかと感じる。
FEAR FACTORYもマシナリーな演奏として名を馳せたが、それでもライヴは肉体至上主義的な、往時のロック/メタルと変わらぬパフォーマンスであるのがそこを証明している。
だからこそ、そのユニゾン度合いが常人離れしている点を叩きつける事に成功もしている。
ただ、本当に大事な点というのは、『DEMANUFACTURE』以降の楽曲の在り方が、❝音楽的に聴ける事を意識したエクストリームミュージックである❞という事に意識を向けてきた点。
その点に於いては、ディーノのギターとバートンのヴォーカルによるコンビネーションの賜物であり、2010年以降この2人がコアメンバーとしている事実からも立証されている事。
その間に、レイモンド、ベースのクリスチャン・オールド・ウルヴァースは袂を分かち、2020年には遂にバートンも脱退してしまった(この辺りの人間関係はこのバンドグッチャグチャなんだよなァ、残念なことに)が、ディーノは現在もバンドを存続させ、最大の危機とも思われていたヴォーカル後任に関しては、マイロ・シルヴェストロという人物によりある意味若返りも図れたパフォーマンスも相俟って、次のアルバムを個人的に期待している。
目下最新作の10th『AGGRESSION CONTINIUUM』がリリースされてから4年が経過しようとしている。
オレにとって強大な影響を与えたアルバムがリリースされてから30年経った今でも、変わらず刺激的な存在である事を新章でも示してほしい。