三浦 展 著「東京は郊外から消えていく。」を読んだ後、自分の住む新潟市を始めとして地方都市の郊外化についてちょっと考えてみる。
新潟市に住んでおられる方ならご存知のとおり、新潟市の郊外化は凄まじい。昭和40年代から中心市街地であった新潟島から人口は流出、住宅地は郊外へ郊外へと広がっていき、それに従って古町に代表される市街地は見事なまでに衰退…、今や「車がないと生活できない…。」とまで言われるようになった新潟市、全国でも有数の郊外化が激しいエリアと言えるかも知れない。
その原因として、モータリゼーションの進展、公共施設の大規模な郊外移転、新交通システムの頓挫…など、他の都市と共通の要因と新潟市独自の要因の両方が考えられると思うが、実際に生活していて感じるのは、雪、そして強風…と、気候が厳しく、車による移動が異様に楽というか、生活がマッチしていた…というのが一番大きなファクターだったように思う。
実際、私も中心市街地から郊外へ脱出したクチだが、「車生活に慣れちゃったら、公共交通機関なんか使う気起きんわな…。」というのが正直な生活実感。家から職場まで車でドア・ツー・ドア、BGMを掛けながらの快適な車通勤を体験しちゃったら、吹きすさぶ横からの雨、雪でいつ来るか分からないバスを待つ…なんて言うのは苦行以外のなにものでもなく、車が使えない高校生まではガマンするにしても、社会人になれば、車通勤できる人はみんな車通勤しちゃうよな…というのが正直なところ。
そんな都市は交通弱者に冷たすぎる、車に依存し過ぎた街は環境的に問題だ、核がない都市なんて都市とは言えない…とかなんとか言う理由で、最近、市街地回帰、所謂00コンパクトシティ構想が注目されてきており、実際、富山、青森、金沢…などはそのような路線で街づくりが行われているようだが、コンパクトシティ…、その評価は定まっていないというか、正直、うまくいっていない…との声も強いのも事実。
まぁ、街づくりについては、10年、20年という長いスパンで評価すべきものとは思うが、現行制度そのままを温存させていて、コンパクトシティを目指そう…と言われても、それはちょっと無理だわな…と思う。
よく、車の乗れない人にとって今の都市は冷たすぎるし不便…と言われるが、実際の話、バスなどの公共交通機関に乗る方が車の運転より遙かに大変だし、これから高齢者になる人の大半は運転免許を持っている訳で、それらの人は公共交通機関を使うより遙かに楽な車の運転を続けられる限り続けるだろう。実際の話、本気で今の郊外化をストップさせ、都市回帰、コンパクトシティを実現させようと思うのなら、車の機会費用を低めるしかないのではないだろうか。
今、政府税調で自動車税制について議論されているが、自動車税や重量税…と乗らなくてもかかってくる固定費が大きい現行自動車税制では、車を持っている限り使わなくては損…とばかり車を使うに決まっているのである。中心市街地に住んでいながら、車を持っていないと不便…というのではコンパクトシティの意味がない。車を完全に捨て去っても生活に不便をきたさない…と言うか、捨て去った方が大いに楽…ぐらいじゃないと中心市街地に人が回帰するはずがないのではないだろうか。
それには徒歩圏内で全て事足りる程、都市中心部のインフラが整備されている事は無論だが、車の費用が高い社会を作らなければならない…と思う訳だが、現状では……。
今、政府税調で自動車税制について議論されているが、個人的には、(前から力説しているけど。)自動車保有にかかる税金をなくしてもらって、ガソリン税一本に統一してもらいたいと思う。(イメージはドイツと同じリッター200円程度。)それをやってもなお、市街地に人が戻らなければそれはそれでしょうがない…と諦めがつくと思うが、現在の税体系では車優遇というか、依存になってしまっても仕方がないシステムになっていて、郊外化を促進していると思う。
三浦展氏は「東京は郊外から消えていく。」と言うが、地方都市では画期的な税制改正がなければ、「地方は市街地から消えていく。」ということになると思う次第。いずれにしろ、次期政権には、ここあたり、抜本的な改正を行って欲しいものだ。














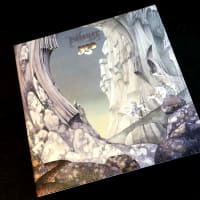



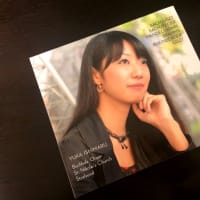


越後線の駅にちゃんと駅前広場を作ってバスを連絡させる、という発想が皆無なんですよね。白山、関屋、青山、小針、寺尾、新潟大学前、内野、内野西が丘・・・・・どれ一つとしてバスのターミナルに使えるような広場がない。
青山なんかはもともと付近が住宅地になってしまってから駅を作ったから仕方がないと思うけれど、新潟大学前や内野西が丘はその気になれば駅前広場を確保することが可能な状態で駅ができたのに、ついに広場はできなかった。内野で言うと、内野駅のもよりのバス停は内野四つ角で、実際に内野四つ角までバスに乗ってそこから内野駅の電車に乗る、という人は結構いるんです。電車とバスの緊密な連絡で客が使いやすくする、という発想を新潟市役所(が担当なんですかね)は考えて欲しい。
連休のときに行ったミュンヘンでは、バス停ごとにきちんと路線図が掲げられていて、地下鉄や地上の電車線の駅に接続する場合ははっきりそれと分かるように大きな丸でバス停の名が表示されていました。地下鉄も地上の電車も、市電もバスも、すべてミュンヘン市の経営なので、市内一日券を買えばどれを利用するのも自由で乗り放題。観光客にとってもすごく便利です。特にバスは、一般には乗りなれている人でないと路線が分かりにくいのが普通ですが、ミュンヘンでは安心して使えました。日本だと東京でも、JR、私鉄、地下鉄東京メトロ、都営地下鉄、都バス・・・・経営主体がたくさんあり過ぎですし、通し券もない。東京は大きすぎるから経営統合は無理かもしれませんが、新潟くらいの都市ならその気になればできるのではないか。まじめに考えて欲しいものです。
新潟市のバス路線図を改めて眺めると、路線がぐちゃぐちゃです。薄く広く広がった市街地では、バス路線が引きにくいからです。乗り換えが多く発生し、定刻どおり来ないバスでは使い勝手が悪いわけで、そうすると「使い勝手が悪い」→「利用者減少」→「減便・リストラ」→「使い勝手が悪い」の完全に悪循環に至っているのが現状です。
人口減少は確実視されているわけで、これからの都市は効率的にまとまっていく必要があります。そういう意味で自由な移動を許すマイカーを排除し、公共交通機関にもっと乗ってもらう社会がこれからのトレンドになると個人的に思います。
ガソリン税いいと思います。無料駐車場に高税をかけるのもアリかと。ノーマイカーデーではぬるい。 移動が制限され、ヒト・モノの効率的移動の基軸がはっきりすれば、まちの核もはっきりしてコンパクトシティ化が一層進むとと思うんですよ。
郊外脱出組が言うのも何なんですけどねw。
鉄道とバスの連絡が全然考えられていない>
これは本当にそうですね。市内の越後線なんて全滅状態ですからね。こんなのを放置して「公共機関のご利用を」と言われても…と言う感じですよね。
イベントぶち上げ大会も結構ですけど、まず、新潟市にはこのようなインフラ整備をお願いしたいと思います。(もはや皆さん、諦めて車オンリー生活になっていると思いますけど…。)
これからもよろしくお願いします。
確かに新潟市の車社会化は本当に凄いですよね。ガソリン税等、車利用優遇について、国レベルで考えて欲しいとは思いますが、新潟市の場合、バスと電車の連携が全くないなど、本当にバスが使いづらいんですよね。
パーク&ライドを含め、本当に考えて欲しいと思います。
これからもよろしくお願いします。