今回は、“I don’t know”に相当するピジン語である。
「私」はピジン語では“mi”で、英語の“me”に由来するようだ。目的格が主格として使われている。ハワイの怪しげな英語でも、やはり“me”が主格として用いられているようだ。日本でも、映画などで日系2世が「ミーはね」と話す場面がよくあったと思う。
スペイン語では、主格は“yo”(「ヨ」または「ジョ」、スペイン語では「ヤ」行と「ジャ」行の区別がない。日本の殿様の「余」を連想させる)だが、目的格は英語と同形の“me”(ただし、発音は「メ」)。このほかに前置詞格があり、“mí”という形である。アクセント記号のない“mi”は所有格である。
ところで、英語の否定文では、be 動詞(かつては本動詞の have も。ピーターとゴードンの「愛なき世界」には、“I know not when”という言い方が出てくる)以外、動詞のあとに“not”を置くのではなく、一般動詞の否定文では動詞の前に“don’t”(“doesn’t”、“didn’t”)を置き、動詞は原形に戻すのだが、これがスペイン語話者には結構、面倒らしい。
スペイン語では、どんな時でも、動詞の前に“no”を置くだけでよいのである。
ピジン語でも、この点はスペイン語同様である。これは、中国語でも同様である。
そうすると、中国語の「私は知らない」に相当する「我不知道(wo bu zhidao)」をピジン語に置き換えると最初が“mi no”となりそうなことが分かる。“know”は“no”と発音が同じなので、別の言葉に置き換えた方がよさそうである。そこでどうしたかは、次回。
ポチッとクリック、お願いします。
↓↓↓
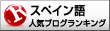 スペイン語 ブログランキングへ
スペイン語 ブログランキングへ


スペイン語とともに考える英語のラテン語彙の世界 (開拓社言語・文化選書)
好評発売中!!こちらは、このブログとは別物です。もちろん、トリビア満載です。

 はじめてのピジン語―パプアニューギニアのことば
はじめてのピジン語―パプアニューギニアのことば
「私」はピジン語では“mi”で、英語の“me”に由来するようだ。目的格が主格として使われている。ハワイの怪しげな英語でも、やはり“me”が主格として用いられているようだ。日本でも、映画などで日系2世が「ミーはね」と話す場面がよくあったと思う。
スペイン語では、主格は“yo”(「ヨ」または「ジョ」、スペイン語では「ヤ」行と「ジャ」行の区別がない。日本の殿様の「余」を連想させる)だが、目的格は英語と同形の“me”(ただし、発音は「メ」)。このほかに前置詞格があり、“mí”という形である。アクセント記号のない“mi”は所有格である。
ところで、英語の否定文では、be 動詞(かつては本動詞の have も。ピーターとゴードンの「愛なき世界」には、“I know not when”という言い方が出てくる)以外、動詞のあとに“not”を置くのではなく、一般動詞の否定文では動詞の前に“don’t”(“doesn’t”、“didn’t”)を置き、動詞は原形に戻すのだが、これがスペイン語話者には結構、面倒らしい。
スペイン語では、どんな時でも、動詞の前に“no”を置くだけでよいのである。
ピジン語でも、この点はスペイン語同様である。これは、中国語でも同様である。
そうすると、中国語の「私は知らない」に相当する「我不知道(wo bu zhidao)」をピジン語に置き換えると最初が“mi no”となりそうなことが分かる。“know”は“no”と発音が同じなので、別の言葉に置き換えた方がよさそうである。そこでどうしたかは、次回。
ポチッとクリック、お願いします。
↓↓↓

スペイン語とともに考える英語のラテン語彙の世界 (開拓社言語・文化選書)
好評発売中!!こちらは、このブログとは別物です。もちろん、トリビア満載です。












 コスタリカへは青年海外協力隊員として派遣された。生活に困ることはないが、かといって、リッチな暮らしができるわけでもない。現地の標準的な給与水準並みの現地手当が支給されていたのである。だからこそ、現地の人並みの生活ができ、いろいろなことを知ることができた。
コスタリカへは青年海外協力隊員として派遣された。生活に困ることはないが、かといって、リッチな暮らしができるわけでもない。現地の標準的な給与水準並みの現地手当が支給されていたのである。だからこそ、現地の人並みの生活ができ、いろいろなことを知ることができた。








