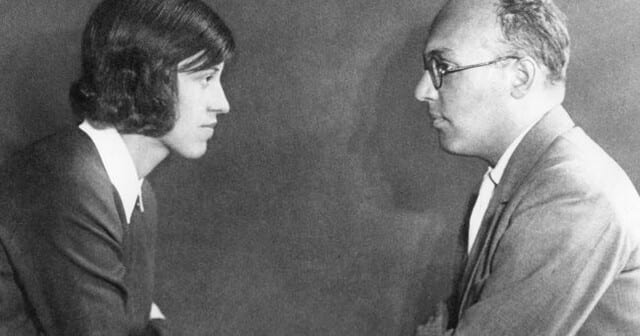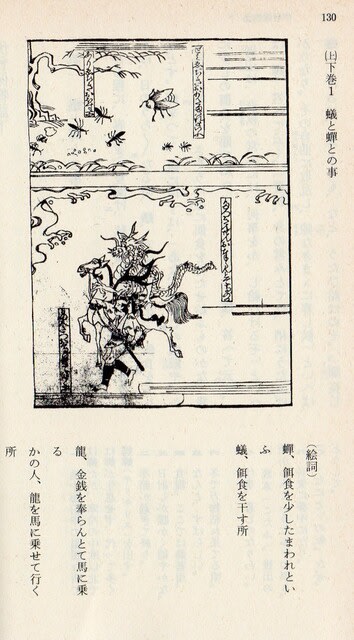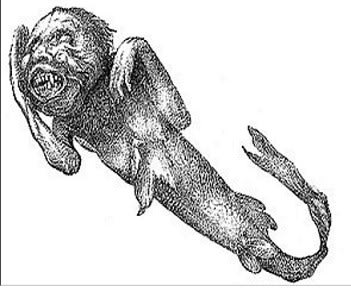2025年7月、猛暑が続く。暑いときに聴く音楽はハワイアンに限る。来月のジャズのセッションでは、ハワイアンの『真珠貝の歌』を歌おう。
『真珠貝の歌』はビリー・ボーン楽団のバージョンが有名だが、ドン・ホーやパット・ブーンなども歌っている。
ところで、『真珠貝の歌』の英語タイトルは”Pearly Shells”なのだが、実は、これは真珠貝ではない。ふと今になって気づいたわけである。真珠貝というのは中に真珠が入っている貝で、主にアコヤガイである。ご覧のとおり、美しくも何ともない無骨な貝である。

【「ぼうずコンニャク魚貝類図鑑」より】
真珠貝にはこのほかにシロチョウガイやクロチョウガイがあるが、いずれも大きな貝で、歌になるような貝ではない。
『真珠貝の歌』の中の『真珠貝』のイメージは小さくてきれいなキラキラ光る貝だろう。そういうのを英語で pearly shells というわけである。これを「真珠貝」と訳したのである。『真珠貝の歌』はディック・ミネによる日本語バージョンもあるので、相当古い歌である。ただし、日本語詞には「真珠貝」という言葉は出てこない。
ネットの辞書を調べてみたが、「真珠貝」に pearly shells の意味が記載されているケースは見当たらなかった。
本物の「真珠貝」は英語では pearl shell または pearl oyster という。
ところで、筆者はかつてコスタリカの Playa Conchal というビーチに行ったことがある。そこは小さな貝殻が砂の代わりになっているのである。

【Trip Advisor より】
この辺にあるキラキラした貝が pearly shells であろう。
ちなみに貝殻はスペイン語では concha というので、conchal は、てっきりその形容詞形だろうと思っていたが、実はそうではなく、「(絹糸が)最高級の」という意味なのであった。とはいっても、やっぱり concha にかけてあるのは明白だろう。
『真珠貝の歌』はビリー・ボーン楽団のバージョンが有名だが、ドン・ホーやパット・ブーンなども歌っている。
ところで、『真珠貝の歌』の英語タイトルは”Pearly Shells”なのだが、実は、これは真珠貝ではない。ふと今になって気づいたわけである。真珠貝というのは中に真珠が入っている貝で、主にアコヤガイである。ご覧のとおり、美しくも何ともない無骨な貝である。

【「ぼうずコンニャク魚貝類図鑑」より】
真珠貝にはこのほかにシロチョウガイやクロチョウガイがあるが、いずれも大きな貝で、歌になるような貝ではない。
『真珠貝の歌』の中の『真珠貝』のイメージは小さくてきれいなキラキラ光る貝だろう。そういうのを英語で pearly shells というわけである。これを「真珠貝」と訳したのである。『真珠貝の歌』はディック・ミネによる日本語バージョンもあるので、相当古い歌である。ただし、日本語詞には「真珠貝」という言葉は出てこない。
ネットの辞書を調べてみたが、「真珠貝」に pearly shells の意味が記載されているケースは見当たらなかった。
本物の「真珠貝」は英語では pearl shell または pearl oyster という。
ところで、筆者はかつてコスタリカの Playa Conchal というビーチに行ったことがある。そこは小さな貝殻が砂の代わりになっているのである。

【Trip Advisor より】
この辺にあるキラキラした貝が pearly shells であろう。
ちなみに貝殻はスペイン語では concha というので、conchal は、てっきりその形容詞形だろうと思っていたが、実はそうではなく、「(絹糸が)最高級の」という意味なのであった。とはいっても、やっぱり concha にかけてあるのは明白だろう。