ソゲリ国立高校の3時間目と4時間目の間のやや長めの休憩、“recess”に戻る。この休憩時間のために、お菓子を教員が交代で、1週間準備することになっている。イギリスのモーニング・ティーの習慣をそのまま持ち込んだようで、今はやっていないとか。
独り者の教員は適当なスナック菓子を買い込んで、簡単に済ませていたが、所帯持ちの教員は奥さんが手作りのお菓子を準備していたようだ。筆者にも当番が回ってくる。当時は、独身なので、適当に済ませてもよかったのだが、つい頑張ってしまったのである。
というのは、近くに適当なレストランがなく、自炊せざるを得なかったからだ。一番近いレストラン(“Kokoda Trail Motel”という名前だったかな。ポートモレスビーの郵便局は“Boroko”にあった。何となく日本語っぽい語感である)でも車で5分から10分ぐらいの距離にあり、メニューもあまりない。ワニ肉を食べることもできるが、結構高い(うまいけど)。それにいつも同じようなものばかり食べていられない。
事前にこういう情報を仕入れていたので、自炊用に料理本を何冊か持って行った。料理をやっているうちに、面白さに目覚めたわけである。一人で食べても味気ないので、同僚をよく招待したことはすでに述べた。
そういうわけで、おやつ当番に当たった時は、妙に張り切ったわけである。
メニューを列挙してみる。
カレー入り揚げ餃子、中華風揚げパン、蒸しパン、生チョコレートを使ったスイーツなどなど。
当初、あまり期待されていなかったが、以後は、大いに期待されるようになり、また、期待に応えていったのである。
ポチッとクリック、お願いします。
↓↓↓
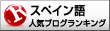 スペイン語 ブログランキングへ
スペイン語 ブログランキングへ


スペイン語とともに考える英語のラテン語彙の世界 (開拓社言語・文化選書)
好評発売中!!こちらは、このブログとは別物です。もちろん、トリビア満載です。

 はじめてのピジン語―パプアニューギニアのことば
はじめてのピジン語―パプアニューギニアのことば




独り者の教員は適当なスナック菓子を買い込んで、簡単に済ませていたが、所帯持ちの教員は奥さんが手作りのお菓子を準備していたようだ。筆者にも当番が回ってくる。当時は、独身なので、適当に済ませてもよかったのだが、つい頑張ってしまったのである。
というのは、近くに適当なレストランがなく、自炊せざるを得なかったからだ。一番近いレストラン(“Kokoda Trail Motel”という名前だったかな。ポートモレスビーの郵便局は“Boroko”にあった。何となく日本語っぽい語感である)でも車で5分から10分ぐらいの距離にあり、メニューもあまりない。ワニ肉を食べることもできるが、結構高い(うまいけど)。それにいつも同じようなものばかり食べていられない。
事前にこういう情報を仕入れていたので、自炊用に料理本を何冊か持って行った。料理をやっているうちに、面白さに目覚めたわけである。一人で食べても味気ないので、同僚をよく招待したことはすでに述べた。
そういうわけで、おやつ当番に当たった時は、妙に張り切ったわけである。
メニューを列挙してみる。
カレー入り揚げ餃子、中華風揚げパン、蒸しパン、生チョコレートを使ったスイーツなどなど。
当初、あまり期待されていなかったが、以後は、大いに期待されるようになり、また、期待に応えていったのである。
ポチッとクリック、お願いします。
↓↓↓

スペイン語とともに考える英語のラテン語彙の世界 (開拓社言語・文化選書)
好評発売中!!こちらは、このブログとは別物です。もちろん、トリビア満載です。
























