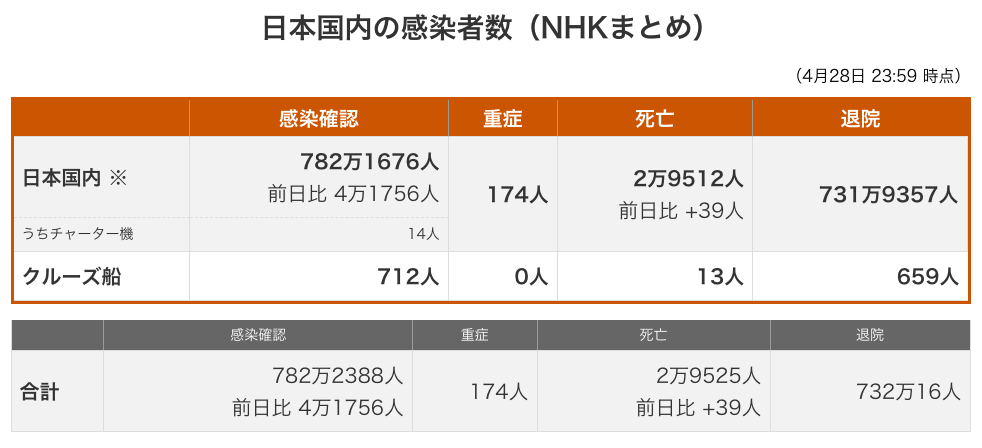「アブラ(脂質、油、脂)を食べると体脂肪になる」
と長年信じられてきました。
しかし近年、この常識が覆されつつあります。
体脂肪の原因は「炭水化物」である、
と。
もちろん、脂質も一役買いますが、
主役はやはり炭水化物。
こちらの記事のによると、脂肪肝の“脂肪”は食事の脂由来が14%、残りの86%は炭水化物・糖質由来と説明されています;
肝臓にたまる脂肪のうち、食事から摂った油や肉や魚などの脂が直接影響するのはわずか14%にすぎません。残りの86%は、体についている皮下脂肪と内臓脂肪が溶け出した脂が60%で、糖質から肝臓で合成される脂肪が26%です。
一方で、
「甘いものを食べると太る」
という常識もありますね。
甘いものは糖ですが、
なぜ糖を摂取すると太るのでしょう?
それは過剰な糖は脂肪として蓄えるシステムが、
人間の身体に備わっているからです。
その主役はインスリン。
これが足らない、あるいは上手く働かない病気が糖尿病であることはご存じですね。
インスリンは血液中の糖を組織が利用できるようにしているホルモン。
そして、余った糖を脂肪として脂肪細胞に貯蔵する働きもあるのです。
これは、人類が飢餓の状態に晒されてきた歴史の中で獲得したものなのでしょう。
余った栄養分(糖)を脂肪として蓄え、
次の飢餓に備える、ということです。
炭水化物の話に戻ります。
炭水化物と言われてもピンとこない方、
「炭水化物 ≒ 穀物(米、小麦、トウモロコシ)」
です。
そして
「炭水化物 ≒ 糖質・糖類」
と切っても切れない仲です。
どういうことかというと、
炭水化物を食べると消化液で分解され、最後は“糖”として吸収されるから。
ですから、
「甘いものを食べるから太る」
と、
「ご飯やパンをたくさん食べるから太る」
は身体にとって同じことなのですね。
言葉をを変えて「白いごはんを食べるのは砂糖を食べるのと同じ」と表現する医師もいます。
肥満にならないためには、
「甘いものを控える」
だけではなく、
「ご飯やパンやパスタを食べ過ぎない」
ことも並行して実行しなければ効果が得られません。
現実世界ではどうでしょう。
・ダイエットで有名なライザップは糖質制限食です。
以上、その道のプロが行っている方法は、
「脂質(油・脂)ではなく炭水化物・糖が脂肪になる」
という考えが基本になっていることがわかります。
もちろん、炭水化物・糖質も栄養として必要ですから、
完全に断つ必要はありません。
ほどほど食べるのがよいということです。
日本人は縄文時代以降、
米を主食においた時点で「糖尿病」という国民病を背負うことになった、
という説があり、私は頷けます。
また、米をたくさん食べるために“しょっぱい”おかず(漬物文化)が発達しました。
これにより「高血圧」という国民病も抱えることになりました。
炭水化物の中には食物線維もあります。
これは人間が消化吸収できず、
糖としてカウントしなくてもよい炭水化物です。
食物線維は腸内細菌のエサになり善玉菌が増えるというメリットがあります。
便秘対策にもなるので積極的に食べてもOKです。
私自身、5年来“緩やかな炭水化物制限”(ロカボ)を実行してきました。
具体的には“主食を食べないだけ”、
つまり“ご飯を食べないでおかずだけ食べる”こと。
厳しい糖質制限をする方は、
とんかつや天ぷらの衣も剥がして食べますが、
そこまでやる決意や勇気がありませんので。
それまで、
「年々体脂肪がついてくるのは運動しないから仕方ないかな」
と半分あきらめていましたが、
ロカボを始めてから、
やせはしませんが体重増加が留まりました。
それから、いくつか気づいたことがあります。
・おかずだけ食べるとすべてしょっぱくて食べられない。日本食のおかずの味付けはご飯がはかどりやすい濃さに調整されている。おかずだけ食べる場合はかなり薄味になるので、高血圧対策になる。
・「おなかいっぱいで動けない」という満腹感は炭水化物による。蛋白質中心の食事を食べ過ぎると「苦しく」なる。
・糖質制限食に慣れると、炭水化物を食べると胃もたれする。胃もたれの程度により、食べたものにどれくらい炭水化物が入っているか感覚的にわかるようになる。この胃もたれが満腹感に通じることがわかった。
・蛋白質中心にすると、満腹感ではなく「もうこの辺でいいかな」と食事を終了するので、食後すぐに動ける。
・「ご飯を食べないと食事をした気にならない」という人は“炭水化物中毒”に陥っている可能性がある。
等々。
<参考>
▢ 「白いごはんを食べるのは砂糖を食べるのと同じ」脳を侵食する"糖質中毒"の恐さ薬物依存症よりずっと治療が難しい
牧田 善二:AGE牧田クリニック院長
▢ ボクサーの食事!減量ダイエット中の食事は?栄養士が教えます!
▢ ライザップ式の食事ルールは痩せる? – メニューやキツイと噂の指導・コンビニで買える商品も大公開!
▢ 医師が警鐘!「フォアグラ肝臓」引き起こす3NG習慣 「脂肪肝」の真犯人は脂肪ではなく「糖質だ」