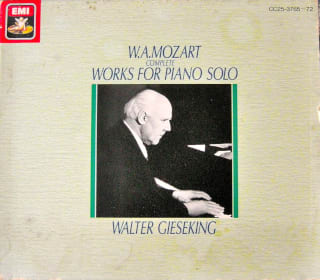【歴史的名盤CD選集】
~ドイツの名ピアニストのワルター・ギーゼキングが弾くモーツァルト:ピアノ音楽全集(全63曲)~
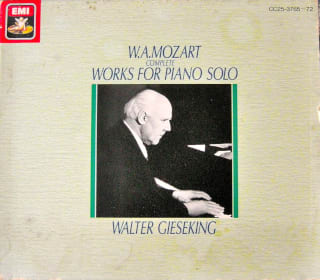
モーツァルト:ピアノ音楽全集(全63曲)<K1~K616>
<Disc 1>
1 メヌエットとトリオ ト長調 K1
2 メヌエット ヘ長調 K2
3 アレグロ 変ロ長調 K3
4 メヌエット ヘ長調 K4
5 メヌエット ヘ長調 K5
6 グラーフのオランダ語歌曲「われら勝てり」による8つの変奏曲 ト長調 K24
7 オランダ歌曲「ウィレム・ファン・ナッサウ」による7つの変奏曲 ニ長調 K25
8 アレグレットの主題による6つの変奏曲 ヘ長調 K54
9 メヌエット ニ長調 K94
10 サリエリの歌劇「ベネチアの定期市」のアリア「わがいとしのアドーネ」による6つの変奏曲 ト長調 K180
11 フィッシャーのメヌエットによる12の変奏曲 ハ長調 K179
12 ピアノ・ソナタ第1番 ハ長調 K279
13 ピアノ・ソナタ第2番ヘ長調 K280
14 ピアノ・ソナタ第3番変ロ長調 K281
<Disc 2>
1 ピアノ・ソナタ第4番 変ホ長調 K282
2 ピアノ・ソナタ第5番 ト長調 K283
3 ソナタ楽章(アレグロ) ト短調 K312
4 ピアノ・ソナタ第6番 ニ長調(デュルニッツ・ソナタ) K284
5 ピアノ・ソナタ第7番 ハ長調 K309
<Disc 3>
1 ピアノ・ソナタ第9番 ニ長調 K311
2 ピアノ・ソナタ第8番 イ短調 K310
3 ボーマルシェの喜劇「セビリヤの理髪師」のロマンス「私はランドール」による12の変奏曲 変ホ長調 K354
4 カプリッチョ ハ長調 K395
5 フランスの歌「ああお母さん聞いて」による12の変奏曲(きらきら星変奏曲) ハ長調 K330
6 ピアノ・ソナタ第10番 ハ長調 K330
<Disc 4>
1 ピアノ・ソナタ第11番 イ長調(トルコ行進曲) K331
2 ピアノ・ソナタ第12番 ヘ長調 K332
3 フランスの歌「美しいフランソワーズ」による12の変奏曲 変ホ長調 K353
4 ドゼードの喜歌劇「ジュリー」の「リゾンは眠った」による9つの変奏曲 ハ長調 K264
5 ピアノ・ソナタ第13番 変ロ長調 K333
<Disc 5>
1 8つのメヌエットとトリオ K315a
2 グレトリーの歌劇「サムニウム人の結婚」の行進曲の主題による8つの変奏曲 ヘ長調 K352
3 ソナタ楽章(アレグロ) 変ロ長調 K400
4 幻想曲とフーガ ハ長調 K394
5 フーガ ト短調 K401
6 幻想曲 ハ短調 K396
7 幻想曲 ニ短調 K397
8 ヘンデルの手法による組曲 ハ長調 K399
9 パイジェルロの歌劇「哲学者気取り」の「主に幸いあれ」による6つの変奏曲 ヘ長調 K398
<Disc 6>
1 小葬送行進曲 ハ短調 K453a
2 サルティの歌劇「とんびに油揚」のミニヨンのアリア「小羊のように」による8つの変奏曲 イ長調 K460
3 グルックの歌劇「メッカの巡礼」の「われらが愚かな民の思うには」による10の変奏曲 ト長調 K455
4 幻想曲 ハ短調 K475
5 ピアノ・ソナタ第14番 ハ短調 K457
6 ロンド ニ長調 K485
ソナタ楽章とメヌエット 変ロ長調 K追加136
7アレグロ
8メヌエット(アレグレット)
9アレグレットの主題による12の変奏曲 変ロ長調 K500
<Disc 7>
1 6つのドイツ舞曲 K509
2 ロンド イ短調 K511
3 ピアノ・ソナタ第18番 ヘ長調 K533
4 ロンド ヘ長調 K494
5 アダージョ ロ短調 K540
6 ピアノ・ソナタ第15番 ハ長調 K545
7 ピアノ・ソナタ第19番 ヘ長調 K追加135&K追加138a
<Disc 8>
1 ピアノ・ソナタ第16番 変ロ長調 K570
2 デュポールのメヌエットによる9つの変奏曲 ニ長調 K573
3 小さなジーグ ト長調 K574
4 ピアノ・ソナタ第17番 ニ長調 K576
5 アンダンティーノ 変ホ長調 K236
6 メヌエット ニ長調 K355
7 アダージョ(グラスハーモニカのための) ハ長調 K356
8 「女はたいしたものだ」による8つの変奏曲 ヘ長調 K613
9 アンダンテ(自動オルガンのための) ヘ長調 K616
ピアノ:ワルター・ギーゼキング
CD:東芝EMI CC25‐3765~72(CD8枚組)
ドイツの名ピアニストであったワルター・ギーゼキング(1895年―1956年)が遺したCD8枚組からなる、「ギーゼキング:モーツァルト/ピアノ音楽全集(全63曲)」は、今日に至るまで、その存在意義は少しも失われていない。これは、ギーゼキングが1956年、モーツァルトの200年祭を記念して録音したものであり、確かに音質自体は、最新の録音技術と比らべると、硬質で重々しいには違いないのだが、音の輪郭はしっかりと捉えられており、充分とは言えないが鑑賞に耐えられるレベルには達している。特に挙げておきたいことは、一人のピアニストが短期間で録音したことによって、一貫した流れの中でモーツァルトのピアノ音楽全63曲の全体像を掌握できることであり、このことは何事にも代えがたい素晴らしいことなのだ。当時“新即物主義”の旗手と言われたギーゼキングは、この録音でも楽譜に忠実に演奏していることが聴き取れる。そして、このことが、モーツァルトの実像を白日の下に映し出す、他に代えがたい貴重な録音ともなっている。ところが、楽譜に忠実にといってもギーゼキングの場合は、杓子定規の硬い演奏スタイルとはまったく異なる。音質自体が実に輝かしい響きを持っているし、確信に満ちたピアノタッチによって、モーツァルト独特の世界を陰影豊かに表現しているのである。(蔵 志津久)