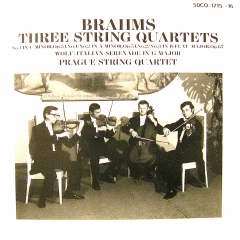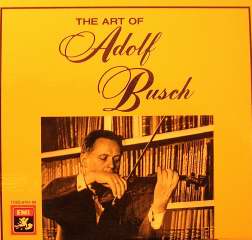シューマン;弦楽四重奏曲全曲
ブラームス:弦楽四重奏曲全曲
弦楽四重奏:メロス弦楽四重奏団
CD:独グラモフォン 423 670-2
このCDにはシューマンとブラームスの弦楽四重奏曲全曲(いずれも3曲)が3枚のCDに収録されている。一見すると特別なCDとは見えないのだが、シューマンとブラームスの弦楽四重奏曲をパッケージにしたところがミソといえるのである。全6曲を聴き通すとシューマンとブラームスの作品の共通点が鮮明に浮かび上がってくる。いずれも3曲である点、第3番がそれぞれ大きなスケールで書かれ、演奏頻度も高いこと、二人とも室内楽曲では多くの名曲を残しているが、その中にあって弦楽四重奏曲は比較的地味な存在である点、などである。このような共通点が生じた背景には、ベートーベンの弦楽四重奏曲の存在があることは間違いないことであろう。何んとかベートーベンの弦楽四重奏曲を超えた作品をつくりたいという二人の思いが、結果として似通った作品に仕上がったということになるのではないであろうか。
もちろん、シューマンとブラームスの弦楽四重奏曲がすべて同じというわけではない。シューマンの作品がロマンの香りが高い、シューマン独特の内向した情緒が幾重にも塗り込められたものに仕上がっているのに対し、ブラームスの作品は、激しい感情の揺らめきとか、外に向かったロマンの謳歌など、あたかもベートーベンの作品を思い起こさせるようなものに仕上がっている。ブラームスの交響曲第1番は、ベートーベンの第10交響曲とも言われている通り、ベートーベンを目標にし、同一の高みに持っていくことに成功したブラームスではあるが、弦楽四重奏曲では、これが思い通りにいったかというと、必ずしもそうではなさそうなのである。確かにブラームスの第3番の弦楽四重奏曲は傑作として現在でも演奏されることが多いが、ベートーベンの弦楽四重奏曲の持つスケールの大きさ、人間の心の奥底に潜む複雑な心理の描写、激しい情熱の吐露、絶望感、人間としての一体感など、時代を超越して我々に訴える圧倒的力強さには、今ひとつ及ばない。
ところで、このCDで演奏しているメロス弦楽四重奏団の演奏は、例えようもないほどの弦の豊穣の響きに唖然とさせられる。弦楽四重奏であるはずなのに、あたかも弦楽合奏団の演奏を聴いているような錯覚にとらわれてしまう。単に4人に息が合っているとか、弦の響きが美しいとかの次元ではなく、もっと大きな重厚な音の響きに体全体が包まれるような心地よさなのである。決して他の弦楽四重奏団には求められない彼ら独特の世界で我々リスナーを魅了してきた。このメロス弦楽四重奏団は1965年結成のドイツの弦楽四重奏団で、ジュネーヴ国際音楽コンクールで最高賞を獲得するなど活躍したが、残念ながらヴィルヘルム・メルヒャーの死により05年に解散してしまった。真に残念なことではある。クラシック音楽は、オペラやオーケストラなどに注目が集まりやすいが、実は弦楽四重奏団の質のレベルこそが、その国や地域の音楽的な水準をはかる上で最も信頼のできる物差しであると確信している。その意味で、日本において地道に息長く活動している弦楽四重奏団には、いつも私は陰ながら敬意を払っているのである。(蔵 志津久)