「今度はハイバリ」って言われて何のことか分からなかった。
「歯威張り・・」
「ハーイ バリー!」
「灰原・・・ナニワ金融道じゃないし・・」
「這いつくばり・・じゃないよね」
「ハイトーンがバリバリ出せるかな・・」
「high volleyならボレーシュートだし・・」
・・・
思い当たらないので先輩に聞くと
「ハイドン・バリエーション、定演の前曲に決まった」とのこと。
なーんだ、今度の定演会場は少し小ぶりだから、ハイドンなんかやるのね。
市民オーケストラの台所事情では、管楽器の降り番が増えるから、
モーツアルトすらなかなかできないのに、よくぞハイドンをやることにしたな~と感心した。
とろでその「ハイバリ」ってどんな曲なのか調べてみようとHaydnで検索しても
なかなかそれらしい曲目が出てこず、Brahmsに突き当たる。
「なんでブラームスが出るの?おかしくない?」とさらに調べると
ハイドンバリエーションの正式な名前は(英語しかわからないけど)
「Variations on a Theme by Haydn」 (ハイドンの主題による変奏曲)で、
作曲家はブラームスで正しい。つまりハイドンのテーマを基にブラームスが変奏したらしいのだ。
小編成の室内楽などではなく、フルオケでベルリン・フィルなども演奏していることも分かった。
「でも本当にハイドンが作った主題なのかな?」と気になりウィキペディアで調べると・・・
『ブラームスは1870年に、友人でウィーン楽友協会の司書、カール・フェルディナント・ポールから、
当時はハイドン作とされていた《ディヴェルティメントHob.II.46》の写譜を示された。』
とある。・・・ということは、ハイドンじゃないのか?・・・
『その第2楽章は「聖アントニウスのコラール」と題されていた。
ブラームスが変奏曲の主題に用いたのがこれである。』
な~るほど、それで・・・
『近年の研究によって、ディベルティメントそのものがハイドン作でないか、ディベルティメントが
ハイドン作であっても主題であるコーラルはハイドン作のものではなく、古くからある賛美歌の旋律を
引用したものと考えられているため、最近は《聖アントニウスのコラールによる変奏曲》と呼ぶ向きも
見られるが、一般には《ハイドン変奏曲》との呼称が定着している。』
つまり、主題の中心はハイドン作ではなく、古くからある讃美歌だったようだ。
さて、その「ハイバリ」の初合わせがあった。実に大変な曲だと分かった。
主題+8変奏曲まであるけど、後半にゆくほど難しくなる。
主題こそハイドンを思わせる、典雅な雰囲気なんだけど、Va1からは一弓で
長い三連譜を弾かなければならないなど、うまくやらないと弓が足りない部分も出てくる。
その後Va2以後 animato→piu vivace→Con motoと、どんどん難しくなり、
・・・第5変奏曲のvivaceではとうとう演奏不可能、演奏放棄となった。
優美なコラールが、チェロ主席でも往生するような、凄まじい速さに変換されているのだった。
ここに至って左指と右腕が利かなくなり 練習を断念して、退散することになった。
午後一杯チェロアンサンブルで練習してきた疲れが出てしまったらしい。
チェロ主席が「ハイバリを初見で演奏するのはやばい」との配慮で、直前まで下練習をしてくれていた。
弾けないことを前提に、あえて本来の速度で、一通り流してみるという練習は大変有効だと思った。
その前には、チェロアンサンブル用の練習もあり、どうやら現在の自分の筋肉の限界となっていたらしい。
その結果、まことに情けないことに、総連後半を断念となってしまったのだった。
・・いわゆる「走り込みが足りない」状態がはっきりした。
我が体力・気力不足はさておいて、ハイバリに初めて触れて思ったことは、
「変奏曲」というのは現代でいえばJazzのアドリブと似ているな~ということ。
Jazzだと、テーマは何でもOK。最初の8小節か16小節をどこからか持ってきて
あとはその雰囲気を感じながら、次第に崩してゆき、最後は原曲の痕跡もないくらいに
演奏者が感じるままに、インプロビゼーションが繰り広げられてゆく。
ハイバりでも、美しいテーマが、時には激しく、荒々しい曲想にまで変えられ
途中痕跡も感じられないまで変貌し、最後には堂々たるテーマに戻る樣は面白く、
もしブラームスが現在生きていたら、Jazzにのめり込んでいたかもしれないと思った。
う~ん、それにしても 散歩、ストレッチ、走り込み・・・
大嫌いな体動かすことをやらないと、とても練習についてゆけなくなりそうだ。










![左手の奥義 「あめんぼう運指]を教わった](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/14/bf/9f3016958710b117391964c084cdbf06.jpg)

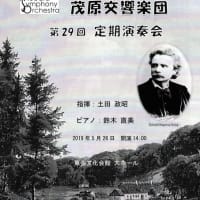













体づくりは大切でしょうが、現在の体力で長く弾ける事を考えるのも体制かもしれません。
確かに若いころのように集中して、一気加勢にということは叶わなくなっているのに、気持ちの勢いだけが残っているんですね。
「今の体力で長く弾ける」という方向、いただきます。