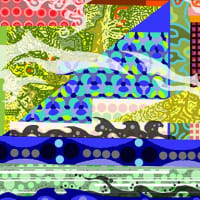神月の子供達
2人が渡の祖父の運転する車で月城村を離れた頃、そこを見下ろす小高い山腹では竹本渡と阿牛ユリの2人が友人達と池を掘っていた。
掘っているのは神月と呼ばれるユリの家の庭だ。勿論、発案者はユリである。春休みにユリは仲間と田んぼで冬眠から覚めたばかりのドジョウを何匹も捕まえた。そのドジョウを飼いたい、夏に金魚すくいで獲った金魚も泳がせたい。まだ可愛らしい小さな緑ガメも水槽にいる。そんな感じで渡やあっちょ、お馴染みのめんめんがユリの指揮のもとにせっせと穴を掘り、掘る側からホースで水を入れている。
自分の子供が他所様の庭に穴を掘って泥だらけになっているとはさすがの綾子も察することはできなかっただろう。日差しはホカホカと暖かく、力仕事に汗の玉が湧いてくる。当初の目的とは違う目的でホースが使われ出すと庭は騒々しい子供達の歓声と悲鳴がかしましいばかりになった。水も盛大に飛び散って、窓硝子と白亜の壁を塗らしていく。水を吸った芝生が無惨に踏み荒らされ、庭木の枝が折れやっと芽吹いた頼りない若葉が水しぶきにはげしくなぶられている。
それを見下ろすテラスに人影があった。
「あああ、あんなにして。」とガンダルファが思わず声をあげた。下にいなくて良かったとしみじみ思う。
「下手したらタトラもあの仲間になってるんだぜ。恐ろしいだろ。」
「ユリ殿に掴まってシンタニどののように背中からホースを突っ込まれるのはさすがにかなわんのう。」
タトラことトラさんが煎れたてのココアのカップを小さな両手で抱え込んだ。
「後で風呂わかしてやらないとな。だいたい暖かいったってまだ春先だぜ、あいつらあんなに濡れたら絶対風邪を引くに決まってるのに。」
「だったら、やめさせたらどうなんです?」コーヒーのお代わりを手に新入社員が開いた椅子に座った。「下に行って、あの場に加わって・・・」
「冗談じゃない。」ガンダルファことガンタはブルブルと身震いした。「ユリは容赦ないからな。俺だって標的にされかねない。カラス、お前もだぞ。」
「お尻、ペンペンしてやればいいじゃないですか。それとも、やはりあなたも社長の娘にはそれはできませんか?」ガンタは無言でカラスを睨んだ。
社長というか部隊長の娘なのはカラスは承知している。トラがため息を付く。
「アギュ隊長はまず、ユリどのを叱らないからのう。」
「それは関係ないよ。上下関係なんてさ。いつだって俺はアギュの代わりに叱ってるつもりだ。効果が感じられないのは、ユリがあんまし聞かないから。それだけだ。」残念ながらと、ガンタは首を振った。
「ただ今は俺自身があんな状態のユリには絶対に近づきたくないだけだって。」
「一緒に遊んでしまいかねないからじゃろが。」
「それもあるって、あるわけないだろ。叱ったところで、やめるもんか。無駄だからだよ。それに、ユリは利口だから濡れたら風邪引くくらいのことはわかってる。そしたら次からはあの子はもうやんないよ。」
「ユリさんの性格をよく把握しているんですね。」
「まあね。」ガンタは水の飛沫に出来た虹を眩しそうに眺めた。
「ひょっとして、父親のアギュさんよりも・・・?」
「何が言いたいんだか。」顔をしかめるガンタに代わりタトラが言う。
「まだアギュ隊長がユリどのの本当の父親か疑っているからなのかの。」
正確には違うのだが遺伝子的にはまちがいない。そこまで教えるつもりはなかった。
「確かにアギュどのが子育てをしていないと言われればそうかもしれんがの。」
「それを言っちゃあ身も蓋もないだろ。」
「わしら宇宙人類はこの地球人類とはちょっと親子のあり方が違うのじゃ。アギュ隊長どのなんてまだ努力している方と言えるの。」「確かにね。」ガンタもうなづく。
「子供は産みっぱなし。誰かが育てればいいと言うのが基本じゃから。」
「では、誰が育てるんです?」
「まず、個人は育てんの。」タトラはそういうとココアを飲み干した。
「連邦の仕事じゃ。」
「それは・・・子供は社会のものだという考え方が徹底しているってことですか。」
「そういう格式張ったものとは違うの。宇宙で暮らしてみれば自分自身の命を守ることでそれぞれが精一杯だったからじゃろ。子供は足手まといになる。」
「ガンター!」ユリの声が上に向けて響き渡った。
「ほらほら来た来た!」半ばほくそ笑んで立ち上がる。
「おまえら濡れたんだろ?穴堀はそれぐらいにして中に入れ!」
下に向かって叫ぶとそれに答えて「寒いよぉ」とか「お腹空いた」とか口々に子供らは叫んでいるようだった。まだまだ緩やかな春の日差しがサンサンと降り注いではいたのだが。いそいそとガンタが室内に消えるとカラスは目を細めて2階より上にある窓を見上げた。
「・・・アギュさんはどこにいるんです? 部屋ですか。」
「そうだろうの。」タトラはさりげなく返すと「ところでどういうわけでカラス殿はここに残ったのかの。」と探りを入れる。「てっきりお気に入りのシドラどのに引っ付いて一緒に行くとばかり思っていたのに。」
「シドラさんには拒絶されましたからね。」カラスも笑みを絶やさない。「それにデモンバルグも今はここにいませんし。どう見たってデモンバルグは私を嫌っていますから。」
「それはそうじゃが・・・確かにジンどのはカラス殿がここにいるから・・居心地が悪いからどこかへ行ってしまったんじゃとは思うがの。」
宿帳に記載された六本木のマンションに本当に帰ったとはタトラは思ってはいない。旅行出版社との打ち合わせだなんて嘘くさいにも程がある。だいたいここ数ヶ月、『竹本』に入り浸りで取材に行った形跡等ないのだから。
大事な渡を置いて、いったいどこへ。とは言っても、アギュが身近にいる以上は渡の安全は完全に保障されていると彼なりに判断したのだろうとタトラは推察していた。デモンバルグはそうとして、この天使はいったい何が目的なのか。
てっきりシドラとバラキに惚れ込んだだけかと楽観視するのは危険だった。
「私はシドささんに限らず、みなさんに興味がありますからね。」
カラスは一人自室にいるアギュの気配を探りながら応える。
自分が4大天使に呼ばれたことをアギュレギオンは知っているだろうか。ヨーロッパの住処を引き払いに戻る途中で御使いによって鴉は天界に呼ばれた。拒まれるどころか、とうとう長年の好奇心が叶って4大天使の聖域に自分も足を踏み入れたわけだ。そこで語られたこと。カラス自身としては自分が4大天使の手先になりたいとも、実際今もそうだとも微塵も思ってはいない。ただ自分自身のアギュへの好奇心を彼等に利用されていることは自覚している。だが、それはお互い様であろう。4大天使もアギュレギオンもどちらもカラスにとってはも捨てがたい研究対象だ。自分、ルシフェイルこと明鴉を通して4大天使はアギュの全てを監視というか把握するつもりなのだ。
「タトラ~手伝ってくれぇ。」ガンタの声が遠くからして、トラは目の前の考え込む鴉をじっくりと観察しながら腰を浮かした。
「では、カラス殿にも手を貸してもらおうかの、新入社員どの。」
「はい、いいですよ。このコーヒーを飲み干してからなら。煎れたてですからもったいない。」手つかずのガンダルファのカップに哀し気に目を走らせる。
尚も油断なく見守りながらもタトラの小柄な体は離れて行った。程よい苦みと香りを味わいながらカラスは目を閉じた。
アギュレギオンの気配。彼は確かにいる、いるはずだ。
でもこの微かな疑いはなんなのだろう。
アギュの影がさっき密かに自分の手をすり抜けたような。
そんな馬鹿な。
階下の喧噪に耳を傾けながら、カラスは口を歪めると残りのコーヒーをゆっくりと飲み下す。
臨海進化体の憂鬱
人ならぬ天使族のカラスのアンテナはまちがってはいなかった。
確かにアギュは神月の屋敷にいる。
屋敷の自室、人としての体を横たえる場所、自分のベッドに。
柔らかいベッドのマットレスの表面は感じた重さに見合って質量を受けとめている。
それはアギュにもわかっている。
自分はこの星にいる人間と同じように・・宇宙に繁茂している人類のほとんどと同じように物質としての肉体を感じていた。でも、実際のアギュは違う。自分でもすべてを掴んでいるとは言えないが。現在、存在を確認できる唯一の臨海した人類であるアギュには自らの体を変化させる事が可能なことを知っていた。肉体である物質の濃度を変えることが。
それまで自分の肉体の状態をとことん突き詰めてみたことはない。本心で言うと、突き詰めてみたいと思ったことはなかったのだ。あまり考えたくないというのが本心だった。必要に迫られる意外はアギュは必死でそのことから全力で目を背けて来たと言える。でもこの数多あるオリオン連邦の地球の中でも『果ての地球』である最果ての太陽系(太陽系と呼ばれる星の集団も実はたくさんあった)その第3惑星に来て次第に考えが変わっていったのを自分でも自覚していた。
2週間前と同じように、少しづつ、息を吐き出す。
目の前に写っているのはこの部屋の丈高い天井。木が枡形に組まれた真ん中に装飾された硝子の電灯が下がっている。和風アールデコとでも言おうか。天井の控えめな彫刻もすべて・・・アギュが愛した少女、ユウリの産まれ育った家の廃墟をベースにして・・・ユウリの祖父に当たる竹本八十助がこの地に建築した最初の建物を正確に再現したものであった。その最上階であるから屋根の向こうは空しかない。
この『果ての地球』にはアギュが知っていた他の惑星とは根本的に違うものがあった。生きた星、無数の生命が自由奔放に繁栄している。そのような星はもはやオリオンにはあまり存在しない。殆どに人類の手が入り、コントロールされ改造されていた。有害な生物は淘汰されている。
アギュが、静かに呼吸を繰り返すと少しずつ、その天井は後退するように半透明になって行った。その遠ざかった視界の間に数多の気泡の渦が脇上がり、満ちて行った。アギュの次元探知モード。再び、それを全開にして解き放ってみようとアギュは思っている。
次元。
臨海しない普通の人間では感知しきれない次元の渦が目の前にあった。
銀河系と呼ばれる広大な星の渦の4分の1以上の範囲に生活圏を広げているオリオン人とカバナ人達からなるオリオン連邦の人々(以後、オリオン連邦人とする)は宇宙には無数の次元があることはもう既に知っている。
もっとも巨大な次元、平行宇宙と呼ばれる存在の実在。それはいわば、この宇宙1つ1つで積み上げられたブロックのようなもので、その連なりは人知には想像もつかない『何か』を形作っているはずだと考えられている。
それ以上はさすがにまだ宇宙人類達にも系統付けられてはいない。今だ、神話の状態だ。その神話の中でビックバンを起こし、常に膨張し続けているこの宇宙も所詮、その1つに過ぎないのだと最近やっとわかってきた。過去、宇宙の始まりを目指した探索船が有人無人含めて幾つも送り出されているが帰って来た物はない。
宇宙の始まりへ近づくにつれて空間と時間というものが著しく変化をしていくらしい。もとより時間というものは人類にしか作用していないのかもしれなかった。それは人類が創造したものの一つでしかないのかもしれない。ひょっとして空間すら。その空間と時間の生み出す次元の変化の嵐・・・次元嵐の波を乗り越えられずに難破あるいは転覆して船達は消息を絶つのだと考えられている。ワープ航法で次元を切り替えた瞬間、どこかで行方不明になってしまうのだ。ひょっとすると今も彼等は黙々と進み続けているのかもしれなかった。銀河系から2000億光年の彼方を今も。
宇宙全体の始まりと終わりは今だに霧の中だ。
その話はそれで置いておくとして・・・この宇宙の話である。
銀河系を抱くこの宇宙のひとつひとつにも、内部には幾つものだぶった次元が内包されている。それはもっとも巨大な次元とは違う。あくまで膨張する宇宙の皮に包まれた次元でしかないことがわかってきている。
それでもそれは、その宇宙に匹敵する大きさの巨大次元なのだ。
その次元同士を繋ぎ、またはそれに絡み付きながら・・・あるいはまったく別な次元として、縦横無尽に走っているもの。ワームホールと呼ばれるそれらも人類が通常の生活を送ってる上ではまったく関係なく、感知すら出来ない領域であった。
物質領域と非物質領域。宇宙は合わせ鏡のようなものと考えられる。
既にオリオン連邦人達はこの次元を自在に移動する術をある程度確立していることは周知の事実。それが宇宙航行の際のワープと呼ばれる航法であることも既に説明されていると思う。
次元の中に時間等が殆ど存在しないことを利用して空間を折り畳むように繋げて進むわけだ。次元の壁を越える度に人体や船等の物理的な物体は分子以下にまで変換され、何度も再変換再構築される。
しかし、さほど大きくもない次元は常に一定ではなかった。ワームホールに至っては消滅や派生が激しく細か過ぎて把握ができない。オリオン連邦人を人種で大別すれば先ほど述べたようにオリオン人とカバナ・リオン人、そしてそれらの混血人種の3種に分けられる。実はもう1つ、二つに別れる分け方がある。
それは星に産まれ、星で生を終える原始星人と宇宙に産まれ宇宙で死ぬ宇宙人類(ニュートロンと総称される)である。宇宙人類達は自らの次元感知能力を極限まで発達させて行った。肉体を脆弱にしてしまったことと、その次元感知能力こそが宇宙に出た人間達の主な進化であるのだ。
彼等は日々変わる次元を察知し、宇宙の中を正確に船を操る。
次元の地図を頭に持った人類達。
その宇宙人類達よりもより進化した存在。
それが臨海進化体。アギュレギオンであった。
空間に存在するというだけで物質はその空間を歪め影響を与えている。
同じように生物が持つエネルギーはその次元に干渉している。
地球という星自体が発するエネルギー。それはそのまま空間と次元を発生させるエネルギーとなる。物理的な磁場と非物理的な磁場。
物理的な磁場はそのままに考えて構わない。所謂オーラとかパワースポットと考えていただければいい。
問題は非物質的磁場とでも言うべき物。これは生物が持つ精神活動が作り出すものだ。とても複雑で把握することは困難を極める。
アギュでさえ掴み切ってはないが・・・人類共通の潜在意識、これはかつてアギュが体験した混沌とかも含まれよう・・・宗教活動や思想、バーチャルや物語世界、人々が言う霊界とかあの世の世界とかも含まれよう。
更に複雑なことに、この世界に住む非物質生物・・・次元生物達の思考や精神活動も含まれていることだった。
それら全てが十重二重にもこの星の人々が唯一、一つであると信じている『現実』の上に多い被さっているのだった。
それらすべてを把握することはアギュにとってもかなり骨が折れる。
ただアギュはこの星に来て以来、ずっと感じて続けている。自分が把握出来る次元というものが確実に増え初めている。とくに薄いレースのように何重にも重なった小さい次元とも言えない層の把握がとてもしやすくなった。
2週間前に初めて試みたように、その場にいながらアギュ自身はじっくりと複数の次元へと滲み出して行く。
ガンダルファがいる。ユリと渡、あっちょとシンタニ。トラもカラスもこの家の洗面所にいる。着替えを持ったカラスがついとこちらを見る。見るがおそらくアギュがわからない。ただなんとも言えない歯がゆいような不信の陰が浮かぶのがわかる。
カラスの憂鬱
自分でも疑い深い、しつこいと思うのだが。
まだ顔をしかめつつ、幾度もカラスは確認している。
アギュはやはり部屋にいる。まちがいない。
でもこの気配は・・・?。このような疑いを抱いたことが最近あったような。
しかし、その時もなんともなかった。それはちょうど・・・2週間ほど前?
シドラ・シデンが出かけた翌日であるからよく覚えていた。
「なんだ、変な顔して。」さすがにガンダルファに見とがめられてしまう。
「いえいえ。」と慌てて取り繕ろった。そういえば。
なんでもこのガンダルファという男もシドラ・シデンと同じくワーム使いとやら言うらしい。彼の使うそのワームとやらはまだ見せてもらった事はないが、この気配はそれであろうか。天界で一部を垣間みたシドラ・シデンの巨大なワームを思い浮かべた。あれは素晴らしい生き物だ。ミカエルがハルマゲドンの龍と見間違うのも仕方がない。できれば他のワーム、ガンダルファの相棒とやらも見てみたい。しかし、ガンダルファにはかったるそうに『それはまた後でな。機会があったらな。』とそっけない。そのうえその話は他所のチビッコの前では話してはいけないと釘を刺されたのであえて聞くこともできない。
「そうだ、カアカア、カラス!」ユリにまで見つかってしまった。
「暇ならカラスも一緒に入ろう、温泉じゃないが足が暖かいぞ。」ユリが湯船に座り足をぶらぶらしている。その目が『アギュを探ってるのか?』と言う。
「いえ、とんでもない。」余裕を示して笑い返した。
「ちぇ!入らないのか。ナグロスもシドラも香奈恵もいないしユリは暇だ。つまらない、ずるいったらないぞ。カラスもどうせ暇なんだろ?暇だとろくなことは考えないからな。」
「言っとくけど香奈恵は遊びに行ったが、ナグロスとシドラは仕事だからな。ついでに言うと、この新入社員も今仕事中だ。」
そういうと、濡れたタオルをカラスに放った。
「シドラはまだ、帰ってこれないのか?なんでだ?おかしいだろ。」
「さあな。ナグロスさんの用事が長引いてるんだろよ。」
「じいちゃんの恩人とか言う相手には会えなかったのか?もう、かれこれ2週間だぞ。ユリは退屈で退屈で死んじまう。」「まさか。死ぬわけないだろが。」
「でも」と渡が別のバスタオルでまだ頭を拭きながらガンタに一番、気になっていたことを尋ねる。「ねぇ、ジンさんまでさ、いったいどこに行ったの?」「知らん。」
「ジンなんかどうでもいいだろ、ワタル。」とユリ。
「仕事だって言ってたけど・・・」本当の仕事なわけないのをあちょとシンタニ以外はわかっていた。「さあな。」とガンタ。
「ねぇ、あのかっこいいジンさんって人さ、かなぶんの母ちゃんと結婚するってほんと?」「僕のママが言ってたけど・・ええと、付き合ってるんですよね。」
ユリ以外は上から下まで濡れた衣服を着替えなければならなかった。
「ケッコン?ケッコンなんかダーレガさせるもんか。」ユリがお湯を跳ねる。
「ユリちゃん、人の家の話に口を出すのはいけないんですよ。」
「うるさい、シンタニザエモン!」
「ぼく、そんな名前じゃありませんよぉ。」
「やめろって!着替えたばかりだろが。」
傍らでは乾燥機が回っている。
子供達は着替えを持っていないのでガンタのTシャツやトラさんの服を借りている。腰にはタオルを巻き、その下はパンツ一丁だ。
「ジンは東京に帰ったんだ。」ガンタが言うと「トウキョウ!ユリだって行ってみたいのにずうずうしいぞ!なんでユリやワタルは行けないんだ!」」と、喚き出した。
「ディズニーランド!」「みんなで泊まるなら山中湖のペンションもいいね。」「3歳の時に連れて行ってもらったらしいんですけど、記憶にないんですよね。」「どこでもいい、みんなで行きたい!」わぁわぁと声が反響してますますうるさい。
「僕達なんてさ、友達の家に泊まるんだってなんだかんだってうるさいのにさぁ、本当にずるいよね。」
「ジンは大人だ。香奈恵は4月から大学だから、もう大人と言ってもいいんだ。おまいらも高校を卒業したら色々許してもらえることが一気に広がると思うぞ。」
「それにだ、よく考えればジンがいないのはきっといいことだ!」
むすっとして相手をしていたガンタにユリが渡を横目で見ながら相づちを求める。
「なぁ。ガンタもジンが邪魔なんだろ?。」
「ジンなんかどうでもいいよ。」「じゃあ、なんでそんなに不機嫌なんだ。」
それはおまいらがうるさくて手がかかるからだとガンタ。
「ガンタ殿は自分の方がナグロスどのに付いて行くはずだと思っておったから悔しいのじゃろ。」
「違うって!」タトラの奴、余計なことを。それは内心、当たっていた。天使から受け取った新しい靴下を子供達に配りながら「だいたいシドラが今回行ってるとこなんて山奥の雪だらけの寒~いぼろ~い農家なんだから。何にも楽しいことなんてあるものか。携帯も通じないし。山降りて電話して来たけど、もう愚痴ばっかりだったんだから。ナグロスさんも困ってたし。なんせ恩人が行方不明なんだからさ。しかもずっと雪に埋もれてるみたいだしさ。ほんと、しけた村なんだ。」誰が、行きたいものかっての。しかし、ガンダルファはシドラとナグロスが待機と称して温泉地に逗留していることはさすがに面白くなかった。まったくうらやましく、許しがたいことだと心から思っている。「ど田舎ねぇ。」と渡。
「あまり神月とかわらないんだね。」
「雪が積もってないだけこっちの方がましか。」「近くに温泉もあるしね。」
「遊んでるようでもの、待機しているのはこれはこれでなかなか、気苦労なことであることよ。飽き飽きしても、帰れないのだからの。」
「だから大人は大変なんだって。仕事は厳しいんだ。」
そんなところにどうして行くのか。自分達は大人になってもそんなせこい仕事はごめん被る。大学生になって山中湖やディズニーランドに行く方がずっといい。早く中学を卒業し、高校生になりたいものだ。
そんな会話を聞きながらもカラスは上階にいるアギュレギオンの気配に神経を研ぎすませてしまう。それをまたタトラがジッと見る。ユリもだった。
進化体だと言うこのタトラもあなどれないがこのユリと言う娘もなかなか油断できないとカラスは気が抜けなかった。
その面白さにカラスの頬はついつい緩んでしまう。
「なんだ、ニヤニヤして。バカか?」ガンタがブスッとお湯を抜きながら言う。
「バカだってさ。」子供達がこそこそと囁き合う。「バカには見えないよ。」と渡。
「香奈ねぇのお気に入りだもんね。香奈ねぇ、バカは嫌いだもん。」
「カナエの趣味はユリにはわからん。」
「いいんですよ、バカでも。なんでも。言って下さい。」カラスはご機嫌になる。
おかしな気配の事はもう気にすることもあるまい。前もなんともなかったのだから。
「私は今みなさんとここにいられるだけで、とっても幸せなんですから。」
もともと天使は寛大な生き物なのだ。明鴉こと堕天使ルシフェイルは心底堕天したわけではないのだから。
その言葉を聞くガンタの顔が一掃、不機嫌になるのもなんて楽しいことだろう。
天使は寛大だが性格が必ずしもいい訳ではないらしい。
悪魔よりかはいくらかマシと言ったところだろう。