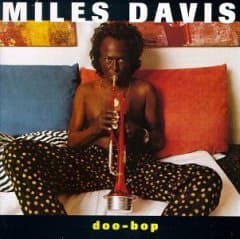最高のジャズヴォーカルアルバムが聞きたいというリクエストがあればこれを薦める。
どんなジャズアルバムでも、必ず「好き」と答える人と「嫌い」と答える人がいるが、このアルバムだけは例外ではないだろうか。今までこのアルバムを「嫌い」と答えた人に会ったことがない。
コルトレーンといえば、目まぐるしいシーツ・オブ・サウンドや難解なフリーキー・トーンを最初に連想しがちだが、彼のアルバムで一番売れたのが「バラード」であるように、彼はこうした静かな曲が得意であったし、ハートマンの低い声と同調させたかのようなアドリヴはさすがだ。ハートマンもコルトレーンのテナーをじっと見つめて、ここぞというタイミングで歌い出す。これで感動しない人がいたらその人には心がないものと思いたい。
たっぷりと男の色気を感じてほしい。