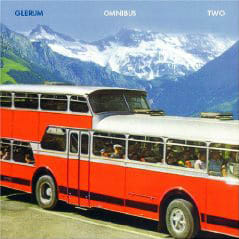この歌(I Still Feel The Same About You)が吹き込まれたのは1951年1月である。
この当時はこういったいいデュエット作品が多かった。
事実、ローズマリー・クルーニーもビング・クロスビーとのデュエットで一躍有名になった人だ。
さて一昨日からの話を続けよう。
このクルーニー・シスターズの歌が流れると部屋中の空気が一変した。線香の匂いが吹き飛んで、甘い香水の香りに包まれた。
みんなの顔にも自然と笑みがこぼれる。
あの先輩の表情も穏やかになり、しばらくは聴き入っていたようだ。
但しこういった曲は何曲も続けて聴いてはいけない。なぜかというと単純に飽きるからである。せいぜい2曲か3曲に留めておくのがコツなのだ。
そこで私は「I Still Feel The Same About You」が終わるとすぐに針を上げてもらった。
「コルトレーンの後でこれはちょっと場違いでしたかね」と私がいうと、先輩は「いやいや、こういうのも悪くない」といった後で、「しかしこれはジャズじゃない」と一言付け加えた。
確かにそうだ。ジャズの要素はほとんどない。ローズマリー・クルーニーはジャズシンガーで通っているというだけの話なのである。
それから小一時間が経ちそろそろ帰ろうかと思った時、先輩がおもむろに「これはしばらく置いていけ」と私のレコードを指さした。
意外にも気に入ってくれたことが嬉しく、私は快く了解した。
しかしこれがそのレコードの見納めになった。
あれから既に約30年が経つが未だにそのレコードは返ってこないのだ。
今となってはそれがどんなジャケットだったかもはっきり覚えていない。しかも「I Still Feel The Same About You」の入ったアルバムがどこを探しても見つからないのである。ここでご紹介する「Sisters」にも収録されていない。
それが最近になって、一昨日ご紹介した「You're Just in Love」というアーリーヒッツに収録されているのを見つけたのだ。
私は小躍りして喜び、それを買い込んだ。
レコードはCDになったが、その甘い歌声は変わらない。感動がじわっとこみ上げてきた。
この曲が私の宝物になった瞬間である。