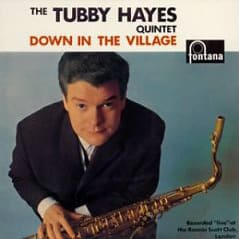今日で8月も終わり。長いようで短かった夏の終わりにこの作品を紹介することに喜びを感じる。
私にとってウエストコーストジャズのイメージは、このアルバムが全てだといってもいい。
リッチー・カミューカとビル・ホルマンによる「ウエストコーストジャズ・イン・ハイファイ」。このアルバムのジャケットはこれ以外にも発売されているが、このアルバムはこのジャケットでなくてはダメなのだ。この夕陽に染まった浜辺を見ながら演奏を聴くと、ウエストコーストジャズの魅力が何倍にもなって返ってくる。
メンバーはというと、フランク・ロソリーノ(tb)、ビル・ホルマン(bs,arr)、リッチー・カミューカ(ts)、コンテ・カンドリ(tp)、エド・リディ(tp)、ヴィンス・カラルディ(p)、モンティ・バドウィッグ(b)、スタン・リーヴィ(ds)で、当時ウエストコーストジャズを支えた面々がずらりと顔を揃えている。
この中でも特に重要なのがビル・ホルマンである。彼はバリトンサックスの演奏もさることながら、アレンジャーとしての手腕を発揮している。ウエストコーストらしい明快な音と曲の組み立ての良さは彼のセンスによるものだ。
針を落として最初に聞こえてくるスイング感たっぷりの明るいテナー、そう、これがリッチー・カミューカだ。彼の音を知り尽くしたホルマンのアレンジがすばらしい。続くホーン・アンサンブルも見事に決まっている。
もう一つ嬉しいことがある。このアルバムには私の大好きな「THE THINGS WE DID LAST SUMMER」が納められているのだ。このことも私の中でこの作品の価値が高まった大きな要因だ。
この曲の入ったジャズアルバムは誰彼かまわず手当たり次第購入しているが、ここでの演奏もなかなかの出来映えだ。
行く夏を惜しむかのような美しいメロディラインに乗って、情感たっぷりのソロとホーン・アンサンブルが展開される。ソロはフランク・ロソリーノのトロンボーンがいい。
う~ん、夏の匂いが消えないうちにもう一度こんな海に出かけたくなってきた。