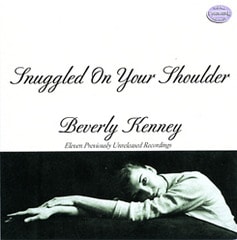まるで水がしたたり落ちるような調べで始まる。
透明感溢れるティングヴァル・トリオ、待望の第3弾である。
私は大体にしてジャケットから影響を受ける単純な人間で、こんな写真を眺めながら聴いていると、本当に水の中に吸い寄せられるような感覚に陥ってしまう。
だからというわけでもないが、ピアノの響き方は全体的にピリッと硬質だ。
そのひんやりした感覚が、前作以上に際立っている。
全体の流れとしては、一曲一曲の演奏時間が短いせいもあるかとは思うが、かなりドラマチックな印象だ。
それぞれの曲の完成度は高いが、通して聴いてみると各曲は大きなストーリーのパーツのように感じてしまう。
正直言って、ここが好みの分かれるところだ。
コテコテなジャズファンなら、もっとトーンの違いや粘っこさを求めるだろう。
しかし、この作品はクラシックのように折り目正しい。
最初から終わりまで計算し尽くしているような生真面目さを覚えるのである。
まぁ、それが北欧ジャズなんだよといわれてしまえば返す言葉もないが、ジャズ特有のグルーヴ感がもう少し欲しいといったら贅沢だろうか。
そんな中で、私は僅か3分にも満たない「Tveklost」や「Makuschla」といった静謐な曲にやすらぎを感じている。
まるで風に揺れる小さな花を見ているような気持ちになるのだ。
もちろんこういった曲はアルバムの主題ではない。
しかしこういった曲が、ほどよい間隔で挿入されているために、全体のバランスが整って聞こえるのである。
先日知り合いの家に行き、ジャズを聴きながらみんなで酒を交わした。
私は数枚のCDを持参したのだが、その中にこのティングヴァル・トリオの「VATTENSAGA」もあった。
このCDがかかる前までは、バルネ・ウィラン、ケニー・バロン、スコット・ハミルトンなどがかかっていたが、このティングヴァル・トリオがかかったとたん、友人の一人がポツリと「このCD、いいね」と呟いた。
そんな風に一瞬にして心を捉えるなんて、なかなかありそうでないことだ。
良質なピアノトリオの底力である。