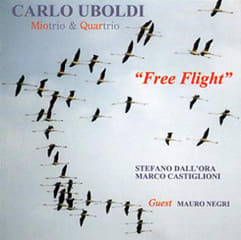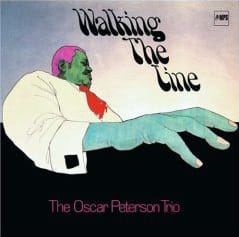ベニー・ゴルソンといえばファンキーを絵に描いたような人だ。
どの曲を聴いても「モーニン」を連想してしまうのだから半端じゃない。
これは決して否定的な意味ではないので誤解しないでほしい。こういう人がいるからジャズは面白いのだと思う。理屈なしに楽しみたい時は実に重宝する。大音量で聴いていると落ち込んでいた気分までも高揚する。
このアルバムはメンバーもベストだ。
まずジャズ・メッセンジャーズの親分、アート・ブレイキーがいる。ファンキージャズの場合、彼がいれば文句はない。いつものようにナイアガラロールは快調だ。
ベースはポール・チェンバース、この人もこういう類のジャズには定番だ。この二人のリズムセクションの起用で、アルバムの制作意図は既に八割方成功していると思っていい。
ピアノはレイ・ブライアント。トリオ演奏の「ゴールデン・イヤリングス」などしか聴いたことがない人にとってはちょっと意外かもしれない。しかし、この起用がピタリと決まった。ブライアントはもともとブルージーなセンスの持ち主であるが、その中においても彼独特な繊細さと大胆さが随所に現れており存在感ある演奏を披露している。
ゴルソンの相手役は「ブルースエット」でもおなじみ、コンビを組むカーティス・フラーだ。彼のトロンボーンがいるお陰で全体の音に厚みが増す。この音の厚みこそがファンキーなムードを作り出す原因なのかもしれない。
さて肝心のベニー・ゴルソンだが、彼のテナーは基本的に重心が低い。最初は冷静にスタートするが、吹き続けていくうちに息継ぎのタイミングが伸びていき、フレーズが流れるようにうねり出す。これこそが彼のテナーなのである。これが嫌いだという人もいるだろう。しかしこの吹き方のお陰で聴く者も興奮状態に陥っていくわけだ。少なくとも私は嫌いじゃない。
映画『ターミナル』で主役のトム・ハンクスが最後にもらうベニー・ゴルソンのサイン、まだ健在でいることの証だ。
私もニューヨークで彼の生のステージを観たいと思った。