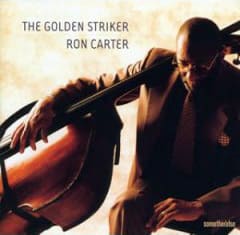このジャケットを手にとってどれだけ眺めただろう。
ジャケットだけをとったら間違いなく私のベスト10には入る作品だ。
街で楽しそうに手をつないでいる今どきのカップルを見ると「フン」と思うが、ここに写っているカップルにはうっとりしてしまう。これも偏見だといわれれば返す言葉もないが、もしこんなカップルを街で見かけたら拍手を贈るかもしれない。
以前はこのレコードジャケットをいつも額縁に入れ部屋の壁に掛けていた。
重要なのはテディ・ウィルソンの演奏だが、このジャケットを見ながら聴くとなぜかとてもいい気分になった。嘘だと思ったらあなたも試しにやってみるといい。古さ・渋さの中にも何ともいえない哀愁が漂ってくるのがわかると思う。
録音も楽想も古いがテディ・ウィルソンの職人技は永遠に新鮮だ。
いつのことだったかは覚えていないが、このテディ・ウィルソンがジャズクラブで演奏している映像を見たことがある。
彼は姿勢良くピアノの前に座り、ほとんど鍵盤を見ることもなくゆったりと弾き出した。その貫禄たるや圧倒的な存在感があった。さすがにレスター・ヤングやベン・ウェブスターといった大物と渡り合ってきただけのことはある。
この映像で私はイチコロだった。そこにもってきてこのジャケットだ。
こんな嬉しい思いをさせてくれる音楽はジャズ以外にはない。