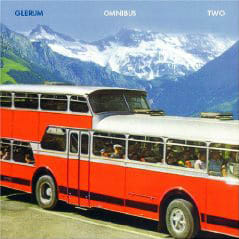昨日、大量にあるレコードの一部を処分した。
とはいっても処分したのはジャズのレコードではない。
以前聞いていたロックやソウルなどのレコードだ。
もう何年も聴いていないので棚の中で半ば骨董品化していて、相当カビ臭くなっていた。
それを端から確かめてみると、出てくる出てくる、懐かしさのオンパレードだ。
古いのはエルヴィスから、ストーンズ、クリーム、ツェッペリンなどなど、数えだしたら切りがないくらいである。
その一枚一枚に想い出が詰まってはいるものの、今となっては無用の長物である。
ここはすぱっと割り切って、仕分け作業を行う。
段ボール箱を脇に置いて、いらないものはこの中にボンボン投げ込んでいく。
トム・ウェイツもクラプトンも、EW&Fも、み~んな段ボールの中に消えていった。
その数200~300枚といったところ。
それでも棚のごく一部に空きができただけだった。
これが何ともむなしいのである。
こういったポピュラー系のレコードは処分してもほとんどが二束三文だ。
買ったときは一枚2000円~2500円程度はしたはずなのだが、売るとなれば一枚約10円が相場である。
何と悲しい運命なのだろう。
ロイ・ブキャナンが演じる「メシアが再び」の切ないメロディが頭をよぎる....。
それに比べジャズのレコードはかなり様子が違う。
オリジナル盤でなくとも、そこそこの値が付くのである。
それだけ需要があるということだ。
そういえば仕分け作業をしている最中に、ピーター・インドの「LOOKING OUT」がポピュラー系のレコードに混じって出てきた。
「おっ!やった~!」と、一人で感激する。
しばらく見ないと思ったら、こんなところにあったのだ。
もともとレア盤だが、いかにもレア盤らしい復活である。
これなんかはかなりの値段が付くアルバムではないかと思う。
早速聴いてみる。
バイオリンとギターとベースの弦がいろいろな風景をつくり出していく。
これを聴くと、ジャンルに囚われない世界が拡がっているのに気づかされるのである。
ジャズって、いったい何だ?
今さらながら、そんなことを考え込んだ。