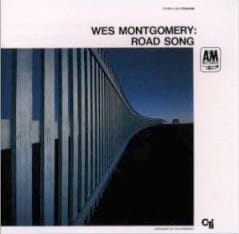パパッパ、パッパパッ、パァ~パッ。で始まる切れのいい明るいリズムとデックスの大らかさが好きだ。
思わずうきうきしてくる。こんな感情は他のサックス奏者からは得られない。根は相当明るい人だ。少なくともこのアルバムの録音時はハイだった。
ただこの時代(50年代)の彼の録音はメチャクチャ少ない。聞くところによればドラッグ漬けで身も心もボロボロだったらしい。もちろん当時のジャズマンのほとんどがそうだったのだから特別な話ではない。ある意味ジャズマンとして真っ当な暮らしをしていたわけだ。しかし、だ。そんな状況にあってこの明るさは特別だ。これが彼の彼たる所以である。
彼と並んでピアノのケニー・ドリューがまたいい。自分の出番が来た時の受け継ぎ方などは実にスムースで、全体の雰囲気をさらに盛り立てていく。私の好きなリロイ・ヴィネガーも相変わらずズンズンズンとウォーキングベースを唸らせる。バックとの相性がいいとこのような名盤が生まれるわけだ。これは名作揃いのベツレヘムの中でもかなり上位にランクされる作品だろう。