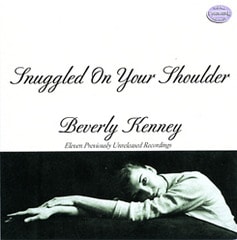うまい!というのはこういう人を指すのだ。
エラにしてもサラにしてもあんまり大物すぎる?のであまり聴く機会もないのだが、カーメン・マクレエも久々に聴いてみるとやっぱり納得させられてしまう人の代表格だ。
まぁ、貫禄勝ちといった感じである。
クールなレイ・ブラウンのベースに乗って「Nice Work If You Get It」が始まる。その第一声を聴くだけで、こりゃあいいなぁ~、と実感すること請け合いだ。
このくらいのテンポ(ミディアムテンポ)が一番スイング感を感じる。
しかも歌詞の一音一音をはっきり発音しているせいか曖昧なところが一つもない。
そこに単音をくっきり出すジョー・パスのギターが絡むのだから、まるで絵に描いたような出来映えだ。
しかし、何といっても彼女の真骨頂はバラードである。
特に「Inside A Silent Tear」は私のお気に入りだ。
彼女の歌声は、まるで温かい海風が頬を撫でるように通り過ぎていく。
ギターとの絡みも抜群。
極端に感情を出すでもなく、かといって押さえすぎず、聴き手と絶妙な関係性を築いている。
こうしたところが「うまい!」といわせる要因だ。
アルバムも後半になるとずいぶんポップな感じになる。
ズート・シムズも登場し、いつになく爽やかテナーを披露する。
こちらも聴きごたえありだが、私はやはり4ビートの曲に魅力を感じる。
やっぱりこういう大物チームの演奏はど真ん中で聴きたいのだ。