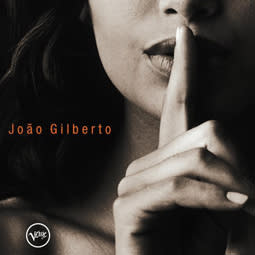私がジャズを聴き始めたのは1975~76年頃だったと思う。
最初はマイルスのカインド・オブ・ブルー、ロリンズのサキソフォン・コロッサス、モンクのブリリアント・コーナーズなどの純然たるジャズを繰り返し聴いていた。
しかしその当時は、そうした4ビートのストレート・ジャズは何だか古くさいというイメージで捉えられていたように思う。
事実、そうしたジャズを人に聴かせてもウケが悪かった。
「なに、これ?」「これのどこがいいの?」と散々な目に遭ったこともしばしばで、それ以来、ジャズは一人で楽しむものという感覚が私の中で育っていった。
だいたい当時はクロスオーバー・ジャズ(後のフュージョン)がすごい勢いで台頭してきており、ウェイン・ショーター率いるウェザー・リポートや、チック・コリア率いるリターン・トゥ・フォーエバーなどが大暴れしていた頃だ。
そのほとんどがエレクトリックなサウンドで、ロックの連中も絶対かなわないほどの神業テクニックを誇っていたし、それがジャズの底力なんだとばかり、ジャズの本質からはかけ離れたにわかジャズファンも数多く誕生したのがこの頃でもある。
まぁ、私も実際よく聴いたし、その類のレコードもずいぶん集めた。コンサートにもよく行った。
しかし今のスムース・ジャズもそうだが、聴いていて気持ちがいいというメロディ中心のジャズからは人間的な情念を感じない。
もちろんそんなものを狙った音楽ではないのだろうから、そこに情念なるものを求めるのはおかしいわけだが、曲がりなりにもジャズと名がついている以上、私のような人間はちょっぴり期待してしまうのである。
そんな中で出会ったのが、このマル・ウォルドロンのレフト・アローンだ。
私はこのアルバムを知って、ストレートアヘッドなジャズの世界に舞い戻ってきたといっていい。
このアルバムはその情念の塊だ。
但し初めての人にはあんまり度が過ぎるので、ジャズはこんなに暗い音楽なのかと勘違いするかもしれない。
ただ暗いのと情念がこもっているという概念は全く違うものである。
ここをきちんと聴けるようになって初めて本当のジャズファンといえるのではないかと思っている。
このアルバムは、チョーがつくくらい有名な「Left Alone」が収録されているため、何だかその一曲のためだけにあるような盤として捉えてしまいがちだが、何度も聞いていると他の曲もなかなか聴きごたえがあることに気づく。
特に「Cat Walk」や「You Don't Know What Love Is」はすこぶるいい。何度でも聴き直したい気にさせる演奏だ。
これらの曲はまるでピアノとベースのデュオ作品のようにも聞こえる。
それだけベースのジュリアン・ユールの存在が大きいのだ。
「Left Alone」におけるジャッキー・マクリーンのアルトもさることながら、その重いベースの一音一音にもたっぷり情念がこもっている。
そこを聞き逃さないことだ。