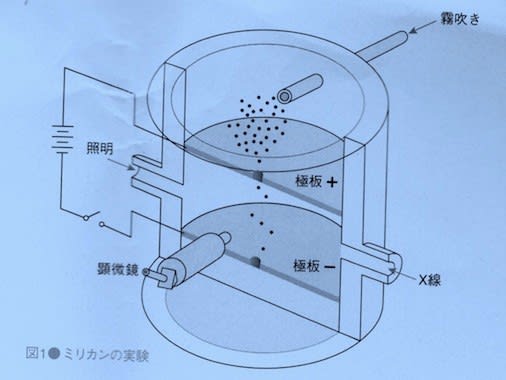ゼノンは古代ギリシアの自然哲学者で南イタリアのエレアの人である。「ゼノンのパラドックス」は時間、空間、運動を考察するためにアリストテレス以来、多くの哲学者が取り上げてきた。それを紹介し、対する庵主の「反論」を示した。ゼノンのパラドックスは幾つかのバリエーションがあるが、次の4つに分けられる。読みやすいように著者が整理・編集している。いずれも、無限分割についての矛盾をどのように解決するか問題だが、純粋にロジックで反論できることをしめす。なお、ゼノンのパラドックスはこれ以外に「競技場」のものがあるが、昔から何がパラドックスかよくわからないとされているので割愛した。
(I) 中点分割の前進型
(II) 中点分割の後進型
(III)飛ぶ矢の静止型
(IV) アキレスと亀の競走型
(I) 中点分割の前進型詭弁とそれに対する反論
『いまA点からB点に矢が放たれたとしよう。矢はB点の半分の点にまで到着したとしても、更に残りの半分の半分にも到着しなければならない。更にその残りの半分の半分の半分にも到着しなければならない。このようにして、矢はB点にまでに存在する無数の中間点を通過しなければならず無限の時間を要することになる。すなわち矢は永遠にB点には到着しない』
中間点は頭で考えると無限にあり、関所で通行税を払うように通過する中点ごとに時間をかければ、無限大の時間が必要となる。しかし点を通過するに要する時間は0なので、トータルでも0である(∞ x 0 = 0)。必要なのは点と点の間の距離を移動する時間の和である。間隔も分割すれば無限にあるではないかと言われかもしれないが、トータル時間は無限等比級数の和となり、有限値に落ち着く(ただし、これは数学的な便法としてそのように定義しただけで、ゼノンのパラドックスの解決にはなっていない)。多くの解説書ではこのように説明しているが、パラドックスの反論としては、ロジックがないので、はなはだおもしろくない。そこで論破のロジックをいろいろ考えてみた。
最初の中点分割のパラドックスは次のように簡単に論破できる。ゼノンは中点が無数に存在するので、B点に到達しないのではないかと言う。しかし、この矢は半分の中間点(M点)に飛んで来るまでにも、無数の中間点という同様のジレンマ(困難)に出会ったはずである。それを乗り越えて半分以上飛んだとしている。どのようにして、このジレンマを克服したのかは分からないが、後半でもそのジレンマが同様に乗りこえられないとする理由は何も考えられない(前半と後半の空間は等価)。すなわち、ゼノンが心配しないでも矢は地点Bに無事に到達できる。
(II) 中点分割の後進型詭弁とそれに対する反論
『上と同様にA点からB点に矢が放たれたとする。AB間の半分の点まで到着するには、その前の半分の半分に着いていなければならない。更にその前の半分の半分の半分にも同様に着いていなければならない。このようにして、矢は限りなく越さなければならない無数の中間点があり、矢は全く進み得ない』
ゼノンはうかつにも矢を飛ばしたために、前の詭弁ではあっさりと論破された。そこで今度は飛ばさない問題を考えた。ある時間で状態αのものが、全く同じ時間で別の状態βになって仕舞う矛盾はその中間の論理が間違っているからである。そもそも因果律が逆転しており、矢はジレンマに出会って動かなくなるはずなのに、ここではそれに出くわす前に予想意思があるかのごとく、最初からA点で動かない。これは次のように論破する。
ゼノンの説によると、矢は飛ぶことによって「無限中点」の困難に遭遇して飛べなくなるという事になる。もし、まったく飛ばないのであれば、ゼノンの前提とした無限中点との遭遇はそもそもおこらない。命題における論理を組み立てた条件そのものに、結論が抵触している。それ故に、この命題の結論は偽である。矢は飛ぶか飛ばないかの2択であるので、「矢は飛ぶ」が正しいことになる。
(III)飛ぶ矢は静止している詭弁とそれに対する反論
『どんな物もある瞬間に一つの場所を閉める場合は、静止している。矢は飛んでいる間のどの時間においても、ある一つの場所を占める。ゆえに矢は飛んでいる間のどの時間においても静止している。飛んでいる間の時間は、そのあいだの瞬間から成立している。ゆえに、矢は飛んでいるあいだじゅう静止している』
今度は矢を静止させて難問を吹きかけてきた。確かに超高速度カメラで飛ぶ矢の映像を撮り、普通のコマ送り (1秒24コマ)で映写すると、矢は空中で静止しているように見える。静止した矢と飛んでいる矢の印刷写真は全く区別できないが(厳密には少しブレている)、後者は運動量を持っているところが違う。写真には矢の運度量は映らない。画像的な存在比較だけしていると、ゼノンの陥穽におちいってしまう。これは次のように時間をずらす思考実験をしてみると誤りがすぐわかる。
ある時間(瞬間)に矢の存在した場所をAとする。1秒後に矢が存在する場所をBとする。もしBがAと同じなら、すなわちA = Bなら、これはゼノンの結論と一致するが、矢は飛んで移動しているという前提には反している。一方、A ≠ Bならゼノンの結論と相違するが、矢は飛んでいるという前提とは抵触しない。どちらが正しいのだろうか? 結論は前提をもとに導き出されたはずなので、論理学の世界では前提をアプリオリーに正として優先しなければならない。すなわち、A ≠ Bが正しい。矢はいつも静止しているという結論は間違いである。
ゴタゴタ理屈をつけないでも、経験法則でA ≠ Bに決まっているが、最初の命題に矛盾があり、このような思考実験で簡単にわかる。ただその矛盾の構造を説明しようとすると、これも難しい。このパラドックスに対してアリストテレスは「時間は瞬間の集まりからなるのではない」と主張した。瞬間をいくら集めても持続的な時間は生まれないとして批判した。もっとも、これで批判になっているのだろうか?
(IV) アキレスと亀の競走詭弁とそれに対する反論
『アキレスと亀が徒競走をすることとなった。アキレス(速度Sa)の方が足が速いのは明らかなので、亀(速度St)がハンディキャップ(Lメートル)をもらい、いくらか進んだ地点(地点Aとする)からスタートすることした。スタート後、アキレスが地点Aに達した時には、亀はアキレスがそこに達するまでの時間分だけ先に進んでいる(地点B)。アキレスが今度は地点Bに達したときには、亀はまたその時間分だけ先へ進む(地点C)。同様にアキレスが地点Cの時には、亀はさらにその先にいることになる。以下同様にアキレスは、いつまでたっても亀に追いつけない』
アキレスと亀のパラドクックスもよく出てくる有名な話だが、これも考え始めると意外と難しい。
アキレスが亀に追いつくのに必要とする時間 T = L/(SaーSt)
これは小学3年程度の算数。
次にゼノンが上で述べたシーケンスで計算していく。
アキレスが A地点に到達するに要した時間Taは
Ta = L/Sa
その間亀の進んだ距離
Lb = Ta x St = (L/Sa) x St
アキレスが地点Bに到達するに要した時間Tb
Tb = Lb/Sa = L/(Sa)^2 x St
その間に亀が進んだ距離
Lc = Tb x St = L/(Sa) ^2 x St 2
アキレスが地点Cに到達するに要した時間Tc
Tc = Lc/Sa = L/(sa)^3 x St2
………….以下同様にこれの繰り返しで、アキレスが亀に追いつくまでのトータルの必要時間Tは、
T = Ta + Tb + Tc + Td ………+ Tn= L/Sa (1 + St/Sa + (St/Sa)^2 + (St/Sa)^3 + ……(St/Sa)^n) = L/Sa x (1 + K + K^2 + k^3 +………K^n)=L/Sa X {1-k^n/(1-k)} ここで K = St/Sa
このあたりは高校程度の等比級数の和の計算。
nが無限大の時はT = L/(Sa-St)となり最初の小学生の計算結果と同じになる(ただし、前に述べたようにこれは数学上の都合でそのようにしているだけ)。
ということは、アキレスと亀の話の途中までは、まじめで正当なことを言っていることになる。おかしいのは最後のアキレスが亀に追いつけないと言ったことであるが、これを正攻法で反論するのは、なかなか面倒なので、ここでは奇手を使う。
アインシュタインの相対性原理では、どの慣性系でも物理法則は同じとされている。そこでアキレスと亀が両方とも動く歩道に乗っていると考える。動く歩道はランナーの走る方向とは反対に亀の速度で動くとする。歩道のそばの観察者にとって、同じ空間に静止する亀にアキレスが近づく形になる。アキレスの速度は少し減るが、亀はいつまでも停止しているので、静止した目標に矢を飛ばしたのと同じ話になる。すなわちアキレスは亀に追いつくことができる。
まとめ
このように論をすすめてみると、ゼノンのパラドックス1~4は反論を予想して、順序正しく並べられていることがわかる。ゼノンの問題を空間・時間論からもういちど考察し直してみたい。
線分ABの点Aから点Bまでをn個の点で均等に分割する。矢が飛ぶに要する時間Tとする。
T =n x Δt + (n+1) x ΔTn、 Δtは点を矢が経過する時間、ΔTnは各区間を経過する時間とする。
点は長さのないものと定義されているのでΔt = 0である。一方、ΔTn = (k x l)/(n + 1) ここでKは常数(速度の逆数)でlは線分ABの長さ。よって T = k x lとなる。
数学的には、途中で線分上にいくつ点をとろうと、パラドックスの入り込む余地はなさそうである。もっとも、ゼノンはこのような算数計算を理解できないと、うそぶくであろうから、本論で述べたような詭弁にたいするレトリックルによる反論が必要なのである。
ゼノンの中点分割でも均等分割でも原理的には同じ理屈であるが、中点分割法では計算がかなり複雑になる。
飛ぶ矢の問題でA点からB点までの移動に要する時間は、矢の秒速を5mとすると、距離を速度で割って10/5=2秒となる。今、すべての中点を経る時間の総和を計算するとT=Σ(1+(1/2) + (1/2)^2 + (1/2)^3+ ……+ (1/2)^n) n=無限大の時はT=2と勝手に定義している。しかし、これを計算機で実際計算させると、例えスーパコンピューターであろうと、人(プログラム)がn値(整数)を増やしていく限り、いつまでも計算は終わらず、途中の答えは1.9999999999……と小数点以下の9が延々と続き、決して2にはならない。限りなく2に近いが2ではない数が続く。ゼノンは「ずぼらな繰り上げ計算はやめて、ちゃんと最後まで計算してくれよ」と主張しているのである。すなわちゼノンのパラドックスを現代風にアレンジすると、理論計算とコンピュター計算との違いを指摘したようなものだ。
このジレンマから抜け出すためには、理論計算を擁護する理屈を考えるのではなく、根本的な仮説導入が必要と思われる。ゼノンのパラドックスの根本には、空間の無限分割可能の思想がある。そこで、多くの物理学者が指摘したように、空間そのものに条件を付けねばならない事になる。頭の中では空間は無限に分割できるが、素粒子やクオークよりさらに桁違いに小さな無限小に近い空間(距離)。そんなものは本当にあるのだろうか?
物理学の素粒子論や量子論によると空間や時間を連続的な量とすると、無限大の困難が常に付きまとう。そこで量子論ではエネルギーや電荷や角運動量がとびとびであるように、空間や時間もとびとびと考えるようになってきた。湯川秀樹博士が非局所場の理論を進めていた頃は、長さの最小単位は10-13(マイナス13乗以下同様)cm(これを1フェルミあるいは1ユカワという)。時間の最小単位は、この長さを光がよぎるのに必要な10-24 秒くらいと考えられていた。さらに統一場の理論などが出て、宇宙の最小の長さは10-33cmで最小の時間は10-44 秒であると言われる。
空間や時間に、これ以上分割できないディジタルな最小単位ΔLを考えると、ゼノンのパラドククスにも気楽に付き合うことができる。空間の距離はすべからくΔL x N(整数)で、きっちりとした10メートルなどは頭で考えた数値で、実際は存在しないのである。さらに時間の最小単位はΔLを光速Cで割ったΔL/Cとなる。ゼノンの矢の先端は最小空間(距離)の端から端をジャンプして移動するのである。最小空間が滑らかにつながっているのか、ギクシャクとつながっているのかわからないが、ともかくそれ以上、分割できないから、めんどくさい無限中点など考えなくても良い。ジャンプしている間の状態はどうなっているかと聞かれると困るが、量子世界ではおそらく確率波になって伝わるのではないかと勝手に考える 。朝永振一郎先生が量子力学の不思議な世界を描いた『光子の裁判』というエッセイがある。量子の一つである光子が、ある点から別の点まで移動したとき。途中の「経路」が存在するかいなかをテーマにしている。マクロな矢の先端も究極はミクロの粒子でできている。
蛇足ながら申し添えると、ミクロな世界では量子論が必要になってくる。量子力学では不確定性原理に基づく方程式がある。それは ΔX (長さ)x ΔP(運動量)= h (プランク定数)で、 ΔXが無限小になると運動量が無限大になり、運動量が無限小になると長さが無限大になる。それゆえ、そのどちらも0にはなれない。これからも飛んでいる矢がある点(瞬間)で静止(運動量0)する事はないと言える。
ゼノンには空間・時間構造がこのようになっていることを説明し、矢はトビトビに線分上を有限回飛んで、無事に目標に到達あるは飛び越えると伝えればよい。これをゼノンが信じるか信じないかは問題外である。ゼノンも、人々が信じ難いことを2500年以上も宣え続けてきたのだ。
参考図書
ジョセフ・メイザー 『ゼノンのパラドックスの謎』松浦俊輔訳 白楊舎 (2009)
追記
2019/04/20
榛葉豊『頭の中は最強の実験室』化学同人 2012
この本では「無限」の定義を二つに分けている。一つは実無限でもう一つは可能無限である。実無限は最小単位としての点で、これが無限個集合して線を形成すると考える。可能無限は操作(人の思考操作)によって生ずるものである。さらに微分・積分は実無限の概念であるとしている。ただ無限の和が有限になるというのは積分での勝手(便宜的)な「定義」で、ゼノンのパラドックスの解決にはなっていない。
2019/04/23
運動とは物が一点に止まっていないことであると定義すれば、もともとゼノンのパラドックスは成り立たない。それが線や点にこだわって論理を展開するので、矛盾が生ずることにハタと気がついた。そもそもゼノンのパラドックスに出てくる、「矢」、「点」、「線」、「中点」、「飛ぶ(運動)」などに、何の定義もなされておらず、読者がそれぞれ勝手な概念で論じようとするから、陥穽におちいるのである。
2019/07/15
九鬼周造の「時間ノ問題ーベルグソンとハイデッカー」に次のような記述がある。 『運動は一点より他点への経過である。前進である。飛躍である。運動を分割することはできない。分割し得るものは経過した空間である。相継ぐ位置である。運動を静止した位置の系列に願訳することは運動に静止を命ずることである。運動以外のものとなることを命ずるのである。ツェノンの逆説は運動と運動者の経過した空間との混同に基いている。「経過する運動」と「運動の経過した位置」とは仝然異ったものである』と。
2019/12/20
光の二つの性質(波動性と粒子性)を統一する理論がアインシュタインの1905論文の一つである。時間の連続性と不連続性の矛盾を統一する仮説(思考実験)が必要とされている。
2020/08/13
0.9999999....は定義として1ではなく数学的な論理といして1であるとする考えもある。ウイキペディ(https://ja.wikipedia.org/wiki/0.999...)を参照されたい。
2020/01/08
カントは先天的であるものは真実であると述べた。ヒトには先天的に時間、点、線の概念が備わっているのだろうか? 動物行動学者のコンラート・ローレンツは、それに関してヒトにも進化論的認識があると述べている。
カール・ポパー、コンラート・ローレンツ 『未来は開かれている』辻 瑆訳 思索社