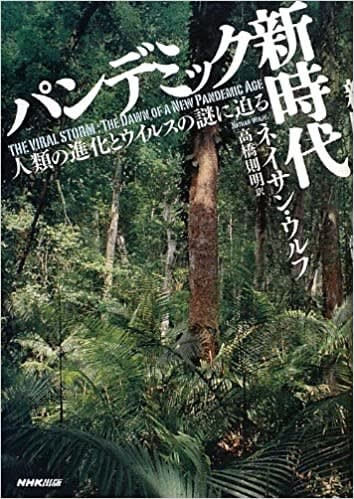ネイサン・ウルフ著『パンデミック新時代 :人類の進化とウィルスの謎に迫る』NHK出版、 2012年
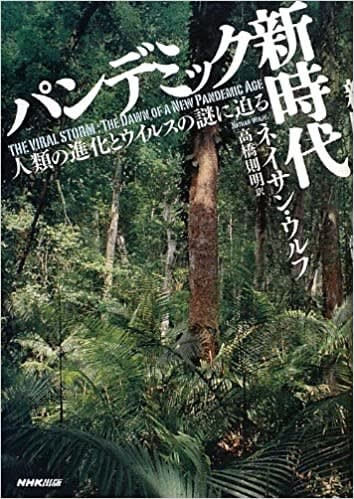
この著者のネイサン・ウルフ (Nathan D. Wolfe)(1970~)は感染学・免疫学の専門家である。スタンフード大学客員教授。 Global Viral(グローバルウィルス予測計画)はヒトに感染するウィルスの拡散を監視し、パンデミックを早期に警告するシステムであるが、これの設立者でもある。
ウルフによると人間の感染症の約70%が動物に由来するという。それも霊長類やコウモリ、げっ歯類をはじめとるするほ乳動物からきている。新型コロナウィルス(COVID-19)はセンザンコウが、SARSはハクビシン由来のウィルスによる感染ではないかと言われている。
この書は、ヒトの進化と感染症微生物とのかかわりの歴史から話が始まるが、庵主の感想や考えも入れながら内容を紹介していく。
雑食は霊長類の中でヒトの特性かと思われていた。しかし伊谷純一郎先生(1926-2001)らの研究によって、そうではない事があきらかにされた。たとえば、チンパンジーは、いかもの食いで300種の植物、23種の昆虫を食べるそうだ。さらに彼らの縄張りに棲んでいる様々なサル類、カモシカやイノシシ、イタチなども手当たりしだいに食べる。
ウルフらも、チンパンジーとヒトの共通祖先は森で集団で狩りをして他の霊長類を食べていたと述べている。鵜澤和宏は、現代人は肉を全栄養摂取量の20-90%もとっているのに、チンパンジーはわずか5%程度としている。
これ以来、ヒトの祖先は血まみれの獲物から様々なウィルスの感染を受けるようになった(ライオンやオオカミのような肉食動物は、こういったリスクの少ない獲物の処理法をしているのだろう)。食物連鎖の頂点にいる肉食性の大型動物ではウィルスの「生態濃縮」がおこる。ウィルスー微生物ー小型動物のすべての食物連鎖のウィルスが体内に入って寄生する可能性がある。
類人猿は生物多様性の高い森に住んでいたが、ヒトの祖先は森からサバンナに進出した。ここで遺伝子のボトルネックがおこり、遺伝的多様性が減少するとともに、身体に寄生あるいは共生するウィルスの種類も減少した。そしてそれに対する抵抗性も減少するか喪失した。
森から出た人類の祖先は、火をおこす技術を発明し、料理を始めた。これによって細菌による食中毒がなくなった。火のおかげで、利用できる食物のレパトリーが格段に増え保存が効くようになった。この革命的なイノベーションによって、人類の人口は急速に増えた。約1万年前から5000年前に人類は狩猟採集時代から牧畜農耕時代に入り、一部は都市に住み始めた。
アフリカで類人猿とともに進化した熱帯の寄生虫や病原微生物は、人類が気温の低い温帯や寒帯に移住するとともに生き残ることができなかった。このことが人間の集団を衰弱させず、人口を増やす条件の一つになった。
じめじめした森から「清潔」な環境に移った人類に、病原微生物の脅威がなくなったかというとそうでもなかった。熱帯地方では蚊を媒介とするマラリアが毎年、約200万人もの生命を奪っている。ヒトの唯一の遺伝的な対抗法は、鎌形赤血球遺伝子といった半端な工夫でしかなかった。森→サバンナ→乾燥地帯へと進出した人類を後もどりさせないバリアーがマラリアである。マラリアを媒介する蚊は森林に限定させずに、水たまりのあるところならどこでも生息できる。
アラスカのような極寒の地まで版図を広げて住まいを拡大した白人が、結局熱帯に大量に住み着けなかったのはこれが原因である。
おそらく、森に住んでいた人類の共通祖先は現在のチンパンジー同様に、マラリア寄生虫に対する抵抗性を身体に持っていたのだろう。しかし、先程述べたボトルネックの際にこれを失ったか、あるいは人類拡散の過程でこの抵抗力をなくした。
それでも、病原微生物のキャリアーである他の動物に接触しなければ問題なかった。
ところが人間は大量の家畜を身の周りにおく生活をはじめた。家畜は飼いならされる前から、それぞれ微生物レパートリーを持っていたので人間と最初に接触した時期から、お互いにそれらを交換しはじめた。さらに野外動物が飼育動物にウィルスなどを感染させ、それがさらに人に感染する。
トリインフルエンザの場合は鶏舎のニワトリが感染してさらに人に感染する。ウシは天然痘の、ニワトリやブタはインフルエンザの、ラクダはMERSのウィルスをヒトに媒介した。家畜だけでなくペット動物も人間との濃厚接触で病原微生物を感染させている。
栽培植物も野外動物からの微生物感染の手助けをした。例えば、農家の近くでマンゴーを栽培すると、これにニパウィルスの保菌者であるコウモリがやって来て糞をする。それをブタが食べて発病し、さらに人にウィルスをうつす。ニパウィルス症は主として脳炎を発症させる死亡率50%の恐ろしい伝染病である。
病原微生物に対する抵抗性が弱くなった人の集団に、なにかのはずみで感染症が広がったとする。その集団が小さいと、たちまち罹る人は罹り死ぬ人は死んで、エピデミックは終わる。エピデミックで滅んだ無数の村や、小さな町の記録は残らない。それをたちまちカバーするほど、ヒトの繁殖力も大きかったのだろう。
病原微生物もほかの動物に移り住むのでなければここで滅びる。その集落は多大な損害を被ることになるが、その微生物に比較的強い体質(遺伝子)の子孫が残る。形態の変化こそないが一種の進化がおこる。
これはまだ交通の発達する前の時代の話であるが、鉄道、道路、飛行機、船など交通手段によって地球は狭くなった。そこでは、人も病原菌も大陸や海洋を瞬時で渡り歩くことができる。ウィルスにとって小さなの人口を相手にしているのではなく、数億から今では70数億もの巨大な数の被感染プールが出現したのである。ウィルスにとっては申し分のない資源だ。
ここから人類の歴史はパンデミックとの戦いの歴史となった。人類がいままでにおこした戦争での死者よりも、パンデミックの犠牲者の数の方がづつと多い。
森を脱出したホモサピエンスはまた森に侵入しはじめた。森林伐採や鉱物資源開発と野生生物取引の拡大のためである(2020/04/07京都新聞夕刊4面参照)。発展途上国では人口爆発により、多くの労働者が森林地帯に入り込み食料になる野生動物の量が増えた。これらには絶滅危惧の問題になっているキツネザルなどが含まれる。
森で鳴りを潜めていた諸々の微生物が、再びヒトと向き合うようになった。生物多様性の危機だけでなく、動物由来の感染症の拡大リスクが増えた。その結果、世界にひろまったのがHIV(チンパンジーのSIV起源)でありエボラウィルス(コウモリ起源)である。COVID-19の原因ウィルスSARS-CoV-2も武漢の海鮮市場付近が発生場所とする説が多い。コウモリーセンザンコウーヒトという感染経路の可能性が論じられている。
いまや、東南アジア、アマゾン川流域、中央アフリカなどのウイルスのホットスポットがエピデミックやパンデミックの感染起源になっている。
人獣共通感染症の微生物は動物から人に感染するだけでなく人から動物にも乗り移る。人に集団免疫が形成されると、ウィルスは自分が絶滅するので、他の種類の宿主を探しているのである。新聞報道(京都新聞2020/04/07朝刊8面「NYのトラも」)によると米ニューヨーク市のブロンクス動物園で飼育されているマレートラやライオンが新型コロナウィルスに感染している事がわかった。せきの症状があり(多分肺炎になっているのだろう)、食欲も減退している。飼育員からトラに感染したとされている。
日本における<森ー野生動物ー感染症>といった文脈での研究は少ない。多分、日本では大陸諸国と違い、動物食は少なくタンパク源として魚介類を取っていたからだ。
ただ鎮守の森のお稲荷さんに狛狐(こまぎつね)を飾るのは、感染病の封じ込めの印かもしれないと庵主は思っている。森の樹木を切り倒して分け入ると恐ろしい病原菌がいるぞという伝承なのではないだろうか? ダスティン・ホフマン主演の映画「アウトブレイク」の中でアフリカの呪術師の次の言葉を思い出すできであろう。「本来人が近づくべきでない場所で、樹木を切り倒したために。目を覚ました神々が怒って罰として病気を与えたのだ」と。
ほかの参考文献
『食文化を考える』「太陽」5月号 (1980) No.255 P120.
鵜澤和宏 『ヒト化と肉食ー初期人類の採食行動と進化』(肉食行為の研究:野林厚志編)平凡社 2018
Youtube(TED Talk https://www.ted.com/talks/nathan_wolfe_the_jungle_search_for_viruses?language=ja:『ネイサン・ウルフのウィルス退治』)でウルフの素顔が見れる。