
ユキヤナギの葉に集合するルリクチブトカメムシの幼虫にクモ(ササグモ?)の幼体が乗っかっている。ルリクチブトカメムシの成虫は瑠璃色の光沢が美しいカメムシ。多くは草地に見られ、イチゴ類やヤナギ類につくカミナリハムシ類を好んで捕食するとされる。京都府では少なくなり「要注意種」となっている。
八方へ走りにげたり放屁虫 阿波野青畝

ユキヤナギの葉に集合するルリクチブトカメムシの幼虫にクモ(ササグモ?)の幼体が乗っかっている。ルリクチブトカメムシの成虫は瑠璃色の光沢が美しいカメムシ。多くは草地に見られ、イチゴ類やヤナギ類につくカミナリハムシ類を好んで捕食するとされる。京都府では少なくなり「要注意種」となっている。
八方へ走りにげたり放屁虫 阿波野青畝
ヴァイバー•クリーガン-リード『サピエンス異変』ー新たな時代「人新世」の衝撃 (水谷淳、鍛原多恵子訳)飛鳥新社 2018年

この書は、人類がその歴史において行動、生活を変化させて来た過程で、身体の構造や機能にどのような影響があったか、さらに未来において文明諸国でそれがいかなる形で表われるかについて述べている。二足歩行による移動を生活の中心にしていた人類は農耕革命、産業革命、情報革命を経て歩く事が少なくなり、様々な身体の不具合を訴えるようになった。腰痛、近視、糖尿病、高血圧、心臓疾患やある精神疾患は、歩かなくなった人類が自ら生み出した人新世における新疾病である。この著者の意見では、ひたすら歩くという事によって、これらの予防や治療ができるということである。
筆者は現代人に日常的な早歩きかランニングを進めている。さらにスクワット(しゃがみこみ運動)も身体によいとしている。また身体のなかの生態系のためにも、緑地や自然環境に、できるだけ触れ続けることを進めている。そこで何種類もの果物や野菜を含む食事をして、腸内生物の多様性を高めて健康を保つように努める必要がある。
「ウオーキングは魔法の特効薬である」と著者のリードは言う(そういえば徘徊老人はなんだか健康そうだ)。このように、この書はいわば常識を展開した凡書のようであるが、「余談」で述べられているいくつかの挿話が結構面白い。たとえば「ニンジンがニンジンでなくなった」の一節では、生産の効率ばかりを考えて促成栽培されるニンジンが、昔のような優れた栄養価を持たないニンジンだと述べている。また口内の唾液のpHは本来中性だが、食事をすると酸性になるので、食後すぐに歯を磨くとそのエナメル質が溶けて、かえって逆効果であると書いてある。pHがもとにもどる寝る前の歯磨きが、やはり有効のようである。
今後、人類におこる身体的あるいは精神的な不具合は、スマフォやパソコンなどの情報器機を使うことによって生ずると予測される。いまでも「メール指」や「スマホ指」が問題になっている。1980年代には「任天堂指」をめぐる同様の懸念があったが、症状としてでなかったので(ほんとうか?)、当時は問題にならなかったそうだ。しかし通勤電車内でスマホを操作する若者の姿をみていると、このような反復運動過多損傷(RSI)は今後の社会的な健康問題になりそうである。そのような事を考える人には好適な参考書であると思う。

ヤガ科のアカテンクチバ (Erygia apicalis )の終齢幼虫のようである。食草はマメ科のフジ、クズ。藤棚の下の家の外壁にいた。シャクトリ虫の仲間かと思っていたが間違いで、「幼虫図鑑」(http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/youtyuu/)の質問コーナーで教えてもらった。成虫については、あまりさえない蛾であるが、同じくhttp://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/youtyuu/HTMLs/akatenkutiba.htmlをご覧ください。
芋虫に思考の皺のありにけり 青山茂根

約24時間の概日リズム(Circadain rhythm)に支配された体内時計の分子的な基盤は、時計遺伝子とその転写産物である各種蛋白のフィードバックループ的な相互作用に他ならないことが分かっている。この分野の成果でもって、2017年にはジェフリー・ホール、マイケル・ロスバシュ、マイク・ヤングの3人が「概日リズムを制御する分子メカニズムの解明」によりノーベル賞を受賞した。
しかし、研究が進むにつれてフィードバックループの構造は高速道路のジャンクションのように複雑さを増して、素人には(おそらく専門家も)分けがわからなくなってきている(下の図1参照)。最近では、おまけに時計遺伝子の発現を制御するノンコーディング領域の DNA 配列もマウス個体の日内リズムの維持に必要であることが報告されている(http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research/research_results/2019/documents/190612_1/01.pdf)。
歴史的には、19世紀にクロード・ベルナールが提案した恒常性が生物学者の哲学で、生物学は変動を伴うリズムよりは恒常性(homeostasis)といったことが注目されてきた。そして、長い間そのメカニズム研究に主眼が置かれてきた。それゆえに、一昔前には体内時計の研究など意味がないとされていたのである。
一方でhomeostasisの現象も細かくみると振動があり、これはフィードバック機構によることが明らかになっていた。いわば”振動の平均”が恒常性といえるのである。おそらくこの短周期のフィードバック機構の一つに、環境のサイクルを受容するシステムがカップルして長周期の体内時計が進化したものと推定される。いまや、これは計時機能に特化しているようなので(大部分の時計遺伝子のdeletionは見かけ上致死的ではない)、以前はどのような代謝的あるいは生理的な機能であったかはわからない(variants産物の解析によってヒントが得られるかもしれないが)。おそらく細胞にとっては2次的な役割を担っていたものであろう。生物によって体内時計が多様であるのは(動物、植物と微生物ではまったく違う)、このような代謝系の利用の方法が普遍的であったと思わせる。

図1.ショウジョウバエの体内時計の分子機構。参考文献(松本顕氏)より転載。
参考文献
松本顕 『時をあやつる遺伝子』岩波書店 2018
アラン•レンベール 『時間生物学とは何か』 白水社 2001

ミヒャエル・エンデ(1929-1995年)はドイツの児童文学者ですが、「モモ」や「はてしない物語」など哲学的で文明批判的な作品を多数、世に出しています。「遺産相続ゲームー地獄の喜劇」(丘沢静也訳、岩波書店、1992年)は、1967年にフランクフルトで初演されたエンデの戯曲「ゲームをぶちこわす者たちー五幕の喜劇的な悲劇(Eine konnische Tragodie in funf Akten)」の全訳です。 とある宮殿に10人の遺産相続人が招集され、それぞれ、封筒に入れられた一枚の書き付けが手渡されます。10人が全員、協力しあって、亡き宮殿の主人の全ての言葉を綴り合わせれば遺産の何物かが得られるものを、お互いに疑心暗鬼となり、あるいは独り占めにしようとして協力せず、最後は全員が地獄の業火に焼き尽くされるというストーリーです。 登場人物は、保険会社社長とその家族、将軍、女教師、若い男性、女猛獣使い、前科のあるならず者、盲目の老農夫、家政婦、執事と公証人などです。それぞれの性格や思考パターンは世間で類型化されたもののいずれかに当てはまります。すなわち、読者は登場人物の一人を自分の代理人として投影しながら筋を追う一種の心理劇となっています。
この作品でエンデは、人間の愚かさ、自己破滅性を表現しようとしていますが、特別の主人公がいるわけでなく、登場人物すべてが解決しなければならない課題を均等に共有しています。エンデはその解説で、誰も悪人として登場するのではなく、みんなそれぞれ自分の想像とか行動基準から抜け出せないので、自分の置かれた状況にふさわしい行動を取る事ができない無能者、いいかえれば馬鹿者なのだと述べています。これはまた、現在の日本の社会の状況を言い表しています。一生懸命やっているように見えて、実は自分の利益や自己保身を思考の中心にしているために、目が曇って物事の連環やダイナミズムを理解できないのです。
これが書かれたのは、東西冷戦の真っ最中で、米ソは何百回も人類を死滅させるに足る核兵器を持ってにらみあっていました。すなわち、作品の背景には冷戦下での核戦争の可能性がありました。エンデは、解説でさらに次のように述べています。 「ヒロシマから核時代が出現し、それ以来何事も混沌として常軌を逸し、自殺にすら等しい行為を繰り返しました。そしていま相続人達が魔法の館に集まって、全員の共通の利益のために協力するのか、それとも、ぞっとするやり方で破滅するのか選択を迫られています」 しかし、こういった世界政治的なテーマとしてではなく、この戯曲を今日的に解釈すると、地球という人類が過去から受け継いだ大事な遺産を、相続人がそれぞれエゴを丸出しにして破滅させてしまうという寓話とも言えます。ローマクラブの報告「成長の限界」が出版されたのは1972年で、これの初演の5年後の事ですが、エンデは際限のない生産力とコントロールできない資源乱獲による地球環境の破壊により、人類が破滅の道へと突き進んでいることをすでに予見していたように思えます。この戯曲の悲劇的結末を予言して登場人物の一人は「もしも、この宮殿が破滅すると、その時は私たちも一千万マルクともども一緒に破滅するのよ。私たちは囚われの身なのを忘れないで」と叫んでいます。
このドラマでは舞台となる宮殿が重要な効果を持っています。最初、舞台になる宮殿は明るく輝いて色とりどりの鳥が群れになって自由に飛び回っています。しかし、ストーリーが展開するにつれ、壁や柱は傾き歪んでいき、あらゆる材出はボロボロになり、女人像や肖像画はミイラや骸骨に変容していきます。周りはむんむん照りつけるように暑く、鳥の死体が山となります。魔法にかけられたような宮殿が、地球そのものを暗喩している事は、こういった情景の推移によって分かります。 いずれにせよ、エンデの主張は、現代社会の破滅は多数の個々のプロセスの総和の結果にあるとしています。言い換えると社会の変革や矛盾の解決は、特定の政党や集団によるトップダウン的な操作によるのではなく、市民の個々人の連結を基盤としたボトムアップな力によるものでなければならないと言っていると思います。
追記 1(2021/05/27)
生産力崇拝思想とは?
現代の経済学と政治学は「社会に成長は絶対に不可欠」とする成長力思想にとりつかれている。資本主義も共産主義も生産力思想による経済成長を通じて、この世が天国になると考えており。ただその具体的な手法についてだけ、言い争っていただけだ。その背景には1)人口はこれからも制限無く増え続ける2)生活水準をあげるために必要というものであった。しかし1)人口については工業先進国では減少し始めていること2)生活水準も飽和していることから、この考えの矛盾が指摘されはじめた。一昔前までは、未知の大陸が成長の発展力であったが、現代では科学技術(イノベーション)がそれに替わっている(ユヴァル・ノア・ハラリ 『ホモ・デウス』河出書房 2018)。
追記2(2021/12/02)
資本主義はシャーロックの本姓、すなわち強欲を踏襲したシステムで人間の生活や地球環境にお構いなく利潤を求める。増資、増産、増人口の3つの歯車をフルに連結させ、ひたすら生産力に拍車をかけてきた。さすれば、資本主義の矛盾を弁証法的に止揚した共産主義の未来を予想したマルクスは、生産力思想をどのように分析し批判したのだろうか。それに取り組んだ労作が斎藤幸平の「人新生の資本論」(集英社2021)である。この書のまとまった評論はべつの機会にゆずりたい。この書は問題提議は適格だがマルクスびいきが災いして、本質が見抜けていないように思える。マルクスは労働の歴史的発展については詳しく分析したが、人類の発祥いらい、この種が地球環境とどのようにかかわってきたかを考察し、総括はしなかった(多分その時間がたりなかった)。この欠落が、後にスターリニズムや現代中国の鄧小平路線を生み出す背景になっている。

ホシミスジ(Neptis pryeri)。コデマリについているホシミスジの羽化成虫と脱皮殻。
(https://blog.goo.ne.jp/apisceran/e/d26a75aa514d0300c1ba41553ccf0444)参照
釣り鐘にとまりて眠る胡てふ哉 蕪村

テオドシウス・ドブジャンスキー(Theodosius Grygorovych Dobzhansky:1900-1975)は20世紀における遺伝学の泰斗の一人である。ロシアに生まれキエフ大学を卒業した後、アメリカに渡りコロンビア大学の動物学の教授として、モーガンと共にショウジョウバエを材料に、ダーウニズムの立場で古典的遺伝学の基盤を作った。ドブジャンスキーをはじめ、この頃の生物学者の大物達は、重箱の隅をつついている昨今の分子生物学者とは大違いで、専門分野を背景に科学、社会、人間などについて思念し様々に持論を展開している。
ドブジャンスキーの著作は多いが、1964年に名著「Heredity and Nature of Man」を表している。日本語訳は「遺伝と人間」(杉野義信、杉野奈保野訳、1973年)で、岩波書店から訳書が出されている。この書はドブジャンスキーの著作の中でも、現代世界の諸問題を扱った含蓄の深い古典である。これは現在、絶版になっているようで、中古本を購入するか図書館で探して読むしかないが、ここではその内容を紹介しよう。
本書の前半は大部分、遺伝学についての基礎知識と遺伝子DNAの構造と機能の解説に当てられているが、後半は広く普遍的概念である人間の個性や、「環境か遺伝か」といった問題、他民族へのステレオタイプ的偏見、多様性の礼讃などを論じているが、「放射線による遺伝的障害」についても1章をあてている。1960年代の放射線影響に関する遺伝学者の一般的な考えを、代表しているものと思えるので、要約的に紹介する。
ドブジャンスキー曰く、生命のそもそもの始まりから常にそうであったように、現在でも、人間においても他のすべての生物においても、突然変異は常に起っている。突然変異なしでは、進化それ自身が起り得なかったはずだ。それゆえ遺伝的負荷は、生命が環境の多様性や変化に進化的な変化によって適応できるようになるために支払う代償だといえる。しかし、この見方を人間にあてはめようとするのは無意味である。それは人間の場合、環境に対する適応は、遺伝的な手段よりむしろ主に文化的な手段によるからである。その上、大多数の突然変異は有害なものだ。人間の場合、突然変異が多く起れば、それだけ多くの人間に苦しみを与えることになる。
ところが、人間はこれまで突然変異の頻度を減らす方法を知らないままできた。それどころか、最近の科学技術の進歩は逆に突然変異率を上げる結果になっている。近年になって、この問題が広く公共の関心を刺激することになったのは当然のことである。つまり、X線やその他の放射線によって人類の受ける遺伝的障害の問題である。1927年に、H・J・マラーはX線を照射したショウジョウバエの子孫は突然変異の頻度が高くなるということを発表した。現在では、すべての高エネルギーの、つまり透過性の強いイオン化放射線は突然変異を誘起するということが知られている。つまり、放射線を受けた個体の子孫には突然変異の出現頻度が増加する。突然変異を誘起しやすい放射線は、X線、ラジウムのガンマ線や核兵器実験による放射性降下物、原爆の灰や原子炉や原子核破壊装置から出る放射線等々である。
これらの被ばく後、影響が比較的早く出てくる症状と、悪性腫瘍(ガン)のように遅く出てくるものがある。遺伝的障害は生殖組織の中で誘発され、子孫に伝えられる突然変異を含んでいる。生理的障害は、どんなに痛ましいものであろうとも、放射線を受けた世代に限られる。しかし、遺伝的障害は放射線を受けた人の子孫に、しかも被曝後何世代にもわたって障害を与える。
生理的障害と遺伝的障害のもう一つの違いも大切なことである。微量の放射線は、生理的には何ら障害はない。というのは生理的障害には、それを生じる最少危険闇値があるからである。ところが、遺伝的障害はそうはいかない。誘起される突然変異の数は放射線の量に比例する。障害が起こらないような放射線の最少値、つまり、安全な値というのはないのだ(いわゆるLNT仮説が主張されている)。
したがって、大気中での原爆実験などからの放射線降下物から受けた放射線の量が如何に少なくとも、それを受けた集団に或る数の変異を誘起することは避けられない。どのような放射線源にしろ、そこから出る放射線の量が、少ないからといって無害であるとはいえない。特に、その放射線を浴びるのが全人類、つまり三十五億(現在では70億)の人間であるとすれば、なおさらのことである。どんなに少人数であっても、罪もない人々を死に到らしめたり、苦しめたりすることは倫理的にいって全く弁護の余地がない(ICRP関連の研究者が口をすっぱくして、“してはいかんよ”と言っている”掛け算”をドブジャンスキーは言う)。
他方、極微量の放射性元素は、すべての生体の中にも、また環境の中にも含まれているので、すべての生命は常にある程度は放射線に曝されてきたのだということも忘れてはならない。ほとんど除去できないこのような放射線のバックグラウンドは常に突然変異を誘起していきた。このバックグラウンド以上に人工の放射線源によって、放射線量がどのくらい増加したかを測定する試みがなされている。当然、放射線量の増加は科学技術の進歩した国が最も大きい。たとえばアメリカでは、人工放射線源のために放射線被ばく量は約二倍にもなっている。これまでのところは、主な人工の放射線原は放射性降下物ではなくて、医療の診断および治療用に使うX線である。放射線医療に用いることからくる恩恵はあまりにも大きく、これをやめるわけにはいかないが、患者にかける放射線はできる限り少なくしなければならない。殊に生殖器の照射に対しては特別要心しなければならない(医療における放射線の過剰照射問題はこの頃からすでにあったようだ)。
以上がドブジャンスキーが1960年代に発表した放射線影響についての見解である。現在、放射能問題で、良識派(悲観派?)が主張するほとんど全ての内容がすでに述べられている。現代世界の文明が、生み出す破滅的なリスクは全て遺伝子が関与しているというのが、庵主の見解である。即ち「放射線障害」、「強毒性インフルエンザ」、「遺伝子組み換え生物」の3つである(地球温暖化問題は誤った仮説と思えるので省く)。放射線は人類の生み出した核と原子力によるもので、ドブジャンスキーが述べたようにヒトの遺伝子に作用しガンを誘発し、遺伝子に悪い変異を起こす。強毒性インフルエンザはウイルス遺伝子に変異や組み換えが自然に生じた結果出てくるものだが、現代世界の流通の構造がその力を増幅しスペイン風邪のようなパンデミック(世界的大流行)を引き起こす。さらに3番目のものは、人類自ら生物の遺伝子を改変し組み換え技術により本来ありえない生物を作りだし、それが予想もつかない災害を地球にもたらすというリスクである。幸い、これだけは人類は未だ経験していない。未来において、これらのクライシスのいずれかが発生した場合に(そのうち二つは経験ずみ)人類を救うのは、遺伝子や文化を含んだ多様性であると考えられる。

ケヤキの葉にできた虫瘤。ケヤキヒトスジワタムシ(Paracolopha morrisoni) という虫によって葉に形成される。
ケヤキフシアブラムシとも言う。虫えいの中で増えた虫に有翅で、脱出してタケやササに移動し、
10月ごろに再びケヤキに帰ってきて、有性世代を産み、卵で越冬するらしい。
春に孵化し、葉の裏側から吸汁してこのような虫えいを作る。
(成虫はhttp://tokyoinsects2.blog.fc2.com/blog-entry-1716.html?spを参照されたい)
飄々といぼを並べし夏欅 楽蜂

フランスの思想家、ピエール・フェリックス・ガタリの「3つのエコロジー」(杉村昌明訳、平凡社、2008年初版)は、現代社会を読み解く重要な手引きである。ガタリの思想を一言でいうと、「自然環境」と「社会」と「人間」の3つのエコロジーが統合されたエコゾフィー(ecologie + philosophie)という視点によって世界を解釈しようというものである。それによると、たとえば個人の健康問題も、家族的なスケールで考えるものではなく、環境(自然)と社会の関係において、解釈し判断すべきという事になる。
講演「エコゾフィーの展望」(同書収録)において、ガタリは盛んに「美的(エステチック)」という言葉を使っている。訳者の注解によるとこれは、人間が持つ感性的な特質という事のようだが、ガタリ自身は、社会は社会的な言葉だけでは解決せず、人間の内面にあるものが絡まってこないと物事の展望が、ひらけないと言っている。この言葉の意味するところは難解であるが、自分の風土や文化や民族について本来的に持っている、これらを愛おしく思う心の発露を呼びかけたものと解釈される。ただこの「美的」の内容が重要で、ユートピアにもなりファシズムにもなる。”他”もしくは”多”を許容する心がなく民族の「美的」にとらわれてファシズムになった例がナチスドイツである。
ガタリは「エコロジーの3つの基本的な作用領域の接合が行われない限り、あらゆる危険や脅威の増大を予測せざるを得ない」と述べている。ガタリはこの書で、ドナルド・トランプを「突然変異的で化け物のような繁殖力を誇る藻類」と批判している(p29)。トランプはこの初版が出された当時、ニューヨークなどの大都市で不動産王として君臨し、貧困者から家を奪い多数のホームレスを生み出した。ガタリもまさか約30年後にこのトランプがアメリカ合衆国の大統領になるとは思わなかったろうが、人の本来の感性では、すなわちガタリの言う「美的感性」では、トランプは決して許容できるものではなかった。 ガタリはさらに、「自然環境(自然)」、「社会環境(社会)」、「精神環境(人の心)」の接合に加えて、「情報環境」の問題を取り上げている。メディアを、権力による支配の道具としてのみネガティブに取り上げるのではなく、そこに新たな社会的コミュニケーションとしての建設的可能性を見ている。「美くしくありたいと思う心(感性)」を持った人たちが、利用可能な全てのコミュニケーション手段で、団結しなければならないと。

ヒカゲチョウ(Lethe sicelis)の幼虫
頭に小さな角があり、尻に一対の棘のような突起がある。ササの類いを食草にしているらしい。
このあたりで成虫が飛んでいるのをみるが、幼虫をみるのは、はじめてである。
日陰蝶追うて林間学校へ 高濱虚子


イソヒヨドリ( Monticola solitarius)のオス。スズメ目、ヒタキ科。アフリカとユーラシア大陸に広く分布する鳥。和名どおり海岸の磯や岩場などで多く見られるが、不思議な事に最近では都市部でもよく観察される(ツバメの雛の捕食をしているという報告もある)。体長は23cmほどで、ヒヨドリよりは少し小さい。オスは頭から喉および背部が暗青色、胸腹部が濃い橙色、翼が黒と美しい。一方、メスは全身がやや暗青色を帯びた茶褐色で、鱗のような模様がある。おもに地上で餌を探し、甲殻類、昆虫類、トカゲなど小動物を捕食する。 単独行動で、群れは作らない。 春にはツグミ科特有の声量のある美声でさえずる。この個体は道路で何を探しているのだろうか?
磯鵯の囀り玉をころがしぬ 右城暮石
追記1)(2022/06/21)
家のテラスで蚕を飼っていると、飼育篭に来て幼虫をイソヒヨドリが食べに来た。これには驚いたが、この鳥は地面の虫を探して餌にしているようである。それにしても目ざとい鳥である。2匹がつがいで近所にくらしている。

クワゴマダラヒトリ(Lemyra imparilis)の幼虫と思える。
ムラサキツユクサの葉にいた。成虫オスの翅は暗褐色でメスは白色。
幼虫はクワ、オオバコ、バラ科の植物の葉の他さまざまな植物の葉を食べる。
毛虫焼く株式欄に火をつけて 土屋利之

ヤブジラミ (Torilis japonica)セリ科ヤブジラミ属の2年草。野原や道端に生えるありふれた野草。和名の由来は、藪に生え、鉤状に曲がった刺毛によって果実が衣服につきやすいのでシラミにたとえたもの。葉は長さ5~10㎝の2~3回羽状複葉。小葉で細かく切れ込み、両面とも粗い短毛が密生する。枝先に小型の複さん散形花序を出し白色の小さな花をつける。
草虱つけ電脳の店に入る 内藤三男

相対性理論による時間影響の一つにはサニヤック効果がある。理想的な時計が二つあって、同じ速さで進むように調整されており、それを赤道上の海面の高さに置く。そのうち一方を、海面に沿って、ジオイド(地球の重力が等しい面の1つであり、地球全体の平均 海面に最もよく整合する)からはずれないように注意して、ゆっくり東へ動かす。移動はゆっくり行なわなければならず、可能なら何年かかってもかまわない。移動する方の時計が、赤道を1周して静止している方の時計と再び出会ったとき、二つの時計を照合してみる。移動が確かに十分遅く、時計がずっと海面の高さにあったならば、回じ時刻を指しているものと予想されるが、そうはならない。移動した時計の方は静止していた時計よりも、207ナノ秒遅れることになる。さらに奇妙なことに、時計が逆方向に進み、西回りに赤道を一周したとすると、今度は移動した方の時計は静止していたよりも207ナノ秒進むことになる。サニャック効果は形を変えた時間の遅れである。地球を慣性座標系と見るか非慣性座標系から見るかで考え方が違うが、結論は同じである。

図1サニャック効果: 時計がA点からB点に地表を移動すると、静止した時計に比べて
影付きの部分に比例した時間のズレが生じる(参考文献の図を転載)
参考文献
トニー・ジョーンズ 『原子時計を計る』青土社 2001.
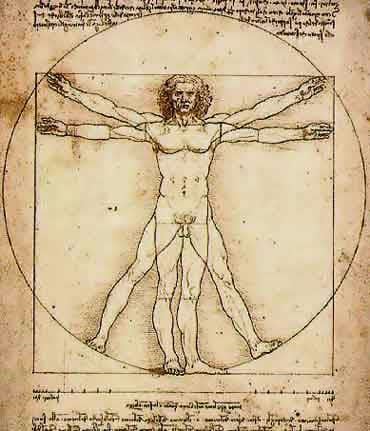
今ではどうか知らないが、日本の大学や研究機関で一時、『文理融合』という言葉がはやったことがある。地球環境関連のある国立の研究所でも、その発足当時、理系と文系のメンバーを混ぜて、プロジェクトチームを作らせた。初代研究所長の目論見は、それによって「いろいろの具材を混ぜてチャーハンのような味わいの成果を得る」というものであった。その目的が達成されたかどうかは評価が分かれるところであるが、ここでの文理融合は理系の人間にとってはとても忍耐力の要るものであったと記憶している。どこで忍耐が要求されるのかは、いろいろあったが一番必要なのは、共同の研究会や報告会においてである。ほとんどの文系の研究者の口頭発表は面白くない。まず内容が聞き手に理解させようという一切の努力がなされていない(ように思える)。もっとも、これはこちらの勉強不足で不明のいたすところかもしれないし、文系人にとっても理系の発表は不親切なものだろうと思い、これは我慢出来る。
しかしながら問題はその発表の形式である。ほとんどの人は原稿の棒読みで何の工夫もない。常々そのような感想を抱いていたが、米国の有名な進化生物学の権威であるスティーヴン・ジェイ・グールド(Stephen Jay Gould: 1941-2002)も、文系の発表に対してズバリ同様の悪口を述べているので紹介する。それは「梯子図と逆円錐図ー進化観を歪める図像 」(『消された科学史』渡辺、大木訳、みすず書房 1997)というエッセイで、少し長いが、以下その部分を引用する。
『たとえば、どんな分野の学者でも経歴を築くうえで重要な足がかりとなる、学会での口頭発表について考えてみよう。私にはとんでもなく皮肉なことに思えるのだが、科学と人文学では、その発表様式に二つの大きなちがいがある。世間の紋切型の常識によれば、科学者が話す内容は経験的なものではあるが、たいていは洗練された言葉づかいやコミュニケーションの巧みさに欠けるのに対し、脂が乗っている人文学者は、少なくとも「えもいわれぬ表現」で聴衆を驚嘆させるのだという。しかしながら、両者間における二つの大きなちがいは、言葉づかいやコミュニケーションの方法において科学者の直観力のほうが優れていることを示している。これを皮肉と言わずして何と言おう。まず第一に、人文学者が発表する際には、ほとんど例外なく書いた原稿を読む(そしてたいていの場合、お粗末にも顔を原稿に埋めんばかりの姿勢で一本調子で読むという、およそ口頭発表にふさわしからぬやり方をする)。科学者は、原稿を読むようなことはまずない。われわれは議論の順序や論理をとくと考え、概略を描いてメモを用意し、即興で話をする。こちらのまさに本物の口頭発表のほうが優れているのは自明であると私は思う。なによりも実際問題として、科学者の戦略のほうが、きちんとした準備にかかる時間が少なくてすむ(人文学者が用意する原稿の多くは、講演後に出版の予定があるわけでもなく、労力のむだである)。
第二に、たいていは、原稿をそのまま棒読みするよりは、即興のスピーチのほうが断然おもしろく、ついつい引き込まれてしまうものである。もちろん原稿を読み上げるにしても上手な人はこの問題をいくつかの簡単なルール(たとえば一文ずつ憶えて聴衆のほうを見ながら話すというような)で克服しているが、実際問題としてうまく読み上げられる人はめったにいない。しかも、下手な朗読がつのらせる退屈度は、即興の講演に不慣れなせいで生じる文法の乱れによる聞き苦しさよりもはるかに救いがたい。私がにらむところ、多くの人文学者は恐怖心から、かねて用意の原稿を読み上げるという戦略を採るのかもしれない。なにしろ何といっても文法的に正しいことが彼らにとっての至高善である。無意識のうちに動詞の活用をIつまちがえるくらいなら、終始単調で退屈で聴衆に理解すらされなくてもかまわないのだろう。その点、科学者はスピーチが文法的に正しいかどうかで同僚から評価されることはまずないため、多少のミスは覚悟のうえで、より良いコミュニケーションの方法を選ぶ。
そして第三に、これが最も重要な点なのだが、同じ英語とはいえ、書き言葉と話し言葉はまったくの別物である。人文学者たるもの、何よりもこのことを心得るべきである。講演用に用意された原稿は、たいていそのままでは活字にはならない(マーティン・ルーサー・キング牧師の「私には夢がある」という例の演説は二〇世紀最高の演説だが、リズミカルな繰り返しを基調とした口誦向きの詩であるため、文章として読むにはまるで適さない)。両者のちがいは多々ある。一つだけ挙げるなら、口頭での話は周到に計算された循環構造をもっていなければならない。発表は一方向に進むだけで、聴衆には前の部分に戻って参照することができないからである。それに対して、書かれた文章はもっと直線的で重複はないほうがいい。読者は途中で前のページにもどって読み返せるからである。このような顕著なちがいは、明らかに視覚的な対象について人文学者が話をするときにも見受けられる。(中略)視覚的な像はわれわれの生活の中心をなしている。生物学用語を使うなら、霊長類は哺乳類のなかで典型的な視覚の動物である(人間の脳が創造した「ホムンクルス」の標準的な図像を一目見れば、大脳皮質が視覚系にいかに奉仕しているかがわかるだろう)。社会的な問題におけるわれわれの判断の多く、とくに感情的なものは像によって左右される。自由の女神像、アメリカ独立を描いたウィリアムズの絵画「一七七六年の精神」、「スラバキ山頂の国旗掲揚」などがなかったとしたら、愛国心は何を拠り所にすればいいだろう。あるいは地下鉄の換気口の格子上に立つマリリン・モンローぬきで現代のアメリカ文化を理解できるだろうか(以上)。
グールドは、このエッセイにおいて文系の進歩のないプレゼンを主題にしたわけではなく、「規範的な図像」(例えばサルが人類に進化する様子など)がどれだけ人々の概念を間違って規定しているかを述べたかったのである。その頭出しに、テーマに関係ない文系の退屈な発表について3ページにもわたって悪口を展開している。日頃、よほど気になっていたのであろう。グールドは文系の講演内容の質については、遠慮して述べていないが、庵主は思うに、言語という「空」を糸巻きの芯にして、それに言葉の糸をグルグルと巻き付けているような話が多い。難しい用語がつぎつぎ続くので、立派な事を述べているように聞こえるが、本人も分かっているのだろうかと思うことがしばしばある。大学における「文系学部廃止」の暴論がでるのには、このような背景があるのではないか。
追記(2019/12/20)
中村輝太郎 『英語口頭発表のすべて』丸善株式 1982でも同じ議論がされている。「読む講演 」でも要点を記したメモ程度にしておくのがいいそうだ。