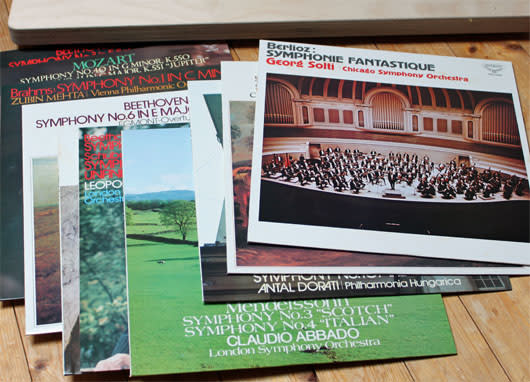昨夜、札幌Kitaraで掲題のピアノリサイタルを聴きました。

ラントシュ氏は、ハンガリーのご出身でリスト音楽院(ブタペスト)の現役教授です。かって、北海道教育大学で教鞭をとられたこともあり、また、札幌で毎年開催される「リスト音楽院セミナー」の指導者として度々、来札しています。
そのためか、会場(小ホール450席)には、セミナーの受講生や音楽家志望と思われる若い方々の姿を多くみかけました。
プログラム
ベートーヴェン:
・ピアノ・ソナタ 第5番 ハ短調 作品10-1
・6つのバガテル 作品126より
第1番 ト長調、第4番 ロ短調、第6番 変ホ長調
・ピアノ・ソナタ 第18番 変ホ長調 作品31-3
ブラームス:
・ピアノ・ソナタ 第3番 ヘ短調 作品5
演奏は、音楽教育に携わる人にふさわしく、正確無比、緻密極まりないもので、安心して聴くことができました。反面、情緒に欠け、堅苦しさを感じさせる部分もありました。
特に、最後のブラームスは、日頃、耳にする機会の少ない曲でもあり、丸ごと演奏を楽しむには至りませんでした。ベートヴェンのパガテルや第18番は、弾き手の特長がよく出た好演だと思いました。