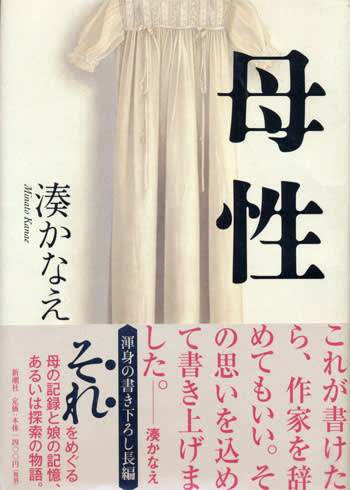09年4月から13年3月までの4年間、朝日新聞夕刊に月一で連載された芥川賞作家の時事コラム集。「何かを終わらせ何かを始めるためには、一つの積極的な意思が要る」というキャッチが本書を代弁する。

内容は多岐にわたるが、連載の中ほどで東日本大震災に直面して著者は苦悩する。
「一般にものごとはゆっくり変化するものであって、終わりや始まりがはっきり意識されることはめったにない。
しかし、劇的な変化は皆無ではない。幸いといっていいかどうか、9.11は日本から遠く、2003年3月20日のイラク開戦はもっと遠かった。
だが、2011年3月11日は日本で起こった。3.11は我々の日付になった。何かが完全に終わり、まったく違う日々が始まる。正直に言えば、ぼくは今の事態に対して言うべき言葉をもたない」と。
また、原発への決別と自然エネルギーへの転換を訴えて、
「子犬が室内で粗相をしたら、その場へ連れて行って、鼻面を押しつけ、自分が出したものの臭いを嗅がせて頭を叩く。お仕置きをして、それはしてはいけないことだと教える。そうやって躾けないかぎり、室内で犬を飼うことはできない。
我々はこの国の電力業界と経済産業省、ならびに少なからぬ数の政財界人から成る原発グループの首根っこを捕まえてフクシマに連れて行き、壊れた原子炉に鼻面を押し付けて頭を叩かなければならない」
庶民感情に沿う勇気ある発言だ。ご一読をお勧めします。