[※ 『原発に挑んだ裁判官』(磯村健太郎・山口栄二) 朝日新聞出版↑]
―――――― (樋口英明さん)《私が大飯原発を止めた理由は4つです。①原発事故のもたらす被害はきわめて甚大。だから、②原発には高度の安全性(事故発生確率が低いこと)が求められるべき。③地震大国日本において高度の安全性があるということは、高度の耐震性があるということにほかならない。④しかし、我が国の原発の耐震性はきわめて低い。ですから原発の運転は許されないのです。これは「樋口理論」と呼ばれています》《あらゆる運転差し止め訴訟で裁判官に原発の脆弱な耐震性を知らしめ、電力会社の非科学性と非常識を理解させることによって、日本の全ての原発は必ず停止できます》 (2022年08月30日[火])
(2022年08月30日[火])
映画『原発をとめた裁判長 そして原発をとめる農家たち』。
【映画『原発をとめた裁判長 そして原発をとめる農家たち』】
(https://saibancho-movie.com/)
(https://youtu.be/AlLlePkIcdE)
『●泊核発電所の運転差し止め…一方、札幌地裁は《廃炉請求については
「必要な具体的事情が見いだせない」として棄却》ってどういうこと?』
タイトルから、『原発に挑んだ裁判官』(磯村健太郎・山口栄二、朝日新聞出版)を思い浮かべました。3人のお一人が、樋口英明・元福井地裁裁判長。
週刊朝日のコラム【『原発をとめた裁判長』の教え 古賀茂明】(https://dot.asahi.com/wa/2022082500104.html)によると、《この秋にお勧めの映画がある。『原発をとめた裁判長』(監督・脚本:小原浩靖)というドキュメンタリーだ。関西電力大飯原発3・4号機の運転差し止め判決と同高浜原発3・4号機の再稼働差し止め仮処分決定を出した樋口英明元福井地方裁判所裁判長が主人公である》。
古賀茂明さん《国民の前で、ちゃんと議論すれば、止めろと言わずに止めるのは簡単だ》…裁判で勝つために ――― 樋口英明理論の浸透を。反・核発電に、高度な工学的知識は不要である…(樋口英明さん)《原発の耐震性は信頼度も基準値も一般住宅より、はるかに劣る》のだから。
『●裁判所も歪む…《国が開発の政策的な枠組みを決め、その下で
電力会社に》核発電所を…《そして裁判所も一体となり…》』
『●2014年5月大飯原発運転差し止め判決…樋口英明さんは《基準地震動を
超える地震が来ないと言えるかどうか…他の原発と共通の問題》』
『●元福井地裁裁判長・樋口英明さん《地震大国の日本には、
北海道から沖縄まで原発を動かせる場所はどこにもない》』
『●反核発電に、高度な工学的知識は不要である…(樋口英明さん)《原発の
《原発の耐震性は信頼度も基準値も一般住宅より、はるかに劣る》のだから』
『●《原発再稼働や増設を唱える連中の頭の中を掻っ捌いて、中身を見て
みたい》(鈴木耕さん)――― なぜ今直ぐ「原状回復」しないの?』
『●《理性と良識》で判断…核発電は《「被害が大きくて」かつ「事故発生
確率も高い」という2つが揃ったパーフェクトな危険》(樋口英明さん)』
『●古賀茂明さん《国民の前で、ちゃんと議論すれば、止めろと言わずに
止めるのは簡単だ》…裁判で勝つために ――― 樋口英明理論の浸透を』
樋口英明さんは、以前から、《地震大国の日本には、北海道から沖縄まで原発を動かせる場所はどこにもない》と。まともな裁判官が、もっと増えないものか…。《老朽原発はもちろん、日本には強い地震に耐えられる原発はひとつたりともない》。高度な工学的知識や科学的な知識は不要だ、だって、《原発の耐震性は一般住宅よりもはるかに脆弱》《原発の耐震性は信頼度も基準値も一般住宅より、はるかに劣る》のだから。《住民や電力会社、弁護士や裁判官までもが「難しいに違いない」と“魔法”にかかってしまう》必要などない。
《毎年のように頻発する、やや強めの地震に襲われても危険ということです。原子炉は強い地震に耐えられても、原子炉に繋がっている配管や配電の耐震性は低い上に耐震補強も難しい。断水しても停電しても原発は大事故につながる。それが福島の教訓です》…何の教訓も得ていません。そのためには、最後に、樋口英明さんは《あらゆる運転差し止め訴訟で裁判官に原発の脆弱な耐震性を知らしめ、電力会社の非科学性と非常識を理解させることによって、日本の全ての原発は必ず停止できます》と仰っています。
『●新高速炉「アベシンゾウ」…愚かな核発電「麻薬」中毒患者・
核燃サイクル教信者の罪を後世に残すために』
『●(リテラ)「あの未曾有の福島第一原発事故を招いた
“最大の戦犯”が、他ならぬ現内閣総理大臣・安倍晋三」』
『●東電核発電人災での国の責任も放棄…《あの未曾有の福島第一原発
事故を招いた“最大の戦犯”》アベ様の責任は追及され続けるべき』
『●高松高裁原発避難者訴訟…《「長期評価」を真摯に受け止めていたら、
遅くとも東日本大震災の前までに、さまざまな津波対策は取れた》』
『●《想定できないから免責されるという論法なら「地震大国」の日本で
原発は稼働させてはならない…原発政策を推進してきた国の結果責任》』
『●《史上最大の公害事件》核発電人災について《東電の旧経営陣に対し、
東電に賠償するよう株主が求めた》株主代表訴訟…13兆円の賠償命令』
『●キシダメ首相は《原発の運転期間の延長に加え》《新増設や建て替えの
検討を明言したのは初めて》――― 命名・次世代革新炉「キシダメ」』
=====================================================
【https://dot.asahi.com/wa/2022082500104.html】
『原発をとめた裁判長』の教え 古賀茂明
政官財の罪と罰
2022/08/30 06:00
この秋にお勧めの映画がある。『原発をとめた裁判長』(監督・脚本:小原浩靖)というドキュメンタリーだ。関西電力大飯原発3・4号機の運転差し止め判決と同高浜原発3・4号機の再稼働差し止め仮処分決定を出した樋口英明元福井地方裁判所裁判長が主人公である。
今年の冬、夏と日本では電力危機が叫ばれた。老朽化した火力発電所の稼働などで幸い停電には至らなかったが、次の冬は、さらに深刻だと政府は危機感を煽っている。さらに、2050年にカーボンニュートラルという日本の目標達成には、火力発電を増やすのは好ましくない。再生可能エネルギーを数カ月で大幅に増やすのも困難だ。
こうなると、原子力発電が切り札だという議論が勢いづく。ついに、岸田文雄首相も老朽原発の運転期間のさらなる延長や次世代原発の建設などの検討を宣言した。岸田政権のある関係者は、7月の参議院選挙前にこう語った。「今、原発について前のめりになることは厳禁だが、選挙に勝てば新増設も含めて原発推進に踏み込んで行く」
だからこそ、政府は再エネ拡大策をまじめにやらず、あえて電力不足を演出した。今や政府の思惑通り、世論調査でも原発再稼働に反対する意見は少数派になった。実は、そこには、「原発は『それなりに安全』なはずだ」という根拠なき思い込みがある。しかし、原子力規制委員会は、常に「審査基準を満たしても安全とは言えない」と言っている。本当はどうなのか。
昨年3月の本コラムでも紹介した原発の安全に関する「樋口ドクトリン」がある。(1)原発事故のもたらす被害は極めて甚大。(2)それ故に原発には高度の安全性が求められる。(3)地震大国日本において原発に高度の安全性があるということは、原発に高度の耐震性があるということに他ならない。(4)わが国の原発の耐震性は極めて低い。(5)よって、原発の運転は許されない(樋口英明『私が原発を止めた理由』(旬報社))。
11年の東日本大震災の最大の揺れは2933ガル(「ガル」は、地震の強さを測る単位)。21世紀最大の揺れは、08年岩手・宮城内陸地震の4022ガルだ。16年の熊本地震は1700台。今世紀の1000ガル以上の地震は18回とかなりの頻度だ。原発の耐震設計基準はと言えば、大飯原発が設計時に405ガル。後に856ガルまで大丈夫だとされたが、他の原発も1000以下が多い。一方、三井ホームの耐震性は5115ガル、住友林業の住宅は3406ガルで、日本の原発がいかに地震に弱いかがわかる。
冬に電力が足りないと言っても、ピーク時に一部の地域で数%不足するというだけの話で、節電などで対応すれば、経済に影響が出ても大した話ではない。それに比べて、原発事故は日本の広範な地域に壊滅的打撃を与える。しかも、毎年日本のどこかで起きるある程度大きな地震が原発の敷地付近で起きれば、大事故になる可能性があるのだ。冬の数日間数%の電力が不足するというのとは全く次元が違う。比較すること自体ナンセンスだ。さらに、原発は戦争で敵に狙われたらほとんど防御不能であることは規制委も認めている。
「電力が足りないから原発だ!」というのがいかに愚かなことか。『原発をとめた裁判長』を見れば誰でもわかる。是非ご覧いただきたい。
※週刊朝日 2022年9月9日号
=====================================================
[※ ↑「原発さえなければと思います」(週刊金曜日、2021年03月12日、1320号)] (2022年08月29日[月])
(2022年08月29日[月])
これまでさんざん ―――――― さらに最も腹立たしいのは、最大の戦犯が未だにのうのうと政治家で居続けていること。最大の戦犯・アベ様が、核発電所を新規に作りたいそうです…正気じゃない。その核発電所に「アベシンゾウ」とでも名付けては如何か? ―――――― と言ってきましたが、そのアベ様も統一協会問題絡みで銃弾に倒れました。
『●高速増殖炉もんじゅ…ニッポンでは、
巨額の「エサ代」を支払い続けるつもりらしい』
『●「(悪)夢の高速増殖炉」もんじゅの延命に向かって着々と
…ドブガネという巨額の「エサ代」は続く』
『●予想に反して「もんじゅ」廃炉へ、一方、
「閉じない環」核燃料サイクルは維持するという無茶苦茶』
『●「核発電は安い」と言っておきながら、
「原発の電力を使っていない消費者にまで負担を強いる方針」』
『●「ふげん」、「もんじゅ」…次の高速炉は
「こくうぞう」、「みろく」? 「白象」とでもしますか??』
『●新高速炉「アベシンゾウ」…愚かな核発電「麻薬」中毒患者・
核燃サイクル教信者の罪を後世に残すために』
『●(リテラ)「あの未曾有の福島第一原発事故を招いた
“最大の戦犯”が、他ならぬ現内閣総理大臣・安倍晋三」』
『●東電核発電人災での国の責任も放棄…《あの未曾有の福島第一原発
事故を招いた“最大の戦犯”》アベ様の責任は追及され続けるべき』
『●高松高裁原発避難者訴訟…《「長期評価」を真摯に受け止めていたら、
遅くとも東日本大震災の前までに、さまざまな津波対策は取れた》』
『●《想定できないから免責されるという論法なら「地震大国」の日本で
原発は稼働させてはならない…原発政策を推進してきた国の結果責任》』
『●《史上最大の公害事件》核発電人災について《東電の旧経営陣に対し、
東電に賠償するよう株主が求めた》株主代表訴訟…13兆円の賠償命令』
さて、「悪夢のような民主党政権」どころか、真の意味での「悪夢の自公政権」「悪夢のアベ様政権」が終わったのかと思いきや…キシダメ氏、正気かね? 《原発への依存度を下げると訴えていた岸田文雄首相が唐突に、原発の運転期間の延長に加え、新増設や建て替えを検討する方針も表明》!? 《新増設や建て替えの検討を明言したのは初めて》!? 次世代革新炉「キシダメ」とでも名付けるの?
我那覇圭・佐藤裕介両記者による、東京新聞の記事【3・11後、初の原発「新増設」を首相が明言 唐突な政策転換、被災者らに十分な説明なく】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/198069)によると、《原発への依存度を下げると訴えていた岸田文雄首相が唐突に、原発の運転期間の延長に加え、新増設や建て替えを検討する方針も表明した。2011年の東日本大震災での東京電力福島第一原発事故後、歴代首相は原発への依存度の低減を掲げており、新増設や建て替えの検討を明言したのは初めて。被災者らに十分な説明をしていないにもかかわらず、エネルギー政策を原発推進の方向に転換した。(我那覇圭、佐藤裕介)》。
さらに、東京新聞の【<社説>原発への回帰 福島の教訓はどこへ】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/198157?rct=editorial)によると、《あの悲惨な原発事故をなかったことにしようというのか。政府がこれまでの方針を翻し、原発の新増設や建て替え、さらには法定寿命の延長まで検討するとの考えを明らかにした。脱炭素の潮流や、電力の安定供給を口実にした原発依存への回帰にほかならない。東京電力福島第一原発事故の教訓を反故(ほご)にしてはならない。》
《脱炭素の潮流》と言いつつ、放射能汚染は気にしない。核発電は、究極の地球温暖化促進なのに、知らないふり。《電力の安定供給を口実にした原発依存への回帰》なのに、ザポリージャ原発で何が起きているのかを無視。安全保障が聞いて呆れる。海岸線沿いに一体何発の《原爆》を並べているの?
でっ、次世代革新炉「キシダメ」は明日にでも完成するのかね? 半年後くらい? 1年後? でっ、どこに造んの? 東京? 首相官邸? 自民党本部? アホですか。核発電麻薬中毒な皆さんは、そりゃぁ、大喜びでしょうね。
=====================================================
【https://www.tokyo-np.co.jp/article/198069】
3・11後、初の原発「新増設」を首相が明言 唐突な政策転換、被災者らに十分な説明なく
2022年8月26日 06時00分
原発への依存度を下げると訴えていた岸田文雄首相が唐突に、原発の運転期間の延長に加え、新増設や建て替えを検討する方針も表明した。2011年の東日本大震災での東京電力福島第一原発事故後、歴代首相は原発への依存度の低減を掲げており、新増設や建て替えの検討を明言したのは初めて。被災者らに十分な説明をしていないにもかかわらず、エネルギー政策を原発推進の方向に転換した。(我那覇圭、佐藤裕介)
松野博一官房長官は25日の記者会見で、従来の政府方針を転換するかを問われ、直接的には答えずに「エネルギーを巡る内外の情勢変化を踏まえれば、次世代革新炉の開発・建設を含め、あらゆる選択肢を排除することなく検討する」と述べるにとどめた。
首相は24日の「GX(グリーン・トランスフォーメーション)実行会議」で原発の新増設などの検討を表明。ロシアのウクライナ侵攻などで電力需給が逼迫ひっぱくしている現状を受け、自らの政治決断で進めると強調した。
福島原発事故後、旧民主党を含めたこれまでの政権は、原発の新増設や建て替えは「想定していない」と説明。首相も20年の自民党総裁選時に出した著書で「将来的には再生可能エネルギーを主力電源化し、原発への依存度は下げていくべきだ」と主張していた。
昨秋の自民党総裁選や衆院選でも、新規制基準に適合した原発を再稼働させる意向は示してきたものの、新増設などを封印する従来の政府方針は踏襲。今年7月の参院選公約で、それまで明記してきた「可能な限り原発依存度を低減」という文言を消したが「安全が確認された原子力の最大限の活用を図る」と記載するにとどめていた。
いずれの選挙でも原発政策が大きな争点となることはなく、与党が勝利し、首相は政権基盤を強化。自身に有利な政治環境を手に入れた途端に、故郷を奪われた被災者や原発の安全性に不安を抱く多くの国民の理解を得ないまま、政府方針を変更して新増設や建て替えを打ち出した。
原発政策に詳しい明治大の勝田忠広教授は「原発政策は(使用済み核燃料を処理して再利用する)核燃料サイクルがうまくいかず、『核のごみ』の最終処分方法も決まらず、既に破綻している」と指摘。その上で「首相はエネルギー危機をあおるばかりで、説明責任を果たしていない。まずは幅広い国民の意見を聞くべきだ」と語った。
【関連記事】政府が原発新増設「検討」と明示…福島事故から封印のはずが推進姿勢 運転期間の延長、計17基再稼働も
=====================================================
=====================================================
【https://www.tokyo-np.co.jp/article/198157?rct=editorial】
<社説>原発への回帰 福島の教訓はどこへ
2022年8月26日 07時43分
あの悲惨な原発事故をなかったことにしようというのか。政府がこれまでの方針を翻し、原発の新増設や建て替え、さらには法定寿命の延長まで検討するとの考えを明らかにした。脱炭素の潮流や、電力の安定供給を口実にした原発依存への回帰にほかならない。東京電力福島第一原発事故の教訓を反故(ほご)にしてはならない。
岸田文雄首相が二十四日、「GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議」の中で表明した。既に再稼働済みの十基に加え、来年の夏以降、新たに七基を再稼働させる方針も示した。
七基の中には、テロ対策上の重大な不備が相次いで発覚、地元自治体だけでなく、原子力規制委員会の強い不信を招いた東電柏崎刈羽原発なども含まれる。ロシアのウクライナ侵攻の影響による原油などの資源高が背景にあるが、政府が強引に再稼働を誘導すれば、安全性確保や住民の不信払拭(ふっしょく)が置き去りにされかねない。
「新増設や建て替えは想定していない」という3・11以来の大方針を転換し、今後、導入を目指す次世代型原発は、従来の軽水炉を改良する「革新軽水炉」や「小型モジュール炉(SMR)」などが想定されるが、安全性も経済性も未知数だ。いずれにしても開発途上で、当面の脱炭素への対応で主役になれるわけではない。
将来を考えるなら、エネルギー輸入の必要がなく、潜在力の高い再生可能エネルギーを充実させる方がよほど現実的で、何より安全だろう。蓄電技術の革新や送電網拡充による電力融通の強化といった面にこそ集中投資し、天候に左右されて供給が不安定だとされる弱点を克服していくべきだ。
原則四十年、特別な安全対策を施して六十年とする原発の法定寿命の延長方針に至っては、「老朽化」を「高経年化」と言い換え、不老長寿の夢を見た安全神話の復活と言うしかない。
「可能な限り原発依存度を低減する」という大方針は、あの福島の悲劇から導き出された重い教訓である。ただ脱炭素、資源高への対応だというのでは、方針転換の十分な理由には到底なりえない。
=====================================================
[※ 『原発に挑んだ裁判官』(磯村健太郎・山口栄二) 朝日新聞出版↑]
―――――― (樋口英明さん)《私が大飯原発を止めた理由は4つです。①原発事故のもたらす被害はきわめて甚大。だから、②原発には高度の安全性(事故発生確率が低いこと)が求められるべき。③地震大国日本において高度の安全性があるということは、高度の耐震性があるということにほかならない。④しかし、我が国の原発の耐震性はきわめて低い。ですから原発の運転は許されないのです。これは「樋口理論」と呼ばれています》《あらゆる運転差し止め訴訟で裁判官に原発の脆弱な耐震性を知らしめ、電力会社の非科学性と非常識を理解させることによって、日本の全ての原発は必ず停止できます》 (2021年10月03日[日])
(2021年10月03日[日])
週刊朝日のコラム【動かせと言って原発を止める方法 古賀茂明】(https://dot.asahi.com/wa/2021092500022.html?page=1)。
《まず、「原発はどうぞ動かしてください」というと議論を始める。その場は国会が望ましい。大手の電力会社の社長を呼んで国民の前で議論するのだ。原発を動かすための議論なら社長たちは拒否できない。そこで、最初に、安全性について質問する。日本には地震が多いから耐震性を高めることが重要だということに同意を求めたうえで、パネルを使って、日本では2000年以降、千ガル以上の地震が18回(ガルは揺れの強さを表す単位)、七百ガル以上は31回起きていることを示す。そのうえで、「民間の耐震住宅並みの強度は達成できていますよね」と質問すると、社長たちは、答えに窮する。なぜなら、住友林業、三井ホームの耐震性は、3400ガル、5100ガルだが、伊方原発は650ガル、高浜原発は700ガルと日本の原発の耐震性は非常に低いからだ。国民の多くは、原発は民間住宅の何倍も頑丈に作られていると信じている。そこで、電力会社の社長がどんなに難しい言葉を使って、原発の敷地だけは安全ですと叫んでみても、国民は「なんだ、これは!」と驚き憤る。こんな原発は止めろということになるのは確実だ》。
反・核発電に、高度な工学的知識は不要である…(樋口英明さん)《原発の耐震性は信頼度も基準値も一般住宅より、はるかに劣る》のだから。
『●裁判所も歪む…《国が開発の政策的な枠組みを決め、その下で
電力会社に》核発電所を…《そして裁判所も一体となり…》』
『●2014年5月大飯原発運転差し止め判決…樋口英明さんは《基準地震動を
超える地震が来ないと言えるかどうか…他の原発と共通の問題》』
『●元福井地裁裁判長・樋口英明さん《地震大国の日本には、
北海道から沖縄まで原発を動かせる場所はどこにもない》』
『●反核発電に、高度な工学的知識は不要である…(樋口英明さん)《原発の
《原発の耐震性は信頼度も基準値も一般住宅より、はるかに劣る》のだから』
『●《原発再稼働や増設を唱える連中の頭の中を掻っ捌いて、中身を見て
みたい》(鈴木耕さん)――― なぜ今直ぐ「原状回復」しないの?』
樋口英明さんは、以前から、《地震大国の日本には、北海道から沖縄まで原発を動かせる場所はどこにもない》と。まともな裁判官が、もっと増えないものか…。《老朽原発はもちろん、日本には強い地震に耐えられる原発はひとつたりともない》。高度な工学的知識や科学的な知識は不要だ、だって、《原発の耐震性は一般住宅よりもはるかに脆弱》《原発の耐震性は信頼度も基準値も一般住宅より、はるかに劣る》のだから。《住民や電力会社、弁護士や裁判官までもが「難しいに違いない」と“魔法”にかかってしまう》必要などない。
《毎年のように頻発する、やや強めの地震に襲われても危険ということです。原子炉は強い地震に耐えられても、原子炉に繋がっている配管や配電の耐震性は低い上に耐震補強も難しい。断水しても停電しても原発は大事故につながる。それが福島の教訓です》…何の教訓も得ていません。そのためには、最後に、樋口英明さんは《あらゆる運転差し止め訴訟で裁判官に原発の脆弱な耐震性を知らしめ、電力会社の非科学性と非常識を理解させることによって、日本の全ての原発は必ず停止できます》と仰っています。
樋口英明さん《私が大飯原発を止めた理由は4つです。…ですから原発の運転は許されないのです。これは「樋口理論」と呼ばれています》:
――――――――――――――――――――――――――――――
【https://maga9.jp/210630-6/】
伊藤塾 明日の法律家講座レポート
なぜ原発を止めたのか~原発の危険性について真剣に議論しよう! 講師:樋口英明氏
By マガジン9編集部 2021年6月30日
……
私が大飯原発を止めた4つの理由
私が大飯原発を止めた理由は4つです。①原発事故のもたらす被害はきわめて甚大。だから、②原発には高度の安全性(事故発生確率が低いこと)が求められるべき。③地震大国日本において高度の安全性があるということは、高度の耐震性があるということにほかならない。④しかし、我が国の原発の耐震性はきわめて低い。ですから原発の運転は許されないのです。これは「樋口理論」と呼ばれています。……
――――――――――――――――――――――――――――――
=====================================================
【https://dot.asahi.com/wa/2021092500022.html?page=1】
動かせと言って原発を止める方法 古賀茂明
政官財の罪と罰
2021/09/28 07:00
(古賀茂明氏)
自民党の新総裁が9月29日で決まる。その結果によって大きく影響を受けるものがある。それは、原発政策だ。
今回の総裁選では河野太郎氏の脱原発政策が揺らいだと話題になった。
河野氏は、再生可能エネルギー最優先を唱えるが、再エネだけでは足りない間は、安全が確認された原発の再稼働は認めると述べた。これが脱原発からの変節だと批判されたのだ。確かに、これまでの自民党の政策と大きくは違わないように聞こえる。だが、それは本心ではないというのが私の見立てだ。
実は、私はかねてより、「原発を動かせと言いながら廃炉にする方法」を提唱している。これは、河野氏にも提案している(返事はないが気に入ってもらえると思う。)簡単に解説しよう。
まず、「原発はどうぞ動かしてください」というと議論を始める。その場は国会が望ましい。大手の電力会社の社長を呼んで国民の前で議論するのだ。
原発を動かすための議論なら社長たちは拒否できない。そこで、最初に、安全性について質問する。日本には地震が多いから耐震性を高めることが重要だということに同意を求めたうえで、パネルを使って、日本では2000年以降、千ガル以上の地震が18回(ガルは揺れの強さを表す単位)、七百ガル以上は31回起きていることを示す。そのうえで、「民間の耐震住宅並みの強度は達成できていますよね」と質問すると、社長たちは、答えに窮する。なぜなら、住友林業、三井ホームの耐震性は、3400ガル、5100ガルだが、伊方原発は650ガル、高浜原発は700ガルと日本の原発の耐震性は非常に低いからだ。
国民の多くは、原発は民間住宅の何倍も頑丈に作られていると信じている。そこで、電力会社の社長がどんなに難しい言葉を使って、原発の敷地だけは安全ですと叫んでみても、国民は「なんだ、これは!」と驚き憤る。こんな原発は止めろということになるのは確実だ。
次に、万一事故が起きた時に損害をすべて賠償するために民間の保険に入ってくださいと要求する。「極めて安全で事故が起きる確率が極めて低いなら、非常に安い保険料で保険を引き受けてくれるはずではないか。安く引き受けてくれないということは、市場では、安全ではないと評価されているからだ」と言えば、やはり社長たちは答えに窮する。国民は、損害賠償できないのに原発を動かすべきではないと思う。
(再稼働に向けた動きが進む島根原発2号機(左)
(C)朝日新聞社)
三つ目に、避難計画の万全性を担保するために原子力規制委員会の審査を受けろと要求する。実際には審査されていないからだ。国民は「えっ?避難計画は規制委の審査を受けたんじゃないの?」と驚き、審査してもらえとなる。だが、専門家が審査したら、絶対に今の避難計画では通らない。
四つ目は核のゴミだ。原発のゴミも適切に処分できるんですよね、と社長に聞く。社長が頷いたら、「では、1カ月以内に最終処分までの計画を出してください」と言う。それは無理だというだろうから、では1年待つと言って、議論を終わる。
これで、全ての原発は動かなくなり、廃炉するしかなくなる。
国民の前で、ちゃんと議論すれば、止めろと言わずに止めるのは簡単だ。新政権には、是非そうした議論をして欲しい。
※週刊朝日 2021年10月8日号
■古賀茂明(こが・しげあき)/古賀茂明政策ラボ代表、「改革はするが戦争はしない」フォーラム4提唱者。1955年、長崎県生まれ。東大法学部卒。元経済産業省の改革派官僚。産業再生機構執行役員、内閣審議官などを経て2011年退官。近著は『官邸の暴走』(角川新書)など
=====================================================
[※ 『原発に挑んだ裁判官』(磯村健太郎・山口栄二) 朝日新聞出版↑] (2021年07月04日[日])
(2021年07月04日[日])
マガジン9の記事【伊藤塾 明日の法律家講座レポート なぜ原発を止めたのか~原発の危険性について真剣に議論しよう! 講師:樋口英明氏】(https://maga9.jp/210630-6/)。
《2014年5月21日、福井地裁の裁判長として大飯原発3、4号機の運転差し止め判決を出した樋口英明元裁判官。「原発事故によって放射性物質が拡散され生命を守り生活を維持することが困難となる危険があれば、人格権に基づいて原発の運転の差し止めを求めることができる」と話します。原発の危険性とは何か、大飯原発の運転差し止め判決に至った理由について詳しく説明してくださいました。[2021年5月29日@渋谷本校]》。
《3・11を経験した私たちの責任 最後に責任について話したいと思います。…最後に、キング牧師の教訓に満ちた言葉を紹介します。〈究極の悲劇は、悪人の圧政や残酷さではなく、善人の沈黙である。結局、我々は敵の言葉ではなく、友人の沈黙を覚えているものなのだ。問題に対して沈黙を決め込むようになったとき我々の命は終わりに向かい始める〉》。
反核発電に、高度な工学的知識は不要である…(樋口英明さん)《原発の耐震性は信頼度も基準値も一般住宅より、はるかに劣る》のだから…。《これは高度な専門技術訴訟ではなく、理性と良識を働かせれば判断できること》。《全ての原発が全く見当外れの低い耐震性で建てられたことが、我々の世代になって初めてわかったのです。こうした原発を後世の人々に押しつけるわけにはいきません。今の時代で解決しなければならない問題です》。
(樋口英明さん)《私が大飯原発を止めた理由は4つです。…ですから原発の運転は許されないのです。これは「樋口理論」と呼ばれています》。
樋口英明さんは、以前から、《地震大国の日本には、北海道から沖縄まで原発を動かせる場所はどこにもない》と。まともな裁判官が、もっと増えないものか…。《老朽原発はもちろん、日本には強い地震に耐えられる原発はひとつたりともない》。高度な工学的知識や科学的な知識は不要だ、だって、《原発の耐震性は一般住宅よりもはるかに脆弱》《原発の耐震性は信頼度も基準値も一般住宅より、はるかに劣る》のだから。《住民や電力会社、弁護士や裁判官までもが「難しいに違いない」と“魔法”にかかってしまう》必要などない。
《毎年のように頻発する、やや強めの地震に襲われても危険ということです。原子炉は強い地震に耐えられても、原子炉に繋がっている配管や配電の耐震性は低い上に耐震補強も難しい。断水しても停電しても原発は大事故につながる。それが福島の教訓です》…何の教訓も得ていません。そのためには、最後に、樋口英明さんは《あらゆる運転差し止め訴訟で裁判官に原発の脆弱な耐震性を知らしめ、電力会社の非科学性と非常識を理解させることによって、日本の全ての原発は必ず停止できます》と仰っています。
『●裁判所も歪む…《国が開発の政策的な枠組みを決め、その下で
電力会社に》核発電所を…《そして裁判所も一体となり…》』
『●2014年5月大飯原発運転差し止め判決…樋口英明さんは《基準地震動を
超える地震が来ないと言えるかどうか…他の原発と共通の問題》』
『●元福井地裁裁判長・樋口英明さん《地震大国の日本には、
北海道から沖縄まで原発を動かせる場所はどこにもない》』
《二〇一四年五月に福井地裁の裁判長として、関西電力
大飯原発3、4号機(福井県)の運転差し止め判決を出した。
今も自分が正しいと確信を持っている。大飯原発の基準地震動
(耐震設計上の想定の揺れ)は七〇〇ガル(揺れの勢いを示す加速度の
単位)で、重大事故につながる限界点は一・八倍の一二六〇ガルだと
関電は主張していた。私は裁判前は、三〇〇〇ガルのような強い揺れに
原発が耐えられるかどうかが争点になると予想していた。ところがふたを
開けてみれば、一二六〇ガルが来たらおしまいだというのは争いが
なかった。主な争点は「敷地内に一二六〇ガルを超える地震は来ない」
という関電の主張の信用性だった。それが争点なら難しい工学的判断は
不要で、理性と良識があれば簡単に解ける問題となる。地震大国の
日本では、原発で基準地震動を超える地震が頻発しており、大飯も
「ロシアンルーレット」状態だった。日本の国策は「安全な原発を
動かす」であって、「何が何でも動かす」ではない。私の「極めて
危険だから動かしてはいけない」という判断は、国策にも忠実だった
と思っている。仮に私が日本原子力発電(原電)東海第二原発の
差し止め訴訟を指揮するなら、ポイントは三つあると思う。一つは、
基準地震動を超える地震が来ないと言えるかどうか。
これは他の原発と共通の問題だ》
『●反核発電に、高度な工学的知識は不要である…(樋口英明さん)
《原発の耐震性は信頼度も基準値も一般住宅より、はるかに劣る》のだから』
=====================================================
【https://maga9.jp/210630-6/】
伊藤塾 明日の法律家講座レポート
なぜ原発を止めたのか~原発の危険性について真剣に議論しよう! 講師:樋口英明氏
By マガジン9編集部 2021年6月30日
2014年5月21日、福井地裁の裁判長として大飯原発3、4号機の運転差し止め判決を出した樋口英明元裁判官。「原発事故によって放射性物質が拡散され生命を守り生活を維持することが困難となる危険があれば、人格権に基づいて原発の運転の差し止めを求めることができる」と話します。原発の危険性とは何か、大飯原発の運転差し止め判決に至った理由について詳しく説明してくださいました。[2021年5月29日@渋谷本校]
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
大飯原発差し止め判決の理由
2014年5月21日、私は福井県にある大飯原発3、4号機の運転差し止め判決を下しました。当日、判決内容を事前に知っていたのは、裁判官3人と書記官1人だけです。福井地方裁判所の所長も、最高裁判所の長官も、原告側も、どんな判決が出るか知りませんでした。しかし、被告側は弁護士も含めて誰一人として法廷に来ませんでした。自分たちが負けると分かっていたから来なかったのです。
私は訴えが提起された当初から「大飯原発が危険だと思ったら止める。思わなかったら止めない」と言っていました。その言葉に従って裁判を進めてきました。関西電力の弁護士たちは、大飯原発が危険かどうかで判断されたら負けるとわかっていたんです。
みなさんは「原発が危険かどうかで再稼働の可否を判断するのは当たり前」と思うでしょう。しかし、多くの裁判では「原子力規制委員会が定める規制基準に施設や地盤が適合しているかどうか」で判断していて、原発が危険かどうかで判断しているわけではありません。私は「大飯原発が危険かどうか」を考えて運転差し止めを決めました。極めて当たり前の裁判をしただけだと思っています。
「危険」には2つの意味があります。たとえばお母さんが子どもに「そこの交差点は見通しが悪くて危険だから気をつけてね」と言う場合の危険は、「事故発生確率が高い」ということです。他方、「自転車で行くんだったら、危険だからヘルメットをかぶってね」と言うときの危険は、先ほどとは違います。ヘルメットをかぶってもかぶらなくても事故発生確率は変わらない。お母さんが心配しているのは、事故で子どもが頭を打って大怪我をすることです。要するに「被害が大きい」ことを危険と言ってるんです。「危険」というときには、この2つのどちらの意味かを考えなくてはいけません。
福島第一原発事故で明らかになったことは、被害の大きさでした。しかし、本当の意味での被害の大きさを知っている人は多くありません。いったい何が起きていたのか、これは原発の仕組みに関係しています。
原発は停電しても断水してもダメ
原発には牛乳瓶みたいな形をした格納容器があり、そのなかに原子炉圧力容器があります。この圧力容器のなかにウラン燃料が入っていて、水に漬けてあります。ウラン燃料の熱で水が沸騰して蒸気が発生し、それでタービンを回して発電しています。
火力発電所も仕組みは一緒です。石油を燃やして水を沸騰させて蒸気でタービンを回しています。しかし、原発と火力発電所では大きな違いが2つあります。ひとつは、原発の格納容器の中には広島型原爆1千発分の「死の灰」が含まれていることです。これが大きな違いです。もう一つはエネルギー量の違いですね。
火力発電所であれば、地震に襲われたら火を止めます。火を止めたら、その瞬間に沸騰しなくなります。原発は、制御棒をウラン燃料の間に差し込んで核分裂反応を止めても、沸騰が続いてしまいます。沸騰が続くとどうなるか。ウラン燃料が頭を出して、溶け落ちてしまいます。溶け落ちないようにするには、ウラン燃料を水と電気で冷やし続けなければいけない。
要するに、火力発電所は地震が来ても火を止めた瞬間に安全になります。しかし、原発は停電してもダメ、断水してもダメ。水と電気でウラン燃料を冷やし続けない限りメルトダウンするのです。ですから、福島第一原発は津波で停電しただけで、あんな大事故になったのです。これが原発の一番厄介なところです。
運よく助かったのは、欠陥があったから
福島第一原発では最悪の事故が起きた、とほとんどの人が思っていますが、実はそうではありませんでした。数々の信じられないような奇跡に救われていました。
まずは「2号機の奇跡」です。2号機はメルトダウンして格納容器が水蒸気と水素でいっぱいになりました。そうなると、「ベント」といって圧力を抜くしかありません。圧力を抜けば放射性物質が出てしまいますが、圧力を抜かなければ格納容器ごと破裂してしまうからです。しかし、当時は停電していたので自動ではベントができません。放射能を浴びてしまうので人間が行ってバルブを回すこともできない。要するに何もできませんでした。
3月15日になると、2号機の格納容器には設計基準の倍ほどの圧力がかかっていました。当時の福島第一原発の吉田所長は、「2号機の格納容器が爆発すれば、放射性物質をまき散らしてしまう。そうなれば東日本壊滅だろう」と思ったそうです。しかし、格納容器は爆発しませんでした。その理由は「よく分からない」のです。
どこか格納容器に弱い部分があって、そこから圧力が抜けたのでしょう。そんなことは絶対にあってはいけないことです。格納容器というのは放射性物質を閉じ込めるために本当に丈夫なものでなければいけません。だけど丈夫ではなかった。いわば2号機は欠陥機であったが故に助かった。これが「2号機の奇跡」です。
奇跡が重なって免れた「東日本壊滅」
さらに4号機でも奇跡がありました。4号機は当時発電しておらず、核燃料が装着されていませんでした。長年の運転で核燃料のエネルギー量が落ちていて、シュラウドという核燃料を入れておく場所も傷んできたので、取り替え工事を行っていました。その工事のために、原子炉ウェルというところに、水がいっぱい張ってありました。
3月11日に停電して、4号機の使用済み核燃料を冷やすための循環水がうまく回らなくなりましたが、エネルギー量が落ちていたために、その日のうちにはメルトダウンしませんでした。しかし、4日もすれば貯蔵プールの水が減って使用済み核燃料が頭を出します。そうなればメルトダウンする。そうなると、福島第一原発から250kmが避難区域になる可能性がありました。東京も含まれています。
しかし今、我々は東京に住めます。なぜかというと、原子炉ウェルと貯蔵プールの仕切りがずれたからです。ずれたことで原子炉ウェルの水が貯蔵プールに入り、メルトダウンを防ぎました。仕切りがずれた原因は今も不明です。本来は震災4日前に原子炉ウェルの水を抜き取る予定だったのですが、工事が遅れていたので水があったのです。ほとんど神がかり的です。さらに、貯蔵プールの上で水素爆発が起きて屋根が吹き飛んだために、放水車を使って破れた天井から水を注入することができました。
実際には、ほかにもさまざまな奇跡が重なりました。いくつも起きた奇跡のうち、ひとつでも欠けていれば東日本は壊滅していたのです。これが、本当の福島原発事故の被害の大きさです。
原発は地震に耐えられるのか
こういう話をすると、多くの人は「それだけ被害が大きなものなら、それなりに事故発生確率も抑えてあるはずだ」と思ってしまいます。たとえば時速300キロで走る新幹線がトラックなどと衝突したら大惨事になりますよね。ですから、そうならないように踏切をなくしています。世の中のものは大抵そうなっているので、「原発での大きな事故は滅多に起きないだろう」と考えてしまうのです。でも、本当にそうでしょうか。
先ほど話したように、原発は停電しても断水しても過酷事故につながります。停電や断水をもたらす一番大きな要因は地震です。配電や配管に関する耐震性が高ければ、原発の事故発生確率も低くなります。では、2000年以降の主な地震の強さと原発施設の耐震性で確認してみましょう。地震の大きさは「マグニチュード」、強さは「震度」で表すことが多いですが、震度は7までしかないので耐震設計では「ガル」という単位を使います。ガルは震度と同じく地震の揺れの強さを測る単位です。
2000年以降の地震でいうと、2016年の熊本地震はマグニチュード7.3、1740ガルでした。一番高いものは2008年の岩手宮城内陸地震で、マグニチュード7.2、4022ガルです。わが国は地震大国ですが、2000年まで地震観測網がありませんでした。全国に地震計を置くようになったのは阪神・淡路大震災以降なので、それ以前はまともな資料がないのです。
次に、原発施設の耐震性ですが、私が判決した大飯原発3・4号機の耐震性(基準地震動)は405ガルで設計されていました。3・11当時には、なぜか700ガルに上がっています。大飯原発だけではありません。福島第一原発は建設当時270ガル、3・11当時は600ガルです。東海第二原発は、建設当時270ガル、3・11のときは600ガルで、今は1009ガルです。いずれも老朽化するに従って耐震性が上がっていくという不思議な現象が起きてます。それでもこの程度の耐震性しかありません。巨大地震が原発を襲ったらもう絶望的です。
巨大地震というのは大体マグニチュード8以上をいいますが、この耐震性ではマグニチュード7あるいは6や5でも直撃すれば危ない。つまり、原発は「被害が大きくて」かつ「事故発生確率も高い」という2つが揃ったパーフェクトな危険だということです。ですから運転を止めるのは当たり前なのです。しかし、3・11以降でも原発を止めなかった裁判は数えきれないくらいあります。
原発容認派の弁解
原発容認派は、原発は硬い岩盤の上に建っているので、地震計が置いてある地表面より揺れが小さいと弁解します。たしかに岩盤の上に直接建っている原発もありますが、そうではないものもあります。たとえば東海第二原発の場合は、岩盤は地下深く300メートルのところにあり、その上に関東ローム層があり、その上に原発が建っています。
また、岩盤の揺れが普通の地面の揺れより小さいとも言いきれません。石川県にある志賀原発は硬い岩盤の上に直接建っていますが、能登半島地震に襲われたときの揺れは490ガルでした。一方、志賀町の地震計は540ガルを記録しています。ほとんど変わりませんでした。柏崎刈羽原発はもっと極端で、地下の岩盤で1699ガルでしたが地上では1000ガルくらいでした。硬い岩盤では揺れが小さいとは言いきれず、例外はいくらでもあります。
もうひとつの弁解に、強震動予測という方法に則って計算すると、原発敷地に限っては将来にわたって震度6や7の地震は来ないというものがあります。しかし、それは本当に信用できるのでしょうか。東大地震研究所の纐纈一起先生が、地震はものすごく複雑な現象で、「地震は観察できない、実験できない、資料がない」と「地震学の三重苦」について話しています。観察と実験と資料というのは科学の基礎ですが、その基礎がないのに地震予知ができると考えるのには無理があります。
日本は列島全体が4つのプレートの境目に位置している世界で唯一の国。非常に複雑な地盤構造があり、世界の地震の10分の1以上が日本で起きています。日本には地震の空白地帯はありません。2000年以降だけでも、日本で1000ガル、2000ガルの地震はいくらでも起きています。こうした科学的事実に基づいて裁判をしなくてはいけません。
なぜ裁判官は原発を止めないのか
では、なぜ多くの裁判官は原発を止めないのでしょうか。理由は簡単です。多くの裁判官は、大飯原発を例にとると700ガル以上の地震が過去に何回起きたのか、700ガルは震度いくつなのか、700ガルでは住宅が倒れるかどうか、といったことを知らないのです。それは原告側の弁護士が教えないからです。
弁護士も裁判官も前例に従って「原子力規制委員会の独立性が高いのか」「原発の施設や敷地が規制基準に合致しているのか」ばかりに関心を払っていて、実際に起きている地震に対して原発の耐震性が高いか低いのかということには関心がなく、そのことについてまったく審理されていません。
ここに、愛媛県の伊方原発について住民らの原子炉設置取消請求を棄却した1992年の最高裁判所判決の骨子があります。法律家というのは最高裁判決を尊重するものですが、この判決では
①原発訴訟は高度の専門技術訴訟であり、
②裁判所は原発の安全性を直接判断するのではなく、規制基準の合理性を判断すればよく、
③その判断は最新の科学技術知見による
と言っています。
たとえば①では、プルトニウムと普通のウラン燃料を混ぜたMOX燃料を原発で使うと危険かどうかの判断は素人にはわからないことです。あるいは、その原発が本当に3000ガルに耐えられるかどうかが訴訟の争点だとしたら、それはとてつもなく難しい専門技術訴訟といえます。しかし「この原発敷地に限っては700ガル以上の地震は来ない」という主張が信用できるかどうか――これは高度な専門技術訴訟ではなく、理性と良識を働かせれば判断できることです。
②も間違いではありません。私はこれを「裁判所は原発の安全性を直接判断する必要まではない。規制基準が国民の安全を図る内容になっているかどうかを審査するのだ」と理解します。規制基準というものは、福島第一原発事故を踏まえて原発の安全性を高めるために設けられました。ですから、「規制基準の合理性」というのは、国民の安全を守れる内容になっているかどうかを考えればいいのです。
今の規制基準は、原発ごとの最大地震動が予測できるという前提で成り立っています。しかし、先ほども話したように地震予測は不可能ですから、地震予測が可能だという前提で作られている規制基準は不合理であり、それでは国民の安全は守れません。
次に③ですが、「最新の科学技術知見」とは何でしょうか。2000年以降、1000ガル2000ガルの地震はいくらでも日本に起きています。これこそが「最新の科学技術知見」です。
多くの法律家がこのように考えることができないのは、極端な権威主義だといえます。権威主義とは、「何を言ってるか」の内容ではなく「誰が言っているか」を尊重することです。最高裁判所が言うのなら原発訴訟は難しい専門技術訴訟に違いない、と争点の設定まで最高裁に委ねてしまうんです。ほかにも科学より科学者を信じる「科学者妄信主義」や「頑迷な先例主義」によって、正当な判断ができなくなっています。
もっと普通に、審判の対象となる「訴訟物」から考えればいいのです。つまり、人格権が侵害されそうになったら、人格権に基づいてその予防措置を求めることができるということです。この場合、人格権が侵害されるというのは原発事故が起きることです。そして、原発事故は停電や断水でも起こり得る。つまり配電・配管の耐震性が低ければ人格権が侵害される危険が高いということなので、それについて調べましょうという発想です。
しかし、多くの裁判ではそのように訴訟物から考えるのではなく、過去の裁判例をみて、学者が支持しているからとか、規制基準の辻褄が合っているから、などの先例主義で判断してしまうのが現状です。
私が大飯原発を止めた4つの理由
私が大飯原発を止めた理由は4つです。①原発事故のもたらす被害はきわめて甚大。だから、②原発には高度の安全性(事故発生確率が低いこと)が求められるべき。③地震大国日本において高度の安全性があるということは、高度の耐震性があるということにほかならない。④しかし、我が国の原発の耐震性はきわめて低い。ですから原発の運転は許されないのです。これは「樋口理論」と呼ばれています。
従前の裁判では、裁判官も弁護士も、電力会社が設定した「専門技術訴訟」という土俵に自ら乗り込んでいました。一部の弁護士が多くの専門書を読み、専門家に意見を聴いて、電力会社との間で専門技術論争をする。たとえば「地震動の計算方法は、武村式がいいか、入倉式がいいか」といったことです。しかし、それは学会で議論することです。原告はもちろん、裁判官やほとんどの弁護士にも分かるはずがありません。その結果、「原子力規制委員会がそう言うなら、尊重しましょう」という結果になるんです。
武村式か入倉式か、ということは本当の争点ではありません。そういう論争はもう止めて、これからの原発差止め裁判は「理性と良識」という土俵で戦いましょう。そうすれば誰でも理解できるし、誰でも議論に加われるし、誰でも確信を持つことができます。
昨年3月11日、樋口理論に基づき、広島地裁で伊方原発3号機の運転差し止め仮処分の申し立てがありました。この申し立て書は、住民が書いています。昔は地震観測記録がなかったのですが、今はインターネットで気象庁の地震観測記録、K-NET(防災科学技術研究所の強震観測網)などを見ることができますし、原発の設計基準がいかに低いのかも調べられます。原発の耐震性が低いということを簡単に立証できるので、住民本人でも訴状を書くことができるのです。
その訴訟の中で、大変なことがわかりました。日本で一番恐れられている「南海トラフ地震が原発直下で起きたとしても、伊方原発の敷地には181ガルしか来ない」と四国電力が言っているのです。181ガルというのは震度5弱です。震度5弱は「棚から物が落ちることがあり、希に窓ガラスが割れて落ちることがある」という揺れです。マグニチュード9の地震というのは、3・11東北地方太平洋沖の地震と同じ。あのとき震源から380km離れた新宿でも、200ガルを超えました。普通に考えればとてつもなくおかしなことですが、専門技術訴訟にのめり込むとこういうことを見逃してしまいます。普通に考えて普通に裁判すれば、勝てると思います。
3・11を経験した私たちの責任
最後に責任について話したいと思います。
私が大学に入学した1972年(昭和47年)当時は、田中角栄内閣の時代でした。そのとき日本は、電源三法を作って原発を各地に誘致しました。その人たちの責任より3・11を経験した私たちの責任は、はるかに重いのです。
その理由は3つあって、一つ目は「死の灰」の問題です。30、40年前の人たちは死の灰の問題を、後世の人たちが科学的に処理してくれるのではないかと考えていました。しかし、それが不可能だということが40年の間にはっきりわかりました。二つ目は、昔の人は、原発事故は滅多に起きないし、起きたところで被害は30キロ圏内で済むだろうと思っていました。しかし、3・11を経験して、そうではないことがわかりました。
そして、三つ目ですが、昔は地震観測網がなかったので、関東大震災の規模でも400ガルを超える程度だろうと考えられていました。大飯原発も405ガルの耐震性で建てられています。しかし、実際には日本には1000ガルどころか4000ガルの地震も起きています。全ての原発が全く見当外れの低い耐震性で建てられたことが、我々の世代になって初めてわかったのです。
こうした原発を後世の人々に押しつけるわけにはいきません。今の時代で解決しなければならない問題です。
最後に、キング牧師の教訓に満ちた言葉を紹介します。
〈究極の悲劇は、悪人の圧政や残酷さではなく、善人の沈黙である。結局、我々は敵の言葉ではなく、友人の沈黙を覚えているものなのだ。問題に対して沈黙を決め込むようになったとき我々の命は終わりに向かい始める〉
*
ひぐち・ひであき 1952年生まれ。三重県出身。京都大学法学部卒業後、83年4月に福岡地方裁判所判事補任官。85年4月より静岡、宮崎、大阪など各地の地方裁判所・家庭裁判所の判事補・判事を経て、2006年4月より大阪高裁判事、09年4月より名古屋地家裁半田支部長、12年4月より福井地裁判事部総括判事を歴任。14年5月21日、福井地裁の裁判長として大飯原発3、4号機の運転差し止め判決、15年4月14日には高浜原発3、4号機の差し止め仮処分決定を出した。17年8月、定年退官。主な著書に『私が原発を止めた理由』(旬報社)。
=====================================================
[※ ↑「原発さえなければと思います」(週刊金曜日、2021年03月12日、1320号)] (2021年06月20日[日])
(2021年06月20日[日])
日刊ゲンダイのインタビュー記事【注目の人 直撃インタビュー/樋口英明氏「耐震性に着目すれば全ての原発を止められる」】(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/290370)。
《コロナ禍のドサクサ紛れに掟破りだ。福島第1原発事故の惨事を機に定めた「運転は40年まで」の原則が骨抜き。運転開始から40年を超える関西電力の老朽原発が23日にも再稼働する。この暴挙に、かつて原発運転を差し止めた元裁判長が「不都合な真実」を喝破する。「老朽原発はもちろん、日本には強い地震に耐えられる原発はひとつたりともない」と――。》
『●60年間稼働させたい高浜原発:
「電気代が高い低いの問題とを並べて論じること自体、許されない」』
『●「老いた馬」ではなく「狂ったゴジラ」:
「麻薬」患者の関電がプルサーマルに続いて「寿命核発電所」…』
『●「仏様のおかげ」はもう期待しない方がいい:
高浜原発、「このゴジラが最後の一匹だとは思えない」』
『●なぜ命を軽々しく賭して、「たかが電気」のために
核発電する必要があるのか? 次も神様・仏様は居るか?』
『●「あとの祭り」: 核発電「麻薬」中毒患者、増殖中
…どんどん壊れ行くニッポン』
『●高浜「寿命核発電所」延命、「安全より
経済優先の時代へと逆戻り」…「規制緩和」委員会(©東新)』
『●寿命核発電所再稼働:「世界は既に廃炉時代
時代の先端を行く方が、地域の実りははるかに多い」』
『●東京電力核発電人災から10年経って、この有様…アンダーコントロール
どころか人災は継続中、しかも、まだ核発電を続けたいという…』
『●「狂ったゴジラ」「老朽原発」「寿命核発電所」…40年超核発電所の
稼働という「麻薬」に手を出す核発電「麻薬」中毒者らの暴走』
「狂ったゴジラ」「老朽原発」「寿命核発電所」さえ、再稼働したいそうだ。処理水という名の汚染水を海洋放出したいそうだ。新規原発さえ、作りたいそうだ。
狂っています、核発電「麻薬」中毒者ら。
『●裁判所も歪む…《国が開発の政策的な枠組みを決め、その下で
電力会社に》核発電所を…《そして裁判所も一体となり…》』
『●2014年5月大飯原発運転差し止め判決…樋口英明さんは《基準地震動を
超える地震が来ないと言えるかどうか…他の原発と共通の問題》』
『●元福井地裁裁判長・樋口英明さん《地震大国の日本には、
北海道から沖縄まで原発を動かせる場所はどこにもない》』
《二〇一四年五月に福井地裁の裁判長として、関西電力
大飯原発3、4号機(福井県)の運転差し止め判決を出した。
今も自分が正しいと確信を持っている。大飯原発の基準地震動
(耐震設計上の想定の揺れ)は七〇〇ガル(揺れの勢いを示す加速度の
単位)で、重大事故につながる限界点は一・八倍の一二六〇ガルだと
関電は主張していた。私は裁判前は、三〇〇〇ガルのような強い揺れに
原発が耐えられるかどうかが争点になると予想していた。ところがふたを
開けてみれば、一二六〇ガルが来たらおしまいだというのは争いが
なかった。主な争点は「敷地内に一二六〇ガルを超える地震は来ない」
という関電の主張の信用性だった。それが争点なら難しい工学的判断は
不要で、理性と良識があれば簡単に解ける問題となる。地震大国の
日本では、原発で基準地震動を超える地震が頻発しており、大飯も
「ロシアンルーレット」状態だった。日本の国策は「安全な原発を
動かす」であって、「何が何でも動かす」ではない。私の「極めて
危険だから動かしてはいけない」という判断は、国策にも忠実だった
と思っている。仮に私が日本原子力発電(原電)東海第二原発の
差し止め訴訟を指揮するなら、ポイントは三つあると思う。一つは、
基準地震動を超える地震が来ないと言えるかどうか。
これは他の原発と共通の問題だ》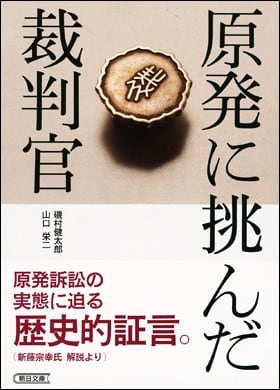
[※『原発に挑んだ裁判官』(磯村健太郎・山口栄二) 朝日新聞出版(https://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=21028)↑]
樋口英明さんは、以前から、《地震大国の日本には、北海道から沖縄まで原発を動かせる場所はどこにもない》と。まともな裁判官が、もっと増えないものか…。《老朽原発はもちろん、日本には強い地震に耐えられる原発はひとつたりともない》。高度な工学的知識や科学的な知識は不要だ、だって、《原発の耐震性は一般住宅よりもはるかに脆弱》《原発の耐震性は信頼度も基準値も一般住宅より、はるかに劣る》のだから。《住民や電力会社、弁護士や裁判官までもが「難しいに違いない」と“魔法”にかかってしまう》必要などない。
《毎年のように頻発する、やや強めの地震に襲われても危険ということです。原子炉は強い地震に耐えられても、原子炉に繋がっている配管や配電の耐震性は低い上に耐震補強も難しい。断水しても停電しても原発は大事故につながる。それが福島の教訓です》…何の教訓も得ていません。そのためには、最後に、樋口英明さんは《あらゆる運転差し止め訴訟で裁判官に原発の脆弱な耐震性を知らしめ、電力会社の非科学性と非常識を理解させることによって、日本の全ての原発は必ず停止できます》と仰っています。
『●東電旧経営陣に無罪判決…《誰も事故の責任を
取らなければ企業に無責任体質がはびこり、また同じことが起きる》』
『●JOC臨界事故で何が起きたでしょうか?…《人が制御
できないなんて恐ろしい。政府は…本当のことを言っていない》』
『●永渕健一裁判長、東電旧経営陣の刑事裁判で「無罪」《判決の
中身もさることながら、その理由があまりにもひどすぎる》』
『●東京新聞の小野沢健太記者によるシリーズ記事【<原発事故
「無罪」>】…《判決に表情変えず 遺族ら「うそー」悲鳴》』
『●裁判所も歪む…《国が開発の政策的な枠組みを決め、その下で
電力会社に》核発電所を…《そして裁判所も一体となり…》』
『●《今なお続く福島の「不条理」》:東電の初期の主張は「無主物」
…裁判所は《放射性物質…農家が所有》と言い放った』
『●伊方原発3号機、広島高裁(森一岳裁判長)が運転差し止めの
仮処分決定…種々の問題に加えて《約10秒》《2~3秒》全電源喪失』
『●森一岳裁判長《原発の危険性検証には『福島原発事故のような
事故を絶対に起こさないという理念にのっとった解釈が必要…』》』
『●《良心に従い職権を行使する独立した存在》ではない
大久保正道裁判長である限り、アベ様忖度な「行政判断」が続く』
『●東京電力核発電人災の刑事裁判: 東京地裁永渕健一裁判長の
判決は、あまりに酷い理由も含めて《司法犯罪とも言える不当判決》』
『●「イチケイのカラス」第2話 ――― 裁判官らの謝罪と憲法第76条
「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この…」』
『●裁判所も歪む…《国が開発の政策的な枠組みを決め、その下で
電力会社に》核発電所を…《そして裁判所も一体となり…》』
=====================================================
【https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/290370】
注目の人 直撃インタビュー
樋口英明氏「耐震性に着目すれば全ての原発を止められる」
公開日:2021/06/14 06:00 更新日:2021/06/14 06:00
(樋口英明氏(撮影)タカオカ邦彦)
■樋口英明(元福井地裁裁判長)
コロナ禍のドサクサ紛れに掟破りだ。福島第1原発事故の惨事を機に定めた「運転は40年まで」の原則が骨抜き。運転開始から40年を超える関西電力の老朽原発が23日にも再稼働する。この暴挙に、かつて原発運転を差し止めた元裁判長が「不都合な真実」を喝破する。「老朽原発はもちろん、日本には強い地震に耐えられる原発はひとつたりともない」と――。
◇ ◇ ◇
――再稼働する美浜3号機の運転開始は1976年。45年も昔です。
45年前の家電を今も使いますか? 大量生産の家電は壊れても最新技術の製品に買い替えればいいけど、原発は大量生産できない。技術は旧態依然で、1つの計器が故障しただけで原発の「止める・冷やす・閉じ込める」の安全3原則は綻び、重大事故が起きかねません。
――再稼働にあたり国は、1発電所につき25億円の新たな交付金を立地地域にぶら下げました。
何を考えているのか、理解不能です。
――福井県知事の合意表明が4月28日。たった2カ月足らずのスピード再稼働にも驚きます。
住民が差し止め訴訟を起こすにも、手続きには月単位の時間がかかる。それを見越した上での素早い動きでしょう。
――老朽原発が「高い安全性」を確保できるか否かが最大の危惧です。
地震大国の日本で原発の高い安全性を担保するのは、信頼できる強度な耐震性に尽きます。原発の耐震設計基準を「基準地震動」と呼び、施設に大きな影響を及ぼす恐れがある揺れを意味します。美浜3号機の基準地震動は993ガル(揺れの強さを示す加速度の単位)。しかし、この国では1000ガル以上の地震が過去20年間で17回も起きているのです。
――具体的には?
2008年の岩手・宮城内陸地震(M7.2)は最大4022ガル、11年の東日本大震災(M9)は最大2933ガルなどです。誤解して欲しくないのは「17カ所」で観測されたわけではないこと。東日本大震災では、震源地から離れた数多くの観測点で1000ガルを超えました。
■「原発の耐震性は一般住宅よりもはるかに脆弱」
――基準地震動を超える地震がいつ襲ってきてもおかしくはない、と。
しかも、美浜3号機の基準地震動は建設当時の405ガルからカサ上げされています。建物の耐震性は老朽化すれば衰えるのに、原発だけは時を経るにつれて耐震性が上がるとは不可思議です。電力会社は「コンピューターシミュレーションで確認できた」と言い張りますが、計算式や入力する数値でどうにでも変わる。住宅メーカーの耐震実験は建物を実際に大きな鉄板の上で揺さぶります。その結果、三井ホームの住宅の耐震設計は5115ガル、住友林業は3406ガル。2社が飛び切り高いのではなく、改正後の建築基準法は一般住宅も震度6強から震度7にかけての地震に耐えられるよう義務づけています。ガルで言うと1500ガル程度の地震には耐えられます。一方、日本の原発の基準地震動は、ほぼ600ガルから1000ガル程度です。つまり、原発の耐震性は信頼度も基準値も一般住宅より、はるかに劣るのです。
――衝撃です。
政府は福島の原発事故後の新規制基準を「世界一厳しい」と自負していますが、耐震性に関しては当てはまりません。
――いつ、その事実に気づかれたのですか。
2012年11月に福井県の住民が中心となって関西電力を相手に提訴した「大飯原発3、4号機の運転差し止め請求訴訟」を担当した際です。原発の耐震性に着目し、調べてみると、すぐ分かりました。当時は大飯原発を含め、大半の原発の基準地震動は700ガル程度。700ガル以上の地震は過去20年間で17回どころではなく30回に跳ね上がります。毎年のように頻発する、やや強めの地震に襲われても危険ということです。原子炉は強い地震に耐えられても、原子炉に繋がっている配管や配電の耐震性は低い上に耐震補強も難しい。断水しても停電しても原発は大事故につながる。それが福島の教訓です。
(2014年に福井地裁で大飯原発の運転差し止め判決
(C)共同通信社)
■電力会社の「地震は来ない」は虚妄
――それにしても、基準地震動の設定が低すぎませんか。
地震学者の間では長年、関東大震災(震度7)でも400ガル程度との認識が主流で、地球の重力加速度(980ガル)以上の地震は来ないとも推測されていました。この考えに従い、昭和時代の原発は建設されたと思います。しかし、1995年の阪神・淡路大震災を契機に、2000年頃には全国の約5000カ所に地震計が設置され、観測網が整備されました。すると、震度7が1500ガル以上に相当することが科学的に判明したのです。
――震度の過小評価に気づけば、原発の運転は諦めるべきでは?
そこで電力会社が「不都合な真実」を隠すのに持ち出すのが「地震予知」です。差し止め訴訟で「原発の敷地に700ガル以上の地震は来るんですか」と聞くと、関西電力は「まず来ません」と答えた。科学で一番難しいのは将来予測。中でも地震の予知は困難を極めます。考察に資するリソースも20年分しかない。「来ない」と断言できっこないのです。地震予知は「予言」に等しく、信じるか否かは「理性と良識」の問題です。だから速やかに差し止め判決を出せたのです。
――その2014年の福井地裁判決を、2018年には名古屋高裁金沢支部の控訴審判決が取り消しました。
退官翌年です。あの確定した判決は、原審で指摘した危険性を認めながら突然、論旨を変えて「原発の是非は司法の役割を超えているので政治的判断に委ねる」と結論づけた。運転停止を求める住民に対して、さも「政治活動」をしているかのレッテルを貼り、論点をスリ替え、司法の役割を放棄したのです。こんな粗雑な判決を放置するわけにはいかないと思い、原発の危険性を広く訴えようと決意しました。
――元同僚の方々の反応は?
特に悪い評判は聞きません。「裁判官は弁明せず」との格言を持ち出すような頭の固い人とは、あまり付き合ってこなかったからかなあ? 裁判官への政治圧力もないですよ。昔は政府方針に従わなかった裁判官が、ひどいドサ回りをさせられたのは事実。けれど、最近は露骨な左遷などありません。
■学術論争の“魔法”から目を覚ませ
――福島の事故後も、原発の運転差し止めを認めた司法判断は必ず上級審で覆ります。その理由をどう考えますか。
先例主義の悪弊です。裁判官が原発訴訟を扱うのは、まれです。滅多に当たらない訴訟を担当すると、裁判官はつい過去の判決を調べてしまう。いくら司法修習生の頃に「自分の頭で考えろ」と叩き込まれても、自分の頭で考えなくなる。判例に頼れば通常は大きな間違いをせずに済むし、何より楽ですから。その傾向は上級審の裁判官ほど強い。そして、ある“魔法”も効いています。
――魔法とは?
1992年に確定した伊方原発訴訟の最高裁判例です。原発訴訟を「高度の専門技術訴訟」とし、今でも最高裁は原発差し止め訴訟を「複雑困難訴訟」と呼ぶ。あくまで一般論に過ぎないのに、最高裁に言われると、住民や電力会社、弁護士や裁判官までもが「難しいに違いない」と“魔法”にかかってしまう。法廷は理解不能な専門用語が飛び交う学術論争の場となり、もともと文系の裁判官はロッカーいっぱいの専門資料にチンプンカンプン。だから、過去の判例を踏襲する判決を出しがちになるのです。
――困ったものです。
裁判官を“魔法”から解き放つには、まず住民側の弁護士が目を覚まさなくてはいけない。熱意ある弁護士でも先例に縛られ、複雑な学術論争を繰り出すのが実情です。住民側弁護士が原発の危険性をシンプルかつ論理的に伝えれば、裁判官も認めざるを得ません。伊方最高裁判例には「原発の安全性の適否判断は規制基準に不合理な点があるかという観点から行うべき」と記してある。はたして地震予知を許す規制基準は合理的なのか。20年間の詳細な地震観測による新たな知見、すなわち「1000ガルを超える地震はいくらでも来ます」という動かしがたい事実に基づく判断こそが合理的であり、「真の科学」と言えます。
――なるほど。
現在、広島地裁で係争中の伊方原発3号機の運転差し止め仮処分申し立て事件では、住民側の弁護団が耐震性に着目。四国電力の「南海トラフ地震が原発直下で起きても、伊方原発敷地には181ガル(震度5弱相当)しか来ない」との試算を追及し、原発訴訟にパラダイムシフトを起こすと宣言しました。あらゆる運転差し止め訴訟で裁判官に原発の脆弱な耐震性を知らしめ、電力会社の非科学性と非常識を理解させることによって、日本の全ての原発は必ず停止できます。
(聞き手=今泉恵孝/日刊ゲンダイ)
▽樋口英明(ひぐち・ひであき) 1952年生まれ、三重県出身。京大法学部卒。司法修習第35期。各地裁・家裁の判事補・判事を歴任。2006年に大阪高裁判事、09年に名古屋地家裁半田支部長を経て、12年から福井地裁判事部総括判事。14年5月に大飯原発3、4号機の運転差し止めを命じる判決を下した。17年8月、名古屋家裁部総括判事で定年退官。現在は原発の危険性を訴える講演活動にいそしむ。今年3月出版の「私が原発を止めた理由」(旬報社)がベストセラーに。
=====================================================

東京新聞の社説【3・11から9年 千年先の郷土を守る】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2020031102000169.html)。
《女川原発は、震源に最も近い原発です。福島同様、激しい揺れと津波に襲われました。到達点よりわずかに高い所にあったため、辛うじて難を逃れたにすぎません。…東北の被災原発を再稼働に導いて、「復興原発」にしたいのか。原発は安全です、ちゃんと制御(アンダー・コントロール)できていますと、五輪を前に世界へアピールしたいのか》。
『●《草木のすべてにセシウムが染みついている。田畑を耕すが自分で
食べるだけ。孫には食べさせないし、売ることもできない》』
《五輪開催年の完全版上映について「国は福島の問題を『終わったこと』
と見せたいようだ。福島の人たちの人生をめちゃくちゃにして
おきながら、はしゃいでいられるのか」と語る》
『●東電核発電人災から9年: 金(カネ)色の五つの輪《オリンピック
聖火リレーを前に「福島はオリンピックどごでねぇ」》』
《「状況は、アンダーコントロール」「汚染水の影響は、港湾内の
0.3平方キロの範囲内で完全にブロック」「健康問題については、
今までも、現在も、将来も全く問題ありません」と。あれから6年。
いま、私たちの目の前にある現実は、どうでしょう》
『●三浦英之記者の質問「今でも『アンダーコントロール』だとお考え
でしょうか」? アベ様のお答え「…その中で正確な発信をした…」!?』
「アベ様のお答えの一部…「正確な情報発信した」!! COVID19問題
と言いい、開いた口が塞がらない…。
息吐く様にウソをつくアベ様の本領発揮」
「アベ様口癖の「悪夢のような旧民主党政権」…あらゆる意味で、
悪夢のような最悪な政権はもはや明白です」
《あれから6年。いま、私たちの目の前にある現実は、どうでしょう。
メルトダウンした核燃料は所在すらつかめていません。壊れたままの
原子炉建屋には毎日百数十tの地下水が流れ込み、ALPS処理汚染水は
溜まり続け、漁民や住民の意思を無視して海洋への放出が
画策されています。(共同声明より)》
『●桜井勝延氏《そこで経験したことは、国も県も政治家も、現場を見も
しないでものごとを決定し、責任をとろうとしないという現実だった》』
女川にしろ、東海第二にしろ、核発電所再稼働なんてやっている場合なのか? 「地元」首長の皆さんは、再稼働に同意するのですか? アベ様の《復興原発》に協力するつもり? 東京電力福島第一核発電所周辺の「原状回復」は完了したのですか? 「福島の百姓は終わりだ」という悲嘆を、《今なお続く福島の「不条理」》を、「福島はオリンピックどごでねぇ」ことを、《福島の教訓》をもう忘れたのですか?
『●言葉が見つかりません…』
《須賀川市の野菜農家の男性(64)は、福島産野菜の一部に国の
出荷停止指示が出された翌日の二〇一一年三月二十四日に自殺した。
遺族によると、男性は原発事故後「福島の百姓は終わりだ」
と話していたという》
『●「原発さえなければ」「福島の百姓は終わりだ」:
東京電力原発人災と自殺には因果関係あり』
『●「原発事故で奪われた生業と地域を返せ」…人災を
起こした東京電力や政府は「原状回復」してみせたのか?』
『●原状回復できない現実: 「12万円で、あとはもう黙ってろ、
自然に放射能さがんの待ってろっつうこと」』
『●「あれだけの事故を起こして被害を出して、
だれか1人でも責任とってやめたか。申し訳ないと謝罪したか」』
《福島第一原発事故から5年。あの時、父親を自死により失った樽川和也さん
が語るドキュメンタリー映画「大地を受け継ぐ」…。制作者らが映画に
込めた思いとは――。井上淳一監督、企画した馬奈木厳太郎弁護士、
出演した白井聡・京都精華大専任講師(政治学)…》
『●3.11東京電力原発人災から4年: 虚しき
「地球にやさしいエネルギー原子力 人にやさしい大熊町」』
『●東電旧経営陣に無罪判決…《誰も事故の責任を取らなければ
企業に無責任体質がはびこり、また同じことが起きる》』
『●《今なお続く福島の「不条理」》: 東電の初期の主張は
「無主物」…裁判所は《放射性物質…農家が所有》と言い放った』
『●《失われた古里》、失われた《本来は恵みをもたらす田畑の土》
…原状回復して見せたのか? 誰か責任は?』
NNNドキュメント’20より。
-- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --
【http://www.ntv.co.jp/document/backnumber/archive/31190.html】
2020年3月8日(日) 24:55【拡大枠】
3・11大震災シリーズ(90)
東日本大震災9年
約 束
~それぞれの道~
東日本大震災から9年。被災地では多くの人が懸命に生きている。家族との約束。仲間との約束。故郷への約束。果たしたい約束がある。それは心の支えだ。津波で流された自宅を再建したいと願う老夫婦。震災で家族を失い、1000年後の命を守ろうと中学時代の仲間と石碑の建立に取り組む青年。原発事故で一度はあきらめかけた牧場を復活させ、将来は息子にバトンをつなぎたいと考える男性。岩手・宮城・福島の3局共同制作で送る。
ナレーター/土村芳 放送枠/55分
制作/テレビ岩手 ミヤギテレビ 福島中央テレビ
-- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --
《◆ふるさとを奪わないで 女川いのちの石碑には、震災直後に生徒たちが詠んだ句を一句ずつ刻んでいます。原発に近い塚浜の公園に立つ十三番目の石碑には、こんな句が添えられました。 <故郷を 奪わないでと 手を伸ばす> この痛切な願い、忘れるわけにはいきません》。《建てているのは、女川中学校卒業生の有志でつくる「女川1000年後のいのちを守る会」》(https://www.inochino-kyoukasho.com/)。
この痛切な願いを、誰よりも忘れたがっているのは、アベ様らではないのですか? だって、《あの未曾有の福島第一原発事故を招いた“最大の戦犯”が、他ならぬ現内閣総理大臣》アベ様なのですから。
『●「想定外」という言い訳は許されない』
『●”原子力発電”という箱を開ける覚悟と、(とりようの無い)開けた責任』
『●SLAPPと原発、沖縄』
『●『DAYS JAPAN』
(2013,SEP,Vol.10,No.9)の最新号についてのつぶやき』
「さらに、斎藤美奈子さんの二つの指摘。「第一次安倍内閣時代…
吉井英勝…「巨大地震の発生…原発の危機から国民の安全を守る
ことに関する質問主意書」
…提言を無視した結果がご覧の通りの事故である」」
『●(リテラ)「あの未曾有の福島第一原発事故を招いた
“最大の戦犯”が、他ならぬ現内閣総理大臣・安倍晋三」』
=====================================================
【https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2020031102000169.html】
【社説】
3・11から9年 千年先の郷土を守る
2020年3月11日
牡鹿半島の付け根に位置する宮城県女川町は、東北電力女川原発のある町です。
リアス海岸の岬を巡るとあちこちで、高さ二メートル、幅一メートルほどの平たい石碑に出合います。「女川いのちの石碑」です。
建てているのは、女川中学校卒業生の有志でつくる「女川1000年後のいのちを守る会」。今月一日、十八基目ができました。
あの日女川町は、最大一四・八メートルの津波に襲われました。
人口約一万人のうち、死者・行方不明者は八百二十七人に上り、全住宅の九割に当たる約三千九百棟が被害に遭いました。
東日本大震災の被災市町村の中で、最も被災率の高かった町だと言われています。
◆大震災を記録に残す
震災翌月、当時の女川第一中(二〇一三年に女川第二中と統合して女川中)に入学した一年生は、社会科の授業で「ふるさとのために何ができるか」を話し合いました。そして「震災を記録に残す」活動の実践に乗り出すことを決めたのです。
町内に二十一ある浜の集落すべてに津波は押し寄せました。
それぞれの津波到達点に石碑を建てておこう、ふるさとの風景に震災の記憶を刻みつけ、千年先まで命を守る避難の目安にしてもらおう-。
街頭やSNSで寄付を募ると、半年で目標額の一千万円が集まりました。
石碑には、警告が刻まれます。
<ここは、津波が到達した地点なので、絶対に移動させないでください。もし、大きな地震が来たら、この石碑よりも上へ逃げてください。逃げない人がいても、無理矢理にでも連れ出してください。家に戻ろうとしている人がいれば、絶対に引き止めてください>
◆津波わずかに高ければ
末尾には、卒業生から未来へ贈るメッセージも添えました。
<今、女川町は、どうなっていますか? 悲しみで涙を流す人が少しでも減り、笑顔あふれる町になっていることを祈り、そして信じています>と。
第一号は一三年十一月、女川浜を見下ろす母校の校庭に建ちました。今年中には二十一基目が完成し、プロジェクトは完了する予定です。
そんな女川町でも、原発再稼働の手続きが最終段階を迎えています。
女川原発は、震源に最も近い原発です。福島同様、激しい揺れと津波に襲われました。到達点よりわずかに高い所にあったため、辛うじて難を逃れたにすぎません。
原発の敷地は、大地震の影響で一メートルも沈下しました。原子炉建屋の壁からは、千百三十カ所ものひび割れが見つかりました。
震災で、満身創痍(そうい)にされた原発です。原子力規制委員会の審査を終えて、規制基準に「適合」と判断されはしたものの、とても安心とは言えません。規制委も安全だとは言いません。
「あと三十センチ津波が高ければ、福島と同じになったと思います。原発に絶対の安全はなく、ふるさと喪失のリスクが付きまとう。福島の教訓です。再稼働を許すとすれば、これからも多大なリスクを、しょっていかねばならんのです。住民の命を預かるものとして、そんなことはできません」
原発から三十キロ圏内にある宮城県美里町の相沢清一町長は、再稼働にきっぱりと「ノー」を突きつけます。
「目の前に、現実の課題が山積みです。風化だなんてとんでもない。(放射性物質をかぶった)稲わらひとつ、処分できない。避難計画をつくれと言われても、なかなか答えが見つからない。高齢者はどうなるか? 複合災害が起こったときは? 途中で風向きが変わったら? 隣町から逃げて来る人たちは?…。(国や東北電力は)何をそう急ぐのか」
東北の被災原発を再稼働に導いて、「復興原発」にしたいのか。原発は安全です、ちゃんと制御(アンダー・コントロール)できていますと、五輪を前に世界へアピールしたいのか。
いずれにしても、原発のある風景や暮らしの中に刻み込まれた震災の痕跡を、見過ごすことはできません。風化を許してはいけません。
その一つ一つが、未来ではなく、今を生きる私たちへの「警告」になるはずだから。
◆ふるさとを奪わないで
女川いのちの石碑には、震災直後に生徒たちが詠んだ句を一句ずつ刻んでいます。
原発に近い塚浜の公園に立つ十三番目の石碑には、こんな句が添えられました。
<故郷を 奪わないでと 手を伸ばす>
この痛切な願い、忘れるわけにはいきません。
=====================================================

東京新聞の記事【高浜1、2号機、新基準に適合 老朽原発が相次ぎ延命も】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201602/CK2016022502000138.html)と、
社説【高浜原発40年超へ 安全文化はどこへ】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016022502000142.html)、
そして、コラム【筆洗】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/hissen/CK2016022502000143.html)。
《原子力規制委員会は…七月七日に運転期間満了を迎える関西電力 高浜原発1、2号機…対策などを進めれば、新規制基準に適合するとの審査書案を了承した。老朽原発が新基準を満たす初めての判断》。
《四十年を超えた関西電力高浜原発1、2号機が、新規制基準に適合と判断された。安全のために定めた「寿命」の原則は、もう、反故にされたのか》。
み~んな、核発電「麻薬」患者、特に、関電は重傷。プルサーマルに続き、今度は「寿命核発電所」を再稼働したいそうだ。アタマオカシイノデハ? 狂っているとしか言えません。
『●関西電力八木誠社長のあの高浜原発:
「プルサーマル原発」に続き「寿命原発」を動かしたいそうです』
『●「値上げ脅迫」: 無策の関西電力・・・
東京電力原発人災以降、一体何をやってきたのか?』
『●川内原発再稼働: 「経済麻薬」=思考停止、
「他の方法で経済発展する手を考えることを放棄させる」』
『●狂気・凶器「プルサーマル発電は新規制基準下では初」
……もう何でもアリな原子力ムラの大暴走』
『●「大切なのは「信頼」だ」…
だからもう病気なんですってば!? 核発電「麻薬」患者』
《原子力規制委員会が老朽化した関西電力高浜原発1、2号機の安全対策に対し、新規制基準に適合していると、判断した。老いた馬をなお走らせるのか》。
「老いた馬」ではなく「狂ったゴジラ」なり。 「愚」を繰り返すニッポン……「このゴジラが最後の一匹だとは思えない」。「仏様のおかげ」にまだ縋ろうとする関電、アベ様、原子力「寄生」委員会、「地元」賛成派、等々。
『●「仏様のおかげ」はもう期待しない方がいい:
高浜原発、「このゴジラが最後の一匹だとは思えない」』
『●「暴走するゾウ、ゴジラを解き放とう
という「愚」」な東電をどのように「信頼」すればよいのか?』
「安全神話」「不老神話」を支えるものが、またしても、経済性とは……原子力「推進」委員会=「寄生」委員会は芯から腐っている。
『●関西電力の「原発再稼働」への言い訳にさせてはいけない』
「原発の稼働が発電コストの低減になるという関電側の主張も退ける。
極めて多数の人々の生存そのものにかかわる権利と、電気代が
高い低いの問題とを並べて論じること自体、許されないと、怒りさえ
にじませているようだ。経済神話の否定である」
「大飯再稼働、差し止め命じる 生存と電気代、同列許さず」
「また、生存権と電気代のコストを並べて論じること自体が「法的には
許されない」ことで、原発事故で豊かな国土と国民生活が取り戻せなく
なることが「国富の喪失」だと指摘。福島事故は「わが国が始まって
以来、最大の環境汚染」であり、環境問題を原発推進の根拠とする
主張を「甚だしい筋違い」と断じた」
「「極めて多数の人の生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いの
問題とを並べた議論の当否を判断すること自体、法的には許されない」
として、経済活動よりも生存に関わる人格権を優先した」
=====================================================
【http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201602/CK2016022502000138.html】
高浜1、2号機、新基準に適合 老朽原発が相次ぎ延命も
2016年2月25日 朝刊
原子力規制委員会は二十四日の定例会合で、七月七日に運転期間満了を迎える関西電力高浜原発1、2号機(福井県)について、原子炉建屋の放射線対策やケーブルの防火対策などを進めれば、新規制基準に適合するとの審査書案を了承した。老朽原発が新基準を満たす初めての判断となった。
東京電力福島第一原発事故後に改正された原子炉等規制法では、原発の運転期間は四十年に制限され、最大二十年間の運転延長は「例外」とされてきたが、早くも例外が認められる見通しとなった。今後、延長を目指す電力会社が相次ぎ、実質的に「六十年廃炉」になっていく恐れがある。
この日の会合で、事務局は、建屋上部に遮へいドームを造り、ケーブルには防火シートを巻き、事故時の対策拠点を新設するなど関電の方針を説明。これらが実行されれば、新基準を満たすとした。委員から若干の質問は出たが、審査書案に異論はなく、議論は十五分ほどで終わった。
規制委は二十五日から三月二十五日まで意見募集を実施して審査書を決定。対策工事の詳細設計や老朽化の審査も進めた上で、延長の可否を決める。
四十年廃炉の原則は二〇一二年、米国の制度も参考にして法制化された。二十年延長の例外規定も設けられたが、当時の細野豪志原発担当相(民主党)は「例外が認められるのは、極めて厳しい。例外中の例外」と明言していた。
四十年超の原発を延命させるためには、新基準で要求される設備を整えるほか、老朽化に伴い原子炉がもろくなっていないか、建屋のコンクリートの強度は十分かなどの審査にもパスすることが求められる。
関電は、1、2号機は出力が八十二万六千キロワット、3、4号機は八十七万キロワットと大きく、新基準などに適応する対策費に四基合わせて約三千百九十億円をかけても採算が合うと判断した。
新基準ができた後、関電美浜1、2号機(福井県)など五基の廃炉が決まったが、いずれも最大五十万キロワット台と比較的小さい。
今後十年のうちに、十五基が四十年を迎え、廃炉か延長か判断を迫られる。しかし、大型化の傾向は明確で、十一基までが八十万キロワット超。もっと新しい原発は百万キロワット超が主流だ。
各社とも方針を明らかにしていないが、採算性を優先すれば、延長を狙ってくる可能性が高い。そうなれば、四十年廃炉の原則は失われることになる。
◆規制委「費用かけ克服」
原子力規制委員会の田中俊一委員長は二十四日の定例記者会見で、老朽原発の関西電力高浜1、2号機(福井県)が新規制基準に基づく審査に適合としたことに関し、「(老朽原発も)費用をかければ技術的な点は克服できる」と述べた。
田中委員長は今後の老朽原発の審査方針について「個々に判断していく」としたほか、高浜原発の追加の安全対策について「新しく原発を造る半分の費用がかかっている。それなりの覚悟があったのだろう」と述べ、関電の対応に一定の評価を示した。
=====================================================
=====================================================
【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016022502000142.html】
【社説】
高浜原発40年超へ 安全文化はどこへ
2016年2月25日
四十年を超えた関西電力高浜原発1、2号機が、新規制基準に適合と判断された。安全のために定めた「寿命」の原則は、もう、反故(ほご)にされたのか。
五年前のあのころに、気持ちを戻してみてほしい。
3・11を教訓として、私たちは繰り返し訴えてきたはずである。
今世紀に入って新たに運転を始めた原発は、東北電力東通1号機など五基しかない。
四十年寿命を厳格に適用し、役目を終えれば直ちに停止、廃炉に向かう。おおむね二〇三〇年代に原発は停止して、北海道電力泊3号機の寿命が尽きる四九年の暮れまでに国内の原発はゼロになる。
その間に、不要になった送電網や港湾施設を活用しつつ、風力や太陽光など再生可能エネルギーを普及させていくべきだ-と。
国民の大勢も、そのように感じていたはずだ。
折しも3・11は、東京電力福島第一原発の1号機が、運転開始四十年を迎えるちょうど半月前。四十年の当日には、原発の廃炉と福島の未来を考えようという市民グループ「ハイロアクション福島原発四十年実行委員会」が、結成イベントを開くはずだった。
廃炉時代は3・11以前から、始まっていたのである。
一二年の年明け早々、当時の民主党政権が「原発の運転期間は原則四十年」の方針を打ち出した。
「ほとんどの原子炉は中性子の照射により四十年で脆化(ぜいか)する」という設計思想に基づいて設定された“寿命”である。
脆化とは「もろくなる」ということだ。
原子炉の心臓部に当たる圧力容器の内側には、核分裂で生じる中性子が当たり続けてもろくなる。つまり、こわれやすくなるのである。その限界が四十年。高レベルの放射能を浴びており、交換も不可能だ。原発の寿命が最長四十年という理屈は通る。
旧式の圧力容器は材質が悪く劣化が早い。四十年も持たないと、前倒しを求める意見も目立つ。
それなのに「一度だけ最大二十年延長できる」という例外規定が、法律に付いてきたのはなぜか。
そして3・11の教訓をこめた新しい原発規制に、なぜそれが踏襲されたのか。
「世界の潮流にならい」というのが政府の説明だった。要は「米国のルールを取り入れた」ということなのだろう。
ところが、本家の米国でさえ、3・11以降、求められる補修や改善に費用がかかり過ぎるとして、延命をやめて、閉鎖、廃炉に踏み切る原発が増えている。二十年という延長期間の方こそ、根拠が薄いのではないか。
◆“不老神話”の誕生か
原子力規制委員会は例外を認める条件として、通常より格段厳しい特別点検や安全対策の大幅な強化を義務付けてはいる。
しかし、心臓部は交換不能、新しい部品のつなぎ目から問題が生じる恐れがあるとの指摘もある。補修による延命にはやはり、限界があるとは言えないか。
経済産業省が昨春示した三〇年の電源構成(ベストミックス)案は、総発電量に占める原発の割合を「20~22%」と見込んでいる。
四十年寿命を守っていては、達成できない数字である。
例外規定の背後には、福島の教訓放棄、安全神話の復活、そして、新増設をも視野に収めた原発回帰の未来が透けて見えないか。
関電は、同じ老朽原発の中でも、出力が低い小型の美浜1、2号機はすでに運転を終了し、美浜3号機を含む中型の運転延長を願い出た=図参照。
安全への配慮からというよりも、補修にかかる費用と再稼働の利益をてんびんにかけ、そろばんをはじいた上での判断だ。
◆工学は寿命を決める
一九五〇年代前半、世界初のジェット旅客機である「コメット」の事故が相次いだ。航空機業界はその反省に立ち「安全寿命設計」という考え方を採り入れた。
たとえば長距離型のジャンボでは、総飛行六万時間、離着陸二万回が“寿命”になるという。
電力業界に安全思想、安全文化が根付いているとは、言い難い。
私たちは、もう一度訴える。
原発の四十年寿命は厳格に守り、円滑な廃炉や核のごみの処分に備えるべきである。
=====================================================
=====================================================
【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/hissen/CK2016022502000143.html】
【コラム】
筆洗
2016年2月25日
男は街角で動かぬ年老いた馬を見たという。一八八九年一月三日、イタリア・トリノでのことだそうだ。御者がどんなに脅しつけても馬は頑として動かない。御者は烈火のごとく怒り、馬を鞭(むち)で打ち始めた▼見かねた男は駆け寄って御者の仕打ちを止めた。泣きながら馬の首を抱きかかえ、そのまま、倒れた▼男は哲学者のニーチェである。二日後、目を覚ましたが、その時には、精神を完全に病んでいたという。ハンガリーのタル・ベーラ監督による映画「ニーチェの馬」(二〇一一年)で知った。キリスト教的道徳や憐憫(れんびん)に否定的だったニーチェだが、この逸話には同情と優しさがあふれている▼あの白黒映画の馬の哀(かな)しげな顔が、振り払っても浮かんでくる話である。原子力規制委員会が老朽化した関西電力高浜原発1、2号機の安全対策に対し、新規制基準に適合していると、判断した。老いた馬をなお走らせるのか▼原発の運転期間は原則四十年でそれを超える高齢原発の「合格」は初めてという。再稼働には原子炉建屋に放射線を遮るドームを建設することや、ケーブルの火災対策強化など必要だが、それさえもが、老いて休ませるべき馬を動かすための無理で非情な鞭に見えなくもない▼しかもそれは馬ではない。間違いや老朽化による変調など絶対に許されぬ、扱いの難しい装置である。鞭打たれるものが心配である。
=====================================================


東京新聞の二つの記事【高浜3・4号機 意見公募 答えず「適合」】(http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015021390070823.html)と、
【高浜・審査適合 「地元」とはどこなのか】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015021302000160.html)。
asahi.comの社説【関西電力高浜原発―再稼働前に地元を見直せ】(http://www.asahi.com/paper/editorial.html?iref=comtop_pickup_p)。
最後に、東京新聞のコラム【筆洗】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/hissen/CK2015021302000129.html)。
「パブリックコメント(意見公募)には、原発が集中立地する危険性や避難計画の実効性が審査されないことなどに多くの意見や疑問が寄せられた。だが、規制委は、事故が起きても一定レベルに収まると想定して判断する姿勢を変えず、すれ違いが目立った」・・・・・・。
「すれ違い」どころか、原子力「ムラ寄生」委員会は「適当」過ぎる。責任感がなさすぎる。
『●日本中が「地元」・・・・・・
大間原発と高浜原発の再稼働問題、「30キロ圏内の声を聴け」ではダメ』
「あとは地元同意があれば、関西電力 高浜原発(福井県)は再び動きだすという。原発事故の恐怖と影響は全国に降り注ぐ-。福島の教訓だったはず。地元とはどこだろう。地元同意とは何だろう」・・・・・・。「九州電力 川内原発(鹿児島県薩摩川内市)に続いて2例目・・・・・・今後の焦点は地元自治体の同意だ。その範囲に法的な定めはない。川内原発では鹿児島県知事の判断で、県と薩摩川内市に絞られた。安倍政権はこれを基本としており、今回も関電と福井県知事は福井県と高浜町のみを同意の対象にする方向」・・・・・・・。
悪魔の負の連鎖。自民党・電力会社をはじめ、原子力ムラ住人はやりたい放題やっている。
アタマオカシイノデハ? 東京電力原発人災で何も学ばない「地元」とは何だろう? たとえ「法的な定め」はなくとも、「東京電力原発人災の教訓」から学べっ! 環境倫理観から、(世界のどこにも原発を稼働して良い場所などないが、百万歩譲っても)ニッポンで原発を稼働させるなんて許されないでしょっ!!
『●原発再稼働の負の連鎖: 「川内方式」を「妥当」なんて、とんでもない!』
「原子力という巨獣が暴れだした時、神仏ならぬ身がいかに非力か。いやというほど悟ったはずなのに、事故対策の不備ぶりを裁判所も危惧するような状態で、なぜ再稼働を認めうるのか」?
大津地裁「再稼働を容認するとは到底考え難い」・・・・・・虚しい空しい、司法の無力。関電や自民党は、裁判所の判決を屁とも思っていないようだ。自身に都合よくしか判断しない。
『●関西電力八木誠社長のあの高浜原発:
「プルサーマル原発」に続き「寿命原発」を動かしたいそうです』
「【大飯、高浜再稼働 「早急な容認考えがたい」】
(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2014112802000128.html)
には、「大津地裁(山本善彦裁判長)は二十七日、
「現時点で差し止める必要性はない」として、却下する決定・・・・・・
決定文では、差し止めの必要性がないとした理由を原発の安全性の
観点からではなく「原子力規制委員会が、いたずらに早急に、
再稼働を容認するとは到底考えがたい」からとした」」
『●「アベノミクス選挙という愚」
『週刊金曜日』(2014年12月05日、1019号)について』
「伊田浩之氏【大飯、高浜原発めぐり大津地裁 再稼働の不備を指摘】、
「原子力規制委員会・・・・・・がいたずらに早急に、新規制基準に
適合すると判断して再稼働を容認するとは到底考え難い」。
川内原発の現状を考えると・・・・・・??
(http://blog.goo.ne.jp/activated-sludge/e/437d41ad3bcdeef8c3d9569fd54d21af)」
「愚」を繰り返すニッポン・・・・・・「このゴジラが最後の一匹だとは思えない」。
『●東電の「万全」神話: 「作業員の安全を祈らずにはいられなかった」』
「東京・有楽町にあるゴジラ像のプレートにこんな言葉が刻まれている。
「このゴジラが最後の一匹だとは思えない」・・▼怪物は、水爆実験に
よって出現する。公開と同じ年の三月、ビキニ環礁で水爆実験の
「死の灰」を浴びた、第五福竜丸事件が下敷きになっている。
原作ではゴジラは第五福竜丸の帰還とともに日本にやってくる
▼「水爆などいい気になっていたら、人間は自分たちの力で完全に滅びる」。
監督の本多猪四郎さん・・・・・・警告は、残念ながら現代に生かされていない。
・・・・・・ゴジラは科学技術を使う人間の心の闇の中にすみ続けている
▼像の言葉は登場する科学者のせりふで、まだ続きがある。
「同類が世界のどこかに現れてくるかもしれない」。ゴジラだらけである」
==============================================================================
【http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015021390070823.html】
【社会】
高浜3・4号機 意見公募 答えず「適合」
2015年2月13日 07時08分
【↑ブログ主注: 勝手ながらコピペさせて頂きました
(http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/images/2015021399070823.jpg)】
原子力規制委員会は十二日、関西電力高浜原発3、4号機(福井県)が原発の新しい規制基準を満たしているとの審査書を正式に決めた。パブリックコメント(意見公募)には、原発が集中立地する危険性や避難計画の実効性が審査されないことなどに多くの意見や疑問が寄せられた。だが、規制委は、事故が起きても一定レベルに収まると想定して判断する姿勢を変えず、すれ違いが目立った。
意見公募には約三千六百件が寄せられた。この日の会合では、主な意見と規制委の見解を併記する資料も公表された。
高浜原発が立地する若狭湾周辺には、関電大飯、美浜、日本原子力発電敦賀の三原発、高速増殖原型炉「もんじゅ」もあわせ計十四基が立ち並ぶ。同時多発的に事故が起き、事故収束の要員が不足したり、他の原発から高濃度の放射性物質が飛来し、高浜での作業ができなくなったりする懸念の声も寄せられた。
規制委は、各原発で十分な要員や資材を準備しており、「それぞれの炉で独立して事故対応にあたれる」と回答。寄せられた疑問には直接答えなかった。
記者会見で、集中立地の問題を問われた田中俊一委員長は「同時多発的に起きても、それぞれのところできちっと対策が取れる」とかわした。
東京電力福島第一原発事故では、放射線量が上がったり、水素爆発の危険が増したりして作業員が待避する事態が何度も起きた。「新基準を満たせば、作業に影響がある事故にならないと決めつけているのはなぜか」との問いもあったが、規制委は新基準が求める対策により「作業に支障がないことを確認した」と回答するにとどまった。
また、地図上では高浜原発に通じる道路は一本の県道しかなく、必要な外部支援が厳しい事態も起きうる。この懸念に対しては、七日間は支援なしに対応できることが新基準の要求だとして、問題ないとの考えを示した。
複数の道があるような記述が回答欄にあったため、規制委や関電に取材すると、「機密」として具体的には明かさなかったが、徒歩による支援要員の投入しか審査していないと答えた。
避難計画の実効性を、規制委が審査すべきだとの意見もあったが、田中氏は「そういう(避難の)事態にならないように規制サイドとしてやっている」と説明した。
(東京新聞)
==============================================================================
==============================================================================
【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015021302000160.html】
【社説】
高浜・審査適合 「地元」とはどこなのか
2015年2月13日
あとは地元同意があれば、関西電力高浜原発(福井県)は再び動きだすという。原発事故の恐怖と影響は全国に降り注ぐ-。福島の教訓だったはず。地元とはどこだろう。地元同意とは何だろう。
何度でも繰り返す。原子力規制委員会の審査書は、安全のお墨付きではない。3・11後の新規制基準を満たすという、いわば車検証のようなものである。
そんな規制委の手続きが終了し、地元同意が焦点になる。法的拘束力はないものの、事実上、再稼働への最後の関門だ。
では地元とは、どこなのか。川内原発の時にも、議論になった。
3・11後に改められた国の安全指針では、原発から半径三十キロ圏内の自治体に、原発事故を想定した避難計画の策定が義務付けられた。そこで、三十キロ圏内にある立地以外の自治体からも、同意を求める声が上がった。当然の要求だろう。
ところが、原子炉の置かれた鹿児島県と薩摩川内市の同意を得ただけで、再稼働の準備は進む。
高浜の場合は、川内よりも複雑だ。三十キロ圏が原発のある福井県だけでなく、京都府と滋賀県にもまたがっているからだ。
京都府は先月末、同意権なしの協定を関電と結ぶ方向で一致した。自治体側からの意見表明は、原発の増設時などに限られる。
滋賀県の嘉田由紀子前知事は「被害地元」という考え方を提唱し、現知事が引き継いだ。原発事故で被害を受ける自治体はすべて「地元」なのである。近畿の水がめである琵琶湖の汚染を恐れる人は、大阪などにも少なくない。
福島の事故では、たとえば、村域のほとんどが三十キロ圏外の福島県飯舘村が、放射能による全村避難を余儀なくされた。どこが被害地元になるかは、その時々の複雑な気象条件次第である。科学的な線引きは難しい。福島の教訓を忘れてはならない。3・11後、地元の意味も大きく変化した。
関電も福井県の西川一誠知事も川内同様、「地元同意は立地自治体(県と高浜町)だけだ」と言う。原発の恩恵を受けない自治体を含めれば、結論に時間がかかるだろう。
電力自由化を控えて、電力会社は再稼働を急ぐ。利益が大きいからである。しかし、最優先すべきはいうまでもなく、安全だ。
国が今なすべきことは、再稼働を急ぐより、原発ゼロへの道筋を示すことである。そうでなければ、多くの国民の不安は消えない。
==============================================================================
==============================================================================
【http://www.asahi.com/paper/editorial.html?iref=comtop_pickup_p】
関西電力高浜原発―再稼働前に地元を見直せ
2015年2月14日(土)付
関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)について、原子力規制委員会が「新規制基準を満たしている」と正式に認めた。九州電力川内原発(鹿児島県薩摩川内市)に続いて2例目となる。
今後の焦点は地元自治体の同意だ。その範囲に法的な定めはない。川内原発では鹿児島県知事の判断で、県と薩摩川内市に絞られた。安倍政権はこれを基本としており、今回も関電と福井県知事は福井県と高浜町のみを同意の対象にする方向だ。
原発事故が広大な地域に被害を及ぼすことは、東京電力福島第一原発事故が示した現実だ。事故前と変わらぬ枠組みで原発を動かしていいはずがない。
同意対象を県と立地の1自治体に限る方式を既成事実化するのではなく、再稼働の前に地元の範囲を定め直すことを改めて求めたい。
高浜原発は、事故時に住民の即時避難が必要な5キロ圏に京都府舞鶴市が含まれる。国が避難計画策定を義務づけた30キロ圏内だと京都、滋賀両府県の8市町が入る。人口は12万人を超え、福井県側の約5万人を上回る。
大飯(福井県)、玄海(佐賀県)、伊方(愛媛県)、島根(島根県)、志賀(石川県)。規制委の審査が進むこれらの原発も、近隣に他府県を含む。
高浜原発での地元同意は、試金石となってこよう。
■立地の権限共有を
地元同意の根拠は立地自治体が事業者と結ぶ安全協定だ。
全国に原発が増えた70年代以降、トラブルも多発した。しかし情報は事業者と国に握られ、地元はしばしばかやの外に置かれた。住民の立場から安全を監視しようと、立地自治体は協定を結び、情報を求めてきた。
福井県が各事業者と結んでいる協定には、事故後の再稼働の事前協議に加え、自治体が原発の運転停止を求めることができる条項もある。事故やトラブルのたび、事業者と粘り強い交渉を重ねて得てきた権限だ。
一方で福島の事故後、周辺市町村の住民も事故に不安を抱き、「立地並み」の協定を望む声が各地の自治体から相次ぐ。
関電はこの求めに否定的だ。京都府と協議中の新たな協定案でも、同意権は認めない方向だ。福井県知事も「立地自治体は責任を持ち、リスクを負ってきた経緯がある」と強調する。
かかわりの薄い地域にカギを握られることには、警戒感もあるだろう。
しかし周辺自治体が再稼働の判断に加わることは、より多くの目で安全性を広く監視していくことにつながる。安全性を独自にチェックし、不十分であれば再稼働にノーと言う。立地自治体が勝ち取ってきたこの成果を周辺自治体と共有することで、同意を得る地元の範囲を広げていきたい。
■避難と同意をセットで
福井、京都、滋賀3府県と関係市町は、国の原子力災害対策指針にもとづき広域の避難計画をつくった。しかし計画通りに避難できるのか、細かな調整は緒に就いたばかりだ。
福井で原発事故が起きれば、3府県の十数万人が主に関西方面へ避難する可能性がある。
渋滞で混乱が生じる恐れもある。避難者用のバスの確保など、詰めるべき課題は多い。
2府5県と4政令指定市でつくる関西広域連合は今年1月、広域避難の実効性確保などに、国が主体的に取り組むよう申し入れた。「実行されなければ、高浜の再稼働を容認できる環境にない」とくぎを刺している。
住民の安全に責任を負う自治体からは、再稼働前の了解を得るのが筋だ。避難対象という側面から、当面は原子力災害対策指針が定めた30キロ圏を同意対象にすべきだ。そのうえで協定で位置づけている地元同意を、将来的には法に明記することを考えてもよい。それほど重いプロセスであることを、事業者側に認識させる意味もある。
■「地元」を結い直す
12年の大飯原発再稼働の時には消費地・関西の首長らが一時反対を表明し、福井県が孤立感を深めたことがあった。電力を使う側の一方的な主張に、福井県では不信感が根強くある。
対立を乗り越え、広い意味での「地元」の関係を結い直す取り組みが不可欠だ。
国主導で、福井と関西各府県の知事、原発30キロ圏の首長に集まってもらい、新たな地元の範囲や権限について、合意形成を図ってはどうだろう。
原発内のプールにたまった使用済み核燃料をどこで貯蔵するか。老朽原発を廃炉にする場合、経済の柱を失う地域をどう支えるか。立地地域と、電力消費地が手を携えて解決しなければならない課題は数多い。
手間はかかる。だが、福島原発事故が残した宿題に向き合う時間を惜しむべきではない。
原発をどうするかは、国民全体で決めていくべきテーマだ。福井と関西とで、それに向けた一歩を踏み出してほしい。
==============================================================================
==============================================================================
【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/hissen/CK2015021302000129.html】
【コラム】
筆洗
2015年2月13日
「仏様のおかげとしか思えないんです」。福島第一原発の3号機ですさまじい水素爆発が起き、にもかかわらず一人も落命せずに済んだ時、当時の吉田昌郎所長は、そう思ったという▼原子力の巨大な力を人間は本当に制御しきれるのか。「できる」というのが原子力ムラの方々の答えなのだろうが、考えてみれば、福井にある技術開発用の原子炉の名は「ふげん」に「もんじゅ」だ▼「普賢菩薩(ぼさつ)は象、文殊菩薩は獅子に乗られ、それぞれ巨獣の強大な力を知恵と慈悲で制している。その姿にあやかり命名した」というから、原子力ムラにはもともと「仏様の力」に頼るところがあったのかもしれぬ▼きのう原子力規制委員会は、関西電力高浜原発3、4号機の再稼働にお墨付きを与えた。この原発の再稼働をめぐっては大津地裁が昨年十一月、住民の避難計画など備えが整っていない現状では、「(規制委が)いたずらに早急に再稼働を容認するとは到底考えがたい」と指摘していたが、その考えがたいことが起きたわけだ▼原子力という巨獣が暴れだした時、神仏ならぬ身がいかに非力か。いやというほど悟ったはずなのに、事故対策の不備ぶりを裁判所も危惧するような状態で、なぜ再稼働を認めうるのか▼仏教界からも脱原発を求め、再稼働に反対する声が上がっているという。「仏様のおかげ」はもう期待しない方がいい。
==============================================================================

東京新聞の社説【原発比率 温暖化を口実にするな】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015021202000174.html)。
「原発は可能な限り減らして、再生エネルギーの導入は最大限-。これが原則だったはず。原発がなければ、温室効果ガスは減らせないのか。地球温暖化対策を原発依存の口実にしてはならない」。
『●関西電力の「原発再稼働」への言い訳にさせてはいけない』
『●誰も責任をとらない自民党議員
・・・・・・3.11東京電力原発人災以前に逆戻りしていて大丈夫?』
「地球温暖化防止の切り札が原子力発電」?? ご冗談を。『不都合な真実』で、原発再稼働へと誤誘導し、破滅へと引きずり込んでいるのは?、一体誰だ? 「原子力=核」発電所は「巨大な「海暖め装置」」、地球温暖化に直接的に大きく貢献している。
「たかが電力のために」、「発電機能付き湯沸し装置」=「死の灰」製造装置を一秒たりとも稼働させてはいけない。
『●「京都議定書の失敗」をあなたたちに言われたくない』
『●『ウォーター・マネー/「水資源大国」日本の逆襲』読了(4/5)』
『●非常時だけでない、恒常的な被爆労働・犠牲でしか
成り立たない原発という特殊な発電システム』
『●東京電力は、これまでさんざん安いと喧伝してきた
発電機能付き湯沸かし器の値上げをするそうです』
==============================================================================
【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015021202000174.html】
【社説】
原発比率 温暖化を口実にするな
2015年2月12日
原発は可能な限り減らして、再生エネルギーの導入は最大限-。これが原則だったはず。原発がなければ、温室効果ガスは減らせないのか。地球温暖化対策を原発依存の口実にしてはならない。
ベストミックスとは、その時代の要請に適切に対応できる電源の組み合わせのことを言う。
二〇三〇年のベストミックスを話し合う経済産業省の小委員会は、焦点の原発比率について、15~20%を軸に検討を進めている。この数字には問題がある。
政府は昨年四月に閣議決定したエネルギー基本計画で、石炭や地熱などとともに「重要なベースロード電源」と位置付けた。
運転コストが「低廉」で変動も少なく、運転時には二酸化炭素(CO2)など温室効果ガスの排出もない-というのが、その理由である。
ただしそれには、福島の教訓を踏まえた条件があるはずだ。
エネルギー基本計画に原発依存は「省エネルギー・再生可能エネルギーの導入や火力発電所の効率化などにより、可能な限り低減させる」と明記されている。
また、原発の運転期間は法律で、原則四十年に制限されている。脱原発依存、再エネ推進、そして四十年廃炉の原則が、大前提なのである。
経産省の試算によると、四十年廃炉の原則を貫く限り、原発が総発電量に占める割合は二八年に約15%になるという。新増設なしに20%はあり得ない。20%を掲げるということは、脱原発依存の旗を降ろすことにならないか。
電力会社は、再生可能エネルギーの高コスト、不安定さばかりを強調する。ところが多くの電力消費者は、安全や廃棄物対策を考慮に入れれば、原子力が決して安価でも、安定的でもないことを、福島の事故を見て知った。そこで温暖化対策が、原発推進の切り札にされつつある。
温暖化対策の国際会議をリードするのは、三〇年までに一九九〇年比40%削減という高い目標を掲げた欧州連合(EU)だ。
そのEUをリードするドイツでは福島の事故後、原発から再生エネへの大転換を進めることで新産業を育成しつつ、温暖化対策にも弾みをつけている。再生エネを増やせばCO2は減る。
脱原発依存と再エネ導入による温暖化対策の推進こそ、福島の事故を経験した国民の声や時代の要請に対応する、日本のベストミックスなのではないか。
==============================================================================

河北新報のシリーズ社説【質疑打ち切りに反発/(上)住民説明 内容限定不安消えず/再稼働の行方・九州川内原発ルポ】(http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201410/20141020_13007.html)、
【是非問う機会設けず/(中)民意集約/「結論ありき」批判も/再稼働の行方・九州川内原発ルポ】(http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201410/20141021_13011.html)、
【県と自治体に温度差/(下)同意範囲/再稼働の行方・九州川内原発ルポ】(http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201410/20141022_71011.html)。
「<「何のため」> 1時間の質疑を終えて残ったのは反発と不満だった」、「A4判両面印刷のアンケート用紙が配られた・・・・・・原発に直接関わるのは1問しかなかった。それも「(地震や津波対策など)説明会で理解できなかった項目」を選ぶだけ。再稼働への意見を聞く設問は全くない・・・・・・原発は一般の行政課題と異なる。首長や議員だけで決められる問題ではない」、「伊藤祐一郎鹿児島県知事は「立地市と県で十分」との考えで、日置市は対象外となる公算が大きい・・・・・・リスクを負っていても、再稼働には口出しできない」。
無謀な川内原発再稼働についての「住民」説明会ですが、「地元」民の声は反映されているのでしょうか? 電力会社、アベ様やその子分たち、原子力「ムラ寄生」委員会、東電株主・宮沢洋一経産相、鹿児島県知事、薩摩川内市議会、原発メーカーときたら・・・・・・原子力力ムラ住人のための「結論ありき」のセレモニーです。彼らには、誠実さの欠片もありません。
『●九州電力川内原発を再稼働させてはイケナイ:
何のための専門家会合? 市民の意見提出??』
『●御岳山噴火は水蒸気爆発なので予測不可
・・・川内原発再稼働「影響せず」、でOKですか?』
『●怒号渦巻く川内市住民説明会:
誰が川内原発再稼働を望んでいるのか?』
==============================================================================
【http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201410/20141020_13007.html】
質疑打ち切りに反発/(上)住民説明 内容限定不安消えず/再稼働の行方・九州川内原発ルポ
(川内原発の安全審査に関する住民説明会。会場では安全性への
不安の声が相次いだ=9日、鹿児島県薩摩川内市)
鹿児島県薩摩川内市にある九州電力川内原発が国の新規制基準適合性審査(安全審査)に合格し、国内第1号となる再稼働に向けた手続きが着々と進む。福島の事故で増幅された地域の不信と不安に、自治体はどう向き合おうとしているのか。住民説明会が開かれた現地を訪れ、東北での課題を探った。(原子力問題取材班)
<「何のため」>
1時間の質疑を終えて残ったのは反発と不満だった。
薩摩川内市で9日夜にあった住民説明会。「何のために開催したのか。もっと丁寧に市民の声を聞くべきだ」。終了後、原発から12キロの地域で自治会長を務める川畑清明さん(58)が吐き捨てるように言った。
説明会は再稼働への同意、不同意の判断を迫られる県と市が共催した。地元住民への説明は法的に定められていないものの、理解促進を目的に独自に企画された。
2013年7月施行の原発新規制基準は、自然災害やテロの対策、放射性物質の拡散防止を求めている。福島の事故を踏まえて基準が厳格化されたとはいえ、住民の不安解消は容易ではない。
「絶対安全には到達できない。できるだけリスクを抑える審査をした」。原子力規制庁担当者の発言に、満席の会場がざわめく一幕もあった。
質問に立った女性の一人は「福島の事故が収束しておらず、説明に説得力があると思っているのか」と詰め寄った。
住民が原発再稼働と向き合う貴重な機会のはずが、質疑は途中で打ち切られた。内容は原則、審査結果に関するものに絞られた。避難計画や地元同意の範囲など、住民の関心が高い事項は受け付けられなかった。
開催は原発30キロ圏を含む5市町で各1回限り。薩摩川内市の場合、出席できたのは約1000人。全人口の1%にとどまった。
<市長は評価>
十分な対話が尽くされたとは言い難いものの、行政サイドは再稼働に向けた地元手続きを着々と進めている。川内原発をめぐる焦点は、既に首長や地方議会の判断に移ろうとしている。
一夜明けた10日、記者会見した岩切秀雄市長は「規制庁は細かく説明してくれた」と評価。次は「市議会の意向を聞く」と語り、住民説明会の追加開催は否定した。
現在、東北電力の女川原発2号機(宮城県女川町、石巻市)と東通原発1号機(青森県東通村)も安全審査を受けている。基準を満たしていると判断されれば、地域で原発の是非をめぐる議論が再燃するのは必至だ。
先行する鹿児島の動向は参考事例となる。深刻な原発災害が今も続く中、どんな対応が東北で求められるのか。より丁寧な住民説明が欠かせないのは明らかだ。
立地自治体となる宮城県の担当者は「(放射性物質の飛散など)福島の事故の影響が及んでいる。手続きを慎重に検討したい」と話している。
[川内原発]加圧水型軽水炉(PWR)の1号機が1984年、2号機が85年に営業運転を開始した。出力はともに89万キロワット。東日本大震災後、2011年9月までに2基とも運転を中止した。運営する九州電力は13年7月、原子力規制委に適合性審査を申請。ことし9月に全国で初めて適合が認められた。
【http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201410/20141021_13011.html】
是非問う機会設けず/(中)民意集約/「結論ありき」批判も/再稼働の行方・九州川内原発ルポ
(説明会の終了後、会場出口でアンケート用紙を投函(とうかん)する市民
=9日、鹿児島県薩摩川内市)
<同意の思惑>
国の新規制基準適合性審査(安全審査)に合格した九州電力川内原発。鹿児島県などが県内5市町で開いた住民説明会では、A4判両面印刷のアンケート用紙が配られた。
設問はわずか六つで、うち三つは性別など回答者の属性を尋ねる内容。原発に直接関わるのは1問しかなかった。
それも「(地震や津波対策など)説明会で理解できなかった項目」を選ぶだけ。再稼働への意見を聞く設問は全くない。
集計結果がどう活用されるかも見通せない。県は「理解不足の項目を確認し、情報提供の方法を検討する」(原子力安全対策課)と説明するにとどまる。
本来、審査結果に対する理解と再稼働支持は同義ではない。アンケート項目の乏しさには「審査内容への理解が進めば再稼働に同意できる」との県の思惑が透けている。
<低い出席率>
こうした行政の姿勢は「再稼働ありき」と映り、住民を原発議論から遠ざける恐れがある。
説明会の全5会場のうち、定員を超す応募があったのは立地自治体の薩摩川内市だけ。原発から半径30キロ圏の4会場は希望者が定員の4~8割程度。平日の夜間開催という事情を勘案しても、高い出席率とは言い難い。
さつま町は定員の半数に満たなかった。町内で眼鏡店を経営する山内義人さん(63)はあえて出席を見送った一人だ。
「再稼働の是非で激論を交わすべきだが、行政側は強引に手続きを進めてしまっている。意見をいくら言っても無駄だ」。山内さんは諦め顔を見せた。
「公開討論会を開いてほしい」「住民投票をやるべきだ」。複数の会場でこうした意見も出たが、県側は否定的な姿勢を崩さなかった。
説明会について、伊藤祐一郎鹿児島県知事は「一般的な形では理解が進んだ」と話す。住民の意見を集約する機会がないままに、再稼働をめぐる手続きは最終局面を迎えようとしている。
<有志尋ねる>
経済性や安全性など、原発を評価する住民の尺度は一様ではない。同意、不同意の判断を迫られる自治体は、多様な価値観をくみ取る努力が欠かせない。
東北では再稼働の判断に向けた取り組みが進む。東北電力女川原発の地元、宮城県女川町の町議有志が今、2500世帯を対象に女川原発再稼働の賛否を尋ねている。12月には県と町に結果を報告する。
企画者の一人、高野博町議(71)は「原発は一般の行政課題と異なる。首長や議員だけで決められる問題ではない」と指摘する。
【http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201410/20141022_71011.html】
県と自治体に温度差/(下)同意範囲/再稼働の行方・九州川内原発ルポ
(再稼働への準備が進む川内原発。同意、不同意を判断する「地元」の
範囲をめぐってUPZ圏内が揺れている=鹿児島県薩摩川内市)
<訴え届かず>
「原子力規制委員会は地元同意の範囲をはっきりさせるべきだ」。鹿児島県日置市の無職牧添正信さん(62)は訴えた。
日置市は、再稼働に突き進む九州電力川内原発がある同県薩摩川内市に隣接する。牧添さんは地元であった10日の住民説明会で「ここも同意が必要な範囲のはず」との思いをぶつけた。
訴えは届かなかった。壇上の規制委関係者から明確な回答はなかった。
地元同意は再稼働の条件の一つだが、国は「地元」を定義していない。伊藤祐一郎鹿児島県知事は「立地市と県で十分」との考えで、日置市は対象外となる公算が大きい。
終了後、牧添さんは「福島の事故では広範囲の住民が当事者になった。同意の在り方について議論を深めなければならない」と語気を強めた。
日置市など原発30キロ圏は緊急防護措置区域(UPZ)となり、防災・避難計画の策定が義務付けられている。リスクを負っていても、再稼働には口出しできない。当然、自治体の不満は強まる。
いちき串木野市は全域がUPZに入る。地元の「避難計画を考える緊急署名の会」の石神斉也代表(81)は「最大の被害を受けかねない住民の意向を無視することは許されない」と憤る。
石神さんらは5月、再稼働反対の署名活動を展開。住民の過半となる1万5000筆以上を集めた。地元市議会は9月、同意範囲の拡大を求める意見書を採択した。
同じくUPZに含まれる出水、姶良両市も再稼働手続きへの関与を求める。姶良市の担当者は「住民の生命、財産を守る自治体が主体性を発揮できないなんて」と嘆く。
税収など原発の実利は立地場所に集中する。恩恵の少ない周辺自治体の関与が増えれば、再稼働は不透明感を増す。
<東北も白紙>
施設の存廃にもつながる判断主体をどうするか。東北の立地県も方針は固まってはいない。
宮城県原子力安全対策課の阿部勝彦課長は「法的根拠がなく、白紙の状態。同意を求めている国が決めるべきだ」と指摘する。青森県も同様のスタンスだ。
福島の原発事故の被害は、大熊、双葉両町の立地自治体にとどまらない。東日本大震災に伴う関連死は福島全域で1800人近い。UPZ外でも安全とは言い切れない。
南相馬市は関連死が400人、避難者が2万1000人以上に達する。桜井勝延市長は「福島の教訓を生かすためにも、最低でも30キロ圏の住民の意見を反映させる必要がある」と強調した。
2014年10月22日水曜日
==============================================================================

videonews.comの記事【マル激トーク・オン・ディマンド 第693回(2014年07月26日)川内原発再稼働の前に知っておくべきこと ゲスト:井野博満氏(東京大学名誉教授)】(http://www.videonews.com/on-demand/691700/003382.php)。
東京新聞の社説【原発パブコメ 広く、深く、声を聴け】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2014080402000128.html)。
『●火山の巨大噴火時の緊急核燃料輸送に
何時間、何日間? 答えは「2年以上」!』
『●原発再稼働という恥ずべき選択 ~「新基準は世界一」
「世界最高レベル」ではなく、「世界一の無責任」~』
「単一のトラブル回避が想定されているため複合的な要因が同時発生した場合に機能するかどうか疑わしい・・・・・・「従来の安全基準に地震や津波対策が加わったものに過ぎず、これでは再稼働を前提に基準が作られていると言わざるを得ない」と厳しい評価・・・・・・いずれも従来の安全基準の手直しに過ぎず、既存の原発でもクリアできることが前提になっているため、とても安倍首相が誇るような「世界最高水準」のレベルにはなっていないと井野氏は酷評」・・・・・・したそうだ。
再稼働ありきの「世界最高水準の規制基準」「新基準は世界一」詐欺であり、世界に向けてまたウソを発信・拡散している。「安心」を喧伝し、「安全」詐欺を働いている。そんなものを許容する「地元」であっては、絶対にいけない。原発などを再稼働しなくても、「豊かな未来」「明るい未来」「豊かな暮らし」は可能だ。
『●川内原発を再稼働させてはいけない!:
九州の「草の根」の勁き底力を見せるとき』
『●原子力ムラ復権阻止を! 今なら引き返せる!!』
『●原発関連交付金・固定資産税などで「財政豊かな」玄海町で、
3.11東京電力原発人災後初の町長選』
『●「豊かな玄海町」へ:
「原子力郷土の発展豊かな未来」「原子力正しい理解で豊かな暮らし」』
==============================================================================
【http://www.videonews.com/on-demand/691700/003382.php】
マル激トーク・オン・ディマンド 第693回(2014年07月26日)
川内原発再稼働の前に知っておくべきこと
ゲスト:井野博満氏(東京大学名誉教授)
九州電力川内原発の再稼働に向けた動きが加速している。
原子力規制委員会は川内原発1号機、2号機の審査を終えて、7月16日に事実上の審査のパスを認める「審査書案」を公表した。8月15日までパブリックコメントを募った上で正式に審査書が確定し、地元の同意が得られれば再稼動が可能になるという流れだ。
電力各社は電力需給の逼迫と燃料費の高騰などを理由に原発の再稼働を目論んでいるが、審査書案の公表を受けて会見した原子力規制委員会の田中俊一委員長は、「原発再稼働の判断についてはコミットしない」と述べている。規制委はあくまで規制基準を満たしているかどうかを科学的な見地から判断するだけで、再稼働の判断は政府が行うものという立場だか、一方で安倍首相は規制委の決定を尊重して再稼働を行うとしており、再稼働の責任をお互いになすりつけているかのような印象は拭えない。
しかし、われわれにとっては何をおいてもまず、今回の規制委による審査で、原発の安全性は十分に確保されたかどうかを十二分に検証する必要がある。5人の委員からなる原子力規制委員会は当初から委員の中立性に疑問が呈されていたが、今年の9月にはさらに元原子力学会会長の田中知氏が委員に就くことが決まるなど、原子力関係業界との接点が指摘される。また、委員の下で実際の審査業務に携わる原子力規制庁の職員も、福島第一原発事故の元凶の一つとして厳しく指弾された旧原子力安全・保安院からの横滑り組がほとんどだ。
今回公表された審査書案は400ページ以上に及び、原発施設の設計の在り方から実際の施工上の対応、電源の安全確保対策、重大事故の想定や緊急時の要員確保まで記述されていて、一見するとあらゆる事態を想定しているかに見える。しかし、東京大学名誉教授で原子力施設に詳しいゲストの井野博満氏は 今回の審査書案では過酷事故への対策が不十分であると指摘する。 原発事故の対応で必要なことは、いかに原子炉を安全に「停める、冷やす、閉じ込める」かが鍵となるが、規制基準が想定している過酷事故のケースはいずれもひとつのトラブルが中心に考えられていて、それと並行して起きる可能性のあるトラブルが十分に考慮されていないと井野氏はいう。
例えば冷却機能を喪失したケースでは、確かにそれをカバーするための対応は何重にも用意されているが、そのどれもが電力が問題なく供給されていて、対応に要する人員は常に確保されていることが前提になっているという。地震や津波で施設が損傷を受けた上に、全電源喪失に見舞われた時、何が起きるかを思い知らされた福島の教訓はどこへ行ったのだろうか。また、電源に関しても規制基準ではさまざま定められてはいるが、これも主に単一のトラブル回避が想定されているため複合的な要因が同時発生した場合に機能するかどうか疑わしいと井野氏は言う。
さらに井野氏は今回の川内原発の場合、規制基準や審査書案を見るだけでは分からない問題もあるという。川内原発では、仮に冷却機能が失われて炉心損傷が起きても、その段階で事態の進行を押さえ込む防護機能が十分ではなく、次に生じるメルトスルーにどう対応するかという対策しか想定されていないという。つまり川内原発では重大事故の際には冷却機能を維持する対策が不十分なため、その時点での対応を諦め、その次の事態に対処することになっていて、その対応を原子力規制委員会も容認しているという。このような事実は専門家が読んで初めてわかることで、一般の人が規制基準や審査書案をいくら読んでも、知ることが出来ない。
安倍首相が誇る世界最高水準の規制基準に関しても井野氏は「従来の安全基準に地震や津波対策が加わったものに過ぎず、これでは再稼働を前提に基準が作られていると言わざるを得ない」と厳しい評価を下す。福島事故で安全神話が崩れ、重大事故や過酷事故が起こりうるとの前提に立った原子力行政が目指されたはずだった。事故後に策定された新しい規制基準は、各数値などはより厳格になっているものの、いずれも従来の安全基準の手直しに過ぎず、既存の原発でもクリアできることが前提になっているため、とても安倍首相が誇るような「世界最高水準」のレベルにはなっていないと井野氏は酷評する。
現在、日本の原発は全て停止している。しかし、そもそもその再稼働を誰がどういった権限で判断するのかという法的枠組みを日本は持っていない。そのため安全基準への適合の可否のみを審査しているはずの原子力規制委員会の判断が、事実上、再稼働にお墨付きを与える格好になっている。このままでは総無責任体制の下で原発だけが回り出すことになり、万が一の事故の際にもその対応が甚だ心配だ。少なくとも安倍首相は「規制委の意見を尊重して」などと逃げずに、「私の責任において再稼働します」と言えないのであれば、再稼働などすべきではないだろう。
既に多方面から指摘されているように、現行の安全基準は周辺住民にとっては最も重要と言っていい、事故の際の避難計画が評価の対象からすっぽり抜け落ちてしまっている。仮に立地自治体によって作成された避難計画が現実離れした代物であっても、現行の制度ではそれを評価して適正化する組織が存在しない。とりあえず防災避難計画の作成が義務づけられているだけで、その内容は問われていないというのが実情だ。これでは安全神話に寄りかかった再稼働と言わざるを得ない。
川内原発再稼働に向けた動きと今回公表された原子力規制委員会による審査書案を参照しながら、原発の規制の在り方、規制基準の問題点、原子力規制委員会や立地自治体の役割と責任などについて、ゲストの井野博満氏とともにジャーナリストの青木理と社会学者の宮台真司が議論した。(今週のニュース・コメンタリーはお休みします。)
プロフィール
井野博満 いの ひろみつ
(東京大学名誉教授)
1938年東京都生まれ。60年東京大学工学部卒業。65年同大学大学院数物系研究科応用物理学専攻博士課程修了。東京大学生産技術研究所助教授、同大学工学部教授、法政大学工学部教授などを経て2006年より現職。高知工科大学客員教授を兼任。工学博士。共著に『福島原発で何が起きたか――安全神話の崩壊』、『福島原発事故はなぜ起きたか』、『徹底検証 21世紀の全技術』など。
==============================================================================
==============================================================================
【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2014080402000128.html】
【社説】
原発パブコメ 広く、深く、声を聴け
2014年8月4日
原子力規制委員会が、川内原発の再稼働について、パブリックコメントを募っている。国民の合意なくして再稼働は許されない。規制委は広く深く積極的に意見を集め、分析を試みるべきである。
パブリックコメントとは、国民、市民の意見である。国や自治体が何かを決めようとする時に、その意思を採り入れる手続きであり、しばしば募集されている。
しかし、ほとんどの場合、国民、市民の関心は薄く、応募はわずかで、単に手続きとして盛り込まれているだけという、イメージが強かった。少なくとも3・11の前までは。
それを変えたのが、前政権が一昨年、革新的エネルギー・環境戦略を決めるに当たって試みた討論型世論調査、意見聴取会、そしてパブリックコメントの三点セットである。約八万九千件もの意見が寄せられ、そのうち約九割が、将来的には原発ゼロを支持していた。
画期的だったのは、これらの議論を検証する専門家らの会合を開いたことだ。
意見を中立的に分析し、安全対策の実効性や発電コスト、使用済み核燃料をどうするかなど、十一の論点を抽出し、「大きな方向性として、少なくとも過半の国民は原発に依存しない社会の実現を望んでいる」と結論づけた。
その上で政府が出した判断が「二〇三〇年代原発ゼロ」という方針だったのだ。
政権は自民党に移ったが、この時の結果が否定されたわけではない。その後このように大規模な国民意見の募集は行われていない。
原子力規制委員会は先月十六日、鹿児島県の川内原発の再稼働を「適合」と認め、十五日までパブリックコメントを募っている。
だが、例えば提出上の注意の冒頭に「日本語に限る」とある。「審査書案に対する科学的、技術的意見と無関係な場合」は、意見として取り扱わないことがあるという。疑問である。
原発の安全性に関しては、世界中から広く英知を集めるのが国の方針だったのではなかったか。何が科学的、技術的なのか、だれがどのように判断するというのだろうか。このように入り口を狭められては、国民の意見を聴くのに消極的だと感じてしまう。
原発の再稼働は、立地地域と周辺自治体だけの関心事ではない。国民的な対話の中から、論点を抽出、検証し、国民の不安や疑問を広く深く解消する作業を経なければ、原発は動かせない。
==============================================================================

CMLの記事(http://list.jca.apc.org/public/cml/2012-December/021277.html)と東京新聞の社説(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2012121202000123.html)。
いい加減な原発行政。これまで政権を担ってきた者たちが如何にいい加減であったのかが分かる。断層が在ろうが無かろうが、お構いなし。
一方、選挙情勢が芳しくないとわかると、とたんにすり寄る元両〝ト〟知事の〝ト〟党。憲法改正を叫び、戦争しましょう!とすり寄るのだから、始末が悪い。
『●田中優子さん「誰の名前を書くのか、その人の品格が問われている」』
================================================================================
【http://list.jca.apc.org/public/cml/2012-December/021277.html】
[CML 021447] 伊藤千尋さんの講演「福島原発事故と憲法9条」を聞きました。
kimihiko ootsuru ・・・・・・
2012年 12月 9日 (日) 23:25:54 JST
友人の皆さん
・・・・・・です。
今日は選挙活動はお休みして三郷で伊藤千尋さんの講演「福島原発事故と憲法9条」を聞きました。
コスタリカの話など思わず涙が出てしまった。
全くメモを見ないで二時間の力の入った講演だった。
世界70カ国を回った経験は他に例を見ない。
150人位で聞くには勿体無い話だった。
今日のテーマはこれでした。
1.原発なんていらない
2.世界から基地が消えて行く。
3.活憲の時代
4.尖閣諸島をどうするか
5.地域から変わる日本
講演後二つの主催団体の人たちと伊藤さんを囲んで珈琲を飲みながらお話をした。
伊藤さんはこれで今年の講演は最後だったようですが年間110回も講演されたそうです。
マスコミ業界の裏話をお聞きしました。
共通の友人の存在もあり親しみを感じました。
いい記事には評価をすることがマスコミの心ある人への激励となり、悪い記事には批判をすることがマスコミをいい方向に導くことに�壓がる事がよくわかりました。
再度お話をお聞きしたいと思いました。
この選挙でもマスコミ批判が大事になっていますし自分で発信出来る時代の市民の役割の大事さを改めて思いました。
http://ootsuru.cocolog-nifty.com/blog/2012/12/9-762f.html
他の土日の記事です。
12月8日(土)応援弁護士100人とともに銀座を練り歩き
http://ootsuru.cocolog-nifty.com/blog/2012/12/128100-ceb4.html
国民は石原が思っている程馬鹿ではありません。
http://ootsuru.cocolog-nifty.com/blog/2012/12/post-6743.html
衆議院選挙の候補と私と政策が近いのは
http://ootsuru.cocolog-nifty.com/blog/2012/12/post.html
笹子トンネル事故の責任は民営化し維持費コストカット3割を命じた猪瀬氏に責任がある
http://ootsuru.cocolog-nifty.com/blog/2012/12/3-464b.html
12月9日(日)の街頭宣伝予定とメデイア出演の予定
http://ootsuru.cocolog-nifty.com/blog/2012/12/129-1494.html
以上です。
人にやさしい東京を!
・・・・・・
・・・・・・
・・・・・・のブログ2
http://ootsuru.cocolog-nifty.com/blog/
================================================================================
================================================================================
【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2012121202000123.html】
【社説】
敦賀・廃炉か 全原発の調査は不可避
2012年12月12日
まっ黒という判定だ。科学者たちは、日本原電敦賀原発2号機が“地震の卵”の上にある危ないものだと評価した。地震国日本の地下は断層だらけではないか。全原発の総点検は避けられない。
四人の専門家の判断は、ずれることなく一致した。活断層だ。敦賀原発2号機の運転開始は一九八七年二月、比較的新しい部類に入る。だが、四半世紀もの間、“地震の卵”と言われる不安定な地層の上に原子炉が乗っていた。背筋が寒くならないか。
敦賀原発の敷地内には「浦底断層」という名の活断層が走っており、破砕帯と呼ばれる断層の一種がそこから枝分かれするように2号機の真下へ延びている。この破砕帯が浦底断層の活動に連動して動き、地震を引き起こす恐れがあるか。つまり活断層であるかどうかが、検討されてきた。
以前から危険は指摘されていた。日本原電は現存する原発では最も古い敦賀1号機の建設時から、破砕帯の存在を知っていた。だが連動して動く恐れはないと今も主張し続けている。つじつま合わせと疑われても仕方あるまい。
このように事業者側に都合の良い報告を、一般に旧原子力安全・保安院のような政府機関が追認し、政治が放置してきたことから原発の安全神話が生まれ、神話への依存が福島第一原発事故につながったのではなかったか。
福島の教訓から今年九月に発足した原子力規制委員会は、電力側の意向を排し、独自の調査に基づいて独自の判断を下すという、当たり前の仕事をしただけだ。
今後、関西電力大飯原発の追加調査をはじめ、東北電力東通原発、北陸電力志賀原発など五カ所で現地調査を実施する。だが、日本列島は地震の巣、近年の調査技術の発達で、新たな活断層が見つかる可能性は高い。このような結果が出た以上、全原発の現地調査を速やかに行うべきではないか。
規制委は、安全基準に満たない原発の停止を命令できるようになる。地震による被災が予見される原発の稼働は、許すべきではない。政府も、科学的知見に基づく規制委の判断を受け入れ、廃炉に向かうべきである。
もちろん、廃炉後の新たな産業と雇用の確保、創出には、政府や自治体が責任を持って取り組むべきだ。
敦賀の場合、既存の送電網や港湾施設などを生かし、新しいエネルギー産業を育てることも、未来への選択肢の一つだろう。
================================================================================

まず、昨日に続いて、日隅さんについての東京新聞のコラム「筆洗」(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/hissen/CK2012061402000115.html)から。
『●NPJ編集長・日隈一雄さん亡くなる』
================================================================================
【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/hissen/CK2012061402000115.html】
【コラム】
筆洗
2012年6月14日
握手を求めると、柔らかい手で強く握り返してくれた。今年二月の出版記念パーティーで会ったのが最後になってしまった。弁護士の日隅一雄さんが亡くなった。四十九歳。末期がんと闘いながら、記者会見場に足を運び、政府や東京電力の責任を鋭く追及した▼新聞記者から転身した日隅さんと初めて会ったのは、十年ほど前の犯罪被害者の話を聴く勉強会だ。被害者の人権を侵害する事件報道を厳しく批判していた▼裁判員制度が始まる前に出版された『裁判員制度と知る権利』(梓沢和幸・田島泰彦編著)の執筆者仲間として議論を重ねた。「残念ながら、日常の取材では、報道機関にとって、警察は監視する対象ではなく、情報をもらう対象となっているのが現状であり、報道機関は、警察が発表したりリークした情報を、疑うことなく報道している」。本の中でもマスメディアに厳しかった▼先月、菅直人前首相を参考人聴取した国会事故調査委員会のインターネットの中継に、日隅さんの顔がちらっと映っていた。元気にされているんだと安心したばかりだった▼最後まで命の炎を燃やし、主権者は誰かを問い続けた。「今の記者はおとなしすぎる」「官僚は常にメディアをコントロールしようとする。勝たなきゃだめだ」と本紙の取材に語っていた。現役の記者よりも、記者魂があふれる言葉をかみしめている。
================================================================================
さて、本日の本題。ビデオニュース・ドットコムの記事(http://www.videonews.com/news-commentary/0001_3/002437.php)と日刊ゲンダイの記事(http://gendai.net/articles/view/syakai/137009)。
首相会見の後の質疑もひどかったらしい。日テレ、読売、ロイター(経済通信社)、ニコ動(視聴者質問代読?)。大飯原発の再稼働問題についての会見で、(大事です、でも)消費税増税の質問をしている場合なのか。別の場ですべきです。マスコミがこれでは・・・・・・。一方、別の記者会見(組閣絡み)で、神保さんはゲリラ的に大飯原発再稼働の(とりようもなく、とるつもりもない)責任について質問している。首相の答えは・・・・・・(1)事故から多くの教訓を得て、二度と起こさないようにした、(2)IAEAを含めてオープンな場で安全基準などを作った、そして、メルトダウンは二度と起きない、(3)夏場の電気確保だけでなく、エネルギー安全保障や値上げ阻止のため、原発再稼働が必要、だそうです。お笑いだ! (1)について、動かさないことが最もリスクを下げるし、(2)について、動かさなければメルトダウンのリスクは下がるし、(3)についても、動かさないことがエネルギー安全保障であり、原発を利用すれば、廃炉のコストなどを考慮すればコストはかさむ。責任という問いに、「絶対安全」神話で答えて、どうするのだろう?
組織デモじゃなく、組合組織的なものでもない女性や老人など、公安警察の理解を超えたデモが首相官邸周辺で起こっている。もっとマスコミはそれを報道すべきであり、首相やその取り巻きにその事実を突き付けてはどうか? 電気利用者が要らないといっている。特に原発で作ったエネルギー入らない、と言っているわけ。
民主党内部からも、大変に遅ればせながら、大飯原発再稼働に反対の声が上がり始めた。
ムダ首相のほとんどなかった支持率が、ますます低下したのではないか。とにかく、酷い会見だった。
================================================================================
【http://www.videonews.com/news-commentary/0001_3/002437.php】
ニュース・コメンタリー (2012年06月09日)
安全神話に依存した原発再稼働の問題点
野田首相は8日、福井県の関西電力大飯原発3・4号機の再稼働を認める意向を正式に発表した。各方面から様々な圧力がかかる中での苦渋の決断だったのだろうが、残念ながらその理由は福島第一原発事故の教訓が十分活かされたものとは到底言えない内容だった。
「大飯原発の再稼働の判断の基軸は、国民生活を守る。これが唯一絶対の基軸である」。首相はこう語り理解を求めた。しかし、4日の会見同様、首相の説明は「事故を起こさないようにすることが、私の責任」「全電源喪失しても炉心の損傷には至らない」など3・11以前の安全神話を繰り返すばかりで、事故が起きた場合の対応についてはまったく言及がなかった。
結局、今週の2回の会見を通じて、総理の口から再稼働の理由として、「電力が足らないから」、「経済的な影響が大きいから」という以上の説明を聞くことはできなかった。
確かに、福島第一原発事故を受け、安全対策などに一定の強化が行わたことは事実かもしれない。しかし、そもそもわれわれは福島第一原発のメルトダウン並びに放射能の外部への漏出の原因が何だったのかについては、確たる情報を得ていない。政府と国会の事故調の調査結果を待っているところだ。原因もわからない中で、「安全対策は万全」、「福島のような炉心損傷には至らない」と何度言われても、どれほどの信用があるだろうか。
また、正当性があろうが無かろうがどうしても大飯だけは再稼働するというのであれば、最低限やっておくべきことがあるはずだ。まずは3・11以前のように炉心溶融は絶対起きないという前提の上に立つのではなく、万が一炉心溶融が起きても放射能が外部に漏れないためのベントフィルターを設置したり、万が一放射能が漏れた時に周辺住民を無事に避難させるための避難訓練や避難ルートの確保、そしてそれでも被害者が出た場合の保険などの賠償措置などを予め万全にしておくことが、福島の教訓なのではないか。
一貫して「再稼働の是非はともかく、その決め方がより重要」との立場をとってきたジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が、今回の再稼働の正当性とそこから見える問題点を議論した。
================================================================================
================================================================================
【http://gendai.net/articles/view/syakai/137009】
「大飯再稼動待った!」国会議員119人署名に菅直人前首相の名前がない
2012年6月12日 掲載
<しょせん、口先だけがまたも露呈>
野田首相が民意無視で宣言した関西電力大飯原発再稼働。消費増税と同じく、こちらも民主党内を二分する騒ぎになっている。当たり前の話で、福島原発の事故原因もハッキリしなければ、国会事故調の報告もまとまっていない。原子力規制庁も発足していないのに、安全基準も何もないからだ。そのため、多くの国民が今なお、再稼働に反対し、民主党の国会議員119人(6月11日現在)が「慎重に判断すべし」と申し入れている。ところが、この署名に肝心の名前がなかった。脱原発にあれだけこだわった菅直人前首相だ……。
この署名は民主党の衆院議員、荒井聰元国家戦略担当相と福島選出の増子輝彦参院議員が中心となって呼びかけたもの。羽田孜元首相、鳩山由紀夫元首相、小沢一郎元代表、渡部恒三元衆院副議長、江田五月党最高顧問、馬淵澄夫元国交相ら119人が署名している。
顔ぶれを見て分かるのは、反野田とか、小沢系だとかは関係なく、党内の派閥を超えて、賛同者が集まったということ。首相経験者も入っているし、前首相である菅が現首相の野田に遠慮して、署名を拒否する理由はない。そのうえ、荒井といえば、菅が閣僚に起用した“お気に入り”だ。なぜ、子分の呼びかけに応じないのか。ますます、菅の名前が名簿にないことが不自然に見えてくるのである。
理由を菅事務所に尋ねたが、締め切りまでに正式な回答はなく、事務所は「本人でないと答えられない」と言うのみ。「結局、あの人は口先だけ……」と改めて、党内の評判を下げている。
「だって野田首相の原発再稼働記者会見のひどかったこと。
理屈もヘッタクレもないじゃないですか。この夏が厳しいのであれば、
期間限定で動かし、その後止めて、安全基準をきちんとしたものにしてから、
再稼働を検討すればいい。再稼働の理由も安全性の確保から
電力供給不足に変わり、最後は値上げを理由に国民生活に影響が
出るとドーカツした。電力会社の無駄を放置して、
『国民生活を守るための再稼働』なんて、よくもまあ、こんな屁理屈を
言えたものです」(ジャーナリスト・横田一氏)
同じような趣旨のことは大阪市特別顧問の古賀茂明氏も指摘している。菅周辺によると、「菅さんも会見には呆れていた」と言う。一応、自身のブログには脱原発の主張をつづっているのだが「それでも沈黙しているのは、小沢グループと連動していると思われたくないんだろう」(菅周辺)なんて、言われている。
「しょせん、菅さんの脱原発もその程度なのでしょうか。
本気で脱原発を目指すのであれば、野田首相を引きずり
降ろさなければウソ。鳩山、小沢両氏とトロイカ体制を復活させて、
民主党の原点に戻るべきですよ」(横田一氏=前出)
何度、国民を裏切れば気が済むのか……と言いたくなる。
===============================================================================

asahi.comの社説(http://www.asahi.com/paper/editorial20120226.html)。すごく「甘口」な社説。
「原発ゼロ社会」なんて原子力ムラ住人・親戚筋には全く見えていないし、視界には無いでしょう。見る気さへ無いし。種々の数字を偽装しようがどうしようが、核燃サイクルに意義があろうが無かろうが、彼らの胸の内にあるのは、「電力不足詐欺」をやってまで、ストレステストという出来試合・茶番でさらなる詐欺を重ねてまで、原発再稼働・原発建設再開・原発輸出に向けて全てをなし崩しに進めるための執念のみ。日本の住民どころか、全世界の人々にどれほどの危機的影響を及ぼすのかなんてお構いなし。「原発をゼロにできる時期について「20~30年後がめどになろう」」や、「すなわち、「安全だから動かす」から、「本当に必要な数だけしか動かさない」への転換」でも極度に甘い認識だと思う。「暗闇の思想」を。
================================================================================
【http://www.asahi.com/paper/editorial20120226.html】
2012年2月27日(月)付
原発の再稼働―需給見通しの精査が先だ
西日本で稼働中の原発がなくなった。東日本で残る2基も定期検査が控える。このまま進むと、5月には日本の電力供給は完全な原発ゼロ状態となる。
一方、電力需給は安定している。暖房需要が減れば、さらに余裕が出てくるだろう。
震災後1年弱に及ぶ節電が、強いられた受け身の努力から前向きの挑戦へと変わり、全国の企業や家庭へと裾野を広げつつある。まさに、「節電は最大の電源」である。
古い火力発電所の稼働で無理をしている面はある。電力不足への懸念が経済活動を制約していることも否定できない。
それでも、節電で経済が失速し、国民生活が混乱に陥っているわけではない。むしろ省エネを通じて経済社会のあり方を変革し、新たな成長につなげる戦略が現実味を帯びている。
それは、日本に54基もの原発がそもそも必要だったのか、という疑問に結びつく。
■見えてきたゼロ社会
私たちは昨年7月、「原発ゼロ社会」を提言した。そのなかで、原発をゼロにできる時期について「20~30年後がめどになろう」と述べた。
しかし、需要ピークの昨年8月を12~16基の稼働で乗り切ったことを踏まえれば、はるかに早く実現できるだろう。
原発政策は、こうした需給面での新たな観点に立ち、発想を根本的に変える必要がある。
すなわち、「安全だから動かす」から、「本当に必要な数だけしか動かさない」への転換である。
目下の焦点は、関西電力・大飯原発3、4号機(福井県)の再稼働だ。原子力安全・保安院は両機のストレステスト(耐性評価)の1次評価を「妥当」とする審査書をまとめている。
だが、ストレステストは重要な機器や設備を対象にしたもので、原発全体に目配りしているわけではない。大地震と津波を対象にしているが、火災などは含まれていない。
保安院の「妥当」判断も、安全性の保証ではなく、計算に問題がないことを示すだけだ。
再稼働の判断で最も重視すべきは、福島の教訓を踏まえた安全基準や防災対策の強化、そして「想定外」のことが起きても次善の策で減災をはかる危機対応の体制整備である。
この作業には時間がかかる。今夏の需要期には、間に合わない。もし、この夏の電力が本当に足りないのなら、暫定的な安全基準に基づいて、動かさざるをえなくなるだろう。
ただし、それには、他の事業者などからの電力確保や節電の要素をきちんと盛り込んだ、信頼性の高い需給見通しを示すことが大前提である。
■なし崩しへの疑念
福島第一原発の事故以来、電力会社が展開してきた「電力不足」キャンペーンは実態とずれていた。もちろん、電力供給に責任を持つ企業が不測の事態を警戒するのは当然のことだ。
しかし、電力業界は自らの利益のため、大飯原発を突破口になし崩し的に原発を動かしたいだけではないか。そんな疑念が国民にある限り、再稼働を訴えても説得力はない。
安全対策が十分に整わない今夏は、原発による電力が欠かせなくなっても、必要最低限のものしか動かさない。政府がそう打ち出すことが、国民の理解を得る最低条件だろう。
この夏を何基の原発で乗り切ることになるか。ゼロなのか。その結果、経済や社会にどのような影響が出るのか。先々の料金の見通しはどうか。
そうした評価を、中長期の脱原発への工程表に生かしたい。
大切なのは、「どう動かすか」ではなく、「どこを閉めるか」という視点である。
まず新しい安全基準や危機・防災対策の枠組みを、早く完成させなければならない。
そして、既存の原発を危険性で仕分けし、早期に閉める炉を決めていく。これまで無視されていた防災・避難対策のコストを反映させることが重要だ。
現段階でも決められることはある。古い原発の廃炉である。稼働から30年以上たつ原発は、福島第一を含め19基、うち3基は40年以上だ。
細かく検査する以前に、老朽化したものから止める。欧州などで重視される「予防原則」の考え方だ。
■「危ない」現実を直視
政府の事故調査・検証委員会は中間報告で、「災害対策のパラダイム転換」を求めた。
そのためには、「原発は危ない」という事実を直視しなければならない。
これまで電力会社も政治家も専門家も、この現実から目を背けてきた。それが「安全神話」を生み、原発反対派との間で建設的な議論が成り立たないまま大震災を迎えてしまった。
脱原発への国民的な合意を築くうえでも、「原発は危ない」という動かしがたい現実から再出発しなければならない。
================================================================================






















