

NPJ(News for the People in Japan、http://www.news-pj.net/index.html)にリンクされていた記事(http://www.fsight.jp/article/10319)です。
「想定外」で許される訳がない。フザケテはいけない。裁判をはじめ、色々な場で「想定すべき事態」が既に何度も指摘されてきたのに、裁判所はウテアワズ、マスコミは報じず、自民党など原発推進の政治家は鼻でせせら笑い、電力会社は〝商機〟に勤しむ。国民も耳を貸そうとしない。騙されることは罪。
それにしても、「原子力安全委員会」や「原子力安全・保安院」の〝安全〟って一体なんでしょうか? この事態を見て何とも思わないのでしょうか?
==========================================
【http://www.fsight.jp/article/10319】
【http://www.fsight.jp/article/10319?ar=1&page=0,1】
未曾有の震災が暴いた未曾有の「原発無責任体制」
2011/03/15 塩谷喜雄 Shioya Yoshio
誤作動や故障を前提としたフェールセーフの仕組みと多重防護に加え、過剰なまでの耐震設計に守られて、日本の原子力発電所にはTMI(米スリーマイル原発)もチェルノブイリもあり得ない――。東京電力と経済産業省が豪語し、マスメディアのほとんどが信じ込んできた原発の安全神話は今、木っ端みじんに崩壊した。
東電の福島第一原発では、3月11日の東北太平洋沖地震(M9.0)のあと、原子炉が次々に炉心溶融を起こし、廃炉覚悟の海水注入に踏み切っても、まだ安定したクールダウン、冷却・停止には至っていない。ただでさえ巨大地震でダメージを受けている周辺住民に、不便な避難生活を強要せざるを得ない状態が続いている。
炉心溶融は「構造的問題」
福島第一原発には6基の原子炉がある。地震発生時に4、5、6号機は定期点検中で稼働していなかった。動いていた1、2、3号機はすべて炉心溶融し、1基もまともに安定した停止状態にできないでいる。2号機に至っては、放射性物質を閉じ込める最後の砦である格納容器にまで損傷が及び、最悪の事態の可能性まで出てきた。
東電自身も、規制当局の原子力安全・保安院も、テレビでしたり顔で解説している学者も、この無残な事態はひとえに、想定をはるかに超える巨大地震が原因「かのように」語っている。それとなく、これだけの大地震だから、水素爆発も炉心溶融も住民避難もいたし方ない、大自然にはかなわない、という空気を醸し出している。
少量とはいえ放射能を含んだ気体を、格納容器から外部環境に放出するベントと呼ぶ苦肉の策を、何を勘違いしたか「ベントに成功」などと発表し、それをそのままメディアは伝えている。安全義務を負う電気事業者としては、内部の圧力も冷却材の水位も制御できずに、やむなくガス抜きするのはどう見ても「赤っ恥」であろう。何とも心優しいマスメディアの対応である。
今回の巨大地震で、東電福島よりも強い揺れに襲われ、より高い津波に見舞われた東北電力の女川原発は、3基の炉がすべてすんなり停止し、ずっと安定した冷却状態にある。それに比べると、東電福島第一の3基そろっての炉心溶融には、構造的な問題があると考えるのが、普通だろう。
想定外ではなかった津波
実は、東電の福島第一は津波に弱く、炉心溶融の危険性があることは、5年前から指摘されていた。想定外などではない。福島第一で想定されている津波、チリ地震津波クラスに遭遇すると、大きな引き波によって冷却用の海水を取水できなくなるといわれる。この引き波による取水停止が、炉心溶融に発展する可能性を、2006年に国会で共産党の吉井英勝議員が質問している。
二階俊博経産相(当時)は善処を約したが、東電は具体的な改善を行なわなかった。東電には地元から改善の要望書も出されているので、津波による炉心溶融の「危険性の指摘」を知らなかったはずはない。百も承知だったのに、素知らぬ顔ですべての原因が想定外の巨大地震にあるかのように振舞っているとしたら、なかなかの役者である。
1、2、3号機の冷却失敗が、吉井議員の指摘した海水の取水停止によるものなのか、東電が主張している外部電源の喪失なのか、それらの複合なのかは、いまだ不明だ。2系統あるはずの非常用ディーゼル電源が働かず、高圧の注水ポンプも3基すべてで不調であることの理由を、東電は全く説明していないし、記者たちは誰も聞かない。
不調だとか働かないとかいうのは、結果であって原因ではない。日本中に不安を撒き散らしている炉心溶融事故の原因について、当事者は語らず、メディアは聞かず、規制当局は糺さない。このもたれあいが日本の原子力が抱える最大の不安要因ではないか。
「バックチェック」を怠った東電
2007年、中越沖地震で東電の柏崎刈羽原発は運転を停止した。この時も、外部の変圧器の火災が大げさに報じられ、原発本体の損傷まで過大に受け取られたと、東電は不満を漏らした。それを真に受けた一部のマスコミは、ダメージを過小評価して運転再開を急ぐ東電にエールを送った。
実は、柏崎刈羽の炉は、設計上の想定を3.6倍も上回る強い力で揺さぶられていた。1000ガル(加速度の単位。柏崎刈羽では300ガル程度と想定していた)を超す重力加速度も記録されたものの、詳細な記録はなぜか消失していた。
中越沖地震の前年、原発の耐震指針は25年ぶりに改定されていた。新規原発だけでなく、既存の炉も新しい基準で検証し直す「バックチェック」が1つのウリでもあった。敷地近くにある断層を徹底チェックして、その地震動を想定した耐震性が求められる。しかし、東電は中越沖地震を起こした敷地の眼前にある断層を精査せず、実質的にバックチェックを怠っていた。
原子力安全委員会や原子力安全・保安院が、これを厳しくとがめたという話は聞かない。そもそも新耐震指針自体がどうにも怪しい存在である。世界で発生するM4以上の地震の6割がこの小さな島国の周辺に集中する。文字通り地震国日本であるが、その新耐震指針は、地球科学的リスク評価をほとんど反映していない、ひたすら業界の都合を優先したものだった。
最たる例が、震源を特定せずに想定すべき地震動を、M6.8の直下型としたことである。未知の断層が動いて強い揺れを起こした地震としては2000年の鳥取西部地震があるし、海岸部の断層が動いて甚大な被害を出した例には阪神大震災がある。共にマグニチュードは7.3である。
誰が考えても、地震国の原発の耐震基準としてはM7.3の直下型が極めて妥当であろう。それが、突然M6.8になった。業界の強い要望が、科学的議論を簡単にひっくり返したのである。検討委員の石橋克彦・神戸大教授は、それに抗議して委員を辞めた。その他の基準についても推して知るべし、である。
産学官のもたれあいが生んだ「虚構の安心」
緩い基準と厳しさを欠く規制。虚構の安心と安全は、東電と東大と経産省という、産学官のトライアングルで築き上げられてきた、といわれる。お目付役のはずの原子力安全委員会は、事業者の言い分に大変理解のある東大の学者がトップに座り、規制の現場を仕切る原子力安全・保安院は、電力業界の旗振り役である経産省の外局、下部組織である。原子力利用の先進国の中で、これほど業界寄りの規制・監視制度を持つ国は他にない。
原子炉等規制法の改正で、事業者責任の明確化とともに、民の自律的事業展開にも道が開けている。それを推進するためにも、官と民、推進と規制の緊張関係は不可欠だ。東電にまともな情報公開を要求することもできず、ただうろたえている原子力安全・保安院の「独立」は急務だろう。もたれあいの結果が福島第一の悲劇かもしれない。今回の事故でも、東電側はどうでもいい数値を事細かに発表し、肝心の炉の異変についてはほとんど口を閉ざし、事態の悪化を覆い隠そうとしている。
たとえば、2号機の格納容器内にあるサプレッションプール(圧力抑制室)の異常については、「格納容器の損傷」というタイトルではなく、「職員の移動」というタイトルで資料を配る。なぜ職員が2号機から退避したのかと問い詰めて初めて、格納容器破損の可能性があるから、ということになる。包み隠さずではなく、包んで縛って丸めて隠すのである。
「安定供給」を旗印に様々な優遇を受けてきたが
それは14日に実施する予定だった「計画停電」とやらでも同じことである。その「計画」の中身を見て、愕然とした。だれも東電をとがめなかったのか。5つに地域分けしたというグループのうち、1と2は、1日に2回、午前と午後に停電に見舞われることになっている。最大6時間。3、4、5のグループは1日1回で最大3時間。都心部は停電なし。6対3対0の振り分けは、だれがどんな根拠で決めたのだろうか。ぜひ合理的な説明を聞きたい。
国難の時に住民ひとしくリスクを分け合って、「輪番」で苦難を負いましょうという提案かと思ったら、東電が自分の都合と慮りで、勝手に決めたようにみえる。
そのまま実施できなかったのは、当たり前だろう。「6」を負担するグループに割り当てられた自治体とその首長が、猛烈な抗議を行なったことは、想像に難くない。電力不足は自らの怠慢が招いたものなのに、どういうつもりだろうか。
しかも、電気事業法にある安定供給の義務を放棄するにあたって、東電からは真剣な謝罪がない。安定供給の一項があるので、電力自由化にも、CO2の排出抑制にも、自然エネルギーの定額買い取りにも協力し難いと言ってきたのは誰だったろうか。
逆に、安定供給を旗印に、様々な優遇を受けてきたのは誰だったろう。今回電力の融通が簡単に行かない理由の1つである東西の電流のサイクル数の違いを是正せずに、地域独占のメリットをむさぼってきたのは誰だっただろう。
今回の巨大地震があぶり出したのは、原子力発電の限界というより、発送電一体の地域独占、9電力体制の賞味期限切れではなかったか。日本のエネルギー戦略にとって、原子力の占める位置は決して軽くない。問題は、それを運営する事業主体に難があるということだ。木川田、平岩、那須と続いた東電の哲学と先見性の経営は、福島原発の非常用電源と同様に「喪失」してしまったのだろうか。
生命を懸けて原発の暴走を止めようと奮闘している東電社員、協力会社社員、自衛隊員には、心から感謝するとともに、被害がこれ以上広がらないことを祈る。
==========================================












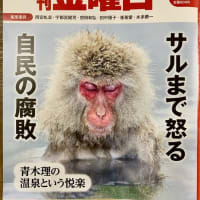
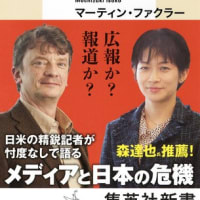
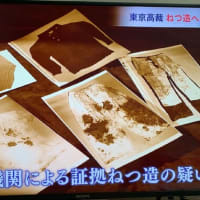

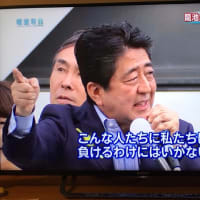

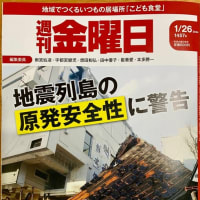







ではなくて、東北電力に引き受けさせて
いたならば、今回の徒方も無い大事故は、
たぶん無かったと言う事ですね。