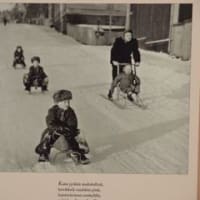ここ数日、在日ベトナム人に関する文献を探したり、目を通したりしている。とりあえず、文献のメモをつけておく。
まず一番印象的なことは、ベトナム人に関する文献は日本語教育学でも社会学でもベトナム難民に関するものがほとんどだということだ。ベトナム難民は1970年代後半から日本政府が受け入れ、さらにその呼び寄せ家族や、二世などで1万人弱が日本に住んでいる。しかし、現在はニューカマーとしてのベトナム人が増加していて、すでにベトナム難民の数をはるかに越えている。
探した中で基本的な知識が得られる文献には次の2つがあった。
*川上,郁雄 (1999) 「越境する家族 : 在日ベトナム人のネットワークと生活戦略」民族學研究 63(4),359-381, (日本民族学会 〔編〕/日本民族学会/日本文化人類学会)
この論文は、文化人類学的なアプローチからベトナム難民家族の適応戦略を個人個人の事例とその背景となる社会的歴史的文脈の中で論じたもの。ベトナム難民の社会的・歴史的文脈について非常に参考になる。ベトナム難民と言っても簡単に1つの集団としてはとらえられないその対立を含んだ多様性が理解できる。また、ベトナム人の移民をディアスポラとしてとらえようとする点は、多言語使用者と通じるかもしれない。
*倉田良樹、津崎克彦、西野史子(2002)「ベトナム人定住者の就労と生活に関する実態調査:調査結果概要」Technical Report, 一橋大学機関レポジトリhttp://hdl.handle.net/10086/14488、
*西野史子、倉田良樹(2002)「日本におけるベトナム人定住者の社会的統合」Technical Report, 一橋大学機関レポジトリhttp://hdl.handle.net/10086/14485
この2論文は社会学の社会的統合の視角から、質問紙調査を試みたもの。最初の論文では関西地区(神戸、姫路)のベトナム難民に対する調査を、次の論文では関東地区(横浜)が対象になっている。神戸では鷹取カソリック教会が舞台になっていて、一度、阪神大震災の後に牧師さんを訪ねてお話を伺ったことがあるので懐かしい。社会的統合とは、EUでは「外国人の社会的な底辺化(marginalization)を防止あるいは阻止する過程」と考えられており、同化や共生とは異なる。このポイントは重要。
他に、以下のような論文が参考になった。
吹原,豊 (2002) 「ライフコースとしての日本語学習:ベトナム人日本語学習者の事例」日本語国際センター紀要 12,1-18,151,157, (国際交流基金日本語国際センタ- 編/国際交流基金日本語国際センタ-/独立行政法人国際交流基金)
福留, 伸子; 増井, 世紀子 (1997) 「インドシナ難民の日本人とのコミュニケーション:国際救援センター退所後1年未満のベトナム人の追跡調査」 筑波大学留学生センター日本語教育論集 (12),171-196, (筑波大学留学生センター非常勤講師,東京国際大学附属日本語学校講師/筑波大学留学生センター)
丹野,勲; 原田,仁文 (2004) 「ベトナム人従業員の仕事・価値観に対する意識調査(1)」国際経営論集 28,145-193, (神奈川大学経営学部出版委員会 編/神奈川大学経営学部/神奈川大学)および(2)
中川,康弘 (2008) 「第3者国環境に住む多言語使用者の調整行動とその規範 : バンコクに滞在するベトナム人女性の事例から」 神田外語大学紀要(20),185-206
まだまだ勉強中なのでえらそうなことは言えないが、やはり最後の中川(2008)を例外としながらも、ベトナム人は1つの方向からしか見られていない、つまり、最初から枠がはめられている。そこが問題なわけだ。
まず一番印象的なことは、ベトナム人に関する文献は日本語教育学でも社会学でもベトナム難民に関するものがほとんどだということだ。ベトナム難民は1970年代後半から日本政府が受け入れ、さらにその呼び寄せ家族や、二世などで1万人弱が日本に住んでいる。しかし、現在はニューカマーとしてのベトナム人が増加していて、すでにベトナム難民の数をはるかに越えている。
探した中で基本的な知識が得られる文献には次の2つがあった。
*川上,郁雄 (1999) 「越境する家族 : 在日ベトナム人のネットワークと生活戦略」民族學研究 63(4),359-381, (日本民族学会 〔編〕/日本民族学会/日本文化人類学会)
この論文は、文化人類学的なアプローチからベトナム難民家族の適応戦略を個人個人の事例とその背景となる社会的歴史的文脈の中で論じたもの。ベトナム難民の社会的・歴史的文脈について非常に参考になる。ベトナム難民と言っても簡単に1つの集団としてはとらえられないその対立を含んだ多様性が理解できる。また、ベトナム人の移民をディアスポラとしてとらえようとする点は、多言語使用者と通じるかもしれない。
*倉田良樹、津崎克彦、西野史子(2002)「ベトナム人定住者の就労と生活に関する実態調査:調査結果概要」Technical Report, 一橋大学機関レポジトリhttp://hdl.handle.net/10086/14488、
*西野史子、倉田良樹(2002)「日本におけるベトナム人定住者の社会的統合」Technical Report, 一橋大学機関レポジトリhttp://hdl.handle.net/10086/14485
この2論文は社会学の社会的統合の視角から、質問紙調査を試みたもの。最初の論文では関西地区(神戸、姫路)のベトナム難民に対する調査を、次の論文では関東地区(横浜)が対象になっている。神戸では鷹取カソリック教会が舞台になっていて、一度、阪神大震災の後に牧師さんを訪ねてお話を伺ったことがあるので懐かしい。社会的統合とは、EUでは「外国人の社会的な底辺化(marginalization)を防止あるいは阻止する過程」と考えられており、同化や共生とは異なる。このポイントは重要。
他に、以下のような論文が参考になった。
吹原,豊 (2002) 「ライフコースとしての日本語学習:ベトナム人日本語学習者の事例」日本語国際センター紀要 12,1-18,151,157, (国際交流基金日本語国際センタ- 編/国際交流基金日本語国際センタ-/独立行政法人国際交流基金)
福留, 伸子; 増井, 世紀子 (1997) 「インドシナ難民の日本人とのコミュニケーション:国際救援センター退所後1年未満のベトナム人の追跡調査」 筑波大学留学生センター日本語教育論集 (12),171-196, (筑波大学留学生センター非常勤講師,東京国際大学附属日本語学校講師/筑波大学留学生センター)
丹野,勲; 原田,仁文 (2004) 「ベトナム人従業員の仕事・価値観に対する意識調査(1)」国際経営論集 28,145-193, (神奈川大学経営学部出版委員会 編/神奈川大学経営学部/神奈川大学)および(2)
中川,康弘 (2008) 「第3者国環境に住む多言語使用者の調整行動とその規範 : バンコクに滞在するベトナム人女性の事例から」 神田外語大学紀要(20),185-206
まだまだ勉強中なのでえらそうなことは言えないが、やはり最後の中川(2008)を例外としながらも、ベトナム人は1つの方向からしか見られていない、つまり、最初から枠がはめられている。そこが問題なわけだ。