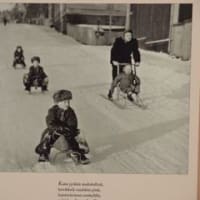そろそろ今年も終わりなので、振り返ったりする。
毎年、新しい歌手を一人か二人発見して新しい気持になるものだけど、今年の白眉は新妻聖子さん。ミュージカルから始まった人だけどそのソプラノの繊細にコントロールされた声の気持ちよさはまさに絶品。帰国子女のお嬢さんというところがいいのかなあ。夏のメルボルンでは1ヶ月毎日何回も聞いて家族に閉口されてしまった。
もう一人、こちらは古くて、ぼくはふつう昔の歌手のCDを買わないのだけど、何の調子か「ふきのとう」の山木康世さんのCDを買ってしまう。昔から、山木さんは歌が下手なのだと思っていて、客観的に言うと確かにそう。しかし、それが味を出す場合もある。「峯上開花」と名付けられたCDの中にはいくつか素朴でいかにも80年前後の風景が思い浮かぶような曲があって、今年のお気に入りになりつつある。らららというあたりに行間の言わないことが込められているようで、ちょっとぐっとくる。山木さんは詩人ですね。
ただ一面氷の真冬の湖に 青白い光の月が 輝いていた
眠りについた町 思い出の眠る町 二人は若かった 身体も心も
ららら・・・あの日の夜空にも 月は輝いていた
*
今週は大学院満期修了で教職についていた大場さんの博論審査があった。接触場面と内的場面の三者会話の参加の役割について論じたもの。発話の方向や、情報保持者と非保持者など、徹底してエティックなカテゴリーで三者会話の発話を追った詳細な記述は、生半可なプロセス調査にはない迫力がある。なぜ徹底してエティックだったのか、それは本人に聞いてもわからないかもしれないけれど、これで出発地点に立てたとしたら、今度は肩の力を抜いて、言語管理やプロセスに自在に踏み込んで行けるかもしれないと思ったりする。広島からわざわざご苦労様でした。苦労が報われましたね。
毎年、新しい歌手を一人か二人発見して新しい気持になるものだけど、今年の白眉は新妻聖子さん。ミュージカルから始まった人だけどそのソプラノの繊細にコントロールされた声の気持ちよさはまさに絶品。帰国子女のお嬢さんというところがいいのかなあ。夏のメルボルンでは1ヶ月毎日何回も聞いて家族に閉口されてしまった。
もう一人、こちらは古くて、ぼくはふつう昔の歌手のCDを買わないのだけど、何の調子か「ふきのとう」の山木康世さんのCDを買ってしまう。昔から、山木さんは歌が下手なのだと思っていて、客観的に言うと確かにそう。しかし、それが味を出す場合もある。「峯上開花」と名付けられたCDの中にはいくつか素朴でいかにも80年前後の風景が思い浮かぶような曲があって、今年のお気に入りになりつつある。らららというあたりに行間の言わないことが込められているようで、ちょっとぐっとくる。山木さんは詩人ですね。
ただ一面氷の真冬の湖に 青白い光の月が 輝いていた
眠りについた町 思い出の眠る町 二人は若かった 身体も心も
ららら・・・あの日の夜空にも 月は輝いていた
*
今週は大学院満期修了で教職についていた大場さんの博論審査があった。接触場面と内的場面の三者会話の参加の役割について論じたもの。発話の方向や、情報保持者と非保持者など、徹底してエティックなカテゴリーで三者会話の発話を追った詳細な記述は、生半可なプロセス調査にはない迫力がある。なぜ徹底してエティックだったのか、それは本人に聞いてもわからないかもしれないけれど、これで出発地点に立てたとしたら、今度は肩の力を抜いて、言語管理やプロセスに自在に踏み込んで行けるかもしれないと思ったりする。広島からわざわざご苦労様でした。苦労が報われましたね。