◎昭和19年の東南海地震によって生じた鉄道の混乱
昨日に続き、高田保馬『社会歌雑記』(甲文社、一九四七)から。
昭和一九年(一九四四)一二月七日、「昭和東南海地震」が発生した(この呼称は、当時のものではない)。この地震によって、東海道線は不通になった。そのアオリを受けた高田保馬は、京都から直江津まわりで、東京に往復したという。
(41) をやみなく汽笛鳴り去り鳴り来る一夜をいねぬ越の直江津(昭和十九年)
これは十二月十日という日付をもつてゐる。愛知静岡の地震があつて東海道線が不通になつてから北陸線と中央線だけが関東と関西とをつなぐ通路であつた。私共の立場では中央線の利用が出来ないので、北陸線経由で東京に往復した。年末に近づくにつれて、列車の混雑は烈しくなつた。月に一二回の東京行もなかなかのことではない。十二月十日の朝に直江津廻り上野行といふ列車にのりこんではみたが、腰かける席などあるわけはない。新聞紙をしいて小さく座つてゐた。大阪で席をとつた一行四名の客の如きは、佳肴珍味を人見よがしに並べてつつき合つてゐる。列車の速力は遅い。直江津に着くまで十二時間、予期した通りの立ち通しである。此上はと思つて直江津で下車して駅前の旅館に一泊した。車内で連〈ツレ〉が出来て、二人は四畳半の一室をふりあてられた。野宿せずに済むだけでもありがたいことである。丁度初雪の晩で町はとけかかつた雪に蔽はれてゐた。同室の客は岐阜の山中から来たといつて、かち栗を火鉢であぶつて私にもすすめた。床に入ては見たが中々にねつかれぬ。機関車を中心として汽笛があちらに鳴つたり、こちらに鳴つたりする。たうとう、睡らずに夜を明してしまつた。直江津の町にとまることなど、これからまづないと思ふが、縁あつて一泊したその晩は、ただ汽笛の連続であつた。翌日、朝五時頃直江津をたつて信越線経由、上野に出た。途中所見。「漸くに下りとなりて雪はだら長野平の冬浅みかも。」「浅間山雪のおもてにかげ動きまひるの空をわたる雲あり。」
短い文章だが、よく当時の雰囲気を再現している。
短歌については、どうこう言えるだけの鑑賞力を持ち合わせていないが、冒頭の一首、文末の二首、ともに良い短歌だと感ずる。特に最後の一首に感銘を覚えた。
二首目にある「雪はだら」は、雪がまだらに積もっている様をあらわす言葉か。
今日の名言 2012・12・27
◎直江津に着くまで十二時間、予期した通りの立ち通しである
高田保馬『社会歌雑記』(甲文社、1947)118ページより。上記コラム参照。当時の時刻表を確認したわけではないが、この列車は、大阪発の直江津まわり上野行きと思われる。筆者は、京都からこの列車に乗り込み(たぶん)、12時間立ち通し、ついに直江津で途中下車したという。直江津駅前で同宿した岐阜人は、米原からこの列車に乗り込んだものと推察される。

















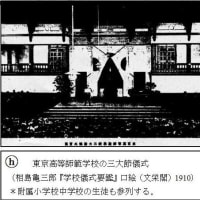
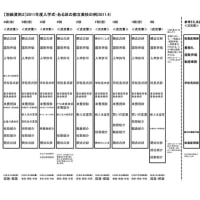
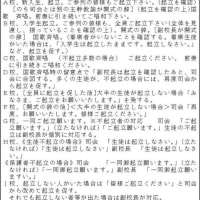








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます