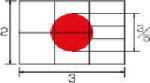盆送り火
2005-08-16 | 行事
今日は(8月16日)は「盆送り火」(月遅れ)の日。
お盆は、祖先の冥福を祈る仏教行事で、地域や宗派により様々なしきたりや習慣がある。盆期間は旧暦7月15日を中心に、7月13日~16日(4日間)の期間に行われるが、今、全国的にみれば、月遅れの8月にするところが多いだろう。盆の入り(13日)の夕方、迎え火を焚いて先祖の霊をお迎えし、供養し、盆明けの今日(16日)の夕方、送り火を焚き、祖先の霊をあの世にお送りする。これが送り火。盆送り、送り盆などとも呼ばれている。
お盆の行事は、親戚一同が集まり、故郷を離れている人では帰郷する人も多い。このため、学校などの夏季休暇のある8月の方がやりやすいだろう。
8月16日の今日、京都で行われる「五山の送り火」も、大がかりな「送り火」。この送り火は、京都盆地を囲む周囲の5つの山に夜、それぞれ「大文字」「左大文字」「船形」「鳥居形」「妙法」の形に火をともすというもので、五つの山に5種類の送り火を焚くところから「五山の送り火」と呼ばれるようになった。非常に壮大で幻想的である。「大文字焼き」という名前で全国に広く知られている。「精霊送り」の意味を持つ盆行事の一形態で、葵祭・祇園祭・時代祭に加え、京都四大行事と称している。関西では、他に、奈良の「大文字送り火」が有名である。ややこしいので、京都の大文字は「五山の送り火」、奈良では「大文字送り火」と呼んでいる。
夏の風物詩ともなっている打ち上げ花火、今は、観光用として行われているが、この打ち上げ花火も元々は、精霊送りの行事であったらしい。江戸時代に初盆の供養として、精霊送りとともに「柱松の花火」という簡単な回転花火を上げていたが、その花火を熊野で作ったのが始まりとされている。私は見たことないが、熊野の花火も、時代とともに規模が拡大しているが、現在の花火大会でも、本来の目的である初精霊供養の要素は消える事が無く、初精霊供養の灯籠焼きや追善供養の打ち上げ花火などがプログラムに組み込まれているそうだ。余談であるが、熊野の花火は、三河地方の花火に続く古い歴史と伝統をもつ行事として受け継がれてきたと言われているが、全国に知られている「三河花火」は、徳川家康が生誕地に火薬製造を特別に認めたのが出発点で、軍事技術を平和利用、そして菅生神社の祭礼で奉納花火が始まったそうだ。三河地方の花火の中では、岡崎の花火が超有名。私は、若い頃、(35年位前)仕事で、岡崎に住んでいたことがある。仕事の関係先から桟敷席に招待され、花火を見たが、神戸などでは見たことのないその豪華さに驚かされ、感激したものである。
盆明けの16日には、送り火とともに、「精霊流し」(しょうりょうながし、またはしょうろうながし)をするところがある。お盆の間、帰って来ていた先祖の霊を、お供え物や灯籠を川や海に流すことで送り出す行事であり、雛祭りの原型とされる流し雛の行事との類似性が指摘されている。近年では河川や海の環境汚染を起こすことから放流を禁止する自治体が多い。
「精霊流し」・・・と言えば、長崎の「精霊流し」が、有名だが、それよりも、あの有名な歌『精霊流し』を思い出すよね~。
せんこう花火が見えますか 空の上から
約束どおりに あなたの愛した
レコードも一緒に 流しましょう
そしてあなたの 舟のあとを
ついてゆきましょう
私の小さな弟が
なんにも知らずに はしゃぎ回って
精霊流しが華やかに 始まるのです
長崎市出身の歌手・さだまさしさんが、自分の従兄弟の死に際して、長崎市で行なわれている精霊流しを題材にして、1974(昭和49)年に作ったそうだ。これが、グループ最初のヒット曲となり、さだまさしさんは、日本レコード大賞作詞賞を受賞した。
今日16日に聞く曲としてはぴったりの歌。とても、いい歌なので、懐かしいその曲を聞いてみよう。
MIDI 「霊(しょうろう)流し」さだまさし作詞・作曲 /歌詞付き
http://www.mahoroba.ne.jp/~gonbe007/hog/shouka/shourou.html
(画像は、京都大文送り火)
(参考:
お盆 (Wikipedia )
http://ja.wikipedia.org/wiki/お盆
京都新聞/大文字・五山送り火
http://www.kyoto-np.co.jp/kp/koto/gozan/dai.html
奈良大文字送り火
http://www1.sphere.ne.jp/naracity/j/ivnt/ivnt_data/ivnt97/
熊野大花火オフィシャルホームページ
http://www.ztv.ne.jp/web/kumanoshi-kankoukyoukai/
お盆は、祖先の冥福を祈る仏教行事で、地域や宗派により様々なしきたりや習慣がある。盆期間は旧暦7月15日を中心に、7月13日~16日(4日間)の期間に行われるが、今、全国的にみれば、月遅れの8月にするところが多いだろう。盆の入り(13日)の夕方、迎え火を焚いて先祖の霊をお迎えし、供養し、盆明けの今日(16日)の夕方、送り火を焚き、祖先の霊をあの世にお送りする。これが送り火。盆送り、送り盆などとも呼ばれている。
お盆の行事は、親戚一同が集まり、故郷を離れている人では帰郷する人も多い。このため、学校などの夏季休暇のある8月の方がやりやすいだろう。
8月16日の今日、京都で行われる「五山の送り火」も、大がかりな「送り火」。この送り火は、京都盆地を囲む周囲の5つの山に夜、それぞれ「大文字」「左大文字」「船形」「鳥居形」「妙法」の形に火をともすというもので、五つの山に5種類の送り火を焚くところから「五山の送り火」と呼ばれるようになった。非常に壮大で幻想的である。「大文字焼き」という名前で全国に広く知られている。「精霊送り」の意味を持つ盆行事の一形態で、葵祭・祇園祭・時代祭に加え、京都四大行事と称している。関西では、他に、奈良の「大文字送り火」が有名である。ややこしいので、京都の大文字は「五山の送り火」、奈良では「大文字送り火」と呼んでいる。
夏の風物詩ともなっている打ち上げ花火、今は、観光用として行われているが、この打ち上げ花火も元々は、精霊送りの行事であったらしい。江戸時代に初盆の供養として、精霊送りとともに「柱松の花火」という簡単な回転花火を上げていたが、その花火を熊野で作ったのが始まりとされている。私は見たことないが、熊野の花火も、時代とともに規模が拡大しているが、現在の花火大会でも、本来の目的である初精霊供養の要素は消える事が無く、初精霊供養の灯籠焼きや追善供養の打ち上げ花火などがプログラムに組み込まれているそうだ。余談であるが、熊野の花火は、三河地方の花火に続く古い歴史と伝統をもつ行事として受け継がれてきたと言われているが、全国に知られている「三河花火」は、徳川家康が生誕地に火薬製造を特別に認めたのが出発点で、軍事技術を平和利用、そして菅生神社の祭礼で奉納花火が始まったそうだ。三河地方の花火の中では、岡崎の花火が超有名。私は、若い頃、(35年位前)仕事で、岡崎に住んでいたことがある。仕事の関係先から桟敷席に招待され、花火を見たが、神戸などでは見たことのないその豪華さに驚かされ、感激したものである。
盆明けの16日には、送り火とともに、「精霊流し」(しょうりょうながし、またはしょうろうながし)をするところがある。お盆の間、帰って来ていた先祖の霊を、お供え物や灯籠を川や海に流すことで送り出す行事であり、雛祭りの原型とされる流し雛の行事との類似性が指摘されている。近年では河川や海の環境汚染を起こすことから放流を禁止する自治体が多い。
「精霊流し」・・・と言えば、長崎の「精霊流し」が、有名だが、それよりも、あの有名な歌『精霊流し』を思い出すよね~。
せんこう花火が見えますか 空の上から
約束どおりに あなたの愛した
レコードも一緒に 流しましょう
そしてあなたの 舟のあとを
ついてゆきましょう
私の小さな弟が
なんにも知らずに はしゃぎ回って
精霊流しが華やかに 始まるのです
長崎市出身の歌手・さだまさしさんが、自分の従兄弟の死に際して、長崎市で行なわれている精霊流しを題材にして、1974(昭和49)年に作ったそうだ。これが、グループ最初のヒット曲となり、さだまさしさんは、日本レコード大賞作詞賞を受賞した。
今日16日に聞く曲としてはぴったりの歌。とても、いい歌なので、懐かしいその曲を聞いてみよう。
MIDI 「霊(しょうろう)流し」さだまさし作詞・作曲 /歌詞付き
http://www.mahoroba.ne.jp/~gonbe007/hog/shouka/shourou.html
(画像は、京都大文送り火)
(参考:
お盆 (Wikipedia )
http://ja.wikipedia.org/wiki/お盆
京都新聞/大文字・五山送り火
http://www.kyoto-np.co.jp/kp/koto/gozan/dai.html
奈良大文字送り火
http://www1.sphere.ne.jp/naracity/j/ivnt/ivnt_data/ivnt97/
熊野大花火オフィシャルホームページ
http://www.ztv.ne.jp/web/kumanoshi-kankoukyoukai/