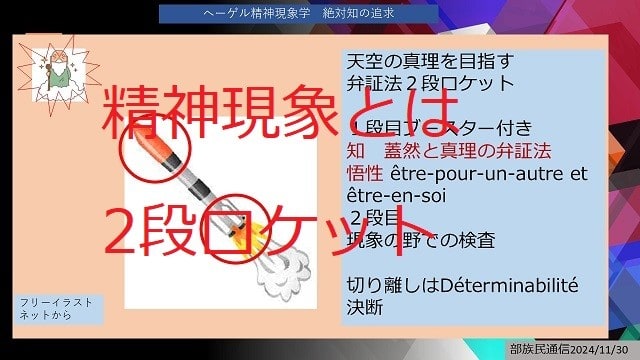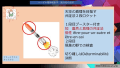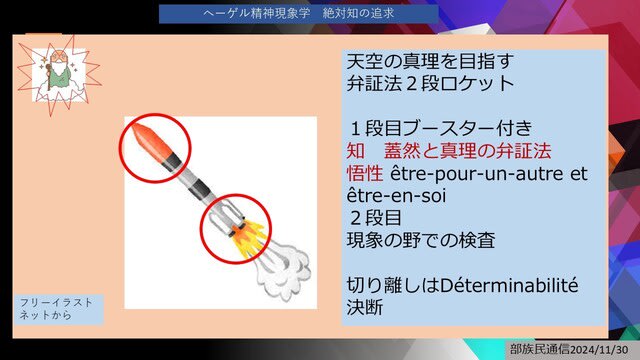本年初の投稿なので肩のこらない話題...「哲学は理解じゃないよ、解釈」その下
(2025年1月11日)et qui s'appellerait le savoir absolu ? Hegel le dit un peu, mais on peut le comprendre tout autrement. L'interprétation de Heidegger, par exemple, est tendancieuse, mais elle est possible, heureusement. C'est pour cela qu'on ne dépasse pas Hegel. Il serait fort possible que le savoir absolu soit, pour ainsi dire, immanent à chaque étape de la Phénoménologie. Seulement la conscience le manque. 絶対知とは誰のことか。ヘーゲルは少しだけ語っている。しかしそれを正反対に理解する人だっている。ハイデッガーの解釈は、傾向的すぎるけど、それも可能です、(彼には)幸せなことに。でもこの事をもって、人はヘーゲルを乗り越えられない。こうも言えるのではないか、現象の一つずつの段階に絶対知は浸透している。悟性はそれを理解しないだけと。
(ハイデッガーの解釈、部族民は語れません。Wiki仕込みくらいを挙げたいのでネットに入ると、色々出てくる。開ける画面は「哲学系」のお偉い様の論文。そこには部族民にとっては「何も」書かれていない。ただアータラコータラで結局、部族民の低級脳ミソは理解しない。
「複雑に絡み合う事象を」簡明にまとめるのが科学者なのだ=レヴィ・ストロースのスンバラシイ言葉=とは真逆、簡単なはずのヘーゲル真理(Hyppoliteがそう解説する)を「哲学的」複雑さに追いやる、こんな解説を読んでいると頭が痛くなる。

Hyppoliteの哲学「講義」が収まるラカン・セミナーの第2冊。表紙はイタリア・マニエリズム大家、モンテーニャのLe Clavaire (ゴルゴダの丘)

部分。良き人ヨセフがイエスの遺骸を引き取るため布地を百人隊長に贈る。後ろの(狡猾な面構え)は総督ピラト。ルーブル蔵
Elle fait de cette vérité qui serait le savoir absolu, un autre phénomène naturel, qui n'est pas le savoir absolu. Jamais donc le savoir absolu ne serait un moment de l'histoire, et il serait toujours. Le savoir absolu serait l'expérience comme telle, et non pas un moment de l'expérience. La conscience, étant dans le champ, ne voit pas le champ. Voir le champ, c'est ça, le savoir absolu.
結局、悟性はこの真実(絶対知は現象の細部に浸透する)をして、もう一つの現象、自然現象を形成してしまう。それは絶対知ではない。言いたいことは絶対知は歴史の一区切りに現れるのではなく、歴史そのものなのだ。絶対知はこうした経験(弁証法)に現れるわけで、一つの節目に出てくるものではない。悟性は(現象の)野に生きるから、この野を見てはいない。現象の野を観察する、これが絶対知なのだよ。
教訓 : 1哲学書は理解できない、著者のわだかまる思考の果ての捻じくれ修辞は、フツー、理解できない。だから解釈する。たまに易しい哲学書はあるが、全く面白くない。仏語界隈の話です。哲学者は文章をしたため、世に公表する。そのときから著作が独り歩きする。読者は文言、行間を読むに集中する。著者はもはや作者ではない。この事情をHyppoliteが簡明に語っている。
2 絶対知は弁証法に潜在(immanent)している。弁証法そのものが絶対知を表現しているノダ。絶対知は歴史そのものだ。ナポレオンは、それまでの開明開放の人道歴史の昇華なのだ。ヘーゲルがこう言ってるが、これって全くマルクスじゃん。サルトルも「弁証法理性批判」で似たこと言ってるぜ。
3 悟性(考える力に属する)はそれ(絶対知の浸透)を理解しないうえ、眼の前を「自然な」現象に捨象してしまう。自然なとは、理性を介在しない、見えるがままの性状として理解する(このあたりはCertitude sensible感じる蓋然で解説している。部族民は1月半ばからBlog投稿する)。
4 ハイデッガーのヘーゲル解釈にHyppoliteは賛同していない風です。それでも « Heureusement » ハイデッガーには都合が良かったんだけど、彼の解釈も実は成り立つ。Hyppoliteのこの皮肉には鼓舞される、先程は諦めたハイデッガーのヘーゲル論に入るべぇと。
ネット断片を読み解くと;ハイデッガーは宇宙理解(彼にしての実存)を個のレベルに引き下げた。ヘーゲルはカント伝統を受け継ぐから、理性(science)を人(全人類)の知性の源においた。個の知は理性に浸透(immanent)されているのか、個それぞれが、それぞれの宇宙観を育成するのか、この対立になるのではないかな。
最後にラカン「ヘーゲルは最後の人文主義者、そこに行き詰まった。フロイトはその出口を見つけた。故に彼は人道主義者ではない」
なんとも意味深の言葉です。 Hyppolite、ラカンに哲学を教える了(1月11日)
後記:レヴィ・ストロースがサルトルを批判した文(野生の思考)に対し、日本の高名なサルトル紹介者(文学系)が放った言葉「レヴィ・ストロースはサルトルを全く理解してない」(1963年)。後にこの語を聞き及んで、私は衝撃を受けた。文学者は作品を「理解」するのかと。考え直して「文学作品は作者、その時代、生活環境とあわせて語られる」ことが多々、伺える。その雄弁な例はユイスマンス、プルースト、漱石龍之介など、皆文豪です。それを称して「理解」と述べたのか。しかし哲学書は、幾度か言うが、文言命です。著作が発表された途端、書物は独り歩きする。デカルトは吝嗇、キルケゴールは女たらし(知らないけど)などを前提にして、著作を論じません(部族民蕃神ハカミ)。
(2025年1月11日)et qui s'appellerait le savoir absolu ? Hegel le dit un peu, mais on peut le comprendre tout autrement. L'interprétation de Heidegger, par exemple, est tendancieuse, mais elle est possible, heureusement. C'est pour cela qu'on ne dépasse pas Hegel. Il serait fort possible que le savoir absolu soit, pour ainsi dire, immanent à chaque étape de la Phénoménologie. Seulement la conscience le manque. 絶対知とは誰のことか。ヘーゲルは少しだけ語っている。しかしそれを正反対に理解する人だっている。ハイデッガーの解釈は、傾向的すぎるけど、それも可能です、(彼には)幸せなことに。でもこの事をもって、人はヘーゲルを乗り越えられない。こうも言えるのではないか、現象の一つずつの段階に絶対知は浸透している。悟性はそれを理解しないだけと。
(ハイデッガーの解釈、部族民は語れません。Wiki仕込みくらいを挙げたいのでネットに入ると、色々出てくる。開ける画面は「哲学系」のお偉い様の論文。そこには部族民にとっては「何も」書かれていない。ただアータラコータラで結局、部族民の低級脳ミソは理解しない。
「複雑に絡み合う事象を」簡明にまとめるのが科学者なのだ=レヴィ・ストロースのスンバラシイ言葉=とは真逆、簡単なはずのヘーゲル真理(Hyppoliteがそう解説する)を「哲学的」複雑さに追いやる、こんな解説を読んでいると頭が痛くなる。

Hyppoliteの哲学「講義」が収まるラカン・セミナーの第2冊。表紙はイタリア・マニエリズム大家、モンテーニャのLe Clavaire (ゴルゴダの丘)

部分。良き人ヨセフがイエスの遺骸を引き取るため布地を百人隊長に贈る。後ろの(狡猾な面構え)は総督ピラト。ルーブル蔵
Elle fait de cette vérité qui serait le savoir absolu, un autre phénomène naturel, qui n'est pas le savoir absolu. Jamais donc le savoir absolu ne serait un moment de l'histoire, et il serait toujours. Le savoir absolu serait l'expérience comme telle, et non pas un moment de l'expérience. La conscience, étant dans le champ, ne voit pas le champ. Voir le champ, c'est ça, le savoir absolu.
結局、悟性はこの真実(絶対知は現象の細部に浸透する)をして、もう一つの現象、自然現象を形成してしまう。それは絶対知ではない。言いたいことは絶対知は歴史の一区切りに現れるのではなく、歴史そのものなのだ。絶対知はこうした経験(弁証法)に現れるわけで、一つの節目に出てくるものではない。悟性は(現象の)野に生きるから、この野を見てはいない。現象の野を観察する、これが絶対知なのだよ。
教訓 : 1哲学書は理解できない、著者のわだかまる思考の果ての捻じくれ修辞は、フツー、理解できない。だから解釈する。たまに易しい哲学書はあるが、全く面白くない。仏語界隈の話です。哲学者は文章をしたため、世に公表する。そのときから著作が独り歩きする。読者は文言、行間を読むに集中する。著者はもはや作者ではない。この事情をHyppoliteが簡明に語っている。
2 絶対知は弁証法に潜在(immanent)している。弁証法そのものが絶対知を表現しているノダ。絶対知は歴史そのものだ。ナポレオンは、それまでの開明開放の人道歴史の昇華なのだ。ヘーゲルがこう言ってるが、これって全くマルクスじゃん。サルトルも「弁証法理性批判」で似たこと言ってるぜ。
3 悟性(考える力に属する)はそれ(絶対知の浸透)を理解しないうえ、眼の前を「自然な」現象に捨象してしまう。自然なとは、理性を介在しない、見えるがままの性状として理解する(このあたりはCertitude sensible感じる蓋然で解説している。部族民は1月半ばからBlog投稿する)。
4 ハイデッガーのヘーゲル解釈にHyppoliteは賛同していない風です。それでも « Heureusement » ハイデッガーには都合が良かったんだけど、彼の解釈も実は成り立つ。Hyppoliteのこの皮肉には鼓舞される、先程は諦めたハイデッガーのヘーゲル論に入るべぇと。
ネット断片を読み解くと;ハイデッガーは宇宙理解(彼にしての実存)を個のレベルに引き下げた。ヘーゲルはカント伝統を受け継ぐから、理性(science)を人(全人類)の知性の源においた。個の知は理性に浸透(immanent)されているのか、個それぞれが、それぞれの宇宙観を育成するのか、この対立になるのではないかな。
最後にラカン「ヘーゲルは最後の人文主義者、そこに行き詰まった。フロイトはその出口を見つけた。故に彼は人道主義者ではない」
なんとも意味深の言葉です。 Hyppolite、ラカンに哲学を教える了(1月11日)
後記:レヴィ・ストロースがサルトルを批判した文(野生の思考)に対し、日本の高名なサルトル紹介者(文学系)が放った言葉「レヴィ・ストロースはサルトルを全く理解してない」(1963年)。後にこの語を聞き及んで、私は衝撃を受けた。文学者は作品を「理解」するのかと。考え直して「文学作品は作者、その時代、生活環境とあわせて語られる」ことが多々、伺える。その雄弁な例はユイスマンス、プルースト、漱石龍之介など、皆文豪です。それを称して「理解」と述べたのか。しかし哲学書は、幾度か言うが、文言命です。著作が発表された途端、書物は独り歩きする。デカルトは吝嗇、キルケゴールは女たらし(知らないけど)などを前提にして、著作を論じません(部族民蕃神ハカミ)。