
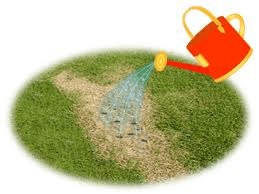
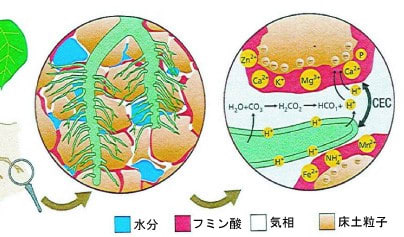





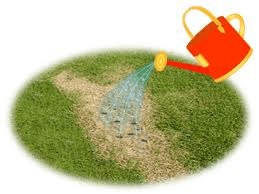
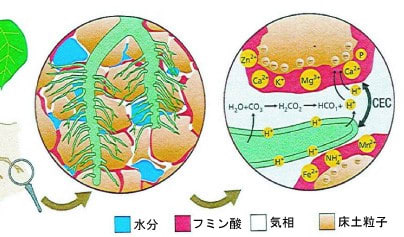





関東平野は約3週間、降雨がなく
大気は乾燥しています!
太平洋側の各地で、
火災のニュースをよく耳にします。
まさに、
「火の用心!」ですね。。
☆
ゴルフコースの
グリーン面の乾燥にも要注意です!
冬場、グリーンが乾燥すると、
プレーヤーの踏圧で、表層が硬くなり、
ターフは擦り切れ、痛みやすくなります。
酸欠気味になるので、
表層温度も上昇しにくくなります。
1月下旬「大寒」頃から始まる、
春の新根(白根)の発根
を促す上でも、
表層は固結・乾燥させないように、
したいものです。
☆
また「冬のドライ」は
そのまま放置すると、
同じ部分が
5月のゴールデンウイーク頃から
ドライスポットに発展し、
7月には、その部分の
撥水状態が原因で、
その部分に、リングが発生しやすかったり、
7月下旬や8月には、
ドライの部位は、
根からの 栄養が摂取できにくいので
ピシウムや炭疽病が侵入しやすくなります。
そのような意味から
「冬のドライ」は軽視せず、
春を迎える前に、改善したいところです!
☆
散水すれば、凍ってしまう、グリーン面の
「冬のドライ」を改善できる要素が
「フミン酸」と「菌根菌」です。
「フミン酸」は土壌の固結を緩和し、
三相バランスを持続する要素です。
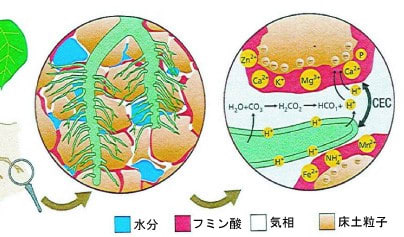
「菌根菌」は根茎周囲に留まり、
根茎周囲の潤いを持続します。
☆
オススメの資材が
「トータルパック(3-0-3)」です。

①17%と豊富な「フミン酸」が
固結を緩和し、
春の新根発根のための
土壌三相バランスを持続します。
②11種類の「菌根菌」が
根茎の潤いを持続します。
③4種類の「バチルス菌」が
砂の表面に吸着した、
撥水の原因となる有機残渣を分解し、
「冬のドライ」を改善・抑制します!
☆

「トータルパック」は
大変、好評価の資材です。
是非、乾燥しているこの時期に
その性能を、検証してみてください!
宜しくお願いします!!
(担当/サバンナブラン スポーツターフ事業部)

「寒九(かんく)の雨」
1月5日が、寒の入り。
寒にはいって九日目に降る雨を
「寒九の雨(かんくの雨)」というそうです。
農家では
豊作の兆(きざし)として喜ぶそうです。
雨が
固結、乾燥した冬の土壌を緩め、
春の発根は、早く始まり、
その年の春の訪れは早く、
稲作などは豊作になるそうです。
☆
今年の関東地方は
1月5日の「寒の入り」以降
1月6日は雪。

1月11日は雨でした。

例年では、
固結・乾燥傾向にある
関東平野の大地も、
今年は、
雨や雪が
乾燥した土壌を潤しているようです、、、
雨が降った後には
土壌には「空相」が生まれ、
地温は、
上昇しやすくなります。
今年の春の訪れは
早いかも、しれません、、、
☆
この時期の「グリーン面」に
オススメの資材があります!
「グルタミン酸」と
「核酸」を主成分とする資材です。

「グルタミン酸」は
日照の不安定なこの時期に
光合成に代わり、
タンパク質合成し、活性を持続します。
また、
「グルタミン酸」
を吸収した植物細胞は
乾燥・凍結しにくいので、
遅霜抑制にも、効果的です。
また、
豊富に含まれる「核酸」は
根の細胞分裂を刺激するので、
新根の成長するこの時期
(生殖成長が栄養成長よりも優先する時期)
に最適です!
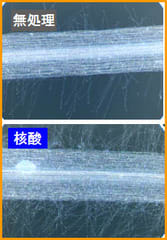
オススメ資材 2)
「リストア・プラス」
1月14日に 汲んだ水を
「寒九の水」といいます。
寒の内の水は、
雑菌が抑えられ腐りにくく、
古来「寒九の水」は
薬になるとまでいわれていました。

「リストア・プラス(3-0-2)」は
「こうぼ菌」を豊富に含む資材です。

寒冷期でも緩やかに活性向上し、
固結・凍結を緩和します。
残留を分解し、糖質に変換し、
貯蔵糖分として蓄えるので
ターフの乾燥・凍結を抑制します。
その結果、
「春の芽出し」も向上します。

11月~3月まで「リストア・プラス」を
毎月1.0cc/m2施肥されたコースで
2月中旬の夜間に積雪があった
翌朝6時ごろのグリーン面周囲の状況です。
☆
宜しくお願いします!
(^。^)

今年の桜開花は例年並みか早めと言われています。
西・東日本の2月から3月の気温は平年並からやや高くなる予想で、
桜のつぼみは順調に生長します。
特に3月後半は晴れる日が多くなり、日差しの暖かさが開花を後押ししそうです。
全国に先駆けて、3月18日に東京から開花がスタートし、
20日に横浜、福岡、高知が続く予想が出ています。

昨年の桜は暖冬の影響で開花が遅れましたが、
年末から度々訪れた寒気の影響で休眠打破が行われ、
やや早めの開花を迎える予想です。
桜の花芽は、
真冬に一定期間、厳しい寒さにさらされると、
低温によって花芽が休眠から目覚め(休眠打破)、
開花に向けて生長を始めると言われています。
1月の上旬の記録的な大雪をもたらした
強い寒気の影響で、
全国的に桜のつぼみの休眠打破は行われたとみられています。
また、本年の
太平洋側の放射冷却による厳しい寒気が
桜の「休眠打破」が進んでいるとも言われています。
◇

「朝晩の気温差が大きい冬を
超えた タケノコ は旨い!」
と千葉県大多喜町の方が言われていました。
大多喜町のタケノコは、
全国のタケノコの中でも秀逸に美味しく、
皇室献上もされている高品質なんです!!
毎年3月下旬ごろから、販売されているので
今年も楽しみにしています!

この冬の厳しい寒暖差ゆえに
「タケノコ」も「ターフ」も
たっぷり貯蔵糖分を蓄えて冬を超えてきているので
今春の芽出しは、
少し早めかもしれません。
◇
24節気「大寒」(1月20日)以降、
ベントグリーンは白根が発根し始めます。
春の芽出しを充実させる上で
オススメの資材があります!
1)新根のための三相バランスを整える「リストア・プラス」です。
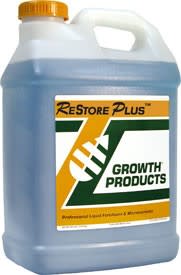
リストアプラスは、酵母+フミン酸の力で、
地温が低くても食いつき
表層土壌の固結を緩和し、気相を確保、持続します。
固結している表層より、
気相が確保された表層の方が地温が上昇しやすく、
芽出しが充実します。

↑11月~3月まで「リストア・プラス」を毎月1.0cc/m2施肥されたコースで
2月中旬の夜間に積雪があった翌朝6時ごろのグリーン面周囲の状況です。
2)根茎周囲の潤いを持続する「ハイドロ・マックス」です。


(ユッカシジゲラ)
100%天然由来成分の浸透剤です。
北米の砂漠地帯に自生する
「ユッカシジゲラ」由来の浸透湿潤成分が
乾燥の厳しい時期でも
新根発根に必要な
根茎周囲の潤いを持続します。
3)ターフを乾燥害、霜害、凍害から守る「ターフバイタル・プロ」です。

「グルタミン酸」を吸収した植物細胞は
乾燥しにくく、凍りにくい事が
大学の研究などで分かってきています。
「ターフバイタル・プロ」は
吸収しやすい単分子遊離グルタミン酸を豊富に含み
ターフ自体を乾燥や霜害・凍害から守ります。
◇
以上です。
是非、お試し戴ければ幸いです!
( ´▽`)

(1月10日 富山市の友人宅)
今週、
私のふるさと「富山県」は雪の中です。
積雪は100cmを超え、
35年ぶりの大雪だということです。

富山県のみならず
上信越・北陸地方は
この大雪の影響で、
スーパーマーケットなどに食料品が届かないなど
生活物流にも不便が出てきているようです。
くれぐれも
雪かきは
屋根からの雪の落下に お気をつけ下さい!
また、
除雪機械の周囲には
近づかないように、安全に充分気をつけて
この大雪を乗り切っていただきたいです。
◇

一方で、太平洋側は、乾燥した気候が続いています。
去る14日などは
関東地方で最高気温が15℃を上回るなど
朝はとても寒く、
昼はカラカラに乾燥する気候が
2月まで続きそうです。
◇
コース管理の皆さんは
グリーン面の乾燥には、たいへん気を配って
いらっしゃると思います。
グリーンの表層は
踏まれて固くなり易い時期です。
固いグリーンは地温が上がりにくくなります。
固いから⇒凍りやすい。
ターフは、乾燥する。
乾燥するから⇒凍り易く、擦り切れ易い。
◇
「冬越し時期」の乾燥対策をパーツ別に考えたいと思います。
1)床表層の乾燥・固結対策
2)根茎部分の乾燥対策
3)葉身部分の乾燥・霜害対策
です。
◇
1)表層の乾燥・固結対策
床土にバクテリアが活動している土壌は空相が多く
固結・乾燥しにくいです。
「こうぼ菌」は地温0~5℃でも活動できる良性菌です。
「フミン酸」は土壌の固結を緩和し、
土壌の三相バランスを持続する要素です。
⇒
表層の乾燥・固結を抑制するには
これらの要素を含んだ
「リストア・プラス」がオススメです!
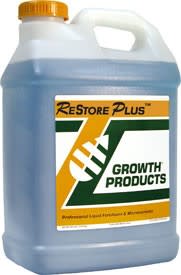
2)根茎部分の乾燥対策
浸透剤は有効な冬のドライ対策です。
天然由来成分の浸透剤はケミカル浸透剤よりも
肥効が長いものが多いようです。
⇒
根茎部分の乾燥の抑制には
天然の「ユッカシジゲラ」由来で、
浸透機能だけでなく
湿潤成分も含有する「ハイドロ・マックス」がオススメです!


↑ 北米の砂漠に自生する「ユッカジジゲラ」
3)葉身部分の乾燥・霜害対策

糖質を含有した葉身は、
乾燥しにくく、凍りにくい。
この事実は良く知られています。
下仁田ネギの白い部分がその象徴ですね!
さらに、
最近の北海道大学の研究などで
知られるようになったのは
「グルタミン酸」を含有した植物細胞も
乾燥しにくく、凍りにくい事実です。
⇒
葉身の乾燥抑制・霜害対策には
「グルタミン酸」含有資材としては
史上最高レベルの含有率である
「ターフバイタル・プロ」がオススメです。

◇
気になる方は
是非、試してみて下さい!
(^O^)

「GO-TO」の影響か?
気候が乾燥しはじめたせいか?
2週間前に、新型コロナ新規患者数は急激に増加をはじめ、
あっという間に全国での新規患者数は第2波のピークを超えました。

第3波の到来?かもしれませんが
あまり過敏になりすぎずに
今までどおり、マスクやアルコール洗浄、手洗い、うがい等を
こまめに励行し、
この「コロナ禍」や
この先の「インフルエンザ」を乗り切りたいものです。
・
今年の冬は「冬らしい冬」と多くの気象予報士さん達が
予想しています。
「西高東低」「冬の乾燥」「擦り切れ」「乾燥害」「霜害」
11月~12月上旬の気温は、太平洋側では高めですが、
既に「冬の乾燥」を感じます。


今週も湿度は低いですね。
グリーン面の乾燥には気をつけて
その先の「乾燥害」「凍害」「擦り切れ」に備えたい時期です。
・
「冬の乾燥」にオススメの資材です!
「表層土壌の乾燥抑制」
に効果的な資材が2つあります。
1)「ハイドロ・マックス」(液体資材)

100%天然の浸透剤です。
ユッカシジゲラ由来の湿潤力もあります。
フミン酸含有なので、表層の空相を持続し、
表層の固結・乾燥を抑制できる資材です。
2)「トータル・パック」(水溶粉末)

「菌根菌」の力で、根茎周囲の潤いを持続できます。
「ユッカシジゲラ抽出物」も含有しており、浸透剤効果もあります。
「フミン酸」が団粒構造を持続させ、固結を抑制します。
「こうぼ菌」が寒い時期でも資材を稼働させます。
「ターフの乾燥の抑制」に
効果的な資材が2つあります。
3)「リストア・プラス」(液体資材)

「こうぼ菌」「フミン酸」が土壌内の有機残渣を分解し、
糖質の変換し、貯蔵します。糖質の含有したターフは凍りにくく、乾燥しにくいです。

4)「ターフバイタル・プロ」(液体資材)

糖分同様に、
植物細胞が「グルタミン酸」を吸収すると
凍りにくく、乾燥しにくいターフ体質になります。
●
未だの方は
是非、お試しいただければ幸いです!
(^O^)

1月26日~27日は近畿地方平野部にも雪が降っていました。
鈴鹿のパーキングエリアの雪を触って、驚きました。
1月の雪にしては、水分をかなり含んでいるのです!
三重と滋賀の県境にある鈴鹿山脈の雪は
福井県の駿河湾を抜けた中国大陸からの冷たい北風が
山脈にぶつかって雪を降らせます。
私の出身の富山平野も同様で
日本海を抜けた中国・ロシアからの北風が
立山連峰にぶつかって雪をもたらします。
私は小中高の12年間を富山で過ごしました。
例年、12月頃から降雪し、2月中旬までの雪は、
ある程度、乾いて軽いのですが
春間近、2月下旬~3月に降る雪は、
水分をたくさん含んでいて、重いのです。
今回、
近畿・東海地方に降ったこの雪は、
1月にこの地域で降る雪にしては、
水分を多めに含んだ
「春前に降るような」雪質のような気がしました。
◇
1月31日の夜に関東地方にも
雪が降りましたが、
例年の南岸低気圧がもたらす雪にしては、
弱い降雪だったような気がします。
この先は、
例年よりも、少し早く、
ひと雨ごとに春に近ずいていくのかもしれません。
◇
24節気で
春の暦に、2つの「雨」があります。
2月19日頃の「雨水」は、新根の成長の為の雨で、
4月20日頃の「穀雨」は、地上部成長の為の雨
のように思えます。
・
72候で見ると、
2月4日頃「東風解凍(とうふうこおりをとく)」
このころから、時折、南東の方角から、風が吹きます。
「冬の南風、雪を誘う」と諺にもあり、
雨や雪も降りますが、
気温は12~1月よりは、高くなってきます。
2月19日頃「土脈潤起(つちのしょううるおいおこる)」
この頃から、時折、雨が降って
土が湿り気を含みます。
雨は、12~1月の固結・乾燥した表層に
気相と液相をもたらします。
グリーン面の「よこ根」の成長が始まるのも
この頃です。
そして、
3月1日頃「草木萌動(そうもくめばえいずる)」
<草木が芽吹き始める頃>には
グリーン面でも「たて根」の成長が始まり、
3月中旬には、
芽数が徐々に動いてくる頃となります。
◆
この時期、成長を開始する「よこ根」にオススメの資材です!
「ミスト12号(3-18-18)」+「リストア・プラス」です。
「ミスト12号(3-18-18)」

分子の鎖の長い 緩効性リン酸12%+亜リン酸6% なので、
気候の不安定なこの時期、
晴天でも、雨天でも約2週間に渡り、表層土壌に留まり、
無駄なくリン酸を吸収させ、新根を発根・成長促進させます。
・
「リストア・プラス」

主成分は
酵母の他、
アミノ酸 5%、フミン酸10%、そして鉄3%です。
酵母は地温が5度以下の寒冷期でも(0度以上あれば)活動します。
乳酸菌、こうじ菌、酵母菌などは
寒冷期の方が他の雑菌の活動が鈍くなるので、良い仕事をします。
旨い酒や味噌が寒冷期に仕込まれるのはこの理由です。
酵母が活動する土壌は空相が持続し、固結・凍結しにくくなります。
酵母は有機残渣を分解し、糖質に変換し、
ターフに貯蔵され、
新根、新芽成長のエネルギーとなるので、
新根発根・春の芽出しも充実します。
糖質を多く含んだ植物細胞は乾燥しにくく、
凍りにくいのも「リストア・プラス」の好評価の理由です。
下の写真は、11月~3月まで「リストア・プラス」を毎月1.0cc/m2施肥されたコースで
2月中旬の夜間に積雪があった翌朝6時ごろのグリーン面周囲の状況です。

◆
宜しくお願いします!
(^。^)

24節季から推測する
ベントグリーンの春の新根の動き は、
◇「大寒(1/20)」~「立春(2/4)」頃には、
白根(ひげ根)の発根が始まり、
◇「雨水(2/19)」頃には、
よこ根の発根が始まり、
◇「啓蟄(3/6)」頃には、
たて根の伸長が、始まり、根数全体が増え、
◇「春分(3/21)」頃には、
根数の増加にともない、芽数が増えて来る頃
といえると思います。
◇
また、スギ花粉の飛散状況も
グリーン面の根の動きの目安になる気がしています。
・

コース脇のスギに花粉がタワワになる頃から
「よこ根」の動きが出てくるような気がします。
・

TVで花粉CMが増える頃には
「たて根」も動き出すような気がします。
・

気象庁予測やニュース報道によれば
✩ 2/中旬(*関東地方では、2/11~14頃 )
花粉飛散開始 → よこ根の発根が始まる頃
✩ 3/上旬~中旬頃
スギ花粉飛散のピーク → たて根の伸長が始まる頃
✩ 3/中旬~下旬頃
花粉飛散開始の約30日後 → 根数が増え、芽数が増えてくる頃
と思います。
◇
春の根の動きにピッタリのオススメ資材があります!
根の成長段階に合わせて
「核酸」→「リン酸」→「NPK」
の順でいかがでしょうか?
1)まず、”核酸”
「大寒(1/20)」~「雨水(2/18)」頃は
「ターフバイタル・プロ」がオススメです。

主成分は「核酸」と「グルタミン酸」です。
(よこ根の赤ちゃんともいえる)白根の成長を充実させるのには
「核酸」が効果的です。
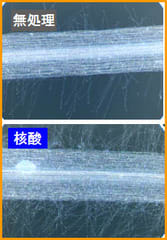 ←「ターフバイタル」の核酸効果
←「ターフバイタル」の核酸効果
また
この時期、西高東低の気圧配置で、乾きやすい表層でも
「グルタミン酸」を吸収する事で
根茎が乾燥凍結しにくくなるので、
乾燥害、擦り切れ、凍害、霜害を抑制できます。
●
2)次に”リン酸”
「雨水(2/18)」前後、
成長を開始する「よこ根」に
「ミスト12号(3-18-18)」がオススメです。

分子の鎖の長い 緩効性リン酸12%+亜リン酸6% なので、
気候の不安定なこの時期、
晴天でも、雨天でも約2週間に渡り、表層土壌に留まり、
無駄なくリン酸を吸収するスペックです。
・

この時期は「リストア・プラス」
と混合施肥すると寒い地温でも、くいつきます!
●
3)そして、”NPK”
「啓蟄(3/6)」頃
「よこ根」はさらに充実し、「たて根」の成長も始まり、
その「根数の充実」が
3~4月の「芽数」につながるこの時期は
「ミスト9号(8-32-5)」がオススメです。
「ミスト9号(8-32-5)」は
メチレン尿素+水溶性リン酸のNPKミストで
1~2cc/m2で 2~3週間の肥効があります。
春と秋の根数充実(よこ根→たて根)、
芽数アップ、発芽・発根、
更新作業後の穴の早いふさがり
にたいへん好評価な資材です。
・

この時期は「エッセンシャル・プラス」
と混合施肥するとさらに「根数・芽数」が充実します!
◇
宜しくお願いします!
(^。^)

雨が降りません!風も強く、
大気は乾燥し、気温も低いです!

関東地方は年が明けてからほとんどの日が冬晴れで、
空気の乾いた状態が続いています。
東京では去年の12月24日(月)以降、
全く雨や雪が観測されておらず、
本日1月11日(金)まで19日連続で降水がありません。
最も長い期間連続で雨や雪が降らなかったのは、1998年の21日間。
今季は本日11日(金)までで19日連続ですが、
東京は12日(土)頃まで晴れが続く予想で、過去最長記録の可能性が出てきています。
◇

上の全国のインフルエンザ流行地図の
黄色やピンク色の地域のゴルフコースは
グリーン面の 乾燥(冬のドライ)、霜害、擦切れに要注意です!
◆
冬にオススメの資材は
凍結に強い”酵母”の「リストア・プラス」
乾燥に強い”天然”の「ハイドロ・マックス」
日照不足に強い”グルタミン酸”の「ターフバイタル・プロ」です。
◇
1)低温による活性の鈍化・凍害の抑制には
「リストア・プラス」です!

「リストア・プラス」の
主成分「酵母+フミン酸」が
寒冷時期の土壌の固結を抑制します。
「リストア・プラス(3-0-2)」は
”こうぼ+鉄” の力で低温下でもくいつき、
緩やかに 寒冷時期の菌体活性を向上 させます。
・
下の写真は、11月~3月まで「リストア・プラス」を毎月1.0cc/m2施肥されたコースで
2月中旬の夜間に積雪があった翌朝6時ごろのグリーン面周囲の状況です。

2) 乾燥・固結の抑制には「ハイドロ・マックス」です!
「ハイドロ・マックス」は
北米大陸の砂漠に自生する「ユッカシジゲラ」から抽出した
100%天然の浸透湿潤資材です。
 ←ユッカシジゲラ
←ユッカシジゲラ
主成分は
ユッカシジゲラ抽出物 90%以上
フミン酸(天然レオナルダイト由来)2%
です。
「ユッカシジゲラ由来の天然湿潤成分」が
ターフに必要な潤いを持続し、
さらに
気相を持続する フミン酸2%含有で、
三相バランスを確保、持続する資材です。
3)日照時間が短い時期の光合成不足、
タンパク質合成を補う資材が「ターフバイタル・プロ」です。

植物は通常、光合成で 炭酸同化作用し、タンパク質合成を行い、
細胞を成長、活性を持続しています。
「グルタミン酸」は
日照時間が短くなり、光合成が鈍っていく時期に
ターフが直接摂取する事で
タンパク質合成を代行し、活性の低下を緩やかにします。
 ←「グルタミン酸」が炭酸同化作用を代行する
←「グルタミン酸」が炭酸同化作用を代行する
◆
以上です。
宜しくお願いします!
(^。^)

←元日は、やや雲がありましたが、かろうじて初日の出を拝めました。
謹賀新年。
本年も宜しくお願いします!
◆
只今、季節は 24節季の「小寒」。
西高東低の冬型の気圧配置が続き、
太平洋側では毎朝、マイナスの寒さです!
大気は寒く、乾燥し、
グリーン面は凍りやすく、
ターフは乾燥しやすい状況が続いています。
◇

しかしながら、
72候では
1月1日「雪下出麦(せつかむぎをいだす)」
1月20日「款冬華(かんとうはなさく)」
とあり、
植物の地下部の動きは、続いている事がわかります。
◇
24節気 1月20日の「大寒」頃からは
ターフの白根(新根/ひげ根)が発根し始めます。
「小寒」~「大寒」前後の
この時期に
表層の三相バランスを持続し、
根茎周囲を乾燥させないように
なるべく凍らせないようにする事が
春の発根~芽出しを充実させる
と思われます。
◇
乾燥したグリーン面に散水したり、
浸透剤を散布する事もある時期です。
ただ、ケミカル浸透剤の中には
界面活性剤が強すぎて、
ターフの表面をパサパサにしてしまう事があるのを
時折耳にします。
◇
以前、
中学生の息子が部活をやっている頃、
冬の時期のフケ、頭皮のカユミで悩んでいて、
カユミを取る効能をうたった
界面活性剤の強い薬用シャンプーを勧めました。
しかし、
洗髪をすればする程、頭皮が乾燥し、
カユミも増し、
さらにフケが出るようになってしまいました。
そこで
植物由来の湿潤系シャンプーを試したところ
頭皮の汚れや皮脂はきれいになり、
かゆみも止まり
ほとんどフケが出なくなりました。
◇
ヒトの頭皮とターフは同じではありませんが、
ケミカル浸透剤の浸透能力を高める上で
含有している界面活性剤とターフの相性は
よく見極めた上で使用したいところです。
◆
冬の乾燥の抑制と潤いの持続には
「ハイドロ・マックス」がオススメです!
主成分「ユッカシジゲラ由来の天然湿潤成分+フミン酸」が
ターフに必要な潤いを持続し、
表層の三相バランスを維持します。
 ←ユッカシジゲラ
←ユッカシジゲラ
天然浸透資材「ハイドロ・マックス」の
主な成分は
ユッカシジゲラ抽出物 90%以上→浸透湿潤効果
フミン酸(天然レオナルダイト由来)2%→気相持続効果
です。


北米大陸に自生する
「ユッカシジゲラ」は
ステロイド・サポニン と ポリフェノール を豊富に含みます。
それゆえ、北米大陸の原住民インデイアンが
シャンプー(汚れ落とし、かゆみ止め)、
すり傷治療、皮膚炎治療等の 薬用として活用していたといわれます。
サポニン→浸透効果、界面活性効果
ステロイド→雑菌の繁殖を止める効果、細胞治癒効果
ポリフェノール→腐敗抑制効果
をインデイアンは自然と知っていたのかもしれません。
◆
宜しくお願いします!
(^。^)

72候で
12月7日「閉塞成冬(へいそくしてふゆとなる)」
<天地の気が塞がって冬となる>
とあります。
「天地の気がふさがる。」
とは
つまり、
大気は冷たく乾燥し、
大地は乾燥して固くなる
と解釈して良いと思います。
◇
今週になって
関東地方も、風は一段と冷たく、
大気は乾燥し始めました。
関東南部のお客様のコースでも
「初霜」が観測されました。
いよいよ冬本番です!
◆
12月13日には
関東地方各地の保健局から
「インフルエンザの流行開始」が発表されました。
・
2018年12月13日
東京都福祉保健局 「都内でインフルエンザの流行開始」
都内のインフルエンザ定点医療機関からの
第49週(12月3日から12月9日)の患者報告数が、
流行開始の目安となる定点当たり1.0人を超えました。
インフルエンザは例年12月から3月にかけて流行しています。

◆
毎年、このインフルエンザの流行の時期
=
グリーン面の固結・乾燥に注意する時期
のように思います。
この時期~2月中旬までの
グリーン面の固結、乾燥、擦り切れを
抑えれば、抑えるほど
来春の芽出しが充実するように思います。
◇
グリーン面同様に
踏圧の多くかかる
テイーグラウンドも
固結、乾燥、擦り切れに注意したい時期です!
◆
この時期の
グリーンにも、テイーグラウンドにも
オススメの資材があります!
「リストア・プラス」+「ハイドロ・マックス」です。
1)固結・凍害の抑制には「リストア・プラス」です!

「リストア・プラス」の
主成分「酵母+フミン酸」が
寒冷時期の土壌の固結を抑制します。
「リストア・プラス(3-0-2)」は
特に「秋・冬の良性菌のえさ」として働き、
”こうぼ+鉄” の力で低温下でもくいつき、
緩やかに 寒冷時期の菌体活性を向上 させます。
・
下の写真は、11月~3月まで「リストア・プラス」を毎月1.0cc/m2施肥されたコースで
2月中旬の夜間に積雪があった翌朝6時ごろのグリーン面周囲の状況です。

●
2) 乾燥・固結の抑制には「ハイドロ・マックス」です!
「ハイドロ・マックス」の
主成分「ユッカシジゲラ由来の天然湿潤成分+フミン酸」が
ターフに必要な潤いを持続し、
表層の三相バランスを維持します。
 ←ユッカシジゲラ
←ユッカシジゲラ
「ハイドロ・マックス」は
北米大陸の砂漠に自生する「ユッカシジゲラ」から抽出した
100%天然の浸透湿潤資材です。
さらに、
気相を持続する フミン酸2%含有で、
三相バランスを確保、持続する資材です。
資材自体が良性菌のえさとなる 100%有機の資材です。
主な成分は
ユッカシジゲラ抽出物 90%以上
フミン酸(天然レオナルダイト由来)2%
です。
◆
宜しくお願いします!
(^。^)

もうすぐ、
2018年も終わろうとしています。
2018年を振り返れば
コース管理を進める上で、
厳しい状況が多かった年と言えます。
まず、
5月の強烈な乾燥
続いて、
7月8月の気温40℃近い異常な高温
そして
9月10月の台風による倒木、塩害、日照不足
◆
もし、地球温暖化がもたらす影響が
このような、
四季のある国、日本らしからぬ
不安定な気象の連発だとすれば
かなり、しっかりした状態で
来春の芽出しを充実させて
来年 2019年を順調に進めていきたいところです。
◇
春の芽出しを成功させる鍵は「晩秋施肥」~「冬越し」にある、
ような気がします。
スポーツターフの1年の計は「冬越し」にあり。
と思うのです。
「冬越し」において
>貯蔵糖分を充実させる
>ターフの乾燥害、凍害を抑える
>表層の固結を抑える
>ターフの擦り切れを抑える
これらのテーマは全て
来春の芽出しを充実させるための
大切な条件と思います。
そして
>ターフと表層を「乾燥」させない事
に「冬越し」のテーマが集約されるような
気がします。
◆
「乾燥」に強い肥培要素と オススメの資材です。
1) 三相バランス→「ハイドロ・マックス」

「ハイドロ・マックス」は
北米大陸の砂漠に自生する「ユッカシジゲラ」から抽出した
100%天然の浸透湿潤資材です。
主な成分は
ユッカシジゲラ抽出物 90%以上
フミン酸(天然レオナルダイト由来)2%
です。
・
固結し、透水性が悪い表層が乾きやすい事は
夏も冬も変わりません。
天然の浸透資材「ハイドロ・マックス」
天然サポニンの浸透効果で、
フミン酸を表層全体に到達させ、
気相を持続し、
「ユッカ」のもつ湿潤成分が
表層とターフの潤いを持続します。
2)「糖質」→「リストア・プラス」

貯蔵糖分の充実したターフは乾燥しにくく、
凍りにくいです。
甘味の充実した「下仁田ネギ」がしっとりしているのも
白い部分に蓄えた糖質のおかけです。

「リストア・プラス」の主成分
「こうぼ菌」は
5℃以下の地温でも働き
土壌内の有機残渣を分解し、
貯蔵糖分に変換し、
ターフに蓄えます。
・
下の写真は、11月~3月まで「リストア・プラス」を毎月1.0cc/m2施肥されたコースで
2月中旬の夜間に積雪があった翌朝6時ごろのグリーン面周囲の状況です。

3)「グルタミン酸」→「ターフバイタル・プロ」

糖質同様に
グルタミン酸の充実した植物細胞は
乾燥しにくく、凍りにくいことが
食品メーカー「味の素」の研究で明らかになっています。
さすが、冷凍食品の旨さを追求しているメーカーの研究です。
日照不足対策で定評のある資材「ターフバイタル・プロ」
は「グルタミン酸」を通常のアミノ酸資材の約10倍も
含んでいる資材です。

4)「菌根菌」→「パーマ・マトリックス」

近頃注目の「菌根菌」ですが、
根の周囲に生存する「菌根菌」が
根茎周囲の乾燥を抑制
している事が分かってきています。
4種類の「内生菌根菌」と
7種類の「外生菌根菌」を主成分とする
「パーマ・マトリックス」を
テイーグラウンドの芝の薄い部分に
すり込んでおくことで
「冬越し」中の乾燥擦り切れを抑え
来春の芽出しを向上させる効果があります。

←この夏、散水の困難な場所での生育に貢献した「パーマ・マトリックス」
◆
以上です。
ご検討いただければ幸いです!
宜しくお願いします。
( ´▽`)

72候で 11月22日は
「虹蔵不見(にじかくれてみえず)」
<大気が乾燥し、虹を見かけなくなる頃>
とあります。
太平洋側のコースでは、
先週頃から
例年の11月にあるような
秋らしい
大気の乾燥を感じる様になりました。
◇
72候で11月27日は
「朔風払葉(きたかぜこのはをはらう)」
<北風が吹き始め木の葉をはらいのける>
この頃から
強い北寄りの風が表層の水分をさらっていきます。
11月下旬以降は
表層土壌の固結・乾燥に気をつけたい時期です。
表層の乾燥・固結は
根茎周囲の温度上昇を妨げ、
来春の芽出しにも影響します。
ターフの乾燥は
凍害や擦り切れの原因にもなります。
これは
グリーン面のみならず、
踏圧ストレスの多い
テイーグラウンドやグリーン周囲にも言える事です。
このポイントを踏まえて
冬越しの準備を進めていきたいところです。
◆
オススメの資材があります。
1)表層の乾燥・固結抑制には
「リストア・プラス」+「ハイドロ・マックス」です。

「リストア・プラス」の「酵母+フミン酸」が
寒冷時期の土壌の固結を抑制します。
「ハイドロ・マックス」の「天然湿潤成分+フミン酸」が
ターフに必要な潤いを持続し、表層の三相バランスを維持します。
2)霜害・凍害抑制には
「ターフバイタル・プロ」です。

「ターフバイタル・プロ」の主成分「グルタミン酸」
を吸収した植物細胞は乾燥しにくく、凍りにくいです。
3)擦り切れ抑制には
「カル・マグ・マックス(7-0-3)」です。
カルシウムやカリウムの効いたターフは
細胞壁が硬く、しっかりしているので
擦り切れにも強くなります。
◇
現在のターフの状況や例年の冬の傾向に合わせて
試していただければ幸いです!
◆
宜しくお願いします!
(^。^)

24節気で11月7日は「立冬」
もう、暦の上では冬です。
気象庁の3か月予報では、
太平洋側は、関東地方、東海地方、近畿地方ともに、
この11月は例年よりかなり温かいという予報です。
たしかに、このところ、最低気温が例年より高めですね!
12月、1月も例年より気温高めで、暖冬傾向といわれています。
◇
ターフがまだ動くうちに
秋雨、日照不足気味で、
物足りない感じの「秋の根数」を充実させ、
暑かった夏に消耗した貯蔵糖分を、しっかり補い
「冬越し」
(乾燥害・凍害・擦り切れ対策)
(来春の芽出しの為の貯蔵糖分の充実)
の準備をしたいところです。
◇
とはいえ
この時期は一雨ごとに気温も下がって来ます。
72候 12月7日は「閉塞成冬(そらさむくふゆとなる)」
ごろまでは、
様々な形で「冬越し準備」が可能と思われます。
◆
気温15℃を下回ると自然界の様々な菌態が活動を鈍らせます。
そんな中、
数種類の限られた微生物、
「酵母菌」「こうじ菌」などは
気温0~5℃でも活動を続ける事ができます。
そのような菌態資材の力を借りるのも良いかと思われます。
◆
オススメの資材が
主成分が「酵母」の「リストア・プラス」です。

「酵母菌」などの微生物は、
有機物を分解するときに有機酸を出すそうです。
発酵の専門家の先生が
「有機酸とは、微生物の汗です。
酵母菌などの微生物は一生懸命、糖を分解して
エネルギーを取り出しながら酸性の汗をかく。
そしてその汗が土の中からミネラルを溶かしだしたり、
キレート化して作物が吸いやすい形に変えたりと、役に立つ。」
と言われていました。
◇
酵母資材「リストア・プラス」が
秋の根数を充実させるメカニズムを説明したいと思います。
・

春~夏に施肥した「鉄」や「カルシウム」は
秋に施肥したリン酸と吸着し、
不可吸な状態で土壌の中に存在しています。
・

土壌内の地温が下がる程、
ほとんどの菌態の活動が鈍り、
晩秋~冬~早春は「酵母菌」の活動の天下です。
・

「酵母菌」は土壌内の有機残渣を分解して
糖質を生成し、ターフに貯蔵させます。
「酵母菌」が糖を分解する時に「有機酸」を放出します。
・

この有機酸が「リン酸」と吸着している
「鉄」や「カルシウム」を引き剥がし、
「リン酸」をターフが吸収できる状態にします。
・

このリン酸を吸収する事で
晩秋でも根数を充実させる事が可能と思われます。
◇

「リストア・プラス(3-0-2)」
主成分
酵母(2200百万CFU/ガロン)
アミノ酸 5.0%
フミン酸 10.0%
キレート鉄 3.0%
カリウム 2.0%
浸透湿潤剤(天然ユッカシジゲラ抽出物)
◇
下の写真は、11月~3月まで「リストア・プラス」を毎月1.0cc/m2施肥されたコースで
2月中旬の夜間に積雪があった翌朝6時ごろのグリーン面周囲の状況です。

◆
是非、試してみて下さい!
(^。^)

24節季は植物・自然のカレンダーです。
2月3日は「節分」は冬の終わり。
2月4日は「立春」は春の始まり。1年のスタートです。
◇
グリーン面での1年のスタートは
「よこ根」の新根成長と思います。
コース付近の植物を観察すると
「よこ根」の成長の時期を知る事ができるように思います。
「梅の開花」=白根(ひげ根)発根~「よこ根」成長始まる時期
「スギ花粉飛散」=「よこ根」成長が本格的になる時期
と思われます。
◇

春の訪れを知らせる梅の花は、
1月下旬~5月上旬まで、約3ヶ月間かけて、ゆっくりと日本列島を北上します。

気象庁のホームページの「梅の開花情報」です。
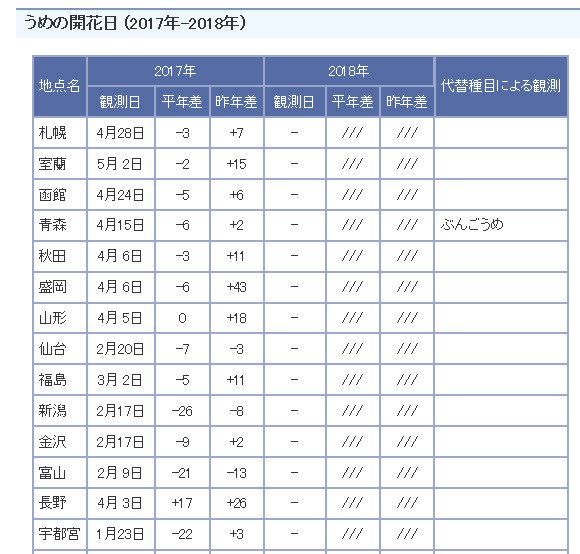

◇

2月1日の午後から2月2日のお昼にかけて、
太平洋側は
関東地方~東海地方~近畿地方まで広い範囲で雪となりました。
多くのコースがこの週末にかけて
融雪に苦労された事と思います。
来週は比較的晴天が多いとの予報です。
雪の下のグリーンは、
まるで冷蔵庫の中の野菜。
その後、雪が溶けて、晴天が続くと
表層はかなり乾燥し、
ターフはパサパサとして、擦切れやすくなりと思われます。
雪どけ後の乾燥部分が
春~夏のドライ相に発展しやすい事もあり、
この時期成長を始める「新根・よこ根」のためにも
気にかけてケアしておきたいところです。
◆
雪どけ後の乾燥抑制や
まだまだ最低温度が低いこの時期の新根成長のための
グリーン面にオススメな資材です!
(1) 凍結や固結の抑制、
新根成長の三相バランス確保には「リストア・プラス」です。


酵母は地温が5度以下の寒冷期でも(0度以上あれば)活動します。
乳酸菌、こうじ菌、酵母菌などは
寒冷期の方が他の雑菌の活動が鈍くなるので、良い仕事をします。
旨い酒や味噌が寒冷期に仕込まれるのはこの理由です。
酵母が活動する土壌は空相が持続し、固結・凍結しにくくなります。
酵母は有機残渣を分解し、糖質に変換し、新根成長エネルギーとなるので
春の芽出しも向上します。
糖質を多く含んだ植物細胞は乾燥しにくく、凍りにくいです。
(2) 乾燥・パサパサには「ハイドロ・マックス」です。
 ←北米大陸に自生する「ユッカシジゲラ」
←北米大陸に自生する「ユッカシジゲラ」
100%天然の浸透資材で、
含有するフミン酸が表層土壌の気相を保持し、
ユッカシジゲラの湿潤成分が
ターフに必要な最低限の液相を持続する能力に優れます。
寒冷時期のドライを抑制する資材としてたいへん定評があります。
 ←フミン酸が土壌の固結を緩和
←フミン酸が土壌の固結を緩和
(3)パサパサしたターフの 擦切れ抑制 には
「カル・マグ・マックス(7-0-3)」です!
カルシウム4%、マグネシウム2%の黄金比で、
カルシウムを完全吸収します。
葉身細胞を強くし、霜害や雪どけ後にありがちな 擦り切れを抑制します。
◆
以上です。
よろしくお願いします!
(^。^)