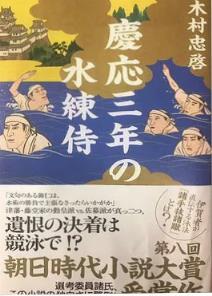安藤優一郎氏の「大名屋敷『謎』の生活」(PHP文庫)に次のような記述がある。
江戸は江戸城を核とする日本最大の城下町である。武士が住む武家地がその約七〇%を占め、町人が住む町人地と寺社地が同じく十五%ずつ分け合った。
歴史好きな方なら、江戸っ子が狭い土地にぎゅうぎゅう詰めに押し込まれるようにして住んでいたという史実をご存じかもしれない。
しかし、次の記述はどうだろうか?
江戸の土地の七〇%を占める武家地の過半は大名屋敷だった。意外にも、将軍のお膝元江戸は、大名屋敷の街という顔を持っていた。
武家人口の約八〇%が地方から出てきた藩士たちで占められた。
確かに、意外。
よく考えてみるとその通りなのだが、武家地の半分が大名屋敷だったというのは盲点だった。
そして、八割の武士が地方出身者。
現代でも東京は地方からの転勤社員が多く住んでいるのだから、似たようなものなのかもしれない。
この大名屋敷は端的に言うと、菊池正芳氏の「江戸大名庭園は挑む」(はる書房)に書かれているように、
大名の住む上屋敷、妻子の住む中屋敷、震災等で上屋敷を失った場合の屋敷である下屋敷の三か所の屋敷を得ることになった。
であったが、あくまでもこれは原則である。
小大名の多くは中屋敷を持たなかったし、複数の中屋敷や下屋敷を持つ家もあった。
たとえば、御三家の尾張藩は、
尾張藩でも市ヶ谷の上屋敷のほか、中屋敷二か所、下屋敷を六か所に備えていた。
小寺武久氏「尾張藩江戸下屋敷の謎」(中公新書)
これらの屋敷は将軍から与えられたもので「拝領屋敷」と言った。
この辺りは、真田宝物館の「お殿様、お姫様の江戸暮し」という企画展の解説本(長野市教育委員会文化財課)に分かりやすい記述がある。
松代藩は江戸にさまざまな屋敷を持っていました。江戸の屋敷は大きく分けて二つの種類に分かれます。
第一は拝領屋敷で、これは将軍から拝領した屋敷をいいます。真田家の場合、①藩主の居所、②隠居した藩主や次代の藩主の居所、③郊外の遊園、災害時の避難所、の三種類がありました。➀は上屋敷で四度の変遷を追うことができます。②は一般的には中屋敷といいますが、真田家の場合、下屋敷をあてています。(中略)③は二箇所から三箇所が常にありました。
第二は抱え屋敷で、百姓の土地を購入した屋敷です。これは資産保有という側面が大きいとされます。拝領地と違い、村に対して年貢を払うという性格の土地(いわゆる年貢地)です。年貢も比較的高かったようです。真田家においては、拝領地が少なかったために、この抱屋敷、抱地を多く持ち、参勤交代で江戸居住となった武士たちの長屋を賄うなどの役割をしています。
真田家は十万石。
けっして小大名ではないが、それでも拝領地は少なかったようだ。
参勤交代の費用で遠国の外様大名は苦しんだ、という記述を時々見るが、大名が苦しんだのは参勤交代の道中での費用ではなく、江戸での滞在費用だったのである。

柳沢吉保が造った六義園。
↓よろしかったら、クリックお願いいたします!
江戸は江戸城を核とする日本最大の城下町である。武士が住む武家地がその約七〇%を占め、町人が住む町人地と寺社地が同じく十五%ずつ分け合った。
歴史好きな方なら、江戸っ子が狭い土地にぎゅうぎゅう詰めに押し込まれるようにして住んでいたという史実をご存じかもしれない。
しかし、次の記述はどうだろうか?
江戸の土地の七〇%を占める武家地の過半は大名屋敷だった。意外にも、将軍のお膝元江戸は、大名屋敷の街という顔を持っていた。
武家人口の約八〇%が地方から出てきた藩士たちで占められた。
確かに、意外。
よく考えてみるとその通りなのだが、武家地の半分が大名屋敷だったというのは盲点だった。
そして、八割の武士が地方出身者。
現代でも東京は地方からの転勤社員が多く住んでいるのだから、似たようなものなのかもしれない。
この大名屋敷は端的に言うと、菊池正芳氏の「江戸大名庭園は挑む」(はる書房)に書かれているように、
大名の住む上屋敷、妻子の住む中屋敷、震災等で上屋敷を失った場合の屋敷である下屋敷の三か所の屋敷を得ることになった。
であったが、あくまでもこれは原則である。
小大名の多くは中屋敷を持たなかったし、複数の中屋敷や下屋敷を持つ家もあった。
たとえば、御三家の尾張藩は、
尾張藩でも市ヶ谷の上屋敷のほか、中屋敷二か所、下屋敷を六か所に備えていた。
小寺武久氏「尾張藩江戸下屋敷の謎」(中公新書)
これらの屋敷は将軍から与えられたもので「拝領屋敷」と言った。
この辺りは、真田宝物館の「お殿様、お姫様の江戸暮し」という企画展の解説本(長野市教育委員会文化財課)に分かりやすい記述がある。
松代藩は江戸にさまざまな屋敷を持っていました。江戸の屋敷は大きく分けて二つの種類に分かれます。
第一は拝領屋敷で、これは将軍から拝領した屋敷をいいます。真田家の場合、①藩主の居所、②隠居した藩主や次代の藩主の居所、③郊外の遊園、災害時の避難所、の三種類がありました。➀は上屋敷で四度の変遷を追うことができます。②は一般的には中屋敷といいますが、真田家の場合、下屋敷をあてています。(中略)③は二箇所から三箇所が常にありました。
第二は抱え屋敷で、百姓の土地を購入した屋敷です。これは資産保有という側面が大きいとされます。拝領地と違い、村に対して年貢を払うという性格の土地(いわゆる年貢地)です。年貢も比較的高かったようです。真田家においては、拝領地が少なかったために、この抱屋敷、抱地を多く持ち、参勤交代で江戸居住となった武士たちの長屋を賄うなどの役割をしています。
真田家は十万石。
けっして小大名ではないが、それでも拝領地は少なかったようだ。
参勤交代の費用で遠国の外様大名は苦しんだ、という記述を時々見るが、大名が苦しんだのは参勤交代の道中での費用ではなく、江戸での滞在費用だったのである。

柳沢吉保が造った六義園。
↓よろしかったら、クリックお願いいたします!