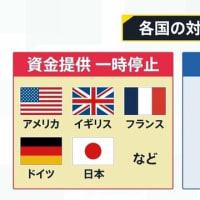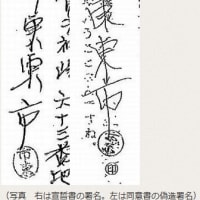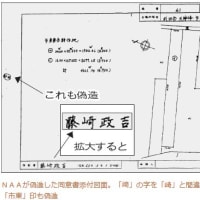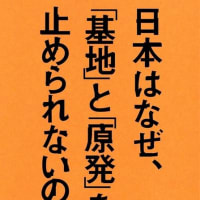外国語のアルファベットって「AEIOU(アエイオウ)」の順番が多いのに、日本は何で「AIUEO(あいうえお)」の順番なんだろう、それに「あかさたな」って、何でこういう順番なんだろうと思っていましたが、ネットでこんな記事を見つけました。抜粋でご紹介します。
サンスクリット語のアルファベットと、仮名の五十音 - 高いお米、安いご飯
サンスクリット語のアルファベットと、仮名の五十音
片仮名は、九世紀初めに、奈良の古学派の学僧たちが漢文を和読するために、訓点として万葉仮名の一部の字画を省略し付記したものに始まると考えられています(たとえば、「阿」の左側部分から「ア」、「伊」の左側部分から「イ」、「宇」の上の部分から「ウ」、江の右側部分からエ、於の左側部分からオなど)。
しかし、ぼくの興味は、個々の仮名文字ではなく、以下のような仮名四十八文字(ないしは五十音)という構成が、つまり「アイウエオ」という順番、および「アカサタナハマヤラワ」という順番からなる文字構成が、どのようにしてできたのかということの方に向かいます。
調べてみると、片仮名四十八文字(あるいは五十音)の構成はサンスクリット語のアルファベットを参考にしているらしい。サンスクリット語のアルファベットとは以下のようなものです。サンスクリット辞書(や用語集)は、単語や用語がこのアルファベットの順番で、つまり左上から右下にかけての順番で、並んでいます。
この表と仮名五十音図を見較べてみます。母音は、ラテン文字で表すと、a、ā、i、ī、u。ū、ṛ、ṝ、ḷ、ḹ、e、ai、o、au で、日本語が直接に対応しない母音もありますが、日本語対応母音は「あいうえお」の順に並んでいます。また子音の配列も (母音)、 k、kh、g、gh、ṅ、c、ch、j、jh、ñ、ṭ、ṭh、ḍ、ḍh、ṇ、t、th、d、dh、n、p、ph、b、bh、m、y、r、l、v、ś、ṣ、s、h となっており、当時の「ts」に近かった「さ行」や、それ以前では「f」よりも「p」に近かった「は行」の発音を考えると、また「y」が「ヤ」、「r」が「ル」(ルの「あ段」は「ラ」)、「v」が「ワ」という発音に相当することを考えると、この順番は「あかさたなはまやらわ」です。
念のために、サンスクリットのアルファベットと仮名五十音(の一部)を重ね合わせてみると次のようになります。

片仮名の起源は九世紀初めの奈良の古宗派の学僧たちの漢文和読だと書きましたが、当時、サンスクリット(悉曇 しったん)(注)を詳しく知っているのは、南都六宗や密教系の僧侶の一部や仏教に造詣の深い帰化人だけでした。そういう人たちが、サンスクリットのアルファベットを参考に、「あいうえお」「あかさたなはまやらわ」「ん」という五十音(あるいはその基礎)を作り上げたのでしょう。
(注)悉曇 (しったん)はサンスクリットのシッダム(siddham)を音訳した漢語である。狭義には母音字を指す言葉であるが、子音字も含めてサンスクリットを表す文字全般を称する場合もある。
そして、いつのころか、この仮名四十八文字の全部が重複なく使われて、無常感の漂うきれいな歌になりました。「色は匂へど 散りぬるを 我が世誰ぞ 常ならむ 有為の奥山 今日越えて 浅き夢見し 酔ひもせず」。
(編集部より)
チョッとかじったことがあるので「習志野」をサンスクリットの文字で書いてみました。(間違っていたらごめんなさい。)
नाराशीनो
日本とインドのつながり、興味深いですね。
コメントをお寄せください。
<パソコンの場合>
このブログの右下「コメント」をクリック⇒「コメントを投稿する」をクリック⇒名前(ニックネームでも可)、タイトル、コメントを入力し、下に表示された4桁の数字を下の枠に入力⇒「コメントを投稿する」をクリック
<スマホの場合>
このブログの下の方「コメントする」を押す⇒名前(ニックネームでも可)、コメントを入力⇒「私はロボットではありません」の左の四角を押す⇒表示された項目に該当する画像を選択し、右下の「確認」を押す⇒「投稿する」を押す