鉄道連隊のこと
イトーヨーカドー津田沼店前から総武線の線路側に出た所にある「津田沼一丁目公園」には、軽便鉄道(けいべんてつどう)の機関車が置かれています。
そして、線路の反対側には、千葉工業大学の赤レンガの門が見えてきます。この門は昔、鉄道第2連隊の正門でした。
大学から商業ビル「モリシア」、習志野文化ホール、そして今年出来上がったタワーマンション(仲よし幼稚園跡地)とこのあたり一帯が、かつての鉄道第2連隊の跡地なのです。そしてイトーヨーカドー津田沼店から新京成の線路までは、その「材料廠(ざいりょうしょう)」となっていました。
図の中央部右側に「鉄道第二連隊」と書いてある所が今の千葉工大通用門。線路の反対側に「鉄道倉庫」とあるあたりが今のイトーヨーカドー

なお、赤レンガの正門は平成10年(1998)に、国の登録文化財として文化庁に登録されています。
軍用列車には一般住民も便乗、まさに新京成線のルーツ
まず、機関車から見ていくことにしましょう。この機関車は、鉄道連隊が使用したK2型機関車の134号機(製造は昭和18年、製造会社は川崎車両)です。
<鉄道連隊の津田沼駅ホームから松戸方面へ発車する列車。軍需品や兵士のほか、一般住民も便乗させた。まさに新京成線のルーツ>(「新京成電鉄 駅と電車の半世紀」より)
研究者の解説によると、軌間600ミリ用の小型タンク機関車であるわりに動輪が5軸あるE型という、凝った仕様になっているのは、演習目的で作られたためだからだとのこと。鉄道連隊ではこれを2輌背中合わせ(双合式)にして使用したそうです。(「新京成電鉄 駅と電車の半世紀」より)
また、1890年にドイツで考案された「クリン・リントナー式」という特殊な遊動輪装置をもち、戦場での急カーブを想定した構造になっているそうです。
戦後は、西武鉄道に払い下げられ、軌間1067ミリ用に改造されて砂利採り線などで使用されたのち、玉川上水の西武運輸中央倉庫の片隅に置かれていましたが、除籍後は埼玉県狭山市にあった遊園地「ユネスコ村」に保存されていました。ユネスコ村閉園後の平成6(1994)年に、鉄道連隊ゆかりの地に里帰りが実現したものです。
K2型は全部で47両作られたそうですが、この134号機が現存する唯一のK2型だと言われています。
戦前は軍隊の鉄道⇒戦後は一時自衛隊が運用⇒今は「ハミングロード」
こうした小型機関車を使って、ここから鉄道連隊の演習線が出ていました。一つは千葉市にあった鉄道第1連隊(現・千葉公園周辺)に向けて、もう一つは松戸市にあった工兵隊に向けて敷設されており、鉄道兵の演習に使われるだけでなく、習志野から千葉、あるいは松戸に向けて点在する軍隊間の連絡用に使われていました。
千葉へ向かう線路(津田沼・千葉間16.7km、また作草部から分れて四街道へ向かう支線7kmがありました)は、戦後は一時、陸上自衛隊第101建設隊(昭和35年~41年)が運用しましたが、その後、撤去され、習志野市内は「ハミングロード(通称マラソン道路)」とよばれる道路になっています。
<演習線だったころのハミングロード>(「新版 習志野ーその今と昔」より)
一方の松戸へ行く線路(津田沼・松戸間26.5km)は、現在は新京成電鉄として営業しています。新京成の路線がカーブの多い設計になっているのは、鉄道敷設の演習用だった名残だとも言われています。また、払下げをめぐって京成電鉄と西武鉄道の争いになったものの、最終的に京成電鉄が引き受けることになり、その代わり、蒸気機関車や貨車等は西武鉄道に払い下げたのだと言います。K2型がユネスコ村にいたのは、そういう関係なのだそうです。
鉄道連隊演習線
http://kashiwa.mokuren.ne.jp/contents/rentai/161/index.htm
鉄道敷設の演習は、さまざまな条件の戦場に、いかにして早く鉄道を敷いて味方の補給路を確保するか、という訓練に明け暮れていました。軌匡式(ききょうしき)レールと言って、鉄道模型のようにあらかじめ枕木が付けてあるレールを貨車に積んで行き、どんどん前へつないで行く工法が取られたそうです。
谷があれば橋を架け、山があれば、トンネルを掘る暇などないのでスイッチバックを繰り返して乗り越える。また、脱線した場合の復旧作業など、すべて時間との戦いの中で、猛訓練が行われていたそうです。また、機関車の運転に関しては、鉄道省(後の国鉄、JR)の機関士に付いて厳しい実習が行われました。そんな様子は、映画にもなりました。
<映画「指導物語」(昭和16年)>
鉄道第2連隊の若い鉄道兵が、佐倉の機関庫に実習に行くお話で、鉄道兵が藤田進、これを指導する老機関士が丸山定夫(後に広島で原爆死)、その娘が原節子という配役。厳しい老機関士はだんだん兵隊に情が移ってきて、娘をこんな男に嫁がせたいなと思うようになりますが、とうとう鉄道連隊に出動命令がくだります。
<原爆の犠牲になった、移動演劇団「さくら隊(「櫻隊」とも表記)」の人たち。一番左上が丸山定夫>
映画の内容はともかく、このYouTubeを再生してみると、17分28秒から鉄道連隊の正門が出てきます。
さらに32分20秒には正門を出た藤田進らが佐倉の機関区に向う場面、
33分37秒では津田沼駅から千葉へ向かう電車に乗り込みます(総武線は、昭和10年には千葉駅まで電化されていました)。

1時間30分17秒には、鉄道連隊を訪ねてきた老機関士が、衛兵所で、連隊が近く出征することを知る場面。
当時の津田沼の風景を偲んでいただきましょう。
シベリア鉄道で東進するロシアに対抗して作られた鉄道部隊
移り変わる車窓の風景、ひなびた田舎の駅舎、眠気を誘うレールの音…。鉄道というものは旅情を誘うものです。しかし、近代の歴史の中で、鉄道が持っていた軍事的な役割を見落とすことは出来ません。明治時代、ロシアのシベリア鉄道がどんどん東に伸びてきたことが当時の日本人にどれほど恐怖感を与えたか、現代の我々にはなかなか理解できないことです。トラックもない時代、モスクワにいる軍隊が、2週間もあれば極東に移動できてしまう鉄道というものは、日本にとって大きな脅威でした。そして、それに対する日本は、戦地にいかに早く鉄道を敷き、正確な運行を確保するかが課題となります。それに特化した工兵部隊として、鉄道部隊が作られたのです。戦地において鉄道を建設し、運行することで前線への補給路を確保すること。そして敵襲を受けた線路の速やかな修理、さらに敵の鉄道を破壊することを任務としました。
明治29年(1896)に、東京・中野に鉄道大隊が編成されたのが始まりでした。
義和団の乱
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%A9%E5%92%8C%E5%9B%A3%E3%81%AE%E4%B9%B1
では臨時鉄道隊を編成し、乱によって破壊された鉄道の修理に従事します。さらに日露戦争では各地で軽便鉄道を敷設し、物資・兵員の輸送などに従事しました。明治39年(1906)には津田沼駅から、ロシア兵を収容した習志野俘虜収容所までの間に軽便鉄道を敷設しています。そして翌明治40年(1907)、鉄道連隊に昇格し、中野から津田沼に引っ越してきます。近衛師団の交通兵旅団に属していました。さらに明治41年には、連隊本部と第1大隊が千葉の椿森に移ります。千葉の部隊を鉄道第1連隊、津田沼を鉄道第2連隊とするようになるのは大正7年(1918)のことです。その5年後に起きた関東大震災(1923)では両連隊とも、各地で破壊された鉄道の復旧に出動しています。
次に連隊の編制ですが、連隊長(大佐)の下に連隊本部があり、大隊は3個。1大隊は3個中隊から成り、1中隊100名ほど、他に材料廠を合わせて1000名ほどの編成でした。但し鉄道第2連隊にはこの他に、練習部、幹部候補生隊、下士官候補生隊が併設されていたそうです。
鉄道連隊、山東出兵に出動。最後は九州で終戦を迎える
昭和に入って鉄道第2連隊は、昭和3年(1928)の山東出兵(済南事件さいなんじけん)に出動します。昭和12年(1937)の日中戦争(日華事変)では、北支(中国北部、の当時の呼び方)に出動、徐州作戦に参加。その後も満州から北支に展開し、昭和20年(1945)には本土決戦に備えて九州に移動、そこで終戦を迎えました。
鉄道連隊の負の歴史、死の鉄道=泰緬(たいめん)鉄道。連合軍捕虜や多くのアジア人労働者の命が犠牲になる
しかし、鉄道連隊の歴史の中で忘れることができないのは、映画「戦場にかける橋」に描かれた泰緬鉄道(泰=タイと緬甸(めんでん)=ビルマ(ミャンマー)の間に通した鉄道)の建設でしょう。太平洋戦争のさなか、日本軍は進駐したタイからビルマに向けて、鉄道を建設します。タイ側からは津田沼で編成された鉄道第9連隊が、ビルマ側からは千葉で編成された鉄道第5連隊が建設を進めるのですが、大変な難工事となりました。また、これに使役した連合軍捕虜の扱いがひどく「Death Railway(死の鉄道)」と呼ばれ、戦後は日本軍の戦争犯罪として追及を受けることになるのです。
鉄道第9連隊がタイのノンプラドックに鉄道の起点となる0キロ標柱を建てたのは、昭和17年(1942)7月5日でした。この鉄道でビルマ作戦への物資輸送ルートを確保する一方、将来マラッカ海峡経由の海上輸送が危険になることに備えようというものでした。しかし、タイ・ビルマ国境の山岳地帯はたいへん険しく、衛生状態も悪かったため、容易には進みません。しかし、連合軍捕虜約5万5千人、アジア各地からかき集めた労働者約20万人を投入し、工事開始からたった1年3ヶ月で全長415キロ(東京~大垣間に相当)の鉄道を開通させたのでした。第9連隊はビルマで、第5連隊はタイで終戦を迎えます。しかし戦後は、この工事における捕虜虐待が重大問題となり、イギリスによって戦犯裁判が行われたのですが、その裁判は公正さを欠いた、報復色の強いものだったと言います。また現在では、捕虜虐待よりも、アジア各地から金で集められた労働者の運命の方が問題だとされています。山岳地帯の難工事で使い捨てにされ、労働者名簿もないため、犠牲者の全貌はわからないままなのだというのです。
<戦争の悲惨さを今に タイ”死の鉄道”>
下をクリックするとテレビニュースの画面が出てくるので、白い右矢印をクリックすれば見られます

タイ“死の鉄道”が今に伝える戦争の悲惨さ|日テレNEWS24
東南アジアのタイに第二次世界大戦中に旧日本軍が建設した鉄道が残されています。「死の鉄道」とも呼ばれ、戦後75年がたった今でも、戦争の悲惨さを...
日テレNEWS24
<枕木1つ命1つ>
映画「戦場にかける橋」(1957) ラストシーン
映画では木造になっているクワイ川(タイ語ではクウェー川)の橋ですが、実際には鉄橋です。これを建設したのは、鉄道第9連隊の第3大隊第5中隊でした。後に空襲は受けたものの現在も使われており、映画のように爆破などされていません。
多大な人的犠牲の上に敷設された路線は、ビルマ側は廃線になっていますが、タイ側では今日も健在で、同国の経済に貢献しているのだそうです。
泰緬鉄道の問題も、習志野から世界の平和を考える礎として、決して忘れてはならないものだろうと思います。(ニート太公望)
コメントをお寄せください。
<パソコンの場合>
このブログの右下「コメント」をクリック⇒「コメントを投稿する」をクリック⇒名前(ニックネームでも可)、タイトル、コメントを入力し、下に表示された4桁の数字を下の枠に入力⇒「コメントを投稿する」をクリック
<スマホの場合>
このブログの下の方「コメントする」を押す⇒名前(ニックネームでも可)、コメントを入力⇒「私はロボットではありません」の左の四角を押す⇒表示された項目に該当する画像を選択し、右下の「確認」を押す⇒「投稿する」を押す










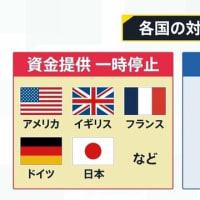


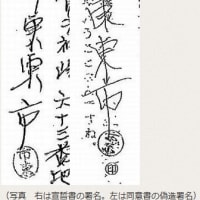
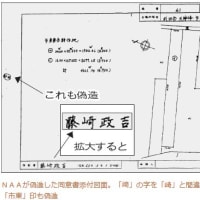




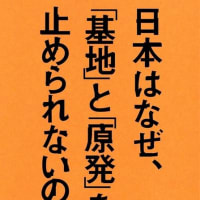





懐かしいです。
二中のところから先も、線路は残っていたんですね。
記憶にありません。
線路の幅は、京成よりも狭かったような気がしています。
二中の耐寒マラソンは習志野原近くまででした。