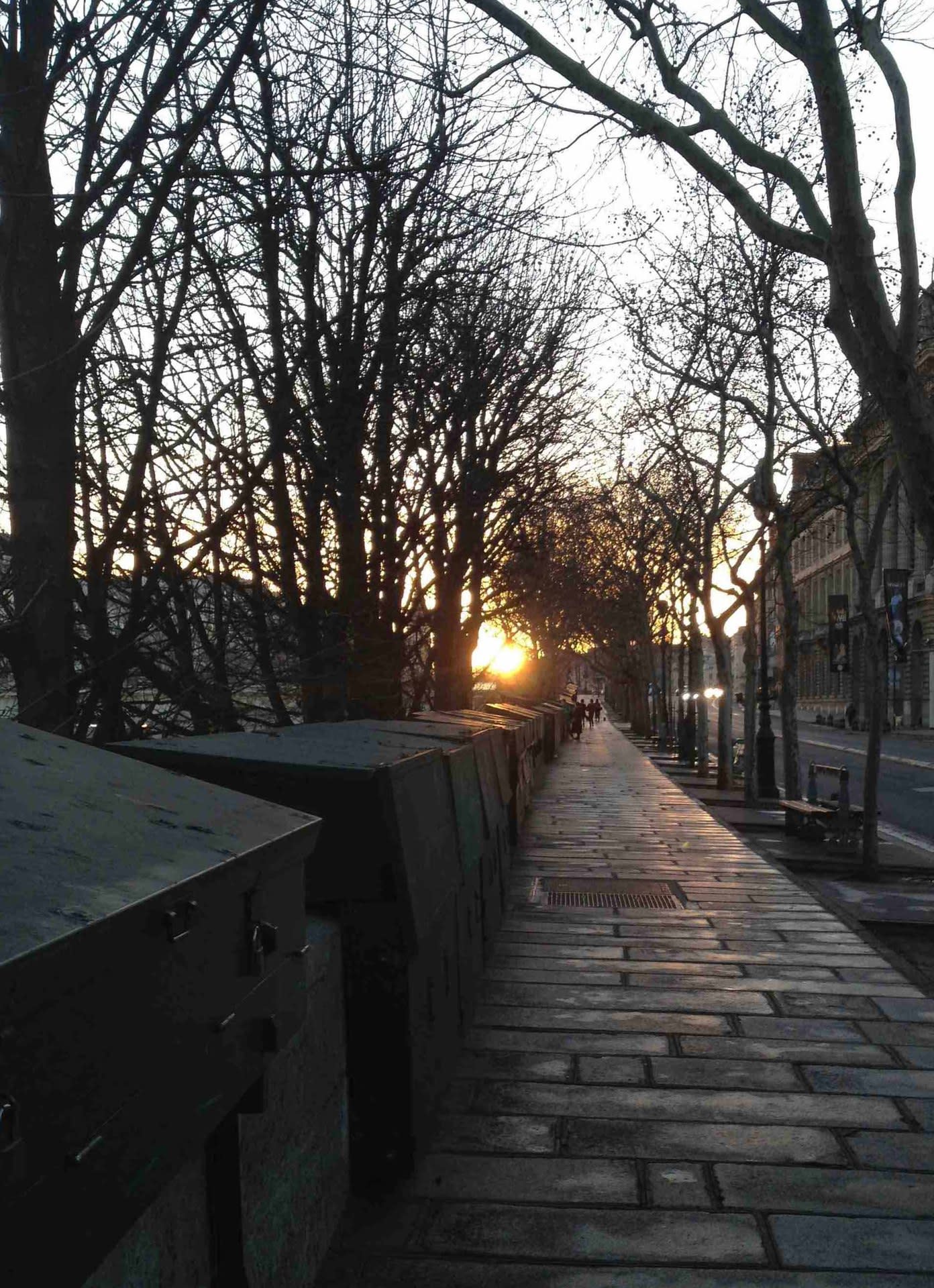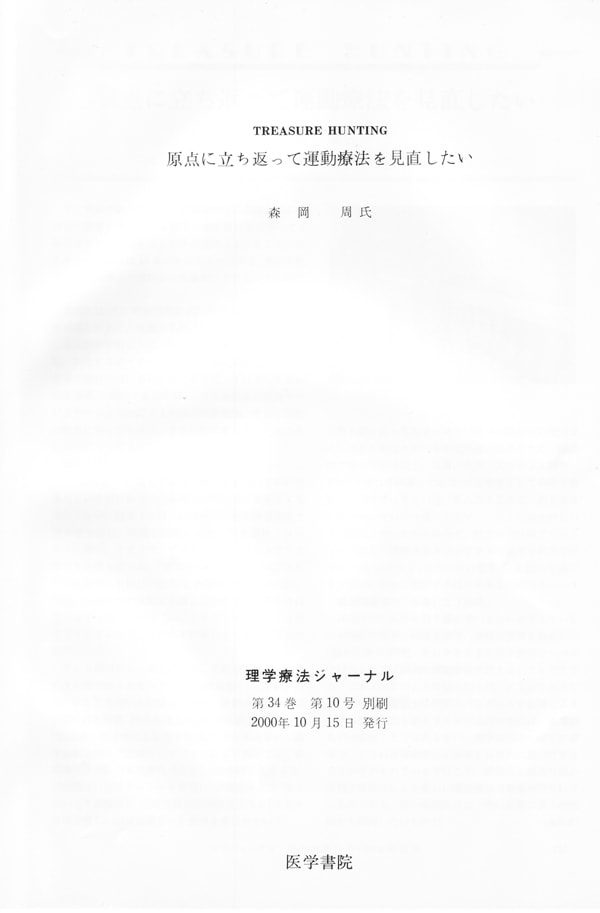今日は午後より日本生理学会大会にてシンポジウム講演をしました。私は慶応大学の里宇教授の後に登壇し、研究室のみんなのデータを中心にうちで取り組んでいる一連の脳イメージング研究ならびに臨床介入研究を紹介しました。運動麻痺、運動学習、痛み、高次脳機能について話しました。
最初に登壇した里宇先生はHANDS, BMI, Neurofeedbackをご紹介されました。最後のスライドの皮質脊髄路の可塑性に関連する神経メカニズムの検証に関するデータはすばらしく感動しました。
僕の後には長崎大学の沖田教授が関節拘縮に関連した研究を紹介。彼の研究室のすばらしさは自前のデータでメカニズムを解明しそのメカニズムに応じて臨床介入を考えその効果が分子や組織レベルでどのような根拠があるかを調べているところです。ほとんどのリハの研究室はそのどちらかが欠損しています。うちの大学の研究室も欠陥だらけです。人のいっていることをただ改良したり、コンバインさせたりしているだけです。メカニズムでは間違いだらけって結構あるんですよ。あえて、言いませんが。。
いずれにしても、彼が理学療法士としてこの生理学会に登壇したのはむしろ心強く生理学者に対して理学療法士の研究がとても質の高いものであることを報告する機会になったのではないかと思います。昨日も彼は痛みのシンポで発表し日本福祉大学の松原氏とPTの代表として発表できた事は、ある意味画期的だったと思います。
最後には早稲田大学の畠山教授が登壇し、工学、デバイスの視点からリハの研究が幅広い哲学の中で成り立っていることが示されました。いずれにしても、スタイルは違えども人間を科学するリハの意味生が、この日本生理学会にて取り上げられたことは画期的だと思いました。
道免先生、村田先生がご登壇されたシンポジウムもいれると、3つのリハ関連のシンポジウムが日本生理学会に取り上げられた事は今後メカニズムと臨床効果のブリッジの可能性の未来を実感するに至りました。この企画をしていただいた本学の金子先生、そして東京医療学院大学の佐久間先生に深謝いたします。
里宇先生は慶應学生時代の金子先生の教え子、沖田先生、畠山先生は金子先生の前任の星城大学の関係。そして私が現職の関係で、みんな断るに断れないという理由でした。。笑。最近長い講演が多くなり25分というタイムプレッシャーがあり、久しぶりに心地よい緊張感に恵まれました。
こういう機会を通じて、自己のレベルを見直すことができます。そして知らないうちに忘れかけている謙虚さを取り戻すことができます。いつまでも上に見られているという社会性はとても大切なのです。そう考えればちまたの療法士の講習会は、どうかな?とも思ったりもします。まあ偉そうにと・・・
いずれにしても、肩の荷がおりました。明日慈恵医大で講演がありますが、もうしばらく何もしたくない気分でもあります。理学療法士に22年前になりましたが、日本生理学会で話題提供するとは夢にも思いませんでした。むしろこのことは派手な講演とか出版とかでなく、きちんとこつこつと研究してきた結果だと思っています。もうちょっとがんばっていかないといけませんね。レベルを上げていきたいと思います。
最初に登壇した里宇先生はHANDS, BMI, Neurofeedbackをご紹介されました。最後のスライドの皮質脊髄路の可塑性に関連する神経メカニズムの検証に関するデータはすばらしく感動しました。
僕の後には長崎大学の沖田教授が関節拘縮に関連した研究を紹介。彼の研究室のすばらしさは自前のデータでメカニズムを解明しそのメカニズムに応じて臨床介入を考えその効果が分子や組織レベルでどのような根拠があるかを調べているところです。ほとんどのリハの研究室はそのどちらかが欠損しています。うちの大学の研究室も欠陥だらけです。人のいっていることをただ改良したり、コンバインさせたりしているだけです。メカニズムでは間違いだらけって結構あるんですよ。あえて、言いませんが。。
いずれにしても、彼が理学療法士としてこの生理学会に登壇したのはむしろ心強く生理学者に対して理学療法士の研究がとても質の高いものであることを報告する機会になったのではないかと思います。昨日も彼は痛みのシンポで発表し日本福祉大学の松原氏とPTの代表として発表できた事は、ある意味画期的だったと思います。
最後には早稲田大学の畠山教授が登壇し、工学、デバイスの視点からリハの研究が幅広い哲学の中で成り立っていることが示されました。いずれにしても、スタイルは違えども人間を科学するリハの意味生が、この日本生理学会にて取り上げられたことは画期的だと思いました。
道免先生、村田先生がご登壇されたシンポジウムもいれると、3つのリハ関連のシンポジウムが日本生理学会に取り上げられた事は今後メカニズムと臨床効果のブリッジの可能性の未来を実感するに至りました。この企画をしていただいた本学の金子先生、そして東京医療学院大学の佐久間先生に深謝いたします。
里宇先生は慶應学生時代の金子先生の教え子、沖田先生、畠山先生は金子先生の前任の星城大学の関係。そして私が現職の関係で、みんな断るに断れないという理由でした。。笑。最近長い講演が多くなり25分というタイムプレッシャーがあり、久しぶりに心地よい緊張感に恵まれました。
こういう機会を通じて、自己のレベルを見直すことができます。そして知らないうちに忘れかけている謙虚さを取り戻すことができます。いつまでも上に見られているという社会性はとても大切なのです。そう考えればちまたの療法士の講習会は、どうかな?とも思ったりもします。まあ偉そうにと・・・
いずれにしても、肩の荷がおりました。明日慈恵医大で講演がありますが、もうしばらく何もしたくない気分でもあります。理学療法士に22年前になりましたが、日本生理学会で話題提供するとは夢にも思いませんでした。むしろこのことは派手な講演とか出版とかでなく、きちんとこつこつと研究してきた結果だと思っています。もうちょっとがんばっていかないといけませんね。レベルを上げていきたいと思います。