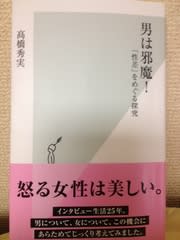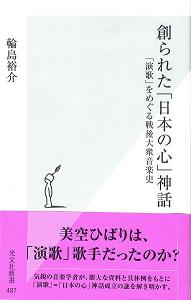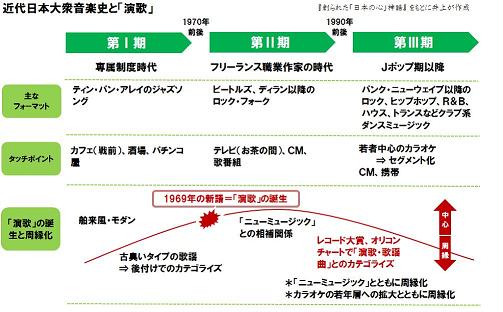1年以上前から気になっていたが、読む機会を逸していたら、
先日、同著者の『C層の研究』が発売されていたことを知った。
ということで本書を一読してみた。
「B層」とはいい加減な造語ではないようだ、一応。
2005年9月の郵政選挙の際、自民党が広告会社スリードに作成させた企画書「郵政民営化・合意形成コミュニケーション戦略(案)」による概念とのこと(同書47ページより)。
国民を「構造改革に肯定的か否か」を横軸、「IQ軸(EQ、ITQを含む独自の概念とされる)」を縦軸としたマトリクスで、「構造改革に肯定的でかつIQが低い層」「具体的なことはよくわからないが、小泉総理のキャラクターを支持する層」がB層とのことだ。
著者の主張を自分なりにまとめるとこういうことだ。
玄人=プロの世界が、素人に浸食されて久しく、大衆社会の負の側面が肥大化しているのが現代だ。
特に政治の世界でのその弊害は目も当てられない。
本書では特に、過去の民主党政権のトップ(僕も感じていて唖然としていたこと)や、橋下徹を鋭い批判の刃で切り刻んでいる。
「そういえば、プロの政治家っていなくなっちゃったよな」とは僕も感じていたことだ。
それを「時代の趨勢」と考え、思考停止状態になってしまったのも自分だ。
1980年前半、吉本隆明が「素人の時代」的なことを言いだしたが、

その「素人の時代」が今世紀に入り、弊害が大きくなり、国を滅ぼしてもおかしくない状況にわが国を追い込んでしまったということだろう。
しかも事態は深刻だ。
詳しくは本書を読んでいただきたい。
大筋において著者の主張には納得させられた。
という僕自身は、「大衆」の一人であり、こういうブログで書きたいことを書き連ねている僕も著者が矛先を向ける「素人」である(影響力は皆無ですが・・・)。
(以下、黒字部分は引用)
今はネット環境が整っていますので、誰でも声をあげることができるようになっている。
要するに、バカが情報を発信するインフラが整ったのです。
こうして素人が玄人の仕事に口を出す時代がやってきました。
分をわきまえる。身の程を知る、恥を知る、一歩下がる・・・・・・。
わが国から、こうした美徳が失われて久しい。
その一方で、マスメディアから自己啓発書まで社会全体一丸となって、「あなたは主人公だ」「もっと自信を持て」「もっと大きな声をあげよ」「社会に参加せよ」と素人を煽り立て、その気にさせている。
今は誰もが参加したがる時代です。そして参加してはならない場所に参加してしまう。
(以上、29-30ページより)
ニーチェの専門家の著者の筆致はアイロニーに溢れている。
これを小気味よいと感じるか、不快と感じるかは大きく分かれるところだろう。
(それも著者のブランディングだろう・・・)
僕は著者の主張に共感しつつも、批判対象を「バカ」と呼ぶ表現には違和感を感じる。
おそらく膨大な知識を備えた教養人であるはずの著者が、
著者の批判する人たちと大同小異であるように感じるからだ。
まるで匿名掲示板の住人たちのように。
おそらく著者はこう言うだろう。
「バカだからバカと呼ぶしかないだろ?」
それでも、「B層」の論者としてのポジションを確立した(?)著者は、その毒舌を持ち味としていくしかないと思う。
それも著者自身というよりも、編集者・出版社の方針かもしれないが。
著者は東日本大震災の後の、「アーティスト」の「ボランティア」に対しても、歯に衣を着せぬ批判をしている。
僕が自分がずっと感じていた「アーティスト」たちへの違和感を的確に表現していると感じ入った。
(以下、黒字部分は引用)
震災後に売れない歌手が被災地に行って歌を唄ったりしました。
あれも「参加」です。
「偽善と思われてもいい」などと言っていましたが、
誰も偽善だなんて思っていません。
ただの迷惑です。
一体、どれだけ高慢になれば「自分の歌で心を癒してほしい」などと言えるのでしょうか。
要するに子供ばかりの社会になってしまった。
(以上、63-64ページより。太字部分は引用者)
言い方はキツイが著者の音楽、特にジャズへの造詣は深そうだ。
また、山下達郎の全アルバムをテキストマイニングし、「ポップス職人」としての山下を尊敬している。
「紋切り型」とはネガティブどころかポジティブな意味でのポップスの本質であることも押さえている。
とにかく、こんな時代だからこそ著者の論はこの国にとって貴重だ。
独裁は民主主義の中からしか出てこないこと。
われわれが信じて疑わなかった「進歩史観」の誤り。
先人たちの労作=古典への軽視。
オルテガの大衆論(僕は80年代に西部邁の書籍で知りました)等々。
毒舌の中ではあるが(=多くの人たちを納得させるにはデメリットではあるものの)、
多くの気づきがちりばめられている。
著者の他の労作も是非、読んでみたい。
***************************************
▼記事へのご意見、Cultural Marketing Lab INOUE. (CMLI) へのお問い合わせは下記メールにてお願いいたします。
sinoue0212@goo.jp
***************************************
▼『コンテンツを求める私たちの「欲望」』
電子書籍(無料)、閲覧数 14,400 突破しました!
私の思想=文化マーケティングの視座が凝縮されています。
http://p.booklog.jp/book/43959
***************************************
お読み頂き有難うございます。
(↓)クリックの程、宜しくお願い申し上げます。

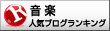 音楽 ブログランキングへ
音楽 ブログランキングへ
 マーケティング・経営 ブログランキング
マーケティング・経営 ブログランキング
先日、同著者の『C層の研究』が発売されていたことを知った。
ということで本書を一読してみた。
「B層」とはいい加減な造語ではないようだ、一応。
2005年9月の郵政選挙の際、自民党が広告会社スリードに作成させた企画書「郵政民営化・合意形成コミュニケーション戦略(案)」による概念とのこと(同書47ページより)。
国民を「構造改革に肯定的か否か」を横軸、「IQ軸(EQ、ITQを含む独自の概念とされる)」を縦軸としたマトリクスで、「構造改革に肯定的でかつIQが低い層」「具体的なことはよくわからないが、小泉総理のキャラクターを支持する層」がB層とのことだ。
著者の主張を自分なりにまとめるとこういうことだ。
玄人=プロの世界が、素人に浸食されて久しく、大衆社会の負の側面が肥大化しているのが現代だ。
特に政治の世界でのその弊害は目も当てられない。
本書では特に、過去の民主党政権のトップ(僕も感じていて唖然としていたこと)や、橋下徹を鋭い批判の刃で切り刻んでいる。
「そういえば、プロの政治家っていなくなっちゃったよな」とは僕も感じていたことだ。
それを「時代の趨勢」と考え、思考停止状態になってしまったのも自分だ。
1980年前半、吉本隆明が「素人の時代」的なことを言いだしたが、

その「素人の時代」が今世紀に入り、弊害が大きくなり、国を滅ぼしてもおかしくない状況にわが国を追い込んでしまったということだろう。
しかも事態は深刻だ。
詳しくは本書を読んでいただきたい。
大筋において著者の主張には納得させられた。
という僕自身は、「大衆」の一人であり、こういうブログで書きたいことを書き連ねている僕も著者が矛先を向ける「素人」である(影響力は皆無ですが・・・)。
(以下、黒字部分は引用)
今はネット環境が整っていますので、誰でも声をあげることができるようになっている。
要するに、バカが情報を発信するインフラが整ったのです。
こうして素人が玄人の仕事に口を出す時代がやってきました。
分をわきまえる。身の程を知る、恥を知る、一歩下がる・・・・・・。
わが国から、こうした美徳が失われて久しい。
その一方で、マスメディアから自己啓発書まで社会全体一丸となって、「あなたは主人公だ」「もっと自信を持て」「もっと大きな声をあげよ」「社会に参加せよ」と素人を煽り立て、その気にさせている。
今は誰もが参加したがる時代です。そして参加してはならない場所に参加してしまう。
(以上、29-30ページより)
ニーチェの専門家の著者の筆致はアイロニーに溢れている。
これを小気味よいと感じるか、不快と感じるかは大きく分かれるところだろう。
(それも著者のブランディングだろう・・・)
僕は著者の主張に共感しつつも、批判対象を「バカ」と呼ぶ表現には違和感を感じる。
おそらく膨大な知識を備えた教養人であるはずの著者が、
著者の批判する人たちと大同小異であるように感じるからだ。
まるで匿名掲示板の住人たちのように。
おそらく著者はこう言うだろう。
「バカだからバカと呼ぶしかないだろ?」
それでも、「B層」の論者としてのポジションを確立した(?)著者は、その毒舌を持ち味としていくしかないと思う。
それも著者自身というよりも、編集者・出版社の方針かもしれないが。
著者は東日本大震災の後の、「アーティスト」の「ボランティア」に対しても、歯に衣を着せぬ批判をしている。
僕が自分がずっと感じていた「アーティスト」たちへの違和感を的確に表現していると感じ入った。
(以下、黒字部分は引用)
震災後に売れない歌手が被災地に行って歌を唄ったりしました。
あれも「参加」です。
「偽善と思われてもいい」などと言っていましたが、
誰も偽善だなんて思っていません。
ただの迷惑です。
一体、どれだけ高慢になれば「自分の歌で心を癒してほしい」などと言えるのでしょうか。
要するに子供ばかりの社会になってしまった。
(以上、63-64ページより。太字部分は引用者)
言い方はキツイが著者の音楽、特にジャズへの造詣は深そうだ。
また、山下達郎の全アルバムをテキストマイニングし、「ポップス職人」としての山下を尊敬している。
「紋切り型」とはネガティブどころかポジティブな意味でのポップスの本質であることも押さえている。
とにかく、こんな時代だからこそ著者の論はこの国にとって貴重だ。
独裁は民主主義の中からしか出てこないこと。
われわれが信じて疑わなかった「進歩史観」の誤り。
先人たちの労作=古典への軽視。
オルテガの大衆論(僕は80年代に西部邁の書籍で知りました)等々。
毒舌の中ではあるが(=多くの人たちを納得させるにはデメリットではあるものの)、
多くの気づきがちりばめられている。
著者の他の労作も是非、読んでみたい。
***************************************
▼記事へのご意見、Cultural Marketing Lab INOUE. (CMLI) へのお問い合わせは下記メールにてお願いいたします。
sinoue0212@goo.jp
***************************************
▼『コンテンツを求める私たちの「欲望」』
電子書籍(無料)、閲覧数 14,400 突破しました!
私の思想=文化マーケティングの視座が凝縮されています。
http://p.booklog.jp/book/43959
***************************************
お読み頂き有難うございます。
(↓)クリックの程、宜しくお願い申し上げます。