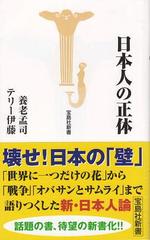本書が画期的であるのは、従来型のパッケージ販売をコアとしたビジネスと、デジタル配信ビジネスという単純な二項対立の図式の中で“デジタル配信派の筆頭”と一般的に捉えられている津田大介氏と、音楽業界のメインストリームで数々の実績を残されてきた牧村憲一氏のジョイントさせたことだと考えます。
単純な二項対立の図式に基づいた議論は不毛とならざるを得ません。
そして津田氏は、デジタル万能主義者ではなく、実は音楽の良質な愛好者(ライブはまだ観たことないですが)であることは僕も知っています。
“渋谷系”の産みの親でもあった牧村氏も、あるべき音楽の姿、レーベルのあり方について優れた感覚とセンスをお持ちの方だということが、本書を読んでひしひしと伝わってきました。
(両氏のご経歴は、amazon 商品説明の著者略歴をご参照下さい)

僕は昨年(2010年)11月に読んでみたんですが、牧村憲一氏の書かれた「あとがき」で、牧村氏と津田氏をジョイントをコーディネートされたのが、風来舎社長の森和夫さんだとわかり、とてもすんなりと納得したものです。「なるほど」という納得感が「スコ~ン」と来るような(笑)。
音楽論からテクノロジー論まで、人によって色々な読み方ができる書籍ですが、以下、僕の意識に刺さった内容をまとめてみます。
■レーベルのあり方
あるべきレーベルの姿、について僕は昨年、残響レコードの記事を書いてきました。
なぜ、メジャーといわれた世界で優れたレーベルが誕生しつつも、それが持続可能なビジネスとして根付かなかったのか?
そのいきさつについて本書で牧村氏が総括されてます。
結局、レコード会社にとっての都合のよい投資の“刈り取り場”がレーベルであったのかもしれないと(同書105ページより)。
(1)パソコン、携帯端末も普及による音楽環境の変化とご都合主義の配信。
(2)ミュージシャンも含め誰もが飛びついてしまったお手軽なカヴァー集、バブル的売り上げを想定した過去の悪癖。
(3)既得権に基づくリスナーへの不親切で不利益な対応。
(4)流行りのものに擦り寄る、音楽性の欠如。
上記のことがらは、現在、レーベルを作る際、そのまま反面教師としてのポイントとなり、それこそ原点回帰ではないか? と牧村氏は指摘します(同書105ページより)。
音楽のクオリティと経営戦略の両立。
レーベルの維持には知識と美意識が必要で、核となるのが人と音楽、そしてヒット。
ヒットとは、短期間の売り上げに留まらず、長い時間を超えて売れ続けるという面もある。
これは、ブランドの発想ですよね。
■経験価値と文化サイクル
津田氏が、地方の人と話された逸話があります(同書218ページ)。
今やamazon.をはじめネットショッピングがあるのだから、遠方のTSUTAYAに行く必要はないのではないか? との問いに、「津田さんは地方をわかっていない。地方には娯楽がないので、CDを借りて返しにいくことが文化的なサイクルである」と言われたそうです。
かつての東京的(六本木WAVE)なものが地方で展開拡散(牧村氏)している。
たとえその場で購入しなくても、場のオーラの中で情報を得たり満足感を得る。
そういう環境づくりは、リアルのショップにとって切実でしょうね。
■CDの付加価値
僕も数年前からずっと、CDの二極化のことは言ってきましたが、本書でも当然、そのことは触れられてます。
牧村氏の対話の中で、もし津田氏がプロモーションを任されたら? との問いに以下のように答えています(同書230ページ)。
(1)アルバムという単位は必ずミニアルバムにする。
(2)CD販売はamazon.とライブ会場に限定。会場販売は全て1,000円で販売し、amazon.の優れたシステムを手軽に利用できる「e謡」販売サービスを行う。
(3)一方で2,000円のCDも出して次回のライブ優先予約券とボーナス・トラックを入れる。
このあたりについては、昨年末に読んだジム・コリンズの『トレードオフ』の内容が頭に浮かんできました。

一言でいえば、あらゆる商品は、「上質さ」と「手軽さ」のどちらかの軸で突出したものが成功するということです。
その両方を狙うことは幻想(幻影)でしかない(二兎を追うものは一兎を得ず)。
両方の軸で突出していなければ、「不毛地帯」でくすぶってします。
新しい商品は、ほとんど「不毛地帯」で生まれ、ヒットする商品は「上質」か「手軽」のどちらかの軸で突出する。
「上質」ないしは「手軽」で、多くの商品がひしめき合っている場合、「上質」なら「手軽の部分で、「手軽」なら「上質」の部分で突出すると、それはイノベーションになる。
そういう要旨です。
そう言えば、「ユニクロ」は、「手軽さ」の勝者ですよね。
『トレードオフ』の図表を自分で編集しなおしてみました(↓)。

著者のジム・コリンズ氏は僕と同じでU2がお好きなようなので、本書にもU2が引き合いに出されてますから、僕もU2の引き合いに出します(↓:iTunes の画面だけU2じゃないですが・・・)。

今までの業界のビジネスモデルにおいては、「コンサート・ライブ」はパッケージ販売のためという位置づけでした。
ところが、生活者にとっての価値のマップは違ってますよね。
これじゃビジネスもうまくいかなくて当然です。
ジム・コリンズは、「上質」をこう定義しています。
上質度=経験+オーラ+個性
「上質」にしても「手軽」(価格・入手の便宜性)にしても、その基準は刻刻と変わっていくものです。
つい10年前までは、「手軽」軸の筆頭にCDなどパッケージ商品がいたもんですが、今や「配信」に敵うはずがありません。
(それまでは、「手軽」さを追求したことでマス・マーケットを拡大してきたわけですよね)
となると、「上質」軸を中心にパッケージ商品をポジショニングしていくことが現実的です。
勿論、「上質」軸でも「コンサート・ライブ」には敵いませんが、「コンサート・ライブ」との関連性の中でCDを位置付けていく津田氏のアイデアは的外れではありません。
津田氏が、クローズドチャネルでCDを1,000円の価格設定にしたのは、決して「手軽」軸を求めたわけではないと僕は考えます。
ただ、それにしても現状のCDの価格が生活者にとって高すぎるというのは僕も検証してますので、曲数と価格の戦略はもっと練られるべきでしょう。
また、津田氏のプロモーション・プランは、(津田氏気に入ったアーティストの場合という仮定で)クローズドチャネル(コンサート会場とネットショップ)のお話でしたので、リアル・ショップのことは触れられていません。そのあたりは別の話になるのでしょうが、それでも「上質」軸でのポジショニングが肝要かと僕は考えます。
「上質」と「手軽」を言い換えると、「愛される」と「必要とされる」ことです。
誰だって「愛されつつ必要とされる」は理想でしょう。
人として生きていく上で、「愛されつつ必要とされる」ケースはあるかもしれません。
しかし、ここが重要なんですが、商品の世界ではあり得ないことなのです。
「音楽」は人にとって必ずしも「必要」とされるものではないかもしれません。
(“NO MUSIC NO LIFE”のコアなファンは別ですけど、若い頃、音楽に入れ込んでいても結婚して子供ができれば音楽を買うことから離れるなんてことは当たり前のことでした)
どうあがいても、「必要とされる」ということでは、飲食品や衣料や教育費のような必需品・サービスには敵わないのです。
ならば、「必要とされる」ことよりも「愛される」ことを求めるのは妥当なことであり、「愛してくれる」人達を増やすべく開拓するべきではないでしょうか?
あと余談なんですけど、「HMV」を買収された「ローソン」さん。チケット販売とパッケージ販売(特にEC)のシナジー効果を狙われていると思うんですが、「上質」と「手軽」のトレードオフには、特にお気をつけてくださいね。
■文化としての可能性
『未来型サバイバル音楽論』の第5章「それでも人は音を楽しむ」、牧村氏と津田氏のトークではいくつも示唆的な発想が出てきます。
「ネットはサロンである」もしかりです。
ソーシャル・メディアにしてもその名の通り、社交の場。
「音」までもネット空間の中で完結してしまうことはないと僕も考えます。
リアルな「コンサート・ライブ」やそれに連なるパッケージ商品の存在は不可欠です。
リアルな体験(コト)や具体的なモノを中心にどう価値づけをするか?
それがビジネスにつながっていくんですが、その価値とは「手軽」ではなく「上質」の軸で位置づけられる。
流行のみを追い求めた消費財、というよりも文化資産ではないかと。
音楽がビジネスとしておいしいビジネスではなくなる。
するとお金しか考えない人達は退場せざるを得ない。
津田氏はこう述べ、音楽と芸能界の切り離しが進むことも示唆しています。
牧村氏も、今までの音楽ビジネスを、「音楽のごく一部を培養し」た結果の「音楽芸能界」「音楽エンタテインメント」と規定しています。
そして、「音楽が属しているものはもっと広く、他の文化とのコラボレーションが可能という意味では、音楽ほど広いものはない」と述べられてます。
“原点回帰”と文化としての可能性。
なかなか楽しみな時代がやってきてるんですね、と思います。
**************************************************************************
お読み頂き有難うございます。
(↓)クリックの程、宜しくお願い申し上げます。

単純な二項対立の図式に基づいた議論は不毛とならざるを得ません。
そして津田氏は、デジタル万能主義者ではなく、実は音楽の良質な愛好者(ライブはまだ観たことないですが)であることは僕も知っています。
“渋谷系”の産みの親でもあった牧村氏も、あるべき音楽の姿、レーベルのあり方について優れた感覚とセンスをお持ちの方だということが、本書を読んでひしひしと伝わってきました。
(両氏のご経歴は、amazon 商品説明の著者略歴をご参照下さい)

僕は昨年(2010年)11月に読んでみたんですが、牧村憲一氏の書かれた「あとがき」で、牧村氏と津田氏をジョイントをコーディネートされたのが、風来舎社長の森和夫さんだとわかり、とてもすんなりと納得したものです。「なるほど」という納得感が「スコ~ン」と来るような(笑)。
音楽論からテクノロジー論まで、人によって色々な読み方ができる書籍ですが、以下、僕の意識に刺さった内容をまとめてみます。
■レーベルのあり方
あるべきレーベルの姿、について僕は昨年、残響レコードの記事を書いてきました。
なぜ、メジャーといわれた世界で優れたレーベルが誕生しつつも、それが持続可能なビジネスとして根付かなかったのか?
そのいきさつについて本書で牧村氏が総括されてます。
結局、レコード会社にとっての都合のよい投資の“刈り取り場”がレーベルであったのかもしれないと(同書105ページより)。
(1)パソコン、携帯端末も普及による音楽環境の変化とご都合主義の配信。
(2)ミュージシャンも含め誰もが飛びついてしまったお手軽なカヴァー集、バブル的売り上げを想定した過去の悪癖。
(3)既得権に基づくリスナーへの不親切で不利益な対応。
(4)流行りのものに擦り寄る、音楽性の欠如。
上記のことがらは、現在、レーベルを作る際、そのまま反面教師としてのポイントとなり、それこそ原点回帰ではないか? と牧村氏は指摘します(同書105ページより)。
音楽のクオリティと経営戦略の両立。
レーベルの維持には知識と美意識が必要で、核となるのが人と音楽、そしてヒット。
ヒットとは、短期間の売り上げに留まらず、長い時間を超えて売れ続けるという面もある。
これは、ブランドの発想ですよね。
■経験価値と文化サイクル
津田氏が、地方の人と話された逸話があります(同書218ページ)。
今やamazon.をはじめネットショッピングがあるのだから、遠方のTSUTAYAに行く必要はないのではないか? との問いに、「津田さんは地方をわかっていない。地方には娯楽がないので、CDを借りて返しにいくことが文化的なサイクルである」と言われたそうです。
かつての東京的(六本木WAVE)なものが地方で展開拡散(牧村氏)している。
たとえその場で購入しなくても、場のオーラの中で情報を得たり満足感を得る。
そういう環境づくりは、リアルのショップにとって切実でしょうね。
■CDの付加価値
僕も数年前からずっと、CDの二極化のことは言ってきましたが、本書でも当然、そのことは触れられてます。
牧村氏の対話の中で、もし津田氏がプロモーションを任されたら? との問いに以下のように答えています(同書230ページ)。
(1)アルバムという単位は必ずミニアルバムにする。
(2)CD販売はamazon.とライブ会場に限定。会場販売は全て1,000円で販売し、amazon.の優れたシステムを手軽に利用できる「e謡」販売サービスを行う。
(3)一方で2,000円のCDも出して次回のライブ優先予約券とボーナス・トラックを入れる。
このあたりについては、昨年末に読んだジム・コリンズの『トレードオフ』の内容が頭に浮かんできました。

一言でいえば、あらゆる商品は、「上質さ」と「手軽さ」のどちらかの軸で突出したものが成功するということです。
その両方を狙うことは幻想(幻影)でしかない(二兎を追うものは一兎を得ず)。
両方の軸で突出していなければ、「不毛地帯」でくすぶってします。
新しい商品は、ほとんど「不毛地帯」で生まれ、ヒットする商品は「上質」か「手軽」のどちらかの軸で突出する。
「上質」ないしは「手軽」で、多くの商品がひしめき合っている場合、「上質」なら「手軽の部分で、「手軽」なら「上質」の部分で突出すると、それはイノベーションになる。
そういう要旨です。
そう言えば、「ユニクロ」は、「手軽さ」の勝者ですよね。
『トレードオフ』の図表を自分で編集しなおしてみました(↓)。

著者のジム・コリンズ氏は僕と同じでU2がお好きなようなので、本書にもU2が引き合いに出されてますから、僕もU2の引き合いに出します(↓:iTunes の画面だけU2じゃないですが・・・)。

今までの業界のビジネスモデルにおいては、「コンサート・ライブ」はパッケージ販売のためという位置づけでした。
ところが、生活者にとっての価値のマップは違ってますよね。
これじゃビジネスもうまくいかなくて当然です。
ジム・コリンズは、「上質」をこう定義しています。
上質度=経験+オーラ+個性
「上質」にしても「手軽」(価格・入手の便宜性)にしても、その基準は刻刻と変わっていくものです。
つい10年前までは、「手軽」軸の筆頭にCDなどパッケージ商品がいたもんですが、今や「配信」に敵うはずがありません。
(それまでは、「手軽」さを追求したことでマス・マーケットを拡大してきたわけですよね)
となると、「上質」軸を中心にパッケージ商品をポジショニングしていくことが現実的です。
勿論、「上質」軸でも「コンサート・ライブ」には敵いませんが、「コンサート・ライブ」との関連性の中でCDを位置付けていく津田氏のアイデアは的外れではありません。
津田氏が、クローズドチャネルでCDを1,000円の価格設定にしたのは、決して「手軽」軸を求めたわけではないと僕は考えます。
ただ、それにしても現状のCDの価格が生活者にとって高すぎるというのは僕も検証してますので、曲数と価格の戦略はもっと練られるべきでしょう。
また、津田氏のプロモーション・プランは、(津田氏気に入ったアーティストの場合という仮定で)クローズドチャネル(コンサート会場とネットショップ)のお話でしたので、リアル・ショップのことは触れられていません。そのあたりは別の話になるのでしょうが、それでも「上質」軸でのポジショニングが肝要かと僕は考えます。
「上質」と「手軽」を言い換えると、「愛される」と「必要とされる」ことです。
誰だって「愛されつつ必要とされる」は理想でしょう。
人として生きていく上で、「愛されつつ必要とされる」ケースはあるかもしれません。
しかし、ここが重要なんですが、商品の世界ではあり得ないことなのです。
「音楽」は人にとって必ずしも「必要」とされるものではないかもしれません。
(“NO MUSIC NO LIFE”のコアなファンは別ですけど、若い頃、音楽に入れ込んでいても結婚して子供ができれば音楽を買うことから離れるなんてことは当たり前のことでした)
どうあがいても、「必要とされる」ということでは、飲食品や衣料や教育費のような必需品・サービスには敵わないのです。
ならば、「必要とされる」ことよりも「愛される」ことを求めるのは妥当なことであり、「愛してくれる」人達を増やすべく開拓するべきではないでしょうか?
あと余談なんですけど、「HMV」を買収された「ローソン」さん。チケット販売とパッケージ販売(特にEC)のシナジー効果を狙われていると思うんですが、「上質」と「手軽」のトレードオフには、特にお気をつけてくださいね。
■文化としての可能性
『未来型サバイバル音楽論』の第5章「それでも人は音を楽しむ」、牧村氏と津田氏のトークではいくつも示唆的な発想が出てきます。
「ネットはサロンである」もしかりです。
ソーシャル・メディアにしてもその名の通り、社交の場。
「音」までもネット空間の中で完結してしまうことはないと僕も考えます。
リアルな「コンサート・ライブ」やそれに連なるパッケージ商品の存在は不可欠です。
リアルな体験(コト)や具体的なモノを中心にどう価値づけをするか?
それがビジネスにつながっていくんですが、その価値とは「手軽」ではなく「上質」の軸で位置づけられる。
流行のみを追い求めた消費財、というよりも文化資産ではないかと。
音楽がビジネスとしておいしいビジネスではなくなる。
するとお金しか考えない人達は退場せざるを得ない。
津田氏はこう述べ、音楽と芸能界の切り離しが進むことも示唆しています。
牧村氏も、今までの音楽ビジネスを、「音楽のごく一部を培養し」た結果の「音楽芸能界」「音楽エンタテインメント」と規定しています。
そして、「音楽が属しているものはもっと広く、他の文化とのコラボレーションが可能という意味では、音楽ほど広いものはない」と述べられてます。
“原点回帰”と文化としての可能性。
なかなか楽しみな時代がやってきてるんですね、と思います。
**************************************************************************
お読み頂き有難うございます。
(↓)クリックの程、宜しくお願い申し上げます。














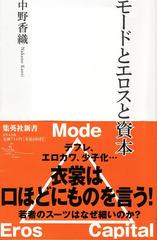










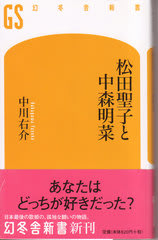
















 」
」