
買い物に出かけ、磁石に引きつかれるように増田書店に入った。
手にしたのは月刊「新潮45」12月号。岩波書店の「世界」を手にしたが、難しすぎる記事が¨¨。それで以前、友人が書いていたのを思い出して「新潮45」にしたのだ。学者の書いた文章よりは、作家やノンションライターの書いた文章の方が読みやすいこともある。学者って、読み手の事を考えて書いているのかなあ。頭のいい人たちの事、自分だけのことを考えて書いていないと確信している。まあ、ここだけの話だが。
目次を見ると「妻たちが語り継ぐシベリア抑留」山崎まゆみ著(124ページから131ページ)があった。
わたしはシベリア抑留の中でも中央アジアに抑留された人たちのことに関心がある。シベリアに抑留された日本人は、元日本兵や民間人、役人も含めて60万人から70万人とも言われている。その中で、大ざっぱに言えば10万人弱が中央アジアに抑留されている。
全体的に言えることだが、抑留された人の人数や亡くなった方の人数の細かいことは分かっていない。
「妻たちが語り継ぐシベリア抑留」では、山崎さんが得意とする新潟県長岡市の花火師・嘉瀬誠次氏の事から話が始まる。嘉瀬氏はシベリアに抑留された体験を持っている。次に、「シベリアに逝きし人々を刻む」を書いて自費出版した村山常雄氏。村山氏もシベリア鉄道の施設に抑留者としてかかわっていた。
そして3人目に、画家の香月泰男氏。彼もシベリアに抑留された体験を持ち、森森林伐採を体験してきた人だった。
山崎さんは、これらのシベリア抑留者の概略にふれながら、その夫人にインタビューした様子を記事に記録している。短い。それぞれ80歳半ばから100歳近い人の取材は、それほど長い時間を要することが出来ない。難しい取材だったと思った。年配の人への取材は難しい。しかし、この人たちの記憶はしっかりしていた。その点は、現時点でのシベリア抑留を知るためにもよかった。よく取材してくれたと思った。
わたしは、キルギスに抑留された人のインタビューを文字化し、確認作業をしている時ということもあり興味深く読ませてもらった。
その他にも、
「原発立地地域の声」小田嶋隆著も面白い。
保守王国と呼ばれていた新潟県で、今回はどうして自民党の候補者が次々と落選したのかを、新潟日報の誌面を通して読み込んでいる。新潟県内の衆議院の選挙区は6つあるが、4つの選挙区で自民党は落選している。しかも、自民党として当選した一人の議員は、元新潟県知事の泉田裕彦氏。この前までは原発反対だった人が、何故か原発推進どころか輸出しようという自民党から立候補して当選している。詳しくは、「新潮45」小田嶋さんの記事を読んでください。

今日は、もう一冊本を買った。こんなに本を買うのは珍しい。ライターと言えども、本を買うのは簡単だが、金を払えば「はい、それまでよ」というわけにはいかない。本を読むにはそれだけの時間がかかる。わたしの場合だが。
今は、電子書籍とかいうのがあり、ノート・パソコンの半分くらいの大きさに1万冊の本の文章や写真が入ると、友人が見せてくれた。だが、1万冊の本を読むには、仕事をしないで毎日1冊の本を読んでも、1万日が必要だ。63歳の私が80歳まで生きて、サイクリングや散歩も旅行もしないで土日も本を読んでいたとしても、6000冊くらいしか読めない。電子書籍なんかいらない。そんなものに時間を取られるよりは、考えたり体験したり、見聞する時間としたい。
まあ、ナマケモノだから、80歳までに多くても1000冊も読めないと思う。その半分かな。原稿を書く際の資料は、その時々で買えばいい。終わったら本は人にあげればいいと考えている。全く今風でないライターだ。でも、情報に振り回されるのはごめんだ。勘弁してください。
前置きが長くなったが、
「息子が人を殺しました 加害者家族の真実」阿部恭子著、幻冬舎新書を買った。Amazonで50円くらいよりある。
実は、私が60歳になった時に出身地の新潟県で中学校の同級会があった。その時に、同級生の一人の女性(仮にsさん)は、父親が会社のお金を使い込んでしまい、その穴埋めのために保証人であった周辺の人が田んぼを売ったり畑を売って弁済したと聞いた。
偶然にも、他の同級生のHさんのお母さんの実家は、田んぼを売って弁済の一部を済ませたという。Hさんは、「Sさんのお父さんのおかげで母親の実家も大変だったんだ」と怒っていた。
しかしSさんの一家は夜逃げをして行方も分からないという。しかも、SさんとHさんの弟は、中学校で同級生で一緒に新潟大学に進学していたという。だが、Sさんの行方も弟さんの卒業も分からないと、Hさんは話す。
「Sさんとお父さんは人格が違うんだから、別々に考えてあげなさいよ」とHさんに話した。だが、Hさんには理解してもらえなかった。
国立市に帰ってから自転車の仲間と駅前でバッタリと会った。彼女は、Sさんと同じ昭和女子大の同級生だった。今度、大学の同窓会の幹事になるというので、Sさんの住所を調べてもらった。
残念ながら名簿の住所欄は空白だったとのメールが入った。ただ、昭和女子大の同級生の一人が、Sさんと電話連絡が取れていることが分かった。
ただし、Sさんがどこに住んでいるかはわからない。
中学校の同窓生名簿を管理している一人に幼馴染がいた。彼に名簿を見せてもらったが、Sさんの住所は空白だった。
2016年の11月13日に、昭和女子大でSさんと同級生だった知り合いから電話があった。Sさんは病気で亡くなったという知らせだった。
中学校の同級生の中には、Sさんと仲のいい同級生がいた。今は千葉県に住んでいる。彼女に、Sさんの亡くなったことを知らせる手紙を書いた。すぐに返事が来た。「わたしは、Sさんのお父さんと同じ会社に勤めているので、その事件は40年前の事ですが、ずっと前から知っていました。ただ、わたしは卑怯だったんですね。毎日仏壇で手を合わせています。連絡をくれて有難う」
と手紙にあった。千葉県に住んでいる同級生に手紙を書くのは初めてだった。年賀状すら書いたことが無かったのだが。
そんなことから、犯罪者とその家族は人格が違うと思いながらも、しっかりと取材をして来なかった自分を反省していた。それに本に手が伸びたんだと思う。
幻冬舎新書には「加害者家族」鈴木伸元著という本があり、2010年に発行されている。以前、この本を読んだことが、今回の購買につながったのかもしれない。近所にある一橋大学の生協で買った1冊だ。Amazonで50円くらいからある。










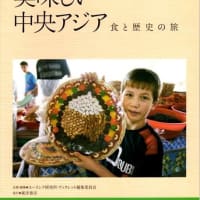
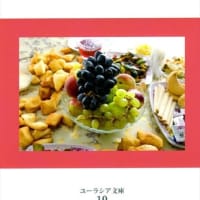


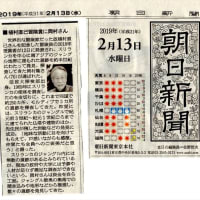
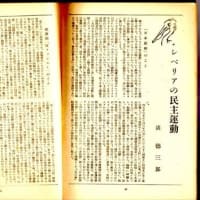
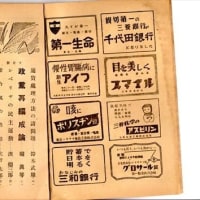
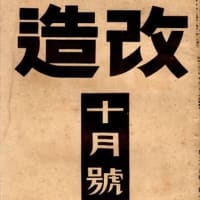


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます