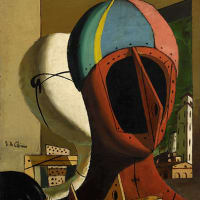※兼好法師(1283?-1352?)『徒然草』(1330-31頃)
(1)
妻(メ)といふものこそ、をのこ(※男)の持つまじきものなれ。(※妻というものこそ、男が持ってはならぬものだ。)
《感想1》兼好法師がここで問題にしているのは、《同居婚》と《妻問(ツマドイ)婚》の優劣の問題だ。兼好法師は、《同居婚》反対派だ。ここで「妻(メ)」とは、《同居婚の妻》(同居する妻)のことだ。《同居する妻》というものを、男は持つべきでないと言う。《妻問婚》こそ理想的だと兼好法師は言う。兼好法師は妻問婚賛成派だ。
(2)
「いつもひとりずみにて」など聞くこそ、心にくけれ、(※「あの人はいつも独りで暮らしていて」などと聞くと奥ゆかしいと思う。)
《感想2》男が「ひとりずみ」とは《独身》ということでなく、結婚しているが《妻問婚》であって、妻と同居する《同居婚》でないということだ。
(3)
「誰がしが婿(ムコ)に成りぬ」とも、また、「いかなる女をとりすゑて、相住む」など聞きつれば、無下(ムゲ)に心劣りせらるるわざなり。(※「誰それの婿になった」とか、「これこれの女を迎えて、同居している」などと聞くと、ひどく幻滅させられてしまう。)
《感想3》「婿(ムコ)に成りぬ」(《婿入婚》)も「女をとりすゑて、相住む」(《嫁取婚》)もともに《同居婚》だ。兼好法師は、過激な《同居婚》反対派で、《同居婚》をしたと聞くと、「ひどく幻滅させられてしまう」。以下、《同居婚》への反対理由を兼好法師が列挙する。
(4)
《同居婚》への反対理由①:ことなることなき女をよしと思ひ定めてこそ添ひゐたらめと、いやしくもおしはかられ、(※《たいした取り柄のない女》を素晴らしいと思い込んで同居しているのであろうと、その男が《取るに足りない》と推量される。)
《感想4》女と《同居婚》する男は《取るに足りない》(「いやし」)と兼好法師は思う。なぜ「いやし」かといえば「ことなることなき女(たいした取り柄のない女)をよしと思ひ定め」たりするからだ。女を見る目がない男だ!
(5)
《同居婚》への反対理由②:よき女ならば、(《注》「この男をぞ」削除)らうたくして「あが仏」と守りゐたらめ。たとへば、さばかりにこそと覚えぬべし。(※もし同居する女が、「よい女」であるならば、男が女をまるで「わが仏」とばかりにかしずいているのであろう。そんな程度の男かと思ってしまう。)
《感想5》男が女を「わが仏」とばかりにかしずく(「らうたし」)のは、男として恥ずかしいと兼好法師は思う。男に大切なのは《公(オオヤケ)》であって、《私事》でないからだ。
(6)
《同居婚》への反対理由③:まして、家のうちをおこなひをさめたる女、いとくちをし。子など出で来て、かしづき愛したる、心憂し。(※ましてや、家の中を取りしきる女は、はなはだ感心しない。また子供などが出来て、女が母として子供にかしづき愛するなど、嫌になる。)
《感想6》『源氏物語』「帚木(ハハキギ)」の「雨夜の品定め」の「美相なき家刀自」(美しさのかけらもない世話女房)批判の影響があるのかもしれない。『源氏物語』では「耳はさみがちに 美さうなき家刀自の、ひとへに うちとけたる後見ばかりをして」(※垂れ下がる額髪をなりふり構わず耳のうしろへ掻き上げて、美しさのかけらもない世話女房が、ひたすらうち解けた世話だけをして)と、一途に恰好など構わず家事に精を出す女性がけなされる。
《感想6-2》また当時、上層階級では公家・武家を問わず、「乳母」が子供を育てた。だから兼好法師は、同居する妻が「子など出で来て、かしづき愛したる」のは「心憂し」(嫌になる)なのだ。
(7)
《同居婚》反対理由④:男なくなりて後、尼になりて年寄りたるありさま、亡き跡まであさまし。(※男に先立たれた後、同居する女が尼になり老いさらばえた様子は、男の死後まで情けないものだ。)
《感想7》妻と同居していた場合、男が死んだ後も、女は男の家に居続け(《嫁取婚》の場合)、あるいは《婿入婚》なら男が住んでいた女の家で、人々は「女が尼になり老いさらばえた様子」を見ざるを得ない。そうした状況は「男の死後まで情けないものだ」と兼好法師は思う。彼はまことに《同居婚》反対、《妻問(ツマドイ)婚》賛成派だ。
(8)
《同居婚》反対理由⑤:いかなる女なりとも、明暮(アケクレ)添ひ見んには、いと心づきなく(※気に入らず)、憎かりなん。女のためも、半空(ナカゾラ)にこそならめ、(※どのような女であっても、朝夕一緒にいて顔を合わせていたのでは、大変気に入らず、憎くなるだろう。女にとっても中途半端になるだろう。)
《感想8》確かに「明暮(アケクレ)添ひ見んには」、息も詰まることもあるだろう。Cf. 今なら、例えば「亭主元気で留守がいい」とか、「濡れ落ち葉」とか言う。
(9)
《同居婚》反対理由⑥:よそながら時々通ひ住まんこそ、年月経てもたえぬなからひ(※仲らひ、間柄)ともならめ。あからさまに(※ちょっと)来て、泊りゐなどせんは、めづらしかり(※新鮮だ、素晴らしい)ぬべし。(※離れていながら時々女のもとに通って住んだりすれば、長い年月が経っても、絶えることのない関係となるであろう。ちょっと来て、泊まっていったりするのは、新鮮で素晴らしい感じがするにちがいない。)
《感想9》兼好法師が《妻問(ツマドイ)婚》に賛成派する理由が、なかなかロマンチックに語られている。
《感想9-2》夫が妻の家を訪ねる《妻問婚》(通い婚)は、古代の婚姻様式で夫婦は別居し,子供は妻の家で育った。平安中期に妻方同居の《婿取婚》=《婿入婚》,さらに鎌倉時代の武家から夫方同居の《嫁取婚》に変わっていく。
《感想9-3》平安末、武家が勃興し妻と同居する坂東の風が上方に入ってくる。鎌倉末の京都人(官人=公家)である兼好法師は『徒然草』のなかで、旧風《妻問婚》をよしとし、新風《同居婚》(《婿入婚》《嫁取婚》)に反対する。
(1)
妻(メ)といふものこそ、をのこ(※男)の持つまじきものなれ。(※妻というものこそ、男が持ってはならぬものだ。)
《感想1》兼好法師がここで問題にしているのは、《同居婚》と《妻問(ツマドイ)婚》の優劣の問題だ。兼好法師は、《同居婚》反対派だ。ここで「妻(メ)」とは、《同居婚の妻》(同居する妻)のことだ。《同居する妻》というものを、男は持つべきでないと言う。《妻問婚》こそ理想的だと兼好法師は言う。兼好法師は妻問婚賛成派だ。
(2)
「いつもひとりずみにて」など聞くこそ、心にくけれ、(※「あの人はいつも独りで暮らしていて」などと聞くと奥ゆかしいと思う。)
《感想2》男が「ひとりずみ」とは《独身》ということでなく、結婚しているが《妻問婚》であって、妻と同居する《同居婚》でないということだ。
(3)
「誰がしが婿(ムコ)に成りぬ」とも、また、「いかなる女をとりすゑて、相住む」など聞きつれば、無下(ムゲ)に心劣りせらるるわざなり。(※「誰それの婿になった」とか、「これこれの女を迎えて、同居している」などと聞くと、ひどく幻滅させられてしまう。)
《感想3》「婿(ムコ)に成りぬ」(《婿入婚》)も「女をとりすゑて、相住む」(《嫁取婚》)もともに《同居婚》だ。兼好法師は、過激な《同居婚》反対派で、《同居婚》をしたと聞くと、「ひどく幻滅させられてしまう」。以下、《同居婚》への反対理由を兼好法師が列挙する。
(4)
《同居婚》への反対理由①:ことなることなき女をよしと思ひ定めてこそ添ひゐたらめと、いやしくもおしはかられ、(※《たいした取り柄のない女》を素晴らしいと思い込んで同居しているのであろうと、その男が《取るに足りない》と推量される。)
《感想4》女と《同居婚》する男は《取るに足りない》(「いやし」)と兼好法師は思う。なぜ「いやし」かといえば「ことなることなき女(たいした取り柄のない女)をよしと思ひ定め」たりするからだ。女を見る目がない男だ!
(5)
《同居婚》への反対理由②:よき女ならば、(《注》「この男をぞ」削除)らうたくして「あが仏」と守りゐたらめ。たとへば、さばかりにこそと覚えぬべし。(※もし同居する女が、「よい女」であるならば、男が女をまるで「わが仏」とばかりにかしずいているのであろう。そんな程度の男かと思ってしまう。)
《感想5》男が女を「わが仏」とばかりにかしずく(「らうたし」)のは、男として恥ずかしいと兼好法師は思う。男に大切なのは《公(オオヤケ)》であって、《私事》でないからだ。
(6)
《同居婚》への反対理由③:まして、家のうちをおこなひをさめたる女、いとくちをし。子など出で来て、かしづき愛したる、心憂し。(※ましてや、家の中を取りしきる女は、はなはだ感心しない。また子供などが出来て、女が母として子供にかしづき愛するなど、嫌になる。)
《感想6》『源氏物語』「帚木(ハハキギ)」の「雨夜の品定め」の「美相なき家刀自」(美しさのかけらもない世話女房)批判の影響があるのかもしれない。『源氏物語』では「耳はさみがちに 美さうなき家刀自の、ひとへに うちとけたる後見ばかりをして」(※垂れ下がる額髪をなりふり構わず耳のうしろへ掻き上げて、美しさのかけらもない世話女房が、ひたすらうち解けた世話だけをして)と、一途に恰好など構わず家事に精を出す女性がけなされる。
《感想6-2》また当時、上層階級では公家・武家を問わず、「乳母」が子供を育てた。だから兼好法師は、同居する妻が「子など出で来て、かしづき愛したる」のは「心憂し」(嫌になる)なのだ。
(7)
《同居婚》反対理由④:男なくなりて後、尼になりて年寄りたるありさま、亡き跡まであさまし。(※男に先立たれた後、同居する女が尼になり老いさらばえた様子は、男の死後まで情けないものだ。)
《感想7》妻と同居していた場合、男が死んだ後も、女は男の家に居続け(《嫁取婚》の場合)、あるいは《婿入婚》なら男が住んでいた女の家で、人々は「女が尼になり老いさらばえた様子」を見ざるを得ない。そうした状況は「男の死後まで情けないものだ」と兼好法師は思う。彼はまことに《同居婚》反対、《妻問(ツマドイ)婚》賛成派だ。
(8)
《同居婚》反対理由⑤:いかなる女なりとも、明暮(アケクレ)添ひ見んには、いと心づきなく(※気に入らず)、憎かりなん。女のためも、半空(ナカゾラ)にこそならめ、(※どのような女であっても、朝夕一緒にいて顔を合わせていたのでは、大変気に入らず、憎くなるだろう。女にとっても中途半端になるだろう。)
《感想8》確かに「明暮(アケクレ)添ひ見んには」、息も詰まることもあるだろう。Cf. 今なら、例えば「亭主元気で留守がいい」とか、「濡れ落ち葉」とか言う。
(9)
《同居婚》反対理由⑥:よそながら時々通ひ住まんこそ、年月経てもたえぬなからひ(※仲らひ、間柄)ともならめ。あからさまに(※ちょっと)来て、泊りゐなどせんは、めづらしかり(※新鮮だ、素晴らしい)ぬべし。(※離れていながら時々女のもとに通って住んだりすれば、長い年月が経っても、絶えることのない関係となるであろう。ちょっと来て、泊まっていったりするのは、新鮮で素晴らしい感じがするにちがいない。)
《感想9》兼好法師が《妻問(ツマドイ)婚》に賛成派する理由が、なかなかロマンチックに語られている。
《感想9-2》夫が妻の家を訪ねる《妻問婚》(通い婚)は、古代の婚姻様式で夫婦は別居し,子供は妻の家で育った。平安中期に妻方同居の《婿取婚》=《婿入婚》,さらに鎌倉時代の武家から夫方同居の《嫁取婚》に変わっていく。
《感想9-3》平安末、武家が勃興し妻と同居する坂東の風が上方に入ってくる。鎌倉末の京都人(官人=公家)である兼好法師は『徒然草』のなかで、旧風《妻問婚》をよしとし、新風《同居婚》(《婿入婚》《嫁取婚》)に反対する。