
『庭師の娘』ジークリート・ラウベ作 若松宣子訳 中村悦子絵 岩波書店
うちがあるA(仮)丁目通りには、この通りのお庭10軒くらいを昔から受け持っている専属の庭師さんがいらっしゃいます(うちは頼んでないけど)。地下足袋履いて、朝から暗くなるまで毎日通りにいて、なんだかA丁目の門番のような。
とっても人見知りで最初は挨拶しても返事もしてくれなかったけれど、ただ単に照れていただけでした
 。植物と子どもには心を開いていて、子どもたちにお菓子をくれたり、わざわざアイスを買って届けてくださったり
。植物と子どもには心を開いていて、子どもたちにお菓子をくれたり、わざわざアイスを買って届けてくださったり 。A丁目はふつうの住宅街とは異なり、山林を所有している人も多いので、山の手入れも大きな仕事。言葉数は少ないけれど、山の生態系にも詳しい庭師さんは、子どもたちにいろんなことを教えてくれる山の先生!「私はバカ(学がない)だから」が口癖の庭師さんですが、本当の意味で賢くないとできない仕事だな~、って常々感じます。
。A丁目はふつうの住宅街とは異なり、山林を所有している人も多いので、山の手入れも大きな仕事。言葉数は少ないけれど、山の生態系にも詳しい庭師さんは、子どもたちにいろんなことを教えてくれる山の先生!「私はバカ(学がない)だから」が口癖の庭師さんですが、本当の意味で賢くないとできない仕事だな~、って常々感じます。そんなわけで、書店で『庭師の娘』を見かけたときは興味津々。読みたいリストに加えてたところ、先日鎌倉で口コミだけで文庫をされてる方のところにあったので、借りて来ました!
≪『庭師の娘』あらすじ≫
メスメル博士のお屋敷に、庭師の親方である父親と住むマリーは、看護師になるため修道院で勉強中の身。しかし、本当にやりたいことは父親と同じ庭師。世間や父親はフランス式の幾何学的な庭園設計が一番だと思っているが、マリーが描く庭は自然と調和した新しい風景式庭園。女性が夢を持つ、やりたいことをやるなど考えられなかった18世紀末のオーストリアで、時代や社会の制約にもめげず、少数の理解者たちの協力を得て、自分の道をひらいていく少女を描く歴史フィクション。
あ~、また素敵な本に出会えて、ほっっっんとに幸せ
 。
。内容は18世紀の話と古いのですが、出版されたのは2007年、日本では2013年とわりと新しいんですね。18世紀は人間の生き方や考え方が大きく変わった驚きと革命の世紀。お屋敷内の生活や街の様子もイキイキと描かれていて、まるで自分もタイムスリップしたかのような感覚が味わえます。そして、中村悦子さんの丁寧な表紙がまたいいんだな。だって、原書はこちらだもの
 。ちょっとポップすぎる気が・・・。↓
。ちょっとポップすぎる気が・・・。↓
この物語、たくさんの実在した人物をモデルに描かれているので面白いです
 。主人公のマリーが仕えるメスメル博士は、近代催眠療法の先駆者で、魅力的なオープンマインドの持ち主。まだ子どもだという理由でなかなか世間から認めてもらえなかったモーツァルトのパトロンになったり、ルソーをはじめとしたフランスの啓蒙思想に影響されている進歩的な考え方の持ち主。メスメル博士から発せられるセンスある言葉の数々に、新しい時代の流れも感じ、非常にダイナミックな世界も感じ取れます。また、年上の妻は少ししか出て来ませんが、柔軟で革命的なアイディアはこの妻のほうから出てくることも多く、このお方もまた魅力的
。主人公のマリーが仕えるメスメル博士は、近代催眠療法の先駆者で、魅力的なオープンマインドの持ち主。まだ子どもだという理由でなかなか世間から認めてもらえなかったモーツァルトのパトロンになったり、ルソーをはじめとしたフランスの啓蒙思想に影響されている進歩的な考え方の持ち主。メスメル博士から発せられるセンスある言葉の数々に、新しい時代の流れも感じ、非常にダイナミックな世界も感じ取れます。また、年上の妻は少ししか出て来ませんが、柔軟で革命的なアイディアはこの妻のほうから出てくることも多く、このお方もまた魅力的 。
。時代の制約にめげないマリーも魅力的ですが、日常をひたすらきちんと生きているマリーの育ての親的存在のブルジがまたいい味出してるんですよねえ。融通が利かない、仕事はきっちり、でも愛情もたっぷり。おかしいと思ったら、自分が仕える主人の望みにでも遠慮なく文句を言う。こういう人がいるとほっとします
 。そして、食べ物がいちいち美味しそう(←重要
。そして、食べ物がいちいち美味しそう(←重要 )。
)。ところで、私は植物を育てられないタイプなのですが、それでもマリーの思い描く庭にはワクワクしました!人間が自然を征服する形の幾何学模様の庭園には興味はないけれど、″神がおつくりになられたままの自然は、魂を清めてくれる”という風景式庭園には心躍るんです。そして、雑草にまで愛情を注ぐマリー。スイバで花壇の縁をかざることを考えたり、雑草をも活かそうとする。
私事ですが、亡き母を思い出し、ちょっぴりしんみりしました。イングリッシュガーデンが好きで、庭の手入れをし、玄関には豪華な切り花を飾りつつも、食卓にはいつも清楚な野の花や雑草の草をとてもセンス良く活けていた亡き母。私とは色々正反対の人でした
 。
。さて、この本のテーマでもある、自分の本当にやりたいことをあきらめないこと。そのために努力をすること。 主人公のマリーはこう思います↓。
生涯ずっと、望みをねじまげながら生きることはできない。そんなことをすれば、きっと石のように固い人間になってしまうだろう。外から見てわからなくても、心はきっと固くなってしまう。
18世紀に比べて今は自由な時代なはずなのに、心が固くなってしまっている人のなんて多いことか。自分のやりたいことをやらないとそうなってしまう。なんだか、最近こういうメッセージばっかり受け取るなあ。
人生は短い。自分の本当にやりたいことをやる!
そのために生まれて来たんですもんね。マリーは特別才能があったから・・・なんて言い訳をしない!誰にでもその人が本当にやりたいことがあるはず。そして、それが見つかったら、マリーのように本人が心折れそうになっても、周りが放っておかないんです。協力したくなっちゃうんですよね。
心の中にもたくさんの花が咲くかのような素敵な物語でした
 。
。









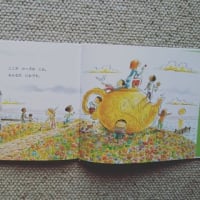

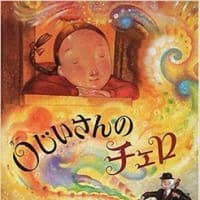
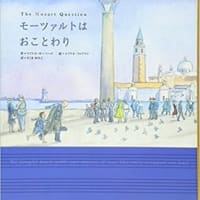
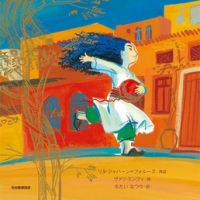
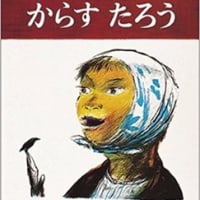
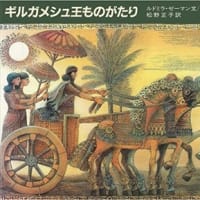



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます