1901年、ギリシャのアンティキテラ島の沖に沈んでいた沈船から引き上げられた青銅の塊(左写真)は長い間その目的が判らなかった。 発見から55年後イギリスの物理学者プライスはアテネでこれと対面し、始めてこれが精密な歯車による、ある種の計算機であることに気がついた。 しかし、この機械の真の目的が明らかになるまでには、また長い年月がかかった。 これが明らかになったのはつい最近、2005年に強力なマイクロフォーカスX線撮影により細部の撮影が可能になって以降のことである。
この機械は30以上(72個という説もある)の歯車を持ち月、太陽、火星、水星の位置を示すと共に月食、日食を予測、計算するアナログコンピュータであったのだ。製作されたのは紀元前一世紀。これと同様な機械は18世紀の時計の出現を待たなくてはならない。
古代人の天文学、暦に関する知識、興味には異常なものがある。最初は農耕を司る王の役割として、種まき、収穫の時期を決めるためのカレンダーから出発したのであろうが、その後の執着振りは度を越えている。マヤ文明に至っては小数点3桁の精度で暦を作っている。
現在我々の使っているグレゴリオ暦の精度は365.2425日/年で実際の公転周期365.2422に対して0.0003日、3300年に一日の誤差を持っているがマヤ暦は365.2420日/年で誤差0.0002日、5000年に1日の差である。 ちなみにグレゴリオ暦では変則的な閏日で誤差を調整するがマヤでは1年が260日の宗教年との連動で示す。
59宗教年 x 260日 = 42太陽年 x 365.242
http://www.geocities.jp/why260days/
文化、文明とは余剰生産が生み出す、とはよく言ったもので、このような精緻、精密な観測に基く天文研究を王権に庇護された神官たちは延々と続けたのだろう。この執着は何処から来るのだろうか?日本でも陰陽師がその役割を担っていたようだが、例えば日食を予測するという事は天変地異を予測する事に等しく、ひいては未来を予測する能力と見られていたのかも知れない。占星術というのは未来予測の願望の現われとすると精密な天文予測は精密な未来予測と同義だったのだろう。もし未来が予測できるとするなら、彼等の執着も理解できるような気もする。












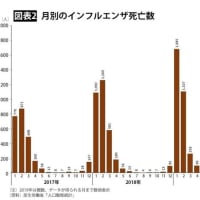
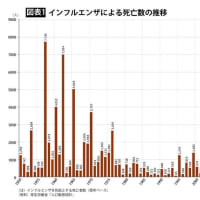
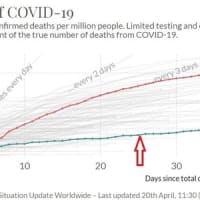
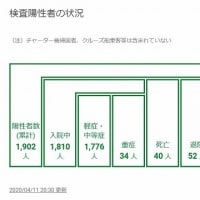
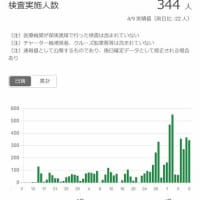
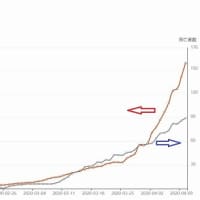
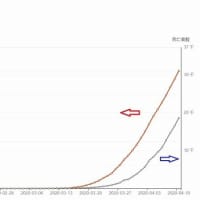

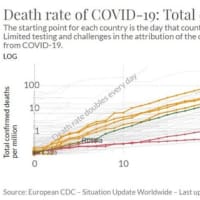
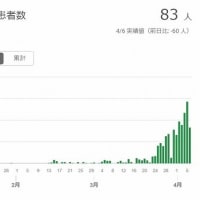
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます