 1974年4月、ロラン・バルトは3週間の旅程で中国訪問団の列に加わっている。スイユ社のバルト担当編集者フランソワ・ヴァール、それからフランスの代表的な前衛雑誌「テル・ケル」の書き手たち、つまりフィリップ・ソレルス、マルスラン・プレネ、ジュリア・クリステヴァも同行した。この旅からたとえばクリステヴァの出世作『中国の女たち』(1974)が生み出されたことは、よく知られている。
1974年4月、ロラン・バルトは3週間の旅程で中国訪問団の列に加わっている。スイユ社のバルト担当編集者フランソワ・ヴァール、それからフランスの代表的な前衛雑誌「テル・ケル」の書き手たち、つまりフィリップ・ソレルス、マルスラン・プレネ、ジュリア・クリステヴァも同行した。この旅からたとえばクリステヴァの出世作『中国の女たち』(1974)が生み出されたことは、よく知られている。しかしバルトは旅行中に4冊のノートに覚書を書いたのみで、結局そのままとなった。彼のもくろみとしては、あまりにも美しく、まぼろしのような日本滞在記『記号の国』(1970)の陶酔的な思い出の続編として、それの中国版を執筆するぞという夢想を抱いたはずだ。しかしそれは、失望と苛立ちにあっけなくかき消された。
「あらゆるものに合理性のテーブルクロスが掛けられているようで、偶発事、襞(ひだ)、突飛なものは稀である。 ≠ 日本」(90頁)
「この一週間、エクリチュールが開花することも、エクリチュールの悦楽を得ることもない。無味乾燥、不毛だ」(100頁)
こうした親日ぶり、反中ぶりは、旅行から35年も経過してからついに初お目見えとなった本書『中国旅行ノート』(ちくま学芸文庫)のあちこちに散見され、私たち日本人の目にはこそばゆいほどである。ただし、この時の中国が文化大革命のまっただ中であり、あらゆる言説、身ぶりが政治的抑圧のクリシェに収斂していた時代だったことも、考慮に入れておく必要がある。《批林批孔運動》(毛沢東の政敵である林彪を、貴族的な礼法主義の生みの親である孔子と同一視しつつ、全否定する国民参加型キャンペーンのこと)の最盛期なのである。単純な見解だが、やはり時代が悪かったとしか言いようがない。では、いつの時代に訪ねれば最良だったのか。それは私にもわからないのだが…。
「索引を作るため自分のノートを読み返しながら、このノートをそのまま出版すれば、間違いなくアントニオーニ的なものとなることに気づく。だが、他にどうすればよいというのか?」(240頁)
ロラン・バルトが中国に行くというモチベーションを持ったのは、どうやらミケランジェロ・アントニオーニが江青女史からの注文を受けて撮ったドキュメンタリー映画『中国』(1972)を見て刺激を受けたからだったようだ。アントニオーニは彼なりに思いを込めて作ったらしいが、完成品は江青女史と毛沢東によって全否定されてしまった。

















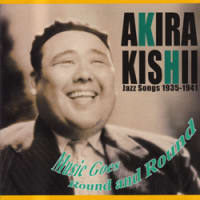


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます